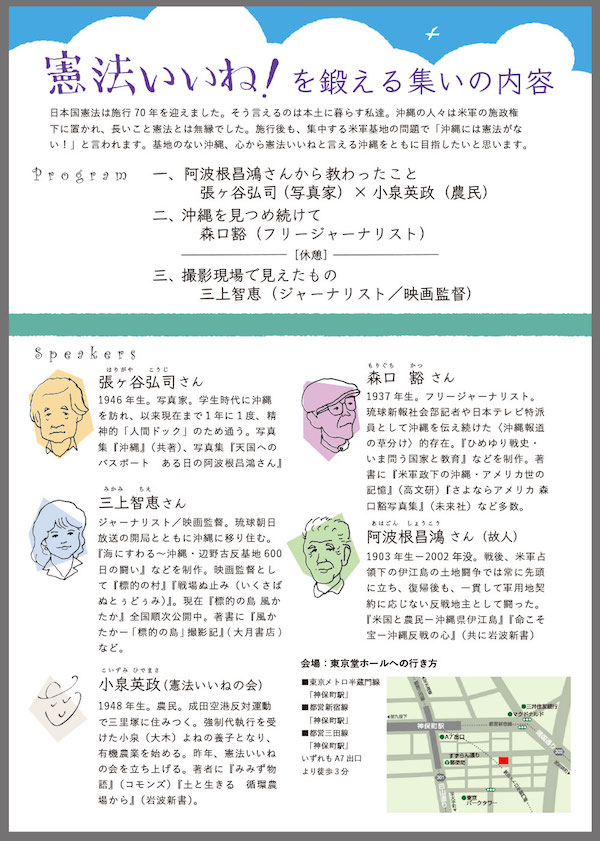沖縄の高江や辺野古の、米軍基地建設に反対する運動の中で奮闘していた宮城節子さんが亡くなった。本人が語るには、進行の遅い珍しいガンで、医者も研究対象として大事にしてくれているとのことだったのだが、病状が急変し、帰らぬ人となった。
葬式はしない、そして散骨をというのが遺言だと聞いて、とても彼女らしいと感じた。集まった友人、仲間たちで相談して、辺野古の海、高江、彼女の農場があった大湿帯(オオシッタイ)、伊江島に散骨する事になったと聞いた。さらに、その相談の中で、彼女が「もう一度、三里塚に行きたい」と強く願っていたということで、ぼくの方に、「よねさんのお墓に散骨できないか」と電話で問い合わせがあった。
宮城さんとは、1970年の日米安保条約にに反対する坐りこみ運動の中で知り合った。その後彼女は、僕たちと同じ時期に三里塚の空港反対運動に参加し、よねさんや染谷のばあちゃん、村のおっかさん達とつきあいを深めていった。
よねさん宅が代執行され、反対同盟がよねさんの住まいとして、東峰の島村さんの畑の一角にプレハブ小屋を建てた時、宮城さんはしばらくの間、同居し、よねさんを気づかった。宮城さんは沖縄出身で、その後一時期、家族の何がしかの事情で沖縄に戻っていた。
宮城さんが居ない間に、よねさんが病に倒れ、いくつかの経過を経て、僕たちが養子になった。反対同盟からの養子要請の候補に宮城さんは含まれて居なかったが、宮城さんがその時いたならば、自ら「私がなる」と申し出たかも知れないと、今になって思う。そういう熱い心の持ち主だった。
僕たちと宮城さんとの関係、そして、よねさんと宮城さんとの関係、「よねさんのお墓に散骨できないか」と尋ねられて、断る理由はなかった。宮城さんは特別なのだ。
宮城さんの散骨に、沖縄の親しかった女性陣が賑やかに7人もいらっしゃると言う。その日を待つ間、宮城さんのことをいろいろ想った。最後に会ったのは、2016年の一月末、沖縄でだった。その頃はとても元気そうで、高江のヘリパッド反対の坐りこみに頻繁に出かけている話や、散骨の場所ともなった伊江島に通って、「阿波根さんの芝居の練習しているんだけど、歌が難しくてなかなか覚えられない」と苦笑いしていた。
阿波根昌鴻(あはごん しょうこう)、名前は聞いたことはあるが、詳しくは何も知らなかった。「阿波根さんの本を読んでみて!」姿なき宮城さんから、そんな声が届いた気がして、阿波根昌鴻著『米軍と農民〜沖縄県伊江島』(岩波新書)を取り寄せて読んで見た。
ちっとも読書家ではないぼくがこんな事を言っても、何の意味もないだろうが、その本は何度も繰り返して、深いところから僕の心を揺さぶってやまなかった。
ぼくの目を開かせた一つは、ぼくが沖縄のことを知らなすぎる事によるが、終戦後、アメリカの施政権下に置かれていた沖縄と、本土に育った僕たちとの、あまりにも異なる境遇の違いだ。沖縄戦で本土を守るための捨て石にされ、直視できない、痛ましく凄まじい戦禍に見舞われた沖縄、そこまでの認識は持っていたつもりだが、サンフランシスコ講和条約によって、沖縄が切り離され、その後もずっと、「沖縄は、アメリカが血を流して得た戦利品だ。あなた達には、YESもNOもない」と言われながら、長い間、アメリカの軍靴の下に踏みつけられていた。
本土の僕たちは新憲法のもと、戦争の放棄や基本的人権などの理念の中で育ったが、沖縄の人々は虫けらのように扱われていた。それをこの国の政府がずっと黙認して来た。沖縄を知ると言う事は、自分自身を知ることになる。
もう一つ、そんな厳しい状況下にあって、阿波根さんをはじめとする伊江島の農民達は結束して、自分達の命を、生活を守るため、銃剣とブルドーザーによる基地建設の為の土地接収に対して、非暴力で果敢に抵抗した。住んでいた家が、野菜が育つ畑が、重機で押しつぶされたり、鉄条網で囲われる。命を繋ぐためには、中に入って食料を得て来なければならない。逮捕者は尽きない、負傷者も出る、米軍に射殺された青年、子供達に少ない食べ物を与えて自分は我慢し、餓死する若い母親、沖縄戦が続いているのと同じだ。
そんな中、農民達を支えた約束事があった。「陳情規定」と名づけられたその箇条書きの文章は1954年に作成されたものだが、63年経た今でも、非暴力の姿勢を具体的に示したものとして、これからも必要とされる非暴力の手本として、僕にはとても貴重に思えた。
その一部を抜粋してみよう。
一、反米的にならないこと。
一、怒ったり、悪口をいわないこと。
一、耳より上に手を上げないこと。
一、大きな声を出さず、静かに話す。
一、軍を恐れてはならない。
一、人間性においては、生産者であるわれわれ農民の方が軍人に優っている自覚を堅持し、破壊者である軍人を教え導く心構えが大切であること。
これらの申し合わせ守り、力を合わせ、島の63パーセントあった基地を31パーセントまで縮小させることが出来たと言う具体的な成果は驚きだ。
もう一度、宮城さんの話に戻そう。
散骨の前日、沖縄から宮城さんの女友だちがやって来た。南国の果物や野菜などを携えて賑やかにやって来た。 よく話すこと、よく笑うこと、よく歌うこと、その明るさに圧倒された。彼女達は宮城さんがそうだった様に、阿波根さんの意志を継ごうとする人たちだ。 宮城さんも、陳情規定に強い関心を寄せていたと言う。
東京での坐りこみ当時、23歳の頃、宮城さんはこんな事を言っていた。「私が生きている毎日って言うのは、全然、非暴力じゃないわね。それこそ、自分の汲んだ水を飲んでね、自分で織ったその着物を着るとか、作った野菜を食うぐらいに、全て請負しなきゃ駄目だと思うんだけれど」。
その後、三里塚をかいくぐるなかで、土に触れ、沖縄に戻ってからは、畑を耕し、機織りを覚え、そして阿波根さんや伊江島の農民達の心に触れ、非暴力の幅を拡げていった。突然の知らせはとても残念だったが、沖縄の魅力的な仲間達が「節ちゃん」の後を継いで行ってくれるのは間違いない。
「辺野古移設が唯一の解決策」との言葉を繰り返す安倍政権の姿は、「YESもNOもない!」と言ったアメリカの軍人に重なる。その政権を選んだのは紛れもなく、本土の僕たちなのだ。
高江、辺野古と、沖縄の厳しい状況が続く。「沖縄とともに生きる」と心に刻む人たちが増えていくことが求められている。