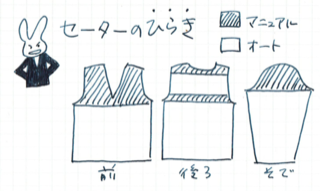吹く風がもう秋ではないと告げている。
恭平が握った石も川風に表面から熱を奪われ、真昼の太陽にさらされたとは思えないくらいに冷たかった。
「辛いことがあれば石を投げろ」
そう教えてくれたのは祖父の達明だった。達明は若い頃ボクシングをやっていて、一度は軽量級世界チャンピオンの挑戦者として取り沙汰されたことがあったそうだ。
「場末の小さなジムでいくら頑張っても、大きなジムには叶わへんのや」
達明は理不尽な大手ジムのやり口に負けて、チャンピオンに挑戦することすらできなかったのだと笑う。ただ、息子の達也、つまり、恭平の父親に言わせれば、そもそもそれほど強くはなかったとのことだ。
「その証拠に、一度、駅前の飲み屋街でチンピラに絡まれたとき、すんまへん、すんまへんとずっと謝ってたんや」
達也は達明の通夜の席でも楽しそうにその話を披露したが、祖母のめぐみはそんな達也にこれまで見たことのない形相で、
「あのな、お父さんは、あんたがまだ小さかったから、謝るしかなかったんや。警察沙汰になったらライセンス剥奪やし、なにより、あんたが怪我でもしたらと思いはったんや。そんなこともわからんのかっ!」
と達也を弔問客の面前で叱りつけた。涙を流しながら達也をにらみつけていた祖母のことを小学校にあがったばかりだった恭平は忘れられないのだった。
達明が逝ってしまってからもう三年が経った。気がついたときには手遅れと言われ、本人も周囲もあれよあれよという間に、達明は言ってしまった。めぐみも達明の後を追うようにちょうど一年後に逝った。
二人が亡くなってしまうと、なぜか父の達也は急に防波堤をなくしてかのように人生の荒波を正面から被るようになってしまった。まず、達也の勤め先が事業の失敗で大規模なリストラを敢行した。社員に責任はなく、自社製品の検査結果隠蔽という上層部の体質の露呈ではあったが、そこそこの大手企業だったために、会社を倒さないように官庁が手を差しのべ、結果、末端の社員をリストラすることで事なきを得たのである。
会社から振り落とされるような形で無職となった達也はなぜか立ち直ることが出来ず、絵に描いたような堕ち方をした。酒を適量以上に飲み、母にあたり、恭平にあたった。母は母で、酒臭い達也と顔を合わせるのが嫌で、パートが終わってもパート先の若い仲間と遊んでくることが多くなった。
小学校三年生だった恭平は、父と母が急速に自分に感心をなくしていくのを感じてはいた。しかし、祖父が亡くなった時のショックに比べれば、父と母から心が離れていくことなど、小さなことだと思えた。そして、もしかしたら、祖父の達明が亡くなったときに、自分たち家族はもう壊れて閉まったのではないかと思うようになった。
恭平は学校にいる間、授業に集中した。授業中の先生の言葉をじっと聞いていると、父と母のことをすっかり忘れることができた。そして、それだけではなく、あらゆる先生の言葉の間から、祖父の言葉が顔をのぞかせる瞬間があることに気付いたのだった。
例えば、国語の先生が、この詩の語尾が揃っているのは韻を踏んでいるというのだ、ということを教えてくれると、ふいに達明の声で、そうや、韻を踏んでいるからこそこの詩はきれいなんや、きれいやという以外に詩には意味なんかないんや、と語りかけてくるのだった。例えば、音楽の先生が、ビバルディの四季を聴かせ、春の温かな風がいかに素晴らしいかを説明し、夏の躍動感がいかに旋律に置き換えられているかを説明していると、達明の声は、つらい春かて、死にたなる夏かてある、だまされたらあかんぞ、と囁くのだ。
何をしていても、ふとした瞬間に祖父の声が聞こえるような気がした。特に河原で石を投げているときは、実際に祖父が横に立っているかのように、祖父の声が聞こえた。もしかしたら、実際にいたのかもしれない。一度、恭平は自分の立っているすぐそばの河原の石が、誰かに蹴られたように、川の中に飛んでいくのを見たことあった。
恭平が初めての達明にここに連れて来られたのは、小学校に上がる少し前だった。恭平には大きな川に見えた。近所の二級河川で、普段の川幅は二十メートルほどだったろうか。両岸の河原が広く、大雨が降ると川幅は倍ほどに広がって見えた。その河原に立って、達明は向こう岸に石を投げた。達明の投げる石は、まっすぐに向こう岸に着いた。大きく弧を描くのではなく、石はまっすぐに一直線に向こう岸に着いた。水面の何十センチか上をまっすぐに、一度も水面にバウンドすることなく向こう岸に届く。恭平も真似をして投げるのだが、石は高く空に向かい、しかも川の真ん中あたりに落ちる。川の流れる音に消されて石が落ちる音さえ聞こえない。ただ、石が川の真ん中に落ちる度に、達明の笑い声が響いた。
いま思うと、達明の投石のフォームは独特だった。ボクシングをやっていたからだろうか。振りかぶるのではなく、アンダースローのような低い姿勢から、まっすぐに拳を突き出すように投げる。恭平も最初の内は真似をしていたのだが、同じ投げ方では、まったく石は飛ばなかった。
それでも、毎日のように河原に出かけ、手頃な石を見つけ、向こう岸に向かって投げていると、知らず知らず距離は伸びた。向こう岸には届かなかったが、石は川の真ん中あたりにまで届くようになり、少しずつ向こう岸に近づいていた。
石を投げ出して半年ほどした頃だろうか。母親が風呂上がりの恭平を見て、悲鳴を上げた。
「あんた、右の肩だけパンパンやないか」
実際に鏡に映して見ると、ひと目で分かるほどに右肩と左肩の大きさが違っていた。祖父と恭平が河原で何をしているのか知っていた母は、義理の父である達明に、
「こんなことさせてたら、恭平がかたわになってしまうわ」
と泣きそうになりながら訴えた。
「わかった。もう石は投げさせん」
そう言った達明だったが、その晩、恭平の部屋にやってきて寝ている恭平に声をかけた。
「こんなことでかたわになんぞならん。それに、肩を壊すからといってやめれるもんなら、最初から誰も石なんぞなげん。どうする。もうやめるのか。投げるのか」
達明はそう恭平に迫った。達明がなぜそんなことを言うのか、わからなかった恭平は怖くなり寝たふりをしていた。
「寝たふりをするのは卑怯や。どうする、明日も投げるのか。投げんのか」
恭平は、祖父から顔を背けたまま、投げる、と小さな声で答えた。
翌日、母がパートに出かけるとすぐに、達明と恭平は河原へと出かけた。昨日のことなど何もなかったかのように、ごく普通にいつもの河原へ出かけ、いつものように石を拾い、いつものように全力で石を投げた。昨日と同じように石は川の真ん中あたりに落ちた。こんなことを続けていても、石は向こう岸に届かないと恭平は思った。すると、そんな恭平の思いを見透かしたかのように、達明は言った。
「お前はもう投げんでええ」
なぜ、急に達明がそんなことを言うのか、恭平にはわからなかった。
「いやや、まだ投げる。向こう岸に届くまで投げる」
恭平が言うと、達明は首を横に振った。
その翌日から達明は恭平を河原へと誘わなくなった。恭平は一人で河原へ出かけるようになった。母親から毎日風呂に入る時に監視されているような気がして、右で十回石を投げたら、左でも十回石を投げた。両方の肩に同じくらい筋肉を付けていれば、河原で石を投げていることがばれないと思ったのだ。
来る日も来る日も恭平は河原へ行き、向こう岸に石を投げた。友だちに誘われ公園で遊んだ日も、帰り道に河原へ立ち寄った。最初の日、空に向かった弧を描き、川の真ん中に落ちていた石は水平に飛ぶようになった。しかし、まだ向こう岸には届かない。焦りは無かった。繰り返し投げていればいつか石は向こう岸に届くという確信があった。恭平のなかには、石を投げている、という気持ちよりも、向こう岸を見つめているという気持ちのほうが強かった。向こう岸を見つめている間に、いつか石は届くようになる。恭平はそう思っていた。
達明があっという間に逝ってしまってからも恭平は毎日河原に立った。達明が亡くなった日、恭平は父と母に連れられて、病室へと入った。祖母のめぐみは達明の手の甲をさすりながら、呆然とした表情で恭平を見た。笑いかけることも出来ず、恭平はめぐみを見た。めぐみは恭平の顔を見たまま、ほら恭平がきてくれたよ、と達明に呼びかけた。達明は力なく笑ったように見えた。そして、微かにまぶたを意図的に細めて見せた。手や他の部分を動かしたくても動かせない達明が懸命に恭平に呼びかけているのだとわかった。
恭平は達明のそばに行くと、祖母と入れ替わり、達明の手の甲に自分の手を重ねた。すると、達明は顔を恭平のほうへと向け、小さな声で囁いたのだ。
「まだ、投げてるのか」
恭平はうなずいた。
「投げてる。まだ投げてる」
そう言ってから、母の顔を見た。母は涙を流しているだけで、恭平のほうを見ることはなかった。すると、達明は続けて言ったのだった。途切れ途切れの声でこう言ったのだった。
「辛い…ことが…あれば…石を…投げろ」
なぜなのか、恭平にはわからなかった。けれど、恭平はうなずき続けた。そして、達明の手を握り続けた。
達明はいったん眠りに落ちた。恭平は母と一緒に家に帰った。病室に残った父と祖母から連絡が入ったのは明け方だったらしい。恭平が達明の死を知らされたのは、翌日学校から帰ってからだった。
その日もお通夜が始まるまでの間、恭平は河原で石を投げた。
あれから三年、河原へ通い続けた。毎日同じ場所で石を投げるので、河原のその場所は草が生えなくなっていた。まるでピッチャーマウンドのように黒い土が円形に見える。その真ん中に立って、恭平は今日も石を投げている。
今日は風が全くない。こんな日は気持ちが乗りにくい。追い風があれば、飛距離が伸びそうだし、向かい風があれば負けん気で力を込めそれだけで力が発揮できそうな気がする。しかし、今日は風がないのだ。
こんな風のない日に、恭平はいつも以上に祖父の存在を感じていた。そして、祖父が亡くなって三年がたった今、そろそろ向こう岸に石が届くだろうという予感を感じていた。それがもしかしたら今日なのかもしれない。そう思いながら、恭平は淡々と石を選び石を投げた。あと、少し、後もう少し。石を投げる恭平の耳元に祖父の声が届いた。
「辛いことがあれば石を投げろ」
この言葉を聞いたのは達明が亡くなった日、以来だった。いちばん思い出していた言葉ではあったが、祖父を感じ、直接その言葉を聞いたのは今日が初めてだった。そして、その言葉を聞いた瞬間に、石を投げかけていた恭平は小さく叫んだ。そして、もしかしたら、自分は間違っていたのかもしれない、と思ったのだ。毎日毎日石を投げるのではなく、辛いことがあったときにだけ、石を投げるのだと祖父は自分に言いたかったのではないのか、と。中学一年になった恭平はそう思い、投げかけた石に思いっきり力を込めた。いつも以上に、肩は身体の後ろに引かれた。歩幅も大きく広がり、恭平は身体が引き裂かれるのではないかと思った。限界まで引かれた右の腕がぐいっと前に回り、今度は限界にまで伸びた。その時、バチッと大きな音がした。すべての動きがストップモーションになった。石は目の前の川面に力一杯投げ込まれ、水しぶきを上げて沈んだ。風が吹き、草が揺れ、同時に、石によってたたき上げられた川面の水滴が恭平の顔に飛んできた。静止画のように動きを封じられながら、冷たいな、と恭平は思った。そして、過ぎの瞬間、信じがたい激痛が走り、恭平はその場に倒れ込んだ。(了)