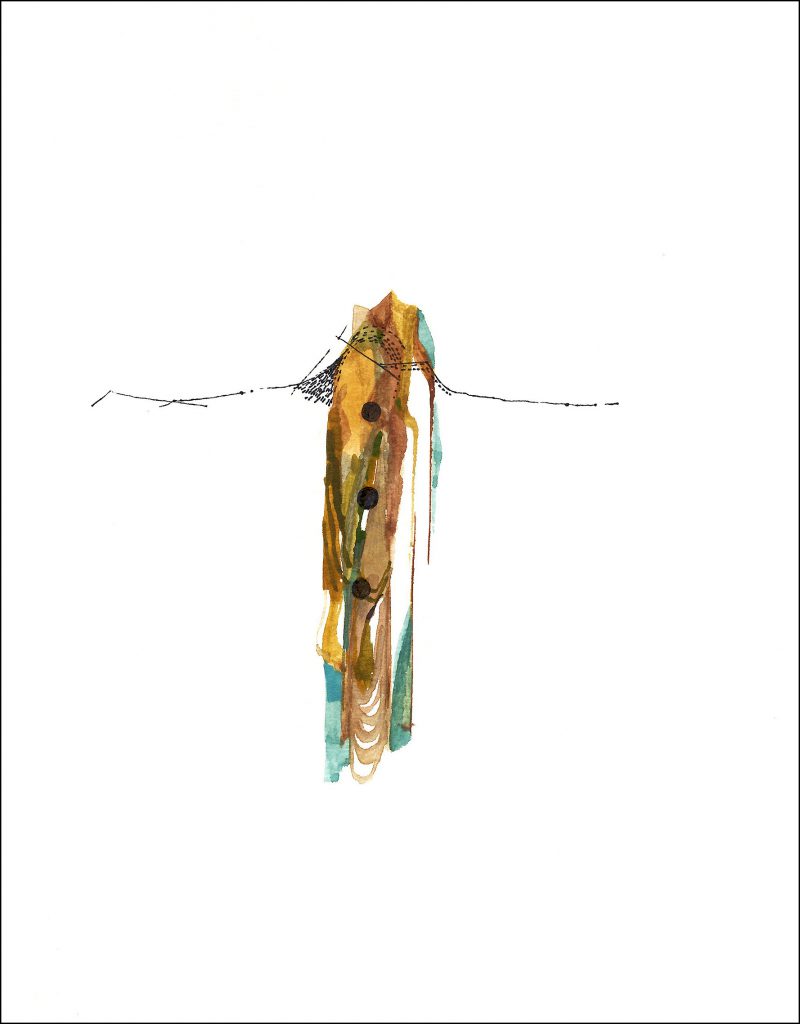編むときは必ず読んでいる。
というか、読まずには編まない。
何らかの本を読むことと編み物を同時にやる。それが私の「編み狂い」のスタンダードな形だ。
編むのと読むのを同時にやるのは私にとってはきわめて普通のことなのだが、人には「えーどうやってんの」とけげんな顔をされる。別にたいしたことではない。まずテーブルに本を開いて固定する。本をよくよく開いてテーブルに置いてから、本の端を携帯とかペンケースなどで固定する。それを前にして座り、「編む」と「読む」を同時にやっていくんだよと丁寧に説明するのだが、「だーかーらー、どうやって、それを、やるの!」と詰問されることがある。困る。だが、いざ聞かれると自分でもよくわからない。
なので、実際にやってみて、目がどんな動きをしているか注意してみた。その結果、1目編むのと同時に目がちらっと動き、半行〜1行ぐらいの文章を脳が吸収していくみたいだった。目は絶えず、本と編み目との間を、非常に軽い動きでささささ、さささと行き来している。でもいちいち顔の角度を変えたりするわけではないので、すべての動きは非常に小さい。
編み方は3種類に限定しているので、ほとんど意識することなくすいすいと編める。本の方も、何十回となく読んだ小説などが中心なので、双方ともに親近感のあるものをまさぐっている感じ。だから並行できるのだと思う。
この状態は、「読みながら編む」というのとも違うし、「編みながら読んでる」ともいえない。中とって、「よぁむ」とでも称すると、気分的にはぴったりする。そして、この「よぁんで」いる状態はたいへん幸せである。私は自分の語彙の中に幸せという言葉がないが、瞬間的な状態として、「よぁんで」いるときはたましいが喜んでいる状態といっていい。たましいがあればだけど。
編むには本が要る。その関係は、ごはんと「ごはんの友」みたいな感じだ。海苔の佃煮とかふりかけとか、梅干しとか。編み物がごはんなら本は「ごはんの友」で、だから、それがなかったらわざわざ白いごはんだけ食べなくてもいいやーと、そういう感じになる。
そのため、「理想の編みかけ」を持って出かけたのに本を忘れたときは編まないし、極端なことを言うと、持っていく本が決まらないから編み物自体をやめることもある。
自分がいつからこんなことをやっているのかよく思い出せないのだが、どうしてこうなるのかというと、たぶん、編み物だけやってると脳が余ってしまうからじゃないかと思う。
先回、編み物には「マニュアルモード」で編めるところと「オートモード」で編むところがあると説明したけれど、私がゆったりと編み狂うのはオートモードでがんがん編んでいるときだ。そういうとき、編み物自体をずっと見ている必要はないし、また何も考える必要はないのである。
そうすると、編み物だけをやっているのでは脳にかなりの面積の「あき」ができるみたいなのだ。私のイメージでは、そのまま編み狂っていたらあいたところが空焚きになりそうだ。煮汁がなくなり……鍋底がカラカラになり……煙が上がる……そんなイメージ。そこへ本を投入すると、水気が回ってちょうどいい。
実は、本を投入してもまだ脳が余ることがある。そこで映画のDVDも動員している。よぁみながら、T映のやくざ映画などを、よく見る。いや、ほとんど見てはいないのだけど同伴してもらう。音は聞こえていて、ストーリーは把握している。私は編みながらどっちの物語にも程よく浸っている。

その結果、私が手にも心にも優しい絹糸を一心に編んでいるとき、本の中では「叔母ちゃんは、そこはあんじょう云うてはるけど、結局あたしが雪子ちゃんを引き留めると見て、あたしを説き付けに来てはるねんわ。そやよってに、気の毒やけど、あたしの立場も考えて貰はんと、………」(谷崎潤一郎『細雪』)というようなことが論じられ、一方モニターの中では「オヤジさん言うといたるがの、あんた初めからわしらが担いどる神輿じゃないの。組がここまでになるのに誰が血流しとるの。神輿が勝手に歩けるいうんなら歩いてみないや、おう!」というようなことが、言われ、私は非常に満足して編みつづけている。でもまあ、存在感としては圧倒的に本>映画だ。
編み物をするときにどんな本がいいかについてはとても気難しい好みがあって、書ききれないので次回にするが、間違いなくいえるのは『細雪』は最高だということだ。大きなドラマが起きず、しかし家庭内の小さなドラマが断続的に続き、女の人たちが衣食住のさまざまなことをしょっちゅう話しあっている。
食と服飾に関する具体的な記述があることは必須条件で、『細雪』でいえば「悦子の好きな蝦の巻揚げ、鳩の卵のスープ、幸子の好きな鶩の皮を焼いたのを味噌や葱と一緒に餅の皮に包んで食べる料理、等々を盛った錫の食器を囲みながら」とか、そういった箇所を舌なめずりして吸収しながら編んでいく。こういう細部が伴う物語は、本当に編み物と合う、編み物を駆り立てる。女の人が束になって出てきて、「もっと編んじゃえ、もっと編んじゃえ」とリヤカーのお尻を押すのですね。おかげでどんどん坂が登れて、さらに編み狂える。
そのため私は文庫版の『細雪』を使い倒して何度も買い換えている(強く開くので、本が痛む)。でも逆に、編まずにこの本を読むかと言うと、今さら……という気がするのも事実だ。
どうしてなんだろう。なんとなくわかってきたのは、さっき書いた「空焚き」とは、編みながらどんどん考えが暴走してろくでもないことばかり考える状態をさしているんじゃないか。だからそうならないように、編み狂っているときは、たえず他人様の物語で適度に薄めるというか、イメージで言うと、他人様の物語の上を滑るようにして時間とわたりあっていくぐらいがちょうどいいらしいのだ。そのためもったいないことに、『細雪』を私は、薄め液にしてしまったらしい。取り返しがつかない。
だが、他にも取り返しがつかない本がいろいろあって、次回はそのことを書こうと思う。よぁむための本については、「これは編める」「絶対編めない」という明確な峻別が可能なのである。
ちなみに、読むと編むを同時にやるのは私だけではないらしい。有名なところでは橋本治さんが、編み物は本を読みながらすると書いていらした。私の推測では、橋本さんは私みたいに何度も読み返したものなどじゃなく、新刊をバンバン読み倒しながら複雑な編み込みのニットを編まれたんじゃないかと思う。脳の生産性が比べ物にもならないという気がする。