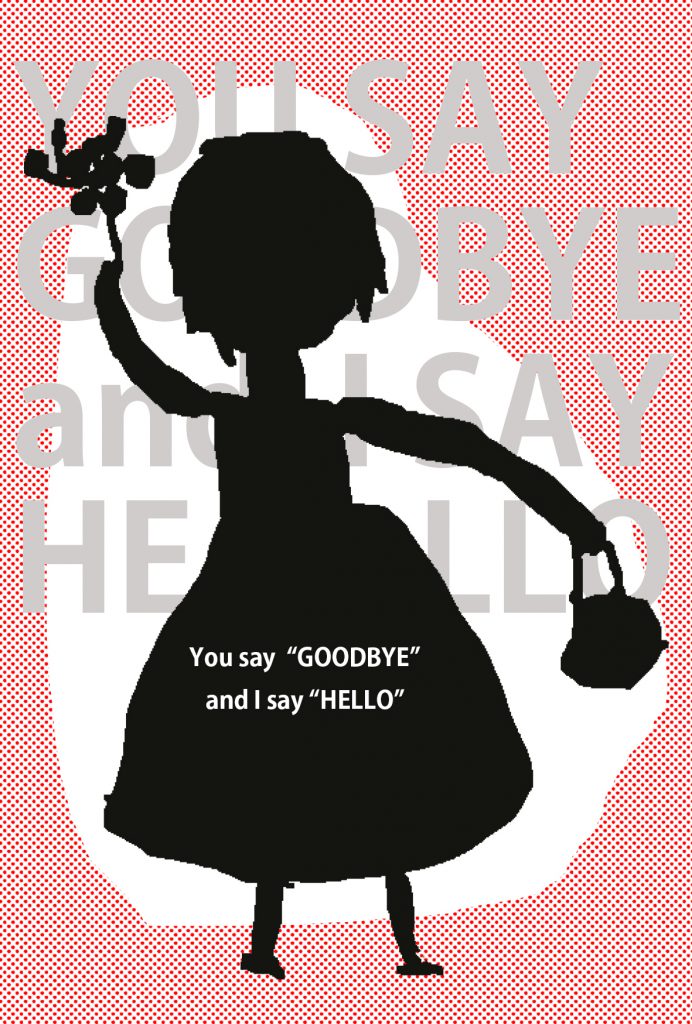静岡駅で鯛めしを二つも買い込み、早速食べてから、これを書いています。子供の頃から、父方の祖父母の住む湯河原に出かける愉しみの一つが、小田原か湯河原の駅で「鯛めし」を買ってもらって東海道線から海を眺めながら食べることでしたから、三つ子の魂なんとか、です。
隣で垣ケ原さんが、我々が今聴いてきたばかりの、藤木さんと福田さんの「死んだ男の残したものは」の素晴らしさを、「あれほど、歌詞の意味をわかって歌ってくれる人はいない」と繰返していて、その言葉どおり、演奏中には周りで洟をすする音や、ハンカチを目にあてる人が沢山いました。ああこれが本当の歌なのだなと感じ入るばかりでした。
道中、この武満さんの歌に端を発して、垣ケ原さんと年末に大阪で演奏する彼の60年代の作品に流れる芯の力強さについて話し、その決然とした信念のようなものは、一昨日の悠治さんの作品にも通じるという話から、先日FMで放送された、湯浅先生のNHK放送用音素材の話にもなりました。
あの時代の音楽や文化には、既視感がないのです。すべてが躍動していて新鮮で、何でもやってやろう、見てやろう、という、貪欲なまでの率直な音への愛情に満ちています。それが、湯浅先生が仰る「未聴感」につながってゆくのでしょう。まあこうなるだろう、どうせこうだろう、という諦観の欠片もない。まるで初めて遊びや物事を吸収する子供のように、好奇心に彩られて全てが愉快で、何物もが掛け替えのない豊かな時間を育んでいたように感じられます。
先日の演奏会の折、悠治さん曰く、当時の作曲は、こうやったらどうなるか試すためだけに書き、書いてしまえば務めは終わったものだったそうだけれど、本来の瑞々しい音は、そうした切っ掛けこそが産み落とすものであったのかもしれません。
垣ケ原さんは、悠治さんこそ常に一番前衛だったに違いないと力説していて、ある人が先日の演奏会の後、50年前当時、情報量が複雑すぎて理解できなかったことが、漸く現代になって、聴衆も処理できる能力を身につけてきたのだろう、と話していたのを思い出しました。「だから結局、悠治さんが一番前衛だったんだよね。ご自分でも気が付いてらっしゃらなかったかもしれないけれど」。そう言って、垣ケ原さんは新横浜で下車してゆきました。
10月某日 ミラノ自宅
家人が日本に戻っているが、息子の弁当の準備は友人にお願いしたので、ゆっくり6時過ぎに起きて、朝食だけ作る。ジャガイモを炒め、上に新鮮な卵の目玉焼きを載せてサラダを添えるだけでも、ただ甘いパンを食べるよりは良いだろう。子供時分に母がやってくれたように、半分に切ったグレープフルーツにナイフを入れて食べやすくして、傍らにならべる。当時は、グレープフルーツの果肉より、食べ終わりそれを絞ってジュースにして呑むのが楽しみだったが、息子はそこには興味がない。よって息子の分もジュースを愉しむ。
息子を学校に送り出し、こちらは折り畳み自転車に跨ってサンタゴスティーノまで走る。そこから中央駅まで15分弱地下鉄に乗り、特急でボローニャへ向かう。
ボローニャの劇場は、駅から歩けない距離ではないが、それでも歩けば15分程度かかるから、自転車を飛ばして5分程度で辿り着けるのは有難いし、今日のようにリハーサル前に、公園で譜読みの続きをして劇場に向かうとき等、便利この上ない。どういうわけか公園では蠅が煩くて、手で蠅を払いつつ、少し汗ばむ陽気の下カセルラを読む。
リハーサル終了後、ボローニャ駅から電車に乗り込むところで、息子に電話をして、家の近所のバールで待ち合わせて夕食を摂る。家に帰ってから料理をするより、早く食べられるし、息子を寝かせることもできる。
10月某日ミラノ自宅
マリピエロの6番交響曲は、一見とても単純そうな楽譜だが、演奏は意外なほどむつかしい。デキリコの所謂形而上絵画にそっくりで、形而上音楽とでも呼びたいが、書かれている音楽と演奏される音楽の間に大きな差異が存在する。
フレーズが4拍子だが、それを一貫して3拍子で書き、とても情熱的なフレーズの処理を、いともそっけなく捨置いたりする。こう書くと新古典期のストラヴィンスキーの難しさを想像させるが、随分視点が違って、別の厄介なのだ。
その上、技術的にも難しいので、2回目のリハーサルでは、楽譜に書かれた初演時の小編成の弦楽合奏から人数を大幅に増やした。少人数では音が潰れてしまうとコンサートマスターのエマヌエレから受けた助言に従ったわけだが、全くもって彼の言うとおりだった。少人数の方が小回りが利きそうだが、実際は逆で、寧ろ人数が多い方が複雑な音型はずっと楽に弾ける。その結果が、近代オーケストラ作品で、あれだけ複雑な音を書き込むようになった。
分かり易い例がマーラーやリヒャルト・シュトラウスのオーケストレーションで、あれにはやはり彼ら自身が指揮をしていた経験がそのまま反映しているのは誰の目にも明白だろう。ワーグナーの革命的オーケストレーションに至る過程にも、やはり指揮者としての彼の経験が活きていて、書く音と鳴る音の落差や、演奏者の皮膚感覚が見えてこそ、実現可能だったのではないか。
彼らの影響を強く受けながら、オーケストラを理想化して音を目いっぱい書き込んだのが、今回のプログラムで言えば、優れたピアニストだったカセルラだ。彼は確かに指揮もしたが、音楽家としての気質はやはりピアニストだったのだろう。理想化された形で音を定着しているので、それらの何をどのように響かせるか、演奏者は一つ一つ吟味する必要がある。丁寧に細かい音を聴かせたいと思えば、鈍重になる。それを避けつつ、書かれた音を出来るだけ聴かせたい、書かれた和音を出来るだけ聴かせたいと思うと、独奏者らとオーケストラとの間で非常にむつかしい匙加減が必要になる。オーケストレーションが厚いので、たやすく独奏者を覆い尽くしてしまうし、何しろ独奏者たちが弾きにくい。
三重協奏曲は名曲の一つで、特に二楽章の美しさは比類ない甘美さを誇る。誰でも一聴すれば、ラヴェルのト調のピアノ協奏曲の二楽章を手本に書いたように見えるが、ラヴェルがカセルラのこの二楽章を手本にピアノ協奏曲を書いたと聞いて愕く。そこではティンパニが薄くリズムを刻んでいて、ほんの少し強調して、と無理をお願いしたところ、独奏者にすぐに却下されてしまった。
この二楽章最後の部分のイングリッシュホルンを、奏者が何故かいつも演奏しないでこちらを見ているので、パート譜を確認すると、その部分はパート譜には書かれていなかったが何故だろうか。これが作曲者の意図かどうか定かでないので、この本番では演奏した。
楽譜が、演奏しづらく、読みにくいのは、作品がホ調で書かれているからに違いない。フラット系の調性へ読み替えてゆくときに、変へ調に読み替え、そこから転調してゆく。ホ調をナポリ調に置けば、変ホ調が基本調性になり、そこから平行調へ逃げれば、今度は変ハ調という実に読みにくく、鳴りにくい調性に容易に辿り着く。言うまでもなく、それをドミナントに変化させれば、そのままホ調に戻れるわけである。
基本的に、和音は調性に則り書かれているが、その上に載せられる旋律やフレーズは、敢えて調性を飛び越えて書かれているので、意識しなければ無調に聴こえる。
そうした楽譜ながら、しばしば楽譜に不備があって、一体何の音か分からない、臨時記号が不明な箇所がいくつか残ったが、それらはパート譜に書き込まれた訂正を参照した。
一つ一つ和音を吟味してゆくと、最終的には実に単純な和音構造が見えてくる。非常に引き延ばされた調性下部構造の上に、無数の多調的装飾を施してあるから、こうした上部構造、旋律に重点を置いて演奏すると、恐らく非常に複雑な音楽に聴こえるに違いない。オーケストラ自身もそうだろう。
併しながら、通常録音を聴くと非常に複雑に聞こえる箇所も、「この箇所、実はすごく分かり易い和音でしたよね。皆さんでこれらの音を聴き合って、浮きあがらせてくれませんか」と一言いうだけで、一瞬にして明快な響きにとって代わられる。調性は、音を互いにぶつけ合うと絶対に浮き上がらない。
一方で、マリピエロは基本的に東洋旋法などを多用するから、エキゾチックな響きにはなるが、第6交響曲の四楽章に顕れるに日本的な旋律は何をあらわすのだろう。カセルラは明らかに古典的なソナタ形式を拡大しているが、マリピエロは、それも順番を入れ替えて重力、方向性を分散している。
併し実際演奏してみれば、実に情熱に溢れた音楽であることがわかる。1946年に書かれ、旧き思い出に捧げられ、曲尾に蜃気楼のような葬送行進曲が浮き上がるさまから察するに、やはり大戦と関係あるのだろうか。
10月某日 ミラノ自宅
ボローニャの演奏会が終わって、ミラノで研鑽を積んでいる久保君と浦部君の曲を演奏するためにジェノヴァを訪れ、東洋文化研究所でマッテオとカルラと日本音楽に於ける「間」についてコンフェレンスに招かれた。
日本の「間」こそが「日本音楽に於ける特徴で、そこには西洋にはない美意識が働き」、「沈黙に深い意味があり」、「日本文化における特徴的な時間感覚は、禅など仏教思想と繋がっている」。
「どうですか」と尋ねられ、「まあ日本にも色々な人が居ますから」と応えると少しがっかりした顔をされる。イタリアに25年近く住む日本人に、日本の「間」について尋ねるところが間違っている。せめて禅寺の近所に住む日本人なら、もう少しは気が利いたことを答えてくれるかもしれない。
関ヶ原の戦いの後首を刎ねられた、熊本の小西行長の没後わずか7年の1607年、殉教者小西を讃える音楽劇「Agostino Tzunicamindono Re Giapponese アウグスティヌス・ツニカミンドノ 日本の王小西行長」が上演されたのがジェノヴァだった、などと言おうかとも思ったが、話が脱線してややこしくなりそうだから、黙っていた。ジェノヴァに招いてくれたマッテオの母親は、東洋文化の研究者だった。
10月某日 ミラノ自宅
ジェノヴァは、古のジェノヴァ共和国の隆盛を偲ばせる豪奢な建物と、娼婦が寂れた玄関先に立つ港町の顔が同居していて、ミラノにもないほどの巨大な銀行の裏に、昼間娼婦が立つ。普通であれば、娼婦が立つ路地と銀行街は別の界隈にあるものなのだが。ジェノヴァの娼婦は昼に春を鬻ぐが、これも他ではあまり見られない光景だろう。普通は、夜の帳とともに街角に女が立つ。
この街が戦後本当に貧しかったころ、ジェノヴァの主婦が春を売って生計を立てていた名残だそうで、近年はアフリカや東欧の女性が立つようになった。尤も足繁く通うのは、船乗りなどより、妻に先立たれた近所の老人ばかりだ、とステファノが苦笑いした。「ジェノヴァ人の性格は」と尋ねると、「性悪なこと」と言って大笑いした。
10月某日 ミラノ自宅
スカラ・アカデミーのフランチェスコが、突然メールを寄越す。ジェノヴァのコンフェレンスの内容について興味があると言う。彼はアカデミーの主管を務めつつ、ボローニャ大に提出する日本音楽に関する論文を準備していて、例の小西行長の音楽劇やら、ミヒャエル・ハイドンの高山右近「右近殿」をモーツァルトが聴いて、それが「魔笛」に影響を与えた可能性の話やら、正倉院以前の伝統音楽や、宣教師のキリシタン音楽が邦楽に与えた影響も話題にのぼった。能とギリシャ悲劇との共通点や、雅楽や舞楽が現在までどれほどシルクロードの影響を色濃く残しているか、日本文化がどれだけ神仏混淆の結果培われたか話す。
とどのつまり、日本にも色々な人がいる、という至極当然の内容に帰結する。彼はスカラのアカデミーに務めているだけあって、蝶々夫人以前のジャポニズム劇に焦点を合わせたいと思っているようだったが、プッチーニの関わりで言えば、例えば彼は中国民謡「茉莉花」を使ってトゥーランドットのlà sui monti dell’Estを書いたけれど、あれが明清楽として長崎民謡になっていると知ったらどうだろう。それでも日本文化の特質は「間」だと言い続けるのか。それとも明清楽は流行歌だから日本文化ではないとされるのか。
そんな流れで久しぶりに落語「らくだ」を見て、こんなに笑ったのは久しぶりというほど笑う。例の死んだらくだが明清楽のかんかん踊りをする下り、あれこそ日本文化の真骨頂ではなかろうか。同じ話をヨーロッパ人にしても、宗教観、死生観がまるで違うから、多分本来の笑いは共有できない気がする。
10月某日 ミラノ自宅
サックスの大石くんと和太鼓の辻さんのための新作。
夏に安江さんと加藤くんのために書いたピアノとグロッケンシュピールのための小品は、オラショがグレゴリオ聖歌の原曲「Gloriosa
domina」に、グロッケンシュピールは「Dies irae」に変化しくものだったが、それと同じことをこの編成でもやってみる。
ねんねしなはれ 寝る子はみじょか 起きて泣く子は つらにくい
あらよ つらさよね 他人のめしは おれはなけれど のどにさす
しっちょこまっちょこよ 酒屋の子守り 酒ばのませて 歌わせて
あめがた にいほお 寝せつけた
大山ぼたん鉱 磯辺の千鳥 日暮れ 夜暮れは 泣いて 暮す 指をくわえて 角に立つ
書き採った歌詞は、或いは間違っているかもしれない。16歳になった少女たちが三年間無償奉公させられた、長崎福江藩の三年奉公の悲しみを歌う「岐宿の子守唄」は、長崎生月島のオラショへ変容する。
参ろうやな 参ろうやな パライゾの寺に参ろうやな
パライゾの寺と申するやな 広い寺と申するやな 広い狭いはわが胸にあるぞなや
しばた山 しばた山 今は涙の先なるやな 先はな 助かる道であるぞなや
この旋律からは、思わず柴田南雄さんの「宇宙について」を思い出す。その歌詞に導かれ、旋律は次第にグレゴリオ聖歌の葬送歌「in paradisum」へと変容してゆく。
In paradisum deducant angeli. in tuo adventu suscipiant te martyres.
天国で迎える 天使たちが。 お前をみちびく 殉教者たちが。
et perducant te, in civitatem sanctam Jerusalem. –
お前を迎える 聖なる街エルサレムに。
Chorus angelorum te suscipiat.
天使たちの歌声が お前をみちびき
et cum Lazaro quondam paupere aeternam habeas requiem.
貧しかったラザロと お前は授かる 永遠の安息を。
10月某日 三軒茶屋自宅
高橋悠治演奏会終了。アンサンブルで一番演奏が難しかったのは、「タラとシシャモ」だろう。予想通りではあったが、しかし悩めば悩むほど音楽は深まってゆく。決して不毛な悩みではなく、掘下げる痛みのようなもの。ドレスリハーサルのときに、悠治さんは、変な曲だと笑っていらしたが、実に美しい名曲だとおもう。今まで演奏されなかったのは実に勿体なかった。
「フクシア」も「石」も、演奏者が朗読してから弾くだけで、音楽が変化する不思議。朗読は聴き手のためのものであるはずだが、言葉は読み手の体内にも深く潜りこむ。
意外な効果があったのは、「ローザス」で、当初増幅しないつもりだったが、急遽有馬さんにお願いしてセットを組んでいただいた。楽譜には残響をつけるように指定があるが、当日のリハーサルで、左右両方のスピーカーに出していた残響を左スピーカーのみに限定し、右スピーカーからは残響なしの音を流すことになった。ものすごく据わりが悪く心地悪い音響なのだけれど、予定調和を逸したこの不安定さが悠治さんの意図だった。だから、次回もし演奏するときは、また違う不安定さを探す必要があるだろう。尾池さんの、あくまでも自然な演奏姿勢も、この曲にはとても合っている。
「石」で悠治さんが拘ったのは、最後の6音だった。実際山澤くんは、本番途轍もなく繊細な、信じられないほど神秘的な音を出した。演奏会後、偶然出会ったIさんから、「石」の最後の音は、物凄く美しかった、と指摘されたので、こちらが愕いてしまった。
家人の「メタテーシス」は、ずっと家で練習しているのが聴こえていたので、長いスパンでの大きな変化に愕いた。指で音を拾っている段階と、たとえ音を外してしまっても耳で弾く段階になると、音楽の深みがまるで変化する。当初はまるでクセナキスのように感じられる音群は、実際楽譜をよく読めば、音の選び方、ピアニズムは、近作と全く変わらないことに唖然とする。
それどころか、使っているフレーズすら、近作に酷似していたりするのである。ただ、その定着方法は違うし、密度も違う。フレーズはフレームを取っ払われ、広い空間のなかに自然体で置かれる。だから、これだけ密度が高い音楽であっても、最終的に必要になるのは、フレーズや音色や強弱であり呼吸なのだった。家人の本番の演奏は、その辺りを特に意識させるものだった。
野趣あふれる「ニキテ」は、思いの外演奏家が喜んで演奏に参加してくれた。棒の先に蓄えられた和幣を震わせ、小石を叩きながら、草を踏み、野を駆けぬける。森のなかを風が吹き抜けてゆく音が聞こえ、時に全員で耳を澄ます。とても素朴な音楽の喜びを改めて実感した。個人的には、女性二人の溌溂とした音に目が覚める思いだった。
「般若波羅蜜多」は、ドレスリハーサルで悠治さんが全員を一列に横並びにしたのが、実に効果的だった。音はよく通るようになったし、何しろ寺の楽師像のような姿を顕すことで、彼らの姿が神々しく感じられた。本番中は一人一人がそれぞれ大好きな仏像に見えて仕方がなかった。
特に経典を演奏している積りはなかったが、それでも無意識にそう感じられたのは、波多野さんが菩薩のように見えたからか。
演奏会後、打楽器の會田くんから頂いたメール
「プログラムの悠治さんが訳された般若波羅蜜多の訳詞が、まさに悠治さんの哲学を表していると感じ、なぜか涙が溢れました。「空」であること、往ける人たちへの思いが感じられました。きっと秋山邦晴さんやそのほか彼岸から聞きに来てくださった方もいらっしゃったと思います」。
10月某日 三軒茶屋自宅
静岡のリハーサルから戻り、松平頼暁さんの声楽作品を聴く。ちょうど「だんじく様の歌」や「ぐるいよざ」など、最近使ったばかりのオラショの旋律が何度も表れ、はっとする。
悠治さんが、枠組みを外して空間のなかに放ったとすれば、松平さんは、まるでコマ録りのアニメーションのように、何度も少しずつ変化させつつ、ひたひたと繰返してゆく。
(10月31日 三軒茶屋にて)