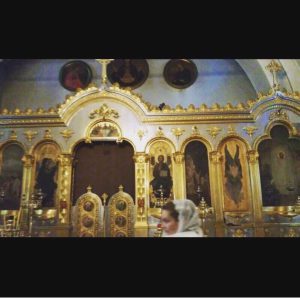大雪注意報中、クリスマスイブにプレゼントを急いで買った帰り道に、車のラジオから昼という時間帯には珍しくレッド・ツェッペリンのStairway to Heavenが聞こえた。車の窓に大きなスノーフレークがぶつかった瞬間がスローモーションで見えた。溶ける直前の雪の結晶の形ははっきりしていて、窓にぶつかった時に音が聞こえた気がした。信号待ちの車の中で青森県でしか見たことがない大きなスノーフレークが窓にぶつかる瞬間をずっと見届ける自分が虚しくなった。「命」も「自由」もなんて、こんなもんだ。「祗園精舎の鐘の声、 諸行無常の響きあり。娑羅双樹の花の色、 盛者必衰の理をあらはす」。平家物語とレッド・ツェッペリン、仏教徒とキリスト教、人類の歴史と未来、全てはこの溶ける雪結晶の美しさにあると思った。
今年のイブとクリスマスは大館の正教会で過ごす予定だったが、体調がすぐれず叶わなかった。100年以上前の小さな木造の教会に、日本で初めて女性としてイコンを描いた山下イリナのイコンがある。私と同じ名前、イリナ。彼女が描く光の優しさに出会ってから私の心はますます素直になった。タルコフスキーの映画、『アンドレイ・ルブリョフ』を思いだした。人間とはイコンのようなイメージを追いかけないと。大館の北鹿ハリストス正教会の中に入ると、いつも祖父母の家に戻る気がする。中から見える円屋根の青の色合いと山下イリナのイコン、日本まできて全てが繋がった。
クリスマスの時期の思い出があまりにも重くて身体が真っ直ぐ立てない。ライダ・レルチュンディ監督の映画「Autofiction」の中で、ずっと横になって、動く時に這う女性たちの身体を思い出した。これでもどこから来るのかわからない優しさを感じた。突然ルーマニアから電話した弟の声が、昔と同じように私を癒す効果があった。そういえば、昔から弟の優しさに救われる自分がいた。
当時、高校生になった私が「家を出る計画」を考え始めた。それは、団地のアパートから、父の暴力から、家族のドラマから逃げたかったのだ。「私がいなくなったら」みんな反省すると思った。みんな、もっと幸せになると思った。私を探す両親を想像しただけで嬉しくて、そしてきっとこれをきっかけに仲良くなれると思った。なので、何日も何回も逃げる作戦を想像した。この団地も、いつも追いかける野良犬も、高校のクラスメイトも私を探し始めるが、私はこの街から消えた不在な存在になるというイメージがしばらく頭から離れなかった。問題は優しくしてくれた弟と祖父母に会えなくなることだった。これに悩んだ。
しかし、弟はある日私の想いが伝わったように、彼のクラスメイトが逃げた話をし始める。彼女も父親の暴力が嫌だったので家を出るが、結局のところ西ヨーロッパのどこかで売春ネットワークに捕まって身売りされ、そこからやっと逃げて恥を忍んで家に戻ったという。この話を聞いて家出は諦めた。それは、1990年年代のルーマニアを生きていた私が、状況の全てを把握しきれない状態だとわかった瞬間だった。当時の人身売買組織、臓器売買の社会問題と自分の身体の危機に気づいた。このタイミングで家から逃げたら違う地獄が待っているのだ。弟の目の青い色合いが、イコンで描かれている青に似ていると今気づいた。彼は子供の時から特別な力を持っていた。彼が女の子、私が男の子で生まれてくればよかったのに。
こうして、私の家出計画は終わりを迎え、高校2年生の夏休みに、ルーマニア北部にある古い修道院を訪ねる旅行に参加した。バスに長い時間乗って、団地の暗い雰囲気から解放された旅になった。ルーマニアの自然に溶け始めたころ突然バスが止まった。二人のヒッチハイカーが乗ってきた。それは若いフランス人男女だった。話を聞くとカップルではなく友達同士で、当時のフランスで人気の旅行先だったルーマニアにやってきた。彼らは私にとって初めて会う外国人だった。男性が私を見つめ始めた。やつれた私の顔はどこが魅力的だったのかわからないが、目が会うたびに何か不思議な優しさを感じた。でも、彼はもう少しでバスから降りてまた旅をする。二度と会わない一瞬の悲しさを感じた。彼の名前は覚えてないが、リヨンという街の出身なのは覚えている。しばらく目で話した気がする。「あなたを助けてあげるよ」というふうに聞こえた。バスがまた止まった。彼は急いで紙にリヨンの住所と電話番号を書いて私に渡した。一緒に旅行していた先生と学生が笑いはじめた。ナンパされたと私をいじるけど、彼が降りた後、小さな包みを開いて鉛筆で薄く書いてあった知らないリヨンという街の住所が恋しくなった。彼に手紙を書くことはしなかったが、世界が広いと初めて分かった瞬間だった。
私にとって、ルーマニア北部の修道院を訪ねる旅がしばらく続いた。印象的だったのはボロネツ修道院だった。この教会の壁は特別な青で描かれていて、世界中から芸術家がこの色を生で見るため集まってくる。私もしばらく言葉を失った。西の外壁のフレスコ画の「最後の審判」のイメージをみた瞬間に自分の中で何か変わった。南にある地獄、北にある天国、天使と悪魔の戦い、人々の魂はどこへ行くのか。でも描かれているシーンの激しさよりも、人と神、聖人と天使、悪魔と大きな魚に乗っているモーゼ、悪魔と人の魂の間に広がる青の色合いが目に染みる。人が文字を読めない時代にイメージでイコンと教会のフレスコ画によって、聖書の言葉の全ては伝わっていた。空よりも、周りの木の緑よりも、神秘的な色を生み出す心が人間に救いを与えると感じた。「ボロネツの青」はどうやって作られたのか未だに知られていないが、直に見るこの色合いが、遠い未来に人間がいなくなった時でも、人間がどんな生き物だったのかわかる気がした。魂の色合いがこの青だ。
ボロネツを離れたバスは、モルドバ地方からマラムレシュ地方に向かった。サプンツァ村にある墓地を訪ねた。それは陽気な墓(Cimitirul Vesel)という名所だ。この墓の十字架に、故人の絵と彼らの人生をコミカルに表現した詩が書いてある。例えば、「私の義母がこの重い十字架の下に休む。もう三日生きていれば、この下に眠るのは彼女ではなく私で、この詩は彼女が詠んだだろう。あなたたち通行人は彼女を起こさないように。また何かやかましく言われても、私にはどうしようもない。この詩を読んでいるあなたが私みたいになりませんように。良い義母を見つけて一緒に平和に暮らせますように。享年82。」
あの時、このような詩を沢山読んで、泣き笑いという複雑な現象が自分の身体に起きた。その時まで感じた生き辛さが消えて、どんな状況でも生き続けることを決心した。そしてたくさん笑うと決めた、最後の最後まで笑うと決めた。死が笑いに変わる瞬間が必ずあると分かった。ブランショがいう「jouissance」が私の中に目覚めた瞬間だ。この間、青森での調査の中で辛い半生を生きた私に、キーインフォマントの女性が言った同じような言葉が浮かんだ。彼女にはどんな恐ろしいことが起きてもいつも踊ったり、笑ったりする力が浮いているという。「私たちは似ている、同じ自由人だ」と彼女に言われた瞬間、救われた。
そう、笑うこと、「腹を抱えながら笑う」という瞬間が必ず訪ねてくる。それは東京に住んでいた時、私が世界で一番尊敬しているダンサー、田中泯さんの舞踊団に入っていたころの、人生で一番刺激を受けた時期だった。ある日、4人一組で踊りを作り、私は元社会主義国からきた一員として、フレームに入らない人々、はぐれるという踊りを考えて、他の人々から暴力を受け、最後に舞台から投げられるというシーンを作った。そしたら、泯さんが私たちのパフォーマンスを見て「最後に立って笑うのよ」と言われた。そうだ、人生で最高のアドバイスを受けた。
さて、高校生の時のルーマニア北部の旅行から団地と工場の街に戻ったあとは、もう家から逃げることを考えることはなくなった。図書館から何十冊もの本を借りて、田舎に戻って、祖父母の家で本を読み続けた。あの時に庭のクルミの木の下で読んでいたカミュの『ペスト』は、今を生きる世界とあまり変わらないが、あの時期に自分の中で目覚めたjouissanceのおかげで泣きながら娘たちと笑う自分がいる。そしてすっかり娘たちにもこのjouissanceが受け継がれた。いつか、娘たちにボロネツの青を生で見せたい。色の感覚が鋭い長女のリアクションが目に浮かぶ。
大学に通うためブカレストに引っ越したときある展示を見に行った。それは人身売買された若いルーマニア女性の写真展だった。金髪で、青い眼、東ヨーロッパの娘たちのライフヒストリーと共に、彼女らのイメージはどこかイコンのようだった。彼女らも14歳の私みたいにただ逃げたかった。暴力から、貧困から、全てから。そして逃げた先には違う地獄が待っていた。でも、写真に残っていた彼女らの美しさが、私に何かを訴えるようだった。私の方が確かに恵まれていた。大学に行けるなんて、勉強し続けるなんて、恵まれている方だと分かった。だからあの時に私は博士課程まで上がりたいと決心した。そして世の中の何かを変える、どんなに大変でも、どんなに苦しくなっても、単純なことだけどみんなやればいいだけの話、自分のできる範囲で。
先日の女性の調査の中で友人の個人史を聞く機会があって、思いもつかない事実に出会った。子供の時から才能に溢れ、絵がとても上手い天才のような彼女が、高校の時にいじめにあい、傷ついたまま社会に出て職場でのいじめにも耐えられなくなって、ある日自殺を図った。手首を切ると痛みがあって、薬を飲む。幸い母親が帰宅し、病院に連れて行く。1ヶ月間の入院で彼女は人間の地獄を見る。さまざまな出会い。統合失調症で入院している、毎日ばっちりと化粧するお河童頭の女性には「愛している」という声が聞こえるそうで幸せそう。ずっと忙しくしていたサラリーマンは、退院したらまた編集者として頑張るというし、自分のところで雇うと言い出す。同じ病室に入院している叔母さんたちは、血圧が400と笑いながらいうような毎日。
そんなある日、同じ20代の女の子といつも通り話をする。その子はそろそろ自分の病室に戻るといい、外を出た途端に何か大きな音が聞こえる。誰かの叫ぶ声。病室から出ると、さっき部屋を出て行った女の子が窓から飛び降りたという。次の日、何も変わらない。看護師さんは相変わらず忙しく動き回り、統合失調症のお河童頭さんには相変わらず愛されているという声が聞こえ、サラリーマンの男性が早く退院して仕事がしたいといい、同じ病室のおばさんたちは血圧を測って「また400だと、ハハ」笑う。その時、友人は悟った。こんなに身近に人が死んでも何も変わらない。「私が死んでも何も変わらない」。死んでも何も変わらないのであれば、生きて世界を変えよう。