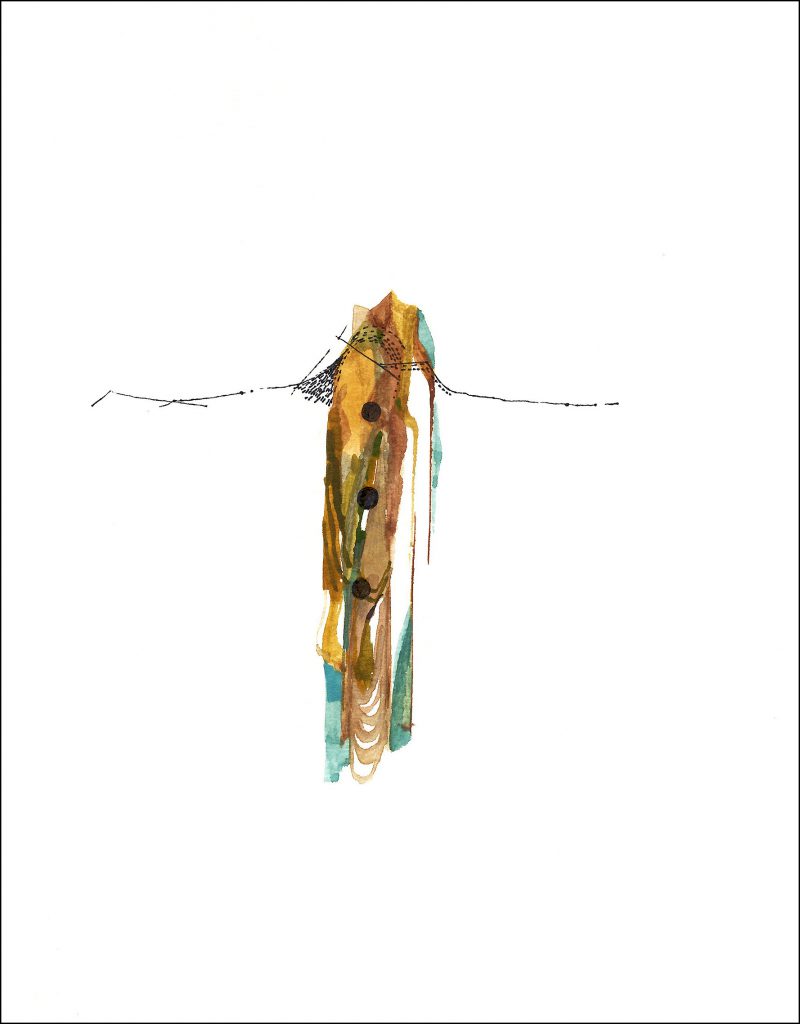この街を選んだ理由はとくにない。6年前、不動産屋のお兄さんに紹介されたアパートは車も入れない小道の奥にあった。玄関には夾竹桃やよくわからない植物がもっさりと茂っていて、辺りの薄暗く陰気臭い雰囲気に少し警戒したけれど、裏手にある共用のベランダにまわったとき、目の前に広がる桜の木々を見て、即座にこのアパートに住むことを決めたのだった。肌寒いあの日、桜の葉がゆるやかな風に乗ってさらさらと散り、夕陽で黄金色に輝いていたのを今でも覚えている。
そして現在、私はこの部屋を出ようとしている。夏は大音量の蝉の声、秋は鈴虫、冬は枯葉の滑る乾いた音、そして春には怖いぐらいに乱れ咲く桜。それらとお別れすると思うと、素直に寂しい。案外自分はここをかなり気に入っていたのだと今更ながら気づく。それなのに、もうここにいてはだめだと感じていて、はやく移動しなければ、と焦っている。行き先も決まっていないのに、この感覚はどこからきているのだろう。
引越しを決めてからは、掃除をしながら今後必要なものとそうでないものを仕分けている。が、とにかく自分が所有しているものの多さに呆れかえっている。これは必要なもの、要らないもの、燃やしたいものと判断しながら、同時に自分にとって本当に大事なものはあるのだろうかと、もはや投げやりに近い妄想をしはじめ、気づいたら一日が過ぎようとしていた。
分子の集合体である物質に記憶やそのほかの何かが入り込み、それがただの素材ではなく、いつのまにか取り替えのきかないものになる。自分にとって何となくそうゆうものはある気がしている。でも、これだと言い切れるものはない。一体まわりの人は何を大事にしているのか。そもそも、そうゆうものがあるのか?と妙に気になりはじめた。
友人である中野さんに大事なものは何かと聞くと、“リコーダー”と答えが返ってきた。彼女とは4、5年ほどの付き合いになる。本作りの仕事で知り合い、いつの間にか飲み友達になった(毎回ついつい夜遅くまで飲みすぎてしまう)。プライベートではギターで弾き語りをし、春になると全国をまわっている彼女がティンホイッスルを吹くことも知っていたけれど、リコーダーの件については初耳だった。
1DKの眺めのよい中野家で赤ワインを飲みながら、彼女のつくったトマト煮込みやポテトサラダ、イチジクをつついていたときのことだ。どんなリコーダーなの?と聞いたとき、私は脳内に1本の笛みたいな物体をもわもわと浮かべていた。ところが彼女はそのことばを聞いたとたん、部屋の各所から次々とケースを取り出してくる。押入れの引き出しやその奥から、本棚の隅から。その動きのすばやさに吃驚する。クライネソプラニーノ、ソプラニーノ、ソプラノ、アルト、テナー、バス、そのほかティンホイッスルや知らない楽器もちらりと見える。リコーダーのケースがコンパクトだからか、まるで部屋中に武器を仕込んでいるような所有の仕方にげらげらと笑ってしまった。笛だけで20本はあるに違いない。
それぞれのケースを開けてもらうと、木製のつやつやしたリコーダーが分解されて入っている。美しい。中野さんはリコーダーを一つ一つ組み立てながら、小学校のころ、リコーダー部に入っていたときの話をしてくれる。教室の隅っこでこっそりリコーダーを吹く子だったらしい。こっそり吹いている感じがなんとなくどころか、すごく想像できる。
全て自分で揃えたものなのかと尋ねると、自分で買ったものと贈りものがあるそうだ。好きと言うと各方面から集まってくるのはよくわかる。私もそれには心当たりがある。ウイスキーだ。自分の大事なものとして挙げるのは違う気がするけれど。
組み立てたリコーダーをひとつずつ吹いていく酔っ払いの中野さんを眺めながら、赤ワインを美味しく飲む。0時をまわり、わたしはすっかり終電を逃していた。