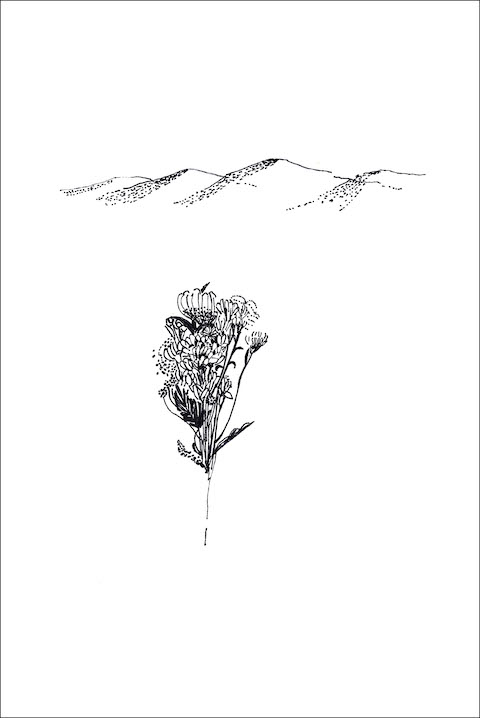巷で「断捨離」という言葉をしばしば耳にするようになりました。特に物欲があるのでもなく、趣味らしい趣味もなく、不要物など捨てるよう常に心掛けていても、少しずつ家に物が増えてきました。ただ最近では、それは自分が音楽を生業にし、生きてゆく上で、過去から連綿と続いてきた時間の重さを、誰かがそれとなく教えてくれているようにも感じるようになってきました。
—
1月某日 三軒茶屋自宅
元旦、珍しく家族揃って町田の実家で朝を迎えた。目が覚めると、子供の頃から使っていた黒漆の重箱と屠蘇器が食卓に用意されていて、息子がさも嫌そうに屠蘇を呷るのが愉快だ。そうして、揃って幼少から食べつけた大根のみの雑煮を食べる。
昔はこれに巾海苔をかけて食べたが、何時しか巾海苔も手に入り辛くなってしまった。この雑煮は元来網元だった湯河原の祖父の処で食べていた。
日は既に沈んでいたが、元旦の晩少し時間もあり、ちょうど湯河原を通りかかったので、思い切って家人と二人で祖父母の墓前に駆け付け、線香を焚き手を併せた。流石に店はどこも閉まっていて、仏花は買えなかった。
英潮院に届く吉浜の波音が心地よく、顔を上げれば満天の星が輝く。日暮れ後に墓参するものではないと言うが、何時でも出かけられるわけもなく、幼少から通い馴れた墓だからと許してもらう。尤も、家人が電灯を照らしていなければ、漆黒に月明りだけでは石階段の足元も覚束なかった。
1月某日 ミラノ自宅
息子に付添ってノヴァラに出かけた際訪れた、分割主義(divisionismo)展覧会に強い衝撃を受けた。以前から興味があった社会派の画家モルベッリ(Angelo Morbelli 1853-1919)の、ミラノの回顧展に行きそびれたから足を運んだのが切っ掛けだったから、当初分割主義そのものには興味はなかったが、実際に眼前で彼らの作品を目にして、鳥肌が立つほど強く心を動かされた。
モルベッリの作品は、写真でしか見たことがなかったので、実物にこれだけ感動するとは想像していなかった。モルベッリだけではない。セガンティーニ (Giovanni Segantini 1858-1899)もロンゴ―ニ(Emilio Longoni 1859-1932)もフォルナ―ラ(Carlo Fornara1871-1968)も、写真からは到底想像できない筆致の瑞々しさと生命力に圧倒された。
ただ、写真と実物の印象がこれだけ乖離した体験は生まれて初めてで、すっかり当惑してしまった。実物を見て改めて写真で鑑賞しても、やはりさほどの感動は蘇らない。そこに興味を覚えて、数日後また息子を連立って展覧会へ赴くと、やはり実物に刻み込まれた筆致の一つ一つは、そのまま身体に響いてくるようである。
当世流行りの三次元絵画などより、手で書き込まれている分、妙に生々しい。以前から特に愛好していたボッチョーニ初期作が生まれる源を目の当たりにしているのだから、興奮せずにはいられない。
分割主義はスーラの点描画法に似て非なるもので、フランス新印象派の点描画と比較すると、そこには音楽、料理、言語、全てに共通する、近くて遠い伊仏文化の差異が明確に浮彫りになる。
女性の社会進出や識字率向上、貧富格差への社会批判など、分割主義の作家が好んだ主題もフランス印象派とは一線を画すが、何より印象派一般の風景が浮き上がるような効果と、分割主義者らの風景をカンバスに刻みこんでゆく効果は、ほんの少しゴッホを思い起こすところもあって、寧ろ反対の印象さえ受ける。今改めてイタリア印象派と呼ばれるマッキア派(macchiaioli)の作品を眺めれば、何か違った印象を持つかもしれない。
分割主義からは、イタリア統一運動に寄り添うヴェルディの触感はもちろん、蓬髪派(scapigliatura)に参加したクレモナ(Tranquillo Cremona 1837-1878)に端を発して、同じ蓬髪派だったボイトの世界観、ヴェリズモオペラの誕生に至るイタリア近代音楽史にまで思いを馳せることができる。
あれだけ丹念に一本ずつ書き連ねた光線に至っては、やはり写真では絡み取ることができないのだろう。
1月某日 ミラノ自宅
アルフォンソよりメッセージが届き、「天の火」のDVDが出来たと聞いて、少々愕いてしまった。
この曲はアルフォンソも親しかったフランコ・モンテヴェッキ(Franco Montevecchi1942-2014)が亡くなった折、彼と残された夫人のために書いたのだが、フランコは裕福な家庭の生まれで、音楽にも幼少から親しんでいた。彼の母親はピアニストだったから、家には旧いスタンウェイが残っていて、フランコ自身もピアノをよく弾いた。
そうして晩年までミラノとトリノの工科大の教壇に立ちバイオエンジニアリングを教えていたが、数年癌で闘病したのち亡くなったのは2014年だったから、もう五年が過ぎたことになる。彼とミーラ夫人は、工科大近くに大きな邸宅を構え、そこで演奏会も何度となく開いていたが、残されたミーラは自分には広すぎるからと、昨年暮れ近所の小さなアパートに引っ越した。
そうして以前の邸宅に残っていた家具の多くを、ちょうど昨日、ミーラや生徒に手伝ってもらい、拙宅に運びこんだところだった。だから、アルフォンソからの便りに吃驚したのだ。
どの家具も元来フランコの家から受継いだもので、ミーラとフランコに子供がいなかったので、拙宅へやってきた。
どれも1900年かそれ以前のものらしいが、詳細はわからない。ただ、現在の家具と違ってそれぞれ強く主張し、個性的な存在感を醸し出している。それらが置かれていた以前の家は、寧ろ実にモダンな造りで、地下室の天井も一面ガラス張りだったが、消防法に抵触するから、売却するため天井もすっかり造り替えられ、演奏会やレッスンに使った、光が差しこんでいた地下の広間は、夜のように真っ暗だった。
この家で、友人たちとアンサンブルを練習を始め、何度となく試演会を開き、友人を招いては少しずつ活動を広めていった。フランコは家人のピアノが好きで、何度も演奏会を開いてくれ、フランコは最後まで彼女のCDを喜んで聴いていた。
真っ暗の家を出る時、ミーラが「Ciao! Casa! サヨナラ!家さん!」と声を掛けていて、流石に胸に込み上げてくるものがあった。
この家具を受け入れる用意をするべく数日間家の整理をしていると、「坊ちゃんのご誕生おめでとう!!洋一くんが僕んちに来てたときのことを思うと、夢のようですね。お母さんになった方ともどもお大事にね。幸せを祈ります。僕は今夏ここで静養しています。軽井沢 三善晃GIAPPONE」という端書きが出てきた。懐かしく読み返していて、ふと気が付くと、その日がちょうど三善先生のお誕生日だった。
年始に荻窪のお宅に伺ったとき、由紀子さんが留学中に同宿していたルーマニア人に教わったというカリフラワー煮込みと、彼女のお父上のチェコ土産のシェリーグラスで、美味のシェリーを振舞って下さったのを思い出す。それどころか前回に等しく、先生が使い残した五線紙と、宗左近さんから贈られた古い蕎麦猪口二客迄いただき、甚だ恐縮する。
ほぼ酒もやらず骨董のコの字も分からない輩には、猫に何某、豚に何某だが、もう何年も肉も食べていないから、そこだけ先生に近づいたかもしれない。先生も滅多に肉は召し上がらなかったと、亡くなった後で由紀子さんが教えてくださった。頂いた端書きを、四客の猪口の下に飾る。
1月某日 ミラノ自宅
林原さんから借りたヘルゲルの「日本の弓術」は、実に含蓄に富む。日本文化をヨーロッパ人が理解するためには、かかる噛砕いた説明が必須であって、ならば逆もまた然りかもしれない。
ヘルゲルは我々と正反対の疑問に苦悩していて、合点がゆく部分もあり、不思議でもある。
自分と音の間に空間があって、そこに感情を込めると音は鳴らないし、輪郭も曖昧になる。クラシック音楽は、西欧の構造やその階層に則って構成されているためか、ほぼこの傾向にある。
我々日本人の特質として、一音入魂が生来備わっているのは、ヘルゲルから見ればどれほど羨ましかっただろう。無になること、無心になること、これは西洋的に考えれば、一音入魂してそこに同化している状態かもしれない。確かにその特質こそが邦楽の美学の礎となっている気もする。
そう考えれば、感情から発音された楽音では、全体を構造的に構築すべき西洋音楽には、表現手段として向かないのが理解できる。音一つ一つが意味を持ちすぎて、文章にならないともいえるし、一語一語が本来それぞれ繋がりたいと欲しても、完結した感情通し関連できないのかもしれない。
それとは別かもしれないが、日本人であろうとイタリア人であろうと、気持ちが先走って音がすくむとき、ちょっとした切っ掛けで視点が変わって、まるで頭にぽっかり第三の眼が開いたように耳が開くのは何故か。自分と音との間に感情の澱が淀んでいなければ、発音された空間の向こうで、気持ちは自然にすっと響きに入り込み、聴き手までそのまま飛んでゆく。
学生たちの耳の訓練も長く担当しているが、そこでは、音を耳で聴かずに、気楽に目で音を見るよう口を酸っぱくして教える。耳で聴いていると、集中するほどに、それは脳が自分に読み聞かせる音となり、現実と相容れなくなる。発音の前に気持ちで押し出すと、脳内の音に気持ちが籠るだけで、現実の音には反映されないのかも知れない。
余程馴れてない限り、楽譜に書かれていることを正しくやろうとすればするほど、音は表情を失ってゆく。正しい音楽など本来存在しない筈なのに、それを求めようとするからか。
人それぞれ話す言葉も使う語彙もイントネーションも違うが、最低限の文法規則は守って話しているのと同じで、音楽上の文法さえ間違えなければ、話す言葉はそれぞれ違ってよい筈だし、誰かの真似をしても、それは似非音楽に終わるだろう。我々素人が正しい日本語を話そうとすればするほど、自らの感情から乖離した、規則的な別の言語になってゆくはずだ。
西洋音楽上の文法とは、音楽を構成する各要素を、順番を間違えずに階層状に並べてゆくことではないか。一番下に構造があり、その上に和声があり、その上に旋律があり、フレーズがあり、強弱や音色などがその上にあるべく、バロック期から後期ロマン派まで、一貫してこのヒエラルキー構造を保持してきた。
例えば、構造上にそのまま強弱を載せれば、強弱に幅がなくなる。強いか弱いか、その程度の意味しか為さないので当然だろう。実際は構造と強弱の間には、さまざまな層が複雑に入り組んでいて、その上に強弱が載っているから、一つとして同じ弱音も強音もない。
一切の強弱の記号を排し、書かれた音を繰返し吟味した後で、その上に載せられた強弱と対峙すれば、より積極的に強弱記号と向き合うことができる。古典派のごく簡潔な指定にも、ウィーン後期ロマン派の一見不可思議な指定にも、同じ姿勢で向き合えるはずだ。第二次世界大戦とともに、かかるヒエラルキーは崩壊したとも言えるが、連綿と継承してきた音楽形態で演奏する上に於いて、本質的にあまり変わっていないようにも見える。
そのようにして楽譜を勉強した後、では自分がこの楽譜からどんな風景を、どんな色を、どんな匂いを感じ、表現したいと思うか。音符から頭が離れて、自分の世界を映し出した途端に、溢れるようにそれぞれの個の言葉を話し始める。それは本人にも他者から見ても不思議な光景で、何故かと問われても、何が起きているのか尋ねられてもよくわからないが、ともかく楽譜から音が解放される様は詳らかになる。
たとえば、先日もベートーヴェンの交響曲一番第一楽章の勉強を始めた二人の生徒に何を表現したいかと尋ねると、一人は自分が住んでいるヴェローナからミラノまで、18世紀風の汽車に乗りながら車窓に眺める風景(実際その時代未だ汽車は通っていなかったが)と言い、もう一人は、自分の住むノヴァラの市民を沢山載せた大きな現在の汽船が、河で火災を起こして人々が逃げ惑う姿だと言う。
因みにその彼曰く、二楽章は光景こそ浮かばないが、一面銀色か黄金色に耀いていると言うので、哀れなノヴァラ市民が昇天し後光が差す様なのか、と皆に大笑いされていた。ベートーヴェンの一番で、かような想像は普通は出来ないが、奇天烈であればあるほど、寧ろ強烈に身体に残像が残るのかもしれない。
国立音楽院で長くチェンバロを教えているルジェ―ロがレッスンに来たときは、モーツァルト「リンツ」第一楽章は、ミラノ南部の田舎をよく晴れた五月の週末に夫人と散歩する様で、第二楽章は夫人と夜半、静かに語らう様だと言ってから、これだけ持ち上げたのだから、夫人には大いに感謝してもらうと笑っていたが、その後で振った彼のモーツァルトは、音も深く、春の風景の光と匂いが漂ってくる実感を伴っていて、一同驚いたものだ。
実際内容はどうでもよいのだが、自分で何某具体的に想像し、口に出した後で演奏すると驚くほど音が変化する。別に自分が思い描いているものを他人に説明する必要もないし、常にそうすべきものとも思わないが、少なくとも楽譜の中に音楽はないと実感するのは無駄ではないだろう。指揮に関して、技術は本質的には意味がないのかもしれない。
(ミラノにて1月25日)