2014年2月号 目次
 111ミドゥー海――船名
111ミドゥー海――船名
言語丸 黒い雪丸 硬い土受ける
言語の黒い雪 硬い土丸 受ける
ミドゥー海 黒い雪硬い土受ける
言語 黒い雪硬い土丸は 受ける
言語 黒雪(くろゆき)丸硬い土
言語 黒雪 硬い土「受ける」丸
黒雪硬土(かたつち)丸 言語の
黒い雪 硬い土に還す 言語の黒
雪丸 硬い土へ「還す」きみの丸
(『核の海の証言』〈山下正寿〉によると、第五海福丸、第八順光丸、第二幸成丸、第十一高知丸、第七大丸、第二新生丸、第十三光栄丸、第七清寿丸が、第五福竜丸のほかに、高校生たちの調べ上げた証言であり、船名です。これらの船名を「日本の記録」は書きとどめておこう。「砂の女」〈安部公房〉ではない、「水の男」を問うと、メールをきのう受け取りました。「水の女」〈折口〉は硬い土のしたに還る。「ひょっとこ」の語源は「火(の)男」ですが、炉心を吹きまくる火の男ですよ、とりかえしのつかない日本語〈言語〉だと言うのにね。オデュッセウスは船名を連ねて。)
 「ライカの帰還」騒動記 その4
「ライカの帰還」騒動記 その4
石川さんとのアポは容易にとれた。彼は今や売れっ子の新進作家で、しかも雑誌は飛ぶ鳥落とす勢いの少年ジャンプ誌である。指定された練馬の喫茶店に赴くときは、少なからず緊張していた。いっきに書き上げた3〜4話分の原作とシノプシスは、読みやすさに留意して、何度か書き直したものを携えている。約束の時間前に到着し、彼が現われるまではと、何も注文せずにひたすら待つことにする。
やがて彼が姿を見せた。緊張はピークである。名刺を差し出して挨拶。注文を聞きに来たウエイトレスに、私が「コーヒーか何か?」と言うと、石川さんは軽く手を振り「いや、ボクはいいです」このとき背中にジワッと嫌な気配が漂ったが、すかさず世間話に切り替え、私が彼の「北の土龍」に注目していることなどを伝えた。彼は礼を言うと「あれ、もうすぐ終わるんで、次の打ち合わせに入っているんですよ」と言う。
そりゃ、そうだろう。ジャンプ誌としては、ここまで育て、目論見どおりのヒット作をものにした新人を放っておくわけがない。ここまでは想定内なのだ。こちらとしては1年でも2年でも待つつもりでいたから、「あなたの絵を思い描いて書いたものです。目を通していただけると幸いです」と原稿の入った封筒を手渡した。彼は無言で封筒を開くと、プリントアウトされた文面に目を落とすわけでもなく、ゆっくりと4つに畳んだ。
「このあと打ち合わせが入ってるんです」と、4つ折りにしたプリント用紙をヒラヒラさせながら、数メートル離れたテーブルに目をやる。振り返ると、そこには2人づれの編集者然とした男たちが座っていて、彼に呼応するように軽く手を挙げた。集英社だ...。目を戻すと彼はすでに中腰になっていて「これ、目を通しておきますんで」と私に告げると、軽く会釈をして席を立ち、そのテーブルに向かってスタスタと歩いて行く。
私は空になった封筒をバッグに戻し、明るい声で会話が始まったテーブルの面々に、ちょこんと頭を下げて喫茶店を後にした。胸にポッカリ穴が開いたような気がして、言い知れぬ虚脱感が漂う。まぁ、こんなもんだろう、という気分にはなれそうになかったので、オフィスには戻らず、その足で小学館に向かう。ヨソの会社なのに自分は何をしてるんだという思いもあるが、ひとりで考えてもどうなるものではない。
小学館の友人は笑いながら「そんなこと、オレたちはしょっちゅうだぜ」と言う。「最初のイメージとは違ってしまったろうけど、要はその作品が世に出るか否かってことじゃないか?」そりゃ、そうだけど...。「もう一度、(イメージを)組み立てるっきゃないぜ。じっくり行くことだよ」...わかったよ。ありがとう。また誰か、作家さんを紹介してもらえるかな?「うん、誰かいるよ。焦らないことだぜ」
その後、1カ月ほどブランクが続く。私はと言えば、小石くんに月刊オートバイ誌で連載してもらう作品の打ち合わせに忙殺されていた。作品の題名は「マギ〜!」に決まる。彼のイメージの中には「鉄の女」と呼ばれたマーガレット・サッチャーがいて、内容は学園ものであり、破天荒だが憎めない男子生徒が主人公になる。マギーと名付けた鉄のバイクに彼がどう係わって行くのか、ここはお手並み拝見というところだった。
例の話はその後さっぱりで、小学館の友人から連絡もない。自分としても心が折れたようになって、続きの話をまとめる気にもなれなかった。考えてみれば、この作品が石川サブロウさんによってできあがるのだというイメージは、自分の中で勝手に大きく膨らんでいたのだろう。今になってみると、なんで? とも思えるのだが、そのときはそう思えたのだから仕方がない。半ば、あきらめかけている自分がいた。
ある日のこと。自分のオフィスにいても仕方がないので、小学館に出向く。ここは広大な1フロアに少年誌と青年誌が一堂に会していて、かの友人が在籍する編集部にたどり着く間に、いくつもの編集部を通り過ぎる。そもそも昼下がりに編集スタッフがいるわけはなく、どこも閑散としたものだ。売れている雑誌のスタッフの多くは夕方に出社して、また社外へと消えて行くのが常である。職業柄、仕方のないことだ。
そんな中でも最近タイトルが上昇中で、近く新しく発刊される雑誌の編集長候補である友人は、ちゃんと席に座っていた。彼は私の顔を見るなり「おー、来たか。まだ見つからないんだよ。あの話は背景やら小道具やらの描写が難しいからなぁ」と言う。こちらも気にしていなかったわけじゃないけど、すぐに作家さんが見つかるとも思っていなかった。そのことを彼に告げると、彼は席を立って私を編集部の一画に案内する。
そこには小学館の新人賞の応募作や、受賞作の生原稿がきちんと収められた棚があった。「この中でさー、これと思うやつ、あるかどうか見てみれば?」...いいの? 私はドギマギしながら言う。これらは小学館にとって貴重な資料であり、財産なのだ。部外者である私に閲覧などさせていいのだろうか? 幸か不幸か周囲に人影はないし、こちらを注視する視線も感じない。私はいくつかのファイルに手を伸ばした。
さすがに、どれもレベルは高かった。絵柄がこなれて来れば、すぐにでも第一線でデビューできそうなものばかりだ。と、その中で目に留まる作品があった。内容は太平洋戦争末期、捕獲した米軍のB17爆撃機を、帝国陸軍の航空隊が東京湾上空で飛行させるというものだ。ストーリーにインパクトのあるオチがないのが残念だったが、描写は巧みで申し分ない。私はそのファイルを手にして彼の席に戻った。
「あー、目が高いじゃないか。それ、スピリッツ誌の新人賞だよ」へぇ、そうなんだ。でもこの人...、吉原さんって言うの? まだデビューしてないよね?「ん? ...う、うん。ちょっと問題があってね。彼、使えないんだ」と、友人が言う。「オリジナル誌の編集部に福田ってのがいるから、オレよりヤツから聞けばいいよ」珍しく、友人は顔を曇らせていた。なんだろう? それは後日、福田氏との話でわかることだった。
福田氏によると、吉原さんはかなりの有望新人であり、昨年に発刊されたスペリオール誌の第1号の巻頭でデビューするはずだったと言う。しかも作品の原作を担当するのは大御所中の大御所、Kさんだ。新人作家のデビューとしては、これほど恵まれた環境は稀に違いない。ヒットは約束されたようなものだからである。ところが、その打ち合わせに新宿のホテルでKさんと待ち合わせた吉原さんは、意外にもこの話を蹴ったというのだ。
怒り心頭のKさんは「アイツは使うな」と言い放ち、憤然として席を立ったという。その場には新生スペリオール誌を任される編集長と、担当を予定していた手練れの編集者も同席していたから、冗談では済まされない。小学館ばかりでなく、大手の出版社で数々の大ヒットを飛ばすメガヒットメーカーのKさんの言葉は重く、これで吉原さんの小学館でのデビューの道は、閉ざされてしまったことになる。
「でも、さ」福田氏は机の状差しからオリジナル誌を1冊取り出し、私に見せる。オリジナル誌なら毎号目を通しているので、見落とすはずはないのだけれど...。よく見ると本誌ではなく、増刊号だ。その巻末に「アラビアのロレンス」でおなじみのT・E・ロレンスを扱った作品が載せられていた。作者は...吉原昌宏。彼ではないか! ダイジョブなの? 福田氏は「Kさんも増刊号までは目が届かないね」と、ニヤリと笑ってみせた。
新人賞を獲得して以来、吉原さんに肩入れしていた福田氏は、彼を放っておけなかったのだろう。しかし吉原さんは小学館の扱いにいまだ憤っていて、福田氏以外の編集者とは会わないのだと言う。ボクでも会えないかしら? と言うと、福田氏は腕を組み、ちょっと考えてから「オレとしては、ヤツに描いてほしいんだよ。でも、年に2回の増刊号じゃ話にならん。一応、話は通しておくよ」ダメもとの、2回目のトライが始まった。
 製本かい摘みましては(95)
製本かい摘みましては(95)
ステンレスのキッチンテーブルを捨てた。10年くらい前に中古で買って、切ったり貼ったりの作業台として使ってきたが、表面の冷たさに手足が耐えられなくなってしまった。丈夫だしきれいだしで、しばらくもらい手を探したけれど折り合いつかず、もう、いいよねと、捨てたのだった。なくなってみると、3つの引き出しと足下のスペースの収納力がいかに大きかったかに驚いた。元材木屋がはじめた家具屋で、同じくらいの大きさの机と似たような収納力のある引き出しを作ってもらって、おかげで触れた手足の冷たさにビクッとすることはなくなった。このひやっとした感じには、古い覚えもある。
小学校の入学祝いに買ってもらったスチール机だ。高さ調節ができて蛍光灯がついていて、前面にはカレンダーと時間表、上は本棚、右に引き出し、左にランドセルをかけられるようになっていて、囲まれる感じが自分だけの小さなお城みたいでうれしかった。当時はあれが流行で、しかも年々付属品が増えて派手になっていたのだと思う。近所のおねえさんたちとの雨の日の遊びの"基地ごっこ"で、この机が餌食になることがあった。まわりに食堂の椅子まで持ち込んで全体に毛布をかぶせたり段ボールで囲ったり、私は最後に招かれて、色水でつくったジュースをのまされて落とし穴にはめられたりした。廊下の隅の足踏みミシンも別の基地になっていた。
建築家の坂口恭平さんは子供の頃、六畳一間の子供部屋にA4サイズの方眼紙に書いた地図を敷き詰めて手づくりRPGゲーム「サカグチクエスト」を作ったり、コクヨの学習机の下に潜り込んで毛布をかけて自分の巣を作ったそうである。『ヘンリー・ダーガー 非現実を生きる』(小出由紀子編集 平凡社コロナ・ブックス 「ヘンリー・ダーガーという技術」)で読んだ。狭い団地生活を反転させるための独立国家をつくろうとする試みだったと書いている。そうそう、そうだったんだよね。なんて思ったこともないくせに、いや、でも確かにそういう感じだったのかもしれない、などと言ってうなずきたくなるほど、坂口さんはうまいことをおっしゃる。うちの机もコクヨだったのだろうか。
スチール机がシールや天地真理やサンリオでいっぱいになったころ、父親が木製の古い大きな机を2つもらってきた。姉も私もスチール机からすぐにのりかえた。選ぶまでもなく、両袖机は南側にある姉の部屋に、片袖机は北側にある私の部屋に運ばれた。私は部屋のドアに黄緑のクレヨンで「じょおうさまのへや」、窓の木枠にはカッターで「eternity」、落書きや改造は格下の部屋での暮らしを反転させるための試みだったに違いない。姉に続いてやがて私も家を出た。小さなワンルームで暮らしながら、いつか両袖机を自分の部屋で使いたいと思うようになった。数年たって願いが叶った。分解して宅配便で送ってもらったら、記憶の中にあったものより数段大きくて焦った。泥棒に入られて何か一つだけ家具を残してやると言われたら、この机を残すだろう。
 本の履歴書
本の履歴書
ひょんなことから、自宅の本棚の一部の写真をFACEBOOKに載せてみた。いわゆる私の興味の履歴書といった感じだろうか。一番多いのは仕事にしているソフトウェア関連と品質管理関連の書籍で、次に多いのは学生時代の専門で今も趣味の範疇においている植物学の本だった。
最近、増えているのはシステム学関連の本です。コミックと小説(SFと推理小説)はデフォルトで多いですが、写真集、特に風景写真の写真集は多いような気がします。この辺は今回は載せてないので、本棚の公開されている写真からは見えていないですが。
このところ、本の販売期間がどんどん短くなっているような気がしている。気が付くと廃版や絶版になっていて、買えなかったり、私の手持ちが中古市場でとんでもない値段で取引されていたりする。中古本の値上がりを目的に所蔵しているわけではないけれど、必要な知識が手に入りにくい時代になったと感じることも多い。一方で、写真では見えない本も多くなってきている。いわゆる青空文庫などの電子本がそれだ。
昔(というくらいの昔ではないけれど)は電子書籍は購入してもすぐに見るための機械やソフトがなくなってしまい、そのまま、読めなくなることが多かった。うちの書棚にもおそらく数冊はそういった読めない本が収容されているはずだ。しかし、最近では汎用のフォーマットが出てきた関係で「読めない本」はなくなりつつあると感じている。とはいえ、過去、読めなくなった経験から大切な本は電子書籍では購入しないので、ほとんど持っている本は青空文庫ばかりだったりする。
ふと、気づくと町の本屋も少なくなってきたことに気づく。そういえば、数日前にも近所で車で立ち寄れた本屋が閉店した。さて、今後、私のまわりの本棚はどうなってしまうのだろうか? はたして、私の本棚はどのように育つのだろうか?
その前に、数十棚分の写真を載せたのに、ほんの数分の一という我が家の満杯になった本棚をどうするかという根本的な問題も残っている。ちなみに、青空文庫の作業待ちの書籍は10箱程度が積まれた状態になっている。これもかたさないといけないですね。
 ジャワ舞踊作品のバージョン 2「メナッ・コンチャル」
ジャワ舞踊作品のバージョン 2「メナッ・コンチャル」
私が連続テーマで何か書こうとすると大体1回目か2回目で挫折するのだが、昨年11月号に続いてジャワ舞踊作品のバージョン2を書いてみたい。
「メナッ・コンチャル」はソロのマンクヌガラン王宮で作られた男性優形の舞踊で、ダマルウラン物語というジャワで作られた物語に登場する人物を描いている。簡単に言うと、戦いに出て死ぬ運命にある男性が恋に身を焦がす様を描いた作品で、いわゆるガンドロン(恋愛)物と呼ばれる男性の単独舞踊の1つだ。スラカルタのマンクヌガラン王家の舞踊家、ニ・ベイ・ミントララスによって作られた。マンクヌガラン王家といえば、ダマルウラン物語を題材に、ラングンドリヤンという女性だけで演じられる舞踊歌劇が作られたことで有名だ。「メナッ・コンチャル」もその歌劇の一場面が独立した形になっているので、男性舞踊だけれど女性によって踊られ、途中で踊り手が恋する姫への気持ちを切々と歌い上げるシーンがある。しかもその曲は、ジャワ人なら誰でも知っている名曲「アスモロドノ」(愛という意味)。宝塚歌劇のように、男装した麗人の美しい声を堪能しながら、歌詞のロマンチックな気分に浸れる舞踊で、いかにも王家らしい華やいだ雰囲気がある。
が、この作品は、一般的にマリディという舞踊家の再振付で有名で、カセットもロカナンタ社から市販されている。ただし、ちゃんと作者名はニ・ベイ・ミントララスだと明記されている(ちなみにレーベルの写真はマリディの娘)。マリディは結婚式か何かでこの作品を見て気に入り、二・ベイ・ミントララスに即、自分ならもっとうまく振り付けられるからリメークさせてほしいと頼んだらしい。マリディ自身がそう言っていたので間違いないだろう。当初、ミントララスにものすごく驚かれたらしいが(失礼な若造だと思ったのではなかろうか)、リメーク版は本人にも気に入ってもらえたとマリディは嬉しそうに語っていた。
マリディ版とミントララス版の最大の違いは、マリディ版ではサンパという曲(影絵芝居ワヤンでは、場面の転換、出陣や戦いの場面で使う)が「アスモロドノ」の曲の最後に追加され、踊り手が戦場に出立することを暗示しながら走り去る場面で終わっていること。ミントララス版では、普通の宮廷舞踊と同様に、最後は床に座って合掌して終わる。そして、歌いながら踊るために、振付は全体にかなりシンプルである。一方、マリディ版では踊り手は歌わない。その分、これでもかというくらい細部が細かい振付になっている(しかも絶えずバージョンアップを繰り返す人なので、毎年友達が習うたびに違う振付になっている)。つまり、マリディ版の演出では、劇的要素がいやが上にも強められ、振付自体でドラマを表現しているのだ。マリディの振付はどれも、とてもドラマチックな展開になる(たとえ元のストーリーがしょうもなくても)。
スラカルタにある国立芸大では、当初、マンクヌガラン王家で踊っていた教員が大学のカリキュラムに「メナッ・コンチャル」を導入したので、当初の芸大バージョンはかなりマンクヌガラン風だった。留学した私が芸大の先生から個人レッスンで習ったのは、このバージョンだった。当時はまだかなり初心だったので、授業についていけるように個人レッスンを受けていたのだが、授業で習ったのは全然違うバージョンだったので、私の頭は大混乱に陥り、結局試験でも古い芸大バージョンで押し通してしまった。実は、その当時、若手の教員がマリディから習ったものをカリキュラムに再導入したので、芸大バージョンがリセットされてしまっていたのだった。私はまだ見たことがないが、ガリマンも「メナッ・コンチャル」のアレンジを手掛けているらしい。それは、わりとあっさりしてマリディ版とは全然違うらしく、たぶん、オリジナルにより近いのかなと思ったりする。
 しもた屋之噺(145)
しもた屋之噺(145)
羽田空港の深夜のラウンジで、雨に濡れた滑走路を眺めながら書いています。昨日の朝羽田に着いたばかりですぐにトンボ帰りするのですが、まるで随分長く東京にいたような心地がしているのは、濃密な時間を過ごした証でしょう。今朝は期日前投票を世田谷区役所で済ませ、打ち合わせの後で恩師のお別れの会に出かけ、少し涙腺が緩んだからと味とめに両親を誘って久々の焼酎を舐めつつ、メジナとイサキの刺身に舌鼓をうちました。時差ボケと焼酎で京急電車で寝込み、今こうして目の前で闇の中を飛び立つ飛行機を眺めています。
三善先生の合唱曲をききながら、先生のピアノの手触りを思い出し、先生が愛したシャランの和声課題を思い、それを大喜びで歌うミラノの大学生の顔を一人一人思い出し、三善先生がご覧になったら、どんなに大笑いされるかと考えています。
会がひけて奥様にご挨拶に伺うと、想いが混濁して言葉が浮かばず口ごもったままで、中学に上がりたての頃、初めて阿佐ヶ谷のお宅に上がった時と、まるで同じでした。自分がそこにいることすらおこがましく思えて、一番後ろの席に小さくなっていて、会が終わると真っ先に会場を後に飛び出しました。日本にいない自分は、こんな時いつもどこかに後ろめたい気持ちに駆られて、責を果たさない、不誠実な自分にどう対峙してよいか分からなくなります。外は雨がしたたか降っていて、濡れねずみになりながら地下鉄まで辿り着いたとき、どうしても奥様にご挨拶だけしたくて、垣ケ原さんにお電話したのでした。
会の最中、由紀子さんが普通の演奏会のように明るく拍手してほしい、先生がホールのそこここを飛び回っているに違いないからと静かに仰られたとき、背骨がじんと痺れる気がしました。果たして自分は音楽と誠実に向き合っているのかしらと、てらてら揺れる目の前の緑色の誘導灯を、改めてうらめしく眺めています。
------
1月某日 コリコ駅前の喫茶店にて
4時に起床し、息子と連れ立ってドゥビーノの駅まで歩く。二人とも無言で、冷気を切るように歩く。見上げると満天の星空。無数の星が天の川から溢れて空一杯を埋め尽くす星の洪水。ふるえるような鳥肌が立つ。
1月某日 自宅にて
アルツハイマーが発症してからのウテルモーレンの自画像を何度となく見なおしているのは、ドナトーニが脳梗塞でたおれた時になぐり書きした、プロムの原稿とどこかが似ているから。一見するとドナトーニは動で、ウテルモーレンは静だが、殆ど自分の顔を認識できないなかで、鼻だけすがるように美しく浮き出し、頭に相当する部分には裂け目が走る自画像が内包する、壮絶なエネルギーに圧倒される。子供に帰ってゆくのではなく、深い霧の中で、自らの存在が外側から消滅してゆく。最後に霧の中から少しだけ顔を覗かせたのは、鼻だった。
1月某日 自宅にて
繰り返し「大喪の儀」のヴィデオを見返して、儀中詠われる、生きた「誄歌」に耳を傾け、何度となく調弦に手を入れる。盤渉調のひびきを、どこまで際立たせられるか、ぎりぎりのところを探す。「誄歌」の和琴は、思い切ってそのまま使う。当初、入れ子構造を何度も重ねてみようと思ったが、結局、「誄歌」を何となしに辿れるような、くねた蔓を描くことにして、歌詞をそのまま遡行する。
そう決めると、面白いことに、ベトナムで使っていた奇妙な漢字が幾つか頭に浮かんでくる。ベトナムの国字は、少し煩わし過ぎるくらい、蔓が躰にへばりついたような奇妙な印象があるのは、単に先入観による思い込みに違いないが、どこか伎楽面の派手さに通じる気もする。
1月某日 自宅にて
仕事の帰りに14番の路面電車に乗ると、酔っ払いが妙齢に絡んでいたので、ちょうど近くに座っていた気のきかなそうな若者に立ってもらい、「おじさんここが空きましたよ」と大袈裟に云うと、素直に「悪いねえ」と言って座ったので、痴漢にしては聞き分けがよいと感心。妙齢もイタリアでは負けていない。傘をつきたて、「これ以上近づくと刺すわよ」と凄む。
1月某日 音楽院にて
笹久保さんが作った映画が届いた。これらは演奏しながら浮かぶ映像を定着したもの、という説明に共感を覚える。
音楽の演奏に際して、無意識に何か刺激や拠り所を欲していることに気づく。それを作為的にやると品位を貶める気がするが、指揮者など、そうした映像による集団心理のイメージ操作で、音楽を豊かする最たるもの。実は昔はそんな安っぽいやり方と馬鹿にしていたが、フリッチャイが、文字通り頭のなかにある映像を必死に音にしている姿をみて、自らを恥じた。
1月某日 自宅にて
亡くなった恩師の誕生日。毎年、「おめでとうございます」と簡単なファクスをしたためてお送りしていたので、今日もふと書きそうになった。もしかしたら、ファクスに紙が吸い込まれていって、そのまま彼の手許に届くかもしれない、と思う。
1月某日 ミラノへの車中にて
夜明け前、無人のボローニャを駅に向って歩くのは、甚だ心地がよい。昨日は打合せの合間に、アッバードが安置されているサント・ステファノを訪れる時間があった。柩は暖房用の紅い電灯に照らし出されていて、思いがけず小さくみえた。花が一輪載せてあり、薄くレクイエムがかかっている。記帳を終えて中に入ると、誰もが無言で柩をじっと見つめていた。買い物カゴやスーパーの袋を小脇に抱えた、近所の老婦人たちが立ち尽くして居て、立ち振舞いがとても美しく見えた。
1月某日 三軒茶屋にて
羽田についてメールを開くと、ミラノの市立音楽院が、市長により「クラウディオ・アッバード音楽院」と命名されたと院長より一斉メールが届く。みんな順番に死んでゆき、思いの外素早くそれぞれの死も既成事実として受け容れられて、歴史という膨大なデータベースに仕舞われる。
先日、息子は参加したいと言って聞かなかったコンクールの本番で派手につかえて、酷い結果になったとか。終わった直後は泣いていたらしいが、すぐに「猿も木から落ちる」と言ったものだから、母親からこっぴどく叱られた。彼はまた「12月の色は何だ」というクイズを自分で考えて得意になっている。答えは「青色」。「12月」を漢字で書けば「青」になる。
 私が消えて、写真が残る
私が消えて、写真が残る
1月最後の日曜日。午後から急に風が強くなって、雲行きに嵐の気配が混じる。こういう天気を片岡さんはうれしく思っているかもしれないな、なんて思いながら出かける。下北沢のB&Bという本屋さんで、片岡義男さんが登場するイベン「BETWEEN カメラ and 万年筆」が開催されたのだ。イベントのお知らせ文によると、写真集『私は写真機』(岩波書店)を完成させたばかりの片岡さんと、名作写真集『NY1980』の著者である大竹昭子さんのトークセッションで、作家にして「撮る人」でもある2人のあいだに立って行司を務めるのは、片岡さんの前作『この夢の出来ばえ』の編集・デザインを担当した川崎大助さんとある。
のっぴきならない用事で、どうしても開始時間に間に合わない。スカイツリーの見える街から電車を乗り継いで、会場にたどり着いた頃には1時間が過ぎてしまっていた。窓際の席から、揺れる電線が見える。夜になってからも風はおさまらない。
会場からの質問の時間になって、印象的な問いが投げかけられた。「なぜ、優れた写真家は言語能力においても優れているのか?」と。言葉そのままに引用できなくて申し訳ないが、片岡さんの答えは、「言葉がもっとも不自然なもので、その次に不自然なものが写真だからでしょう。不自然なものをつくり出す能力として両者が共通しているからでしょう。」というものだった。言葉によってつくられた世界(小説)、写真によってあらわされた世界、そのどちらをも片岡さんは「不自然なもの」と呼んでいて、その言い方にひっかかって、色々と思いを巡らせることになった。
『私は写真機』には、写真とともに4つの短い文章が掲載されているが、冒頭「なぜ写真機になるのか」を読むと、「不自然」の意味がさらに理解できる。片岡さんは、少年の日に触れながら、「曇った日は、すべて均一に揃った現実のなかに自分も取り込まれた」が、「晴れた日の僕は、意識の上でどこかその日の外にいて、外から晴れた日を見ていた。」と言う。そして、「曇った日をリアルだとすると、晴れた日は、それを外からとらえる自分の問題として、リアリティだった、と言ってみようか。リアルが現実そのものなら、リアリティとは、自分がとらえる現実、というものだ。」という核心にふれる言葉が続く。
世界に向き合って立っている自分、世界から切り離されている自分、そのあり方は、ある日意識される。世界から切り離されているあり方が「不自然」なのだ。あえて、それをやろうとする行為、それが「不自然」なのだ。「言葉」というものも、あえて世界と向き合って、名付けようとする行為だから「不自然」なのだろう。「自分がとらえる現実」と言っても、「自分勝手にとらえる」のではない。世界を鏡のようにうつしながら、移動していく人間の姿が、イメージとして浮かぶ。『私は写真機』という題名はぴったりだなと思う。
片岡さんは、暮らしを取りまいているものを撮る。手を加えたりしていないのに、現像された写真は非日常に見える。このことが持つ意味については、まだわからない。
 オトメンと指を差されて(66)
オトメンと指を差されて(66)
わたくしが妙な擬音語・擬態語を用いることは今回の回数のちょうど半分の回で触れたりなんぞ致しましたけれども、そういえば最近わたくし気づいたことがあるのですよ。もちろん今でもチョコレートを食しますときは「しょこらしょこら」というフレーズが頭のなかに響いているのですけれども、そう、わたくし普段からよく飴ちゃん(普段は声をよく使う職業でもあるので主にのど飴であるわけなのですが、そう、関西では飴のことを飴ちゃんと常にちゃんづけをするんであくまでも飴ちゃん)をなめるときに流れるフレーズは......
「かんろちゃんかんろかんろ」
あとそうです、日常生活では省エネだったり差し替えだったりでコンセントのプラグの抜き差しをよくするんですが(というかわたくしの下宿にはそもそもコンセントの数が少ないというかタコ足配線もあんまり好きくないのでしないっていうのもあるんですがとにかくプラグの抜き差しをよくするんですが)、そのときに頭のなかで復唱するフレーズっていうのが......
「こはくのせいれいよわれにちからをさずけあたえたまえっ」
それにその、わたくし作業をしているときには結構動画サイトをバックグラウンドで開いていることが多くてですね、そのときにはだいたい VOCALOIDといういわゆる電子的な歌声をBGMにしながらキーボードをぺけぺけしているんですけど(それもだいたい「初音ミク」さんのものが結構な割合を占めていたりなんかしたりして)、まあその動画を開くというかリンクを踏むというか再生ボタンを押すというかそういう曲を聴き始めるための動作をしているときには、意識のなかで自動的に詠じられる言葉があって......
「のーびーすむんでーれくとりすむーさみかーつねかんたー」
うーん、これは。これはこれはこれは。......擬態語どころか文章いや呪文に近いものにすらなっているではありませんか。いったいいつからどこからこうなってしまったんだ......いやいやいや、イメージとしては擬態語のつもりなんですよ、マンガのコマにそれらの行動を取るわたくしが描かれていたらその横に添えてあるようなそんなつもりなので。
とはいえ多少なりとも宗教的な環境で育ってきた人であるならば祈りやら宣誓やらフレーズやらがある一定の場面や行動と無意識に接続されていてふっと浮かび上がってくるなんていうことがあるってことをわかってくださるんではないかと無宗教の国とも言われるこの島で期待したってどうしようもないことは百も承知ではあるんですが、無駄にフレーズが凝っていったりするあたりはわたくしもまだいわゆる「中二病」なるものが心の片隅に残っているのかもしれません。
あ。もしかすると「中二病」をご存じない方がここにいらっしゃるのかもしれないのでここでわたくしはわたくしの地元であるところの町でロケハンが行われたるところのただいま大ヒット放映中のTVアニメ「中二病でも恋がしたい!」をことさらに強調してみるためにその第1話の冒頭のナレーションを引用してみるのですよはい!
「みなさんは「中二病」という言葉をご存じだろうか? 思春期を迎えた中学2年の頃にかかってしまうと言われる、恐ろしくも愛すべき病で、形成されていく自意識と夢見がちな幼児性が混ざり合って、おかしな行動をとってしまうという......アレだ。」
何やらその病(という比喩)は、子どもが背のびするような感じでやたら難しい言葉や漢字を用いたり格好つけたりするような趣でもあるのですが、わたくしの場合は子ども時代に無理して自意識を落ち着かせていた分、今さらに自意識と幼児性がぶり返しているというか「オトメン」はどこかそういうところがあるのできっと通じるところがあるんだろうなーと思っていたらやっぱりそうでしたね!
っていうかそんなことはどうでもいいのでありまして「中二病でも恋がしたい!」のお話はわたくしの地元の町やらその周辺で物語が巻き起こっておりますのでご興味をお持ちになられた方におかれましてはどうぞ一度ご視聴下さい。青空文庫に参加したときのわたくしっていうのはだいたいあんな感じの場所であんな感じであんな人たちと一緒に生きていたのだと考えてくださっておおむね間違いないのではないだろうかと思います。(登場人物の誰がわたくし、なんて無粋なことは言わないですけれども)
 脈
脈
目を瞑り、微かに開くと
煙とホコリが髭のよう
秘密の記号 線 明日の足音
血は旅をする
どこまでも遠く
地図の中を歩き回った
夏の星はどの海に沈む?
脈はどこまで繋がっている?
疑問と夢は窓硝子を眺めている
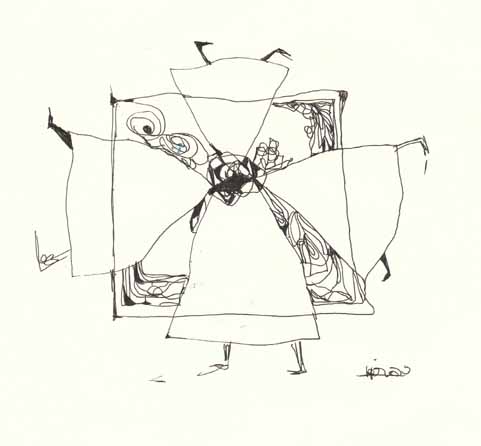
 爪を切る。
爪を切る。
膝頭を見える程度のスカートをはいた女が目の前に座っている。背筋をすっと伸ばして、でも退屈そうに座っている。
列車は空いていて、私の座っている六人掛けのシートにも、女が座っている向かいのシートにも他に乗客がいない。だから、私と女が同じようにシートの真ん中に座り、真正面で向き合っている構図はとても不自然だ。
それでも、わざわざ席を移動するという気にもなれず、しかも、女が動じていないように見えるのがしゃくに障り、私も女の真正面から動かない。そもそも、私が女の前に座ったのか、女が私の前に座ったのかが判然としない。
各駅停車の列車が二駅か三駅過ぎた頃、退屈そうに見えた女の顔が少し曇ったように見えた。その表情に誘われるように私は再び女をしっかりと見つめる。改めて眺めると、女の衣服はとても上質なもののように思われた。地味な色味なのだけれど、派手すぎず沈みすぎない光沢が品の良さを感じさせた。きっと安くはないものなのだろうということは、安い服ばかり着ている身だからこそよくわかる。
まだ充分に若い女だけれど、もしかしたら、若いと言われることに戸惑いを感じるくらいの年齢にはなっているのかもしれない。
そんな女に退屈そうな表情はとてもよく似合っていたのだが、曇った顔には小さな違和感があるのだった。その違和感は女の細かく動く指先を見つけると嫌悪にかわった。
女は左手の中指か薬指あたりの爪の先を気にしていた。爪が伸び過ぎているのか、それともささくれでも出来ているのか、一度気付いてしまった爪の先の何かを無視することができなくなっているようだった。
そんな女を眺めながら、私は身体の深い疲れに目を閉じた。そして、女を真ん中に置いた風景を閉じたまぶたの裏に思い浮かべた。女はパノラマのような車窓を背負っていて、木々の緑を映し、拓けた田畑を見せたあと、大きな海原へと色を変えた。
刻々と変わっていく風景を背にした女は、やっぱり背筋を真っ直ぐに伸ばして、きれいな膝頭の出た細くて美しい足をぴたりとそろえて座っている。さっきまでの曇った顔はなくまるで背後の風景が見えているかのような晴れやかな面持ちでこちらを見ている。
少しまどろんだのか、小さくしゃくりあげるように私は目を覚ました。そして、女の表情を確かめようとして、ゆっくりと女に目を向けてみると、女は爪を切っていた。女が爪切りを持ち歩いていたということがとても不思議だったのだが、現に目の前の女は爪切りを右手に持ち、左手の指先の爪を切っていた。
私がまどろんでいる間に手にした小さなバッグの中から爪切りを出し、さっきまでしきりに気にしていた爪の先を切っているのだった。列車の中で注意深く、爪を切っているのだった。
私はそれをじっと見つめている。女と同じように、ちゃんと切れるかどうかを心配しながら、じっと見ている。この女は列車の中で、人前で爪を切るのだ、と思いながら見つめている。自分で爪を切っているわけでもないのに、いくぶん緊張しながら爪を切っている女を見つめている。
何度か注意深く爪切りを動かすと、上手く切れたかどうかを女は片方の手の親指の腹で撫でて確認する。一通り爪の先を親指の腹で撫でると、女はとても満足そうな表情を作り、そして、小さく長く息を吐いた。おそらく私もいま満足そうな表情をしているのだろうと思う。揺れる列車の中で、うまく爪が切れたことと、やっと女が爪を切り終えたことに、私は安堵し、満足しているのだった。
女は私の表情に気付くと、素早く爪切りをバッグにしまい込んだ。
すると、今度は私自身が自分の指の爪が気になってきてしまう。気になって気になって仕方がなくなってしまう。女に気付かれないように、私は女がやっていたように親指の腹で他の指先をさわってみる。(了)
 アジアのごはん(61)タイのデモ
アジアのごはん(61)タイのデモ
タイのバンコクに来ている。バンコクの街はどんよりと霞んで、目もよく見えない。バンコクもpm2.5がひどいのである。日本の sprinterという予測システムがネットで一週間程度のpm2.5の大気予測を出していて、アジア全体の大気の流れ、pm2.5の流れがよく分かる。中国から日本へ濃いpm2.5が流れてくる情報を見て外出するかしないか決める毎日だが、いつもバンコクあたりの濃いpm2.5の雲が気になっていた。ラオスやタイ北部も濃い。こちらは山焼きや山火事の煙によるpm2.5。バンコクは、排気ガスや工場排気が多い地元産のpm2.5だろう。
確かに目がちょっと痛いし、目がかすむけれど、日本のpm2.5の濃い時のような激しい頭痛、呼吸困難のような胸の苦しさ、体全体の不調、といった激しい症状は起こらない。日本にやってくる中国由来のpm2.5がいかに化学物質や、汚染物質が満載なのか、体をもってして実感してしまうのであった。
それでも、今日はバンコクに来て初めてすっきりと晴れた。1月28日にやってきたのだが、バンコク在住の友人たちから「今バンコクは経験したことがないほど寒い」だの、「今夜は14度しかない」とかさんざん脅されて、長そでを多めに持って来たりしたのに、北極由来の寒気はちょうど去ってしまったらしく、連日きっちり暑い。どうしてくれる、この長そでの服たちを。
バンコクではpm2.5が多くて、かすんでよく先が見えない日が多い。タイに来るまでは今のタイの反タクシン運動についてもいまひとつもやもやとして、すっきり見えていなかったが、昨日ちょうどデモ行進に遭遇して、反タクシン・デモ隊の雰囲気を感じることができた。ちょっとだけ目の前の空気が晴れたような気がするので、今月はタイのデモのことを書こう。
昨日、友人が「今日はデモ隊がオンヌット方面をデモ行進中だから、出かけるときはBTS高架鉄道で行ったほうがいいですよ」と電話してきてくれた。今回はオンヌットのさらに西のウドムスックというBTSの駅に近いコンドミニアムが宿だ。「なにか特に騒ぎが起きそうな様子とかは?」「いやそれはないです。ただ、片側車線封鎖しながら行進するから渋滞するんで」
ちょうど、もっと先のプロムポン駅近くに買い物に行こうと思っていたので、じゃあ問題ないね、と連れと出かけた。プロムポン駅に着くと、高架の駅からみんな下を見ている。寄ってみると、下の道路は車が走っていない。「デモ隊が来るんじゃない?」迷彩服で武装した兵士が二、三人駅に立っているのは上から爆弾など投げたりするのを警戒しているのだろう。
待っていると、まず歓声が遠くから聞こえてきて、沿道にも市民が集まってきた。ちょうど昼休みで、会社の社員やデパートの職員や、工事現場の労働者も立って見ている。タイ国旗カラーの応援グッズを売り歩く人もいる。旗を振っている人もいる。まず、バイクの一団が旗を振りながらやって来て、続いて人々が三々五々歩いてきたと思ったら、すごい数の人が続々と歩いてきた。みんなニコニコしながら、旗を振ったり、手を振ったり。後ろから巨大なスピーカーを積んだ車が軽快な歌を流しながらやってくる。ラ〜ラ〜ラ〜なんとか〜〜オクパイ・タクシン〜! シュプレヒコールというにはあまりにも楽しい「タクシン出ていけ」ソングというか、コールである。
何千人もの人が歩いて行って、ちょうど人波が切れたので、駅から降りて買い物に行った。日用品や食料を買い込んで駅のあるスクムビット通りに戻るとまた新たなグループのデモ隊が道にあふれているではないか。さっきより多い。しかも先も後ろも見えないぐらい続いている。反対車線は車が通っているのだが、デモ隊の歩く車線に入ってこないよう自分たちで自主的に交通整理しながら移動していく。デモ行進には救急隊もついて動いている。ホイッスルがうるさいという話もあったが、まあ、歓声みたいなものだった。
歩いていると、「昼休みの間だけデモしてた」という会社員がぱらぱらとデモを抜けて会社に帰っていく。この人数、合わせると1万人以上いるだろう。リーダーは要所要所にいるのだが、参加する人が自主的にいろいろこなし、自分の出来る範囲でデモに参加していく。みんなゆるゆると、力まずに歩いていく。う〜んなかなかいいね、このデモ。
今回のデモは、タクシン派のインラック内閣が、かつて民主化運動によって政権から追われ、汚職で有罪判決を受けたタクシン元首相に恩赦を与え、帰国(亡命中)を実現しようとしたことに端を発する。さらに農民からのコメ買取政策が破たんしたうえ、取引先の中国企業がダミー会社だったり大規模な汚職がらみの疑惑も出てきた。
今回の反タクシン派のリーダーは元民主党幹部のステープ氏。連日集会で激しいスピーチで聴衆を盛り上げている。しかし、どうも違和感があるな、と思っていた。ステープはインラック政権が生まれる前の民主党政権時代にタクシン派の赤グループのデモ隊に向けて警察隊に排除命令を出した男なのだ。この武力行使の強制排除で何十人もの死者が出て日本人の記者もフランス人の記者も巻き添えで殺された。結果、民主党はこの責任を取って政権を辞任、その後、総選挙でタクシン派が圧勝してインラック政権が誕生した。民主党支持派の多いバンコクでも、そういう武力で抑え込もうとした民主党のやり方に失望した人は多かった。そのステープがなぜ今回多くの人に支持されているのか? だいたい、いままで、インラック政権にそんなに不満だったのか。いちおう、選挙で選ばれた政府で首相なわけだし、この秋まで、反タクシン運動は表面化していなかったので、ちょっと唐突な感じがしたのも確かである。いくらタクシン派がいやでも、選挙で勝てないからといって、駄々をこねるようにデモで国政を混乱させていいのか?
とまあ、民主主義は選挙の結果を尊重するのが絶対であると思っている日本人や欧米人はそう思ってしまうわけだが、いや、正直タイに来る直前までヒバリもそう思っていたのである。しかし、タイのデモのユーチューブでタイ人の寄せたたくさんのつぶやきコメントを読んで、あ〜そうなのか、と納得がいった。
デモに参加している人たちは、反タクシンであるが、けっしてすべてがステープ支持なわけではない、のだった。インラック政権が崩壊しても、ステープが政権を取ろうとしたら、またデモが起こるだろうともいわれている。とにかく、今の政権は顔がインラックにかわっただけで、閣僚はタクシン時代と同じ(ものすごい悪相ぞろい)利権と汚職まみれの古狸たちである。もう、うんざりなのだ、タクシンの影の内閣は。
今回の反タクシン・デモに集う人たちは、シンボルカラーを作らず、タイの国旗の色である青白赤のストライプ模様のグッズを身に着ける。中には黒を着る人も多いが、これは「抗議」を示す色らしい。前回の反タクシン、民主化運動が途中から王党派(王室利権派)に牛耳られ、ゆがめられていった反省に基づいて、王党派や政党の運動に取り込まれないようにしていく気持ちだろう。黄色は今のプミポン国王のシンボルカラーで、黄色い鉢巻をしている人もいるが、それが中心になることはない。
日本にいるときにマスコミの情報だけで見ていると今回の騒ぎは「タクシン派VS民主党支持派」とくくられていたが、人々は民主党のために集まっている、のではなかった。タクシン派以外の政党の選択肢として、民主党はありなのだが、民主党のために反タクシン・デモをやっているのではないのである。タクシン派以外の政党が選挙で勝てないのは、タイの選挙の内実が民主主義とはとうてい言えない状態でもあるからだ。大半の議員がさまざまな利権に深く結びついており、そして大半の地方の票が金で買われているのが現実なのである。(日本もよく似ていますが)
そういえば、原発反対・秘密保護法反対デモに対して自民党の石破幹事長が「デモはテロと同じ」と、文句は選挙で勝ってから言えみたいな発言をしたが、タイのデモも、選挙制度がきちんと機能していないゆえの意思表示とも言えるのだった。ちなみにタイの反タクシン・デモはいたって平和的であり、非暴力をモットーとしている。(攻撃を仕掛けてくるのはタクシン派)集会拠点に行けば、無料で飲み物や食べ物が供され「それがおいしいのよね〜」と毎日のように集会に顔を出しているプンちゃんは言っていた。「もちろん、カンパはするよ〜」。アジテーションの演説だけでなく、アーティストがステージで歌って踊る、まるでコンサート会場なタイのデモ。日本でも原発反対金曜デモの自由な雰囲気を思い出していただければ、けっしてタイ人がふざけたり、中途半端に反政府運動をしているわけではないというのが分かっていただける‥かな‥。
 正月がふたつ
正月がふたつ
こんなにキツイ「赤の他人」の死は初めてです。
十二月に友人から届いたメールに書かれていた。はじめはドラマー青山純。次にムーンライダーズのかしぶち哲郎。最後に大瀧詠一。大晦日は久しぶりに仕事も休みだったので実家で過ごし、紅白で泉谷しげるのバックでドラムを叩いている上原ユカリ裕の姿を確認する。村八分、ごまのはえ、シュガーベイブのドラマーとして。また大瀧詠一、山下達郎、ジュリー、忌野清志郎のアルバムやライヴにも参加していた。青山純が山下達郎の「ペイパー・ドール」での上原ユカリ裕のノリ、それを自分が演奏する際に納得いくノリが出せるまでかなり時間がかかった、というようなことを掲示板に本人が書いていた。最近、ブログよりもそのひとの発言はツィッターやフェイスブックでしか確認できないことが多い。まして掲示板などセキュリティでブロックされる。つぶやくことも実名登録することもしていない自分あてに友人からのぞくことのできないネットワークからの情報が届く。
年が明けて若松恵子さんより「Raindrops」のきまぐれ飛行船特集号が届く。読み終わると「キツイ」のがかなり軽くなった。夜中に今年初めてCDを注文する。プレスリーの五〇年代から六〇年代初頭のアルバムを集めた四枚組をふたつ。最初に「ブルー・スエード・シューズ」から始まる。ジョン・レノンもカヴァーしていた。そのレコードのライナー・ノーツにプレスリーのヴァージョンよりオリジナルのカール・パーキンスのヴァージョンが好みであことが書かれていたような記憶がある。後にオリジナルのカール・パーキンスもエルビスのスタイルに変化することを大瀧詠一が一昨年のアメリカン・ポップス伝で紹介していた。
昔、成人の日だった日の明け方、右のこめかみの少し上あたり1センチくらいの裂傷、ニット帽に血を付け、指や足やらに擦り傷をつけて、これ以上公けにできないくらい醜態をさらして帰ってきたらしい。記憶がさだかでない。起きたら頭や指やらに絆創膏が貼られていた。ネット接続しかできないスマホも無くしたらしい。酒量を昨年から減らしていたけど調子こくとこういう目に遭う。怒られる。
旧の正月、年末に受けた健康診断の結果が届く。ガンマGTPの値は順調に正常に近かづき体脂肪率も順調に下がり18%台。だが悪いほうのコレステロールが上がっていたのでこのままだと投薬します、ときつい口調で言われたが。頭から血を流しても記憶が確かでないことからなおさねば、と思いながら実家からの旧正月のご馳走のおすそ分けをつまむ。
 希望の足
希望の足
ヨルダンの国境、ラムサに住むイマッドさんは、シリア難民だ。耳を澄ませばバシーン、バシーンと爆発音が聞こえてくる。国境は閉じられているが、けが人だけは、国境を越えてくるので、イマッドさんは、ポンコツのバンを借りて患者を病院やリハビリセンターなどに送り届けている。全くのボランティアだ。そこで僕たちは、毎月500ドルを支払ってガソリン代、車のメンテ代にしてもらっている。うち100ドルはイマッドさんの経費だ。もちろんそんなのでたりるはずはない。シリア難民に群がる援助ビジネスも盛んでNGOでやとってもらったら、1000ドル位は稼げるだろうに、イマッドさんはお金のことなど気にしない。
その日はわけがあってサファウィという町で待ち合わせをしたのだが、僕の方がいろいろ時間かかってしまってすっかり彼を待たしてしまった。彼の車は窓がちゃんと閉まらないのでともかく寒い。そして、止まるたびにエンジンがかからなくなる。ブースターの接触が悪いのかトンカチであちこち叩いているうちにエンジンがかかる。そういうのを3回繰り返してようやくイルビッドのリハビリセンターに到着した。
ここは、シリア人たちが自分らでお金を集めてやりくりしている。イマッドさんは張り切って、ミルクとジュースを買ってみんなに配るという。車椅子で何人かが集まってきた。ナガムさんという女性は、16歳。一年前に結婚した。夫のムハンマドさんは20歳でダラーで農業をやっていた。ミサイル弾が飛んできて彼女の右足は吹っ飛んでしまった。その時おなかの中に7か月の赤ちゃんがいたが、崩れ落ちた瓦礫がおなかにあたって、流産してしまったそうだ。そんな状況だとすっかりふさぎ込んでしまうのだが、夫婦そろって笑顔が絶えない。別にミルクをもらったから大喜びというわけでないのだろう。「どうして、そんなに前向きになれるの?」って聞いてみた。「ここでは、足がないからって特別なことではないんです。ごく当たり前のこと。みんなで助け合っている。神が決めたことだから」とムハンマッドさんが言う。
12歳のムスタファ君。2か月前に、クリーニング屋の前に座っていたらロケット弾が飛んできた。一発とんできたのでみんな逃げたが、2発目にあたってしまった。その場で、右手、右足がもげてしまった。徴兵されるのを恐れ、先に逃げてきた19歳のお兄さんが面倒を見ている。
兄は、ムスタファが怪我したときの動画を見るか? と聞いた。携帯電話の中に入っているというのだ。さすがに本人のいる前で見るわけにはいかないであろうと断るが、「ムスタファは何度も見ているから大丈夫だ」という。その映像は、血まみれのムスタファがベッドに横たわり、右足はぐちゃぐちゃにつぶれていた。右腕を誰かが持ち上げると、皮一枚でぶら下がっていて、それをねじり切ろうとしている。ムスタファは意識があり、起き上がろうとするが、周りから抑えられる。そして悶絶。
このおぞましい映像をムスタファ君は何度も見続けている。しかし、トラウマを抱えているようには見えなかった。名前を書いてもらうが、利き腕を失ったので、上手く字が書けない。それだけではない。「しばらく学校に行ってないから忘れちゃった」と笑っている。将来の夢ってあるのかなって聞いたら、ともかく早く勉強したいと言う。ムスタファは、とても強い子だ。文句ひとつ言わずにほほえんでくれた。
http://www.jim-net.net/event2/2013/12/-1021419at.php
また、バレンタインに向けたチョコ募金、在庫が少なくなってきました。是非早めにお申し込みを。
http://www.jim-net.net/choco/
 掠れ書き37
掠れ書き37
何の理由もなく一連の音が心に浮かび、聞こえる音を書きつけるという単純な作業を続けるのが作曲ならば、このとき「聞こえる」と「創る」とはおなじではないだろうか。ところが「聞こえた」音を書いてみると、どこかちがってしまっている。だからといって、修正を重ねていると、いつか耳は閉じて、構成する慣れた手がはたらいている。
音楽を聞くときは、すべてを受け入れるのではなく、ちがう道をさぐっている。この音楽でもいいかもしれないが、ある瞬間にこれでないものが一瞬見えるような気がする。長い年月に川は流れを変えるように、聞こえる音楽のなかに、聞こえない別な支流があり、どの流れも谷をめざして流れ下る。
規則的に区切られていないリズム、白い音符だけの音楽。17世紀フランスの鍵盤奏者たちの「拍のない前奏曲」のジャンルなかでも、未出版のメモだけが残されたルイ・クープランの場合は、不規則に崩された和音とその間を走る線、景観生態学でいう飛び石と回廊の空間で、ジョン・ケージのナンバーピースは、それらの飛び石が偶然に集まったような和音が点滅する空間だった。近代音楽は管理と統制の時代の音楽で、和声は調和(harmonia)の近代的概念で、調性は単純化した中央支配の道具とも言えるだろう。
前奏曲は書かれた即興だった。音楽史をさかのぼり、ルイ・クープラン以前、旅する音楽家フローベルガーのアルマンド、その師だったフェラーラのフレスコバルディのトッカータ、そしてモンテヴェルディの「第2作法(seconda pratica)」、論理より感覚を、多くの声を平等に操作する技術から、自由なメロディーの抑揚へ。でもポリフォニーからモノディーへの歩みはその代償のように和声を発展させる。
白い音符の音楽の別な使いかた。音高と順序だけを記すのは、それが音楽のなかでもっとも重要な要素だからではなく、書くことができる最小限の部分で、スプーンの柄のようにスープから突き出ていて、アルキメデスの梃子のように、動かしながら探っている先端は見えず、書けず、ことばにもならない。演奏は固定したリズムを離れて、わずかなうごきや強弱・緩急のちがいを捉え、アクセントを変えながら多彩なパターンをその場で創りだす。だがそれらは定着せず、その場に応じて毎回やり直して、演奏は完結することはないだろう。
最小限の楽譜は秘教的なものとみなされれば、それを解読し、分析し、和声構造やリズムの規則性を発見することで、既成の音楽的秩序に引き戻すのが音楽学の務めなのだろうか。そういう試みが無用とは言えないが、光を知りながら陰の側にいて、見えている構造は仮の足場以上のものとせず、風が吹きすぎ、さまざまな種子を呼び起こして入り乱れる軌道に舞わせるように、解釈のおよばない部分に触れながら、すぎていく一回の演奏で遠くまで逝き、また反ることができれば、手慣れた型が聞きなれない響きを立てる時がくるだろう。音楽は聞こえるものでありながら、聞こえないものの兆しともなって......