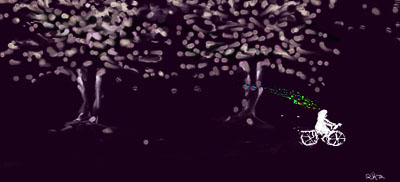慌しく時間が過ぎていった今月も終わろうとしていて、オーケストラとの練習の合間、指揮台に寝転がって劇場の天井のライトをぼんやり眺めながら、いろいろな風景を思い返していました。
震災後成田にアリタリア機で降り立つとき、乗客がみな少し緊張して思いつめた表情をしていたこと。朝の成田空港でカツカレーを頼んだとき、出された水を飲むのを無意識に一瞬ためらい、後ろめたい感情に襲われたこと。
年末に他界した祖母の墓参に湯河原へ出かけた折、時差で疲れて東海道線で眠りこんでいて目が覚めると、思いがけず茅ヶ崎の線路端に並ぶ母方の祖父の墓地を通り過ぎるところだったこと。祖母の墓誌に刻まれた真新しい日付は奇しくも自分の誕生日で、海に程近い親戚の家に立ち寄ると、津波に対し半ば絶望的な心地で暮らしていたこと。
息子に付き添った東京の小学校の入学式は咲き誇る桜が美しく、記念写真を撮りながら自分が小学校に入った時に着物姿の母親と撮った写真を思い出したこと。思えばあれは誰が撮ったものだったのだろう。父か或いは誰か友人が撮ってくれたものだったのか。それからの三週間、「起立、礼」の号令すら知らなかった息子には、とても新鮮だったであろうこと。学校は道路を隔てて目の前にあって、ほんの短い距離だけれども、自宅から学校まで、小さい身体に似合わないランドセルを背負って一人で通学することに息子が得意になっていたこと。
イタリアでは小学校の間はずっと親が送迎しなければならないので、日本でなければ出来ない体験だったけれど、授業についてゆけるのか不安で、窓から校庭の一年生をちらちら目で追ったりしたこと。昔は一学年6クラスはあったのが今は2クラスしかなくて、学年全体で一緒に体育をする姿に少し驚いたこと。毎日繰り返される余震や、耳慣れなかった防災放送、それに続いて校庭に走り出してくる銀色の防災頭巾を被った子供たちのこと。
東京より肌寒かった四国に仕事にでかけ、まるで別世界のように感じたこと。
高松のフェリーを見ながら、外海に面したヴェニスの岸壁に停泊する客船を思い出したこと。
春、なだらかに続く山に桜や桃が散らしたように咲きほころんでいて、桃の深みのある彩に感銘を受けたこと。
日本の春の趣に、あたりの空気にまで染み通るような艶かしさを覚えたこと。
リハーサルを終え夜半閉まりかけのラーメン屋に駆け込んだときのこと。何気なく置かれていた出来たての叉焼が美味しそうで、思わず少し切ってほしいとお願いすると、年配の親父さんが、店には出さない一番美味だという縁側の脂身を自慢げにこそげ落として出してくれたこと。彼の讃岐弁はよく聞き取れなかったけれど、叉焼の美味しさとともに心に残っている。
岡山に抜ける電車が海を渡るとき、高所恐怖症と余震の恐怖で息苦しくなったこと。あそこで地震が起きて電車が止まっても、足がすくんで非常用通路に下りる勇気はなかったに違いない。お宮参りのおくるみを抱えた華やかな女性たちが賑わいを添える春の春日大社で、友人が十二単であげた結婚式の床しさ。奈良の建築に塗られた朱の大陸的な味わい。
東京に戻って久しぶりにみんなで集った「味とめ」が、思いの他元気で安心したこと。夜のハチ公前を通ると、電光スクリーンの消えた思いがけない暗さに子供の頃通った渋谷を思い出し、蒸し暑く、人間臭い節電中の通勤電車にすこしだけ懐かしさを覚えたこと。
ミラノに戻る飛行機は驚くほど空いていて、マルペンサ空港のパスポートコントロールには、アフリカの移民が犇きあい、ここには当然ながら別の現実があったこと。ミラノに街に降り立つと、身体の奥のどこかで緊張の糸が解れて、日本の人々思って申し訳ない心地に駆られたこと。久しぶりに会うオーケストラのメンバーの元気な様子も嬉しく、一日のリハーサルを終え、ふらりと立ち寄る劇場脇の「ラニエリ」のラム酒漬けの小さなババと立ち飲みコーヒーが、身体を染み通る幸せに感じたこと。
つい先日まで、せめて息子が死ぬまで、彼が惨い戦争や紛争に巻き込まれず恙無く暮らしてゆけることのみ願って暮らしていて、ささやかな希望は平和だと信じていたけれども、この言葉がただ諍いごとのみに使われるのではないことを、噎せ返るように咲く桜と一緒に、こんな形で知ってしまったこと。