しゃらしゃら しゃりり
柔らかく鳴るボラ・ミンピ。
ガムランボールとも呼ばれるお守りを
知り合いの妊婦さんが身につけていた。
ボラ・ミンピの優しい音は
お腹の中の赤ちゃんにも、ちゃんと聴こえている。
しゃらしゃら しゃりり
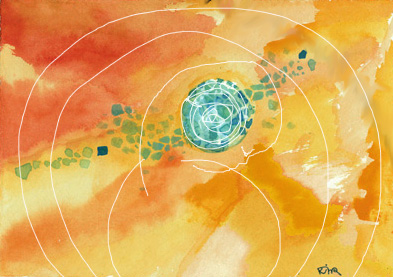
しゃらしゃら しゃりり
柔らかく鳴るボラ・ミンピ。
ガムランボールとも呼ばれるお守りを
知り合いの妊婦さんが身につけていた。
ボラ・ミンピの優しい音は
お腹の中の赤ちゃんにも、ちゃんと聴こえている。
しゃらしゃら しゃりり
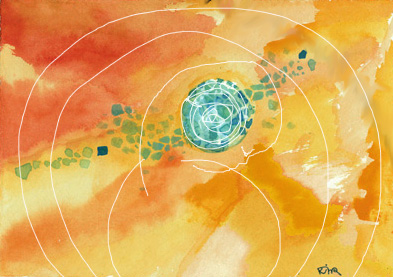
八月の旧盆過ぎて何やら、うちの上をいろんな飛行機が飛ぶようになった。ここらへんは長い二本の滑走路の延長線上じゃない。短い滑走路の上から少し外れたところだけど、演習空域を少し変えたのかなあ、と思いつつ九月になり朝夕は涼しい風が少し吹くようになったがお日さまが出ている限りは直射日光は暑い。
台風15号ぐるっと一周したあと、最低気温が最高気温30度、最低気温は25度以下。涼しくなったなあ、と思うも束の間、熱帯夜。日差しも夏に逆戻り。でも雲だけは秋の雲。首都圏直撃の台風の映像をテレビで見ながら、よくあんな風の中で傘さす勇気あるなあ、あの風じゃ外に出ちゃだめでしょ、と思いつつもこちらでは台風でも飲み屋街は営業している。台風になるとテンション上がり酒盛りする輩大勢。
九月はじめ、今年の四月からピアノを習い始めた娘、九月からツェルニーにすすむはこびとなったためお月謝が五百円増しとなります。えっ、そんなシステム聞いてないないよ〜。これから習う楽譜が変わるごとにお月謝値上げ? こちらのお給金はいっこうに上がらない。
八月にきたパソコンに苦戦しつつもいろいろ設定を変え、少しなれてきたが、キーボード、マウスの安っぽいこと。その上、家族共用の携帯電話、アンドロイドが増えた。これも少しいじってみたが、まあわかりにくいところいっぱい。少しお勉強必要、通信費は多くなる。この際、デジタル通信一切やめる、ということもすこし考えてみよう。
四月以来、段ボールの中に追いやられたCDを整理するため、久しぶりに電動丸鋸を出し、CDの棚を作るため合板を切る準備。作業着、ゴーグル、防塵マスクはないので普通の使い捨てマスクをまとい、上を飛ぶ飛行機に負けないくらいの騒音で板を切る。あとはやすりをかけて、オイルステンをシンナーで薄めて板にこすりつけるだけ。久々の丸鋸はかなりの音響、切れ味悪い。
冷たい月に輪をかけて引っ張る
その紐の影には
凍った太陽が沈んでいる白い湖の風景だけが
ぼんやりと映っていた
深い夜には
そう
小指の足音だけが
まるで石を投げる涙の瞳のように
絶え間なく鳴り響いていた
一度放たれたは矢は
どこかへ突き刺さるまで飛び彷徨い続ける
授業でこんな実験をしてみた。各自それぞれ自由に色えんぴつで絵を書いてきてもらう。具象、抽象、どんな絵でもいい。あらかじめその絵を言葉で説明できるように言っておく。全員が集まり、ひとりひとりがその絵を言葉だけで説明し、他の人がそれをききながら色えんぴつで言われた通りの絵を書いていく。物体の名称はそのまま使ってよいが、その場所や大きさを表現するのは難しい。右上の雲は「上半分から2センチから紙下半分くらいまで8モク(雲のやまのこと)」など。同じ説明でもまったく違う絵ができあがる。言われたような物体がそこにあることはあるが、全体のバランスを計ることとはむずかしい。具象でも抽象でもそれはあまりちがいがない。
これはスペースシャルの飛行士と地球の基地との交信で大切なことらしい。テレビでやっていた。危機のときの状況説明に必須なのだろう。とても複雑な色つきの図形を正確に描画できるらしい(実際にやっているところはやらなかった)。どうやったらそんなことができるか考えてみたが、なかなか難しい。簡単な図形ならできる。しかし机といっても形や大きさ、角度などいろいろある。できるだけ正確に伝えても言葉の感じ方でも変わってくる。実際、生徒たちは原画に対して意味不明な説明をしたし、絵を書いた。二人ほど、非常によく似た絵を書いた人もいた。そのちがいは、言葉の正確で具体的な表現、ききとり能力、正確な描写、それと勘のようなものだろう。
机ではなく、サザエさんならどうだろうか。みんなに頭のなかのサザエさんを書いてもらう。みんな一応、サザエさんを知っている。確かにサザエさんを思い浮かべることはできる。サザエさんと思うものは紙に書こうとするとサザエさんからズレていく。比較的近い人もいるが、髪型の特徴だけが残されて、眼や口の細部は曖昧になる。机のような機能や概念に親しみのあるものは別として、われわれの生きているほとんどの世界はそのようにあいまいなものなのだろう。そして言葉で説明することも難しい。ひとつズレるとそのズレがより大きなズレを引き起こしていく。しかし、それがおもしろい。オリジナルはどんどん形を変えていく。
荀子の訳に変調の詩とある
月明かりには旧い国歌
祖国の終わったあとから
まだ歌っている独立
終わる言語の西夏に
倒立する等身大の硝子玉
はいあがる遺跡
俑をならべるシルク・ロード
嬰 すこしあがり
変調の砂埃 沈む夕陽に
詠 いつまでも詠
恋しい馬の白骨 歌う骸骨
汚染するのか遺跡
(「詠 いつまでも詠」、会える日、出番、きみが恋する世界、草葉の光り、すべてが待っているから。)
葉っぱの落ちた柿の木の奥に大きな藁葺き屋根の家。日差しを受けて、軒下に並ぶ真っ白な和紙の端が浮いている。
乾き反る和本表紙や百舌猛る
東京葛飾の日枝神社近く、水本小合上町で和本表紙作りを生業とする家を訪ねた石田波郷の句だ。波郷は昭和32年3月から江東区、墨田区、江戸川区、葛飾区、足立区にカメラマンとともに足を運び、季節ごとの風物や景色を文章と句にして読売新聞に掲載した。昭和21年に疎開先から親戚の家をたよりに江東区に移り、病を抱えながら焦土に得た畑を耕し幼い子供二人を育てて10年、低い土地にむくむくとわきおこる戦後を記録した。連載は115回にわたり、昭和41年に『江東歳時記』(東京美術)として刊行。なるほどこの本と地図を片手に、界隈を歩きたくなる。
この地での和本表紙作りは、天明元年に地元の名主細谷秀蔵が始めた。蔦屋重三郎など複数の得意先を抱えたが、のちに謡本の表紙や官庁の綴込表紙、帙畳紙(ちつたとう)などをてがけるようになって、支那事変をきっかけに家と謡本表紙作りの権利を買い取った一色さんが引き継いだ。生麩糊をひいたりロールで型をつけたりする行程を見学した波郷は、「古い大きな藁葺屋根の下でするにふさわしい仕事である」と書いている。
波郷は最初の句集『石田波郷句集』(昭和11年 沙羅書店)の編集装丁を自らおこなっている。村山古郷『石田波郷伝』(昭和48年 角川書店)によると、「俳句の上下は揃えず、ノンブルは日本数字、製本はボール紙抜きのクルミ本略装、本文はアンカット、化粧裁ちせず、函は一枚ボールの折畳み」「表紙は鳥の子紙で装釘され、句集名も著者名も文字は一切印刷されていず、真白」、山口誓子は「馬酔木」昭和11年2月号に「どっから見ても白面(パイパン)なのでパイパン句集だ」と評したそうである。
今秋、山本義隆さんの『福島の原発事故をめぐって いくつか学び考えたこと』(みすず書房)を手にして、なぜだかこの「パイパン句集」という言葉を思い出したのだった。表紙カバーと帯の地は白であるがタイトルも著者名ももちろんあって、際立ってシンプルでも気取ったものでもない。100ページの本文はゆったりと組まれ、1000円という値段が似合うように感じられた。「みすず」にと依頼されて書いたものが長くなってしまっておそるおそる渡したら、いっそのこと単行本にしましょうと言われたとあとがきにある。もしも「本」になれるなら、素っ気なく、なにげない装丁が似合うものでありたいと思う。今日は秋晴れのよい休日。工事の音に起こされた。ときおりの風に洗濯物がひるがえる。
41
「何を持っている、彼は?
彼は彼が持っているものを持っている。
でも何を?」(ウォレス・スティーヴンズ)
おれがおれである以前にはなくて
いつしか所有が始まったものとは何だったのか
本能的な哲学ではなく野蛮な言語でもないだろう
日焼けした椰子の実でもなく狼の毛皮の聖書でもないだろう
おれはただ歩いた一歩のその足跡において
そのつどの小さな面積に見合っただけの経験を得た
所有とは物ではなく、そんな足跡の累積だった
持つことと失なうことの区別もよくわからないな
狂ったような力で吹きつけてくる風に気まぐれな心を飛ばすとき
そのとき「持つこと」自体が失なわれて
「すべて」がきみを丸ごと捉えることがある
星から斜めの光がさしてくる
おれのすべての足跡が砂漠に還元される
42
光の中への閉め出しという事態が想像できなかった
ここから、この光から
逃れるということができない
壁もなく、扉もなく、屋根もなく、風見鶏もいない
光が恩寵であっても音楽であっても
それをかわすことができない
不思議なことにそんな出口なしの状況でも眠りは訪れる
熱い砂浜で皮膚の表面がどんなに
焦げ、傷つき、悲鳴をあげるとしても
網膜をシャワーのようにつぶつぶとした光にさらしながら
暗闇がふと希望のように、あるいは夢として
思い出として訪れるのだ
光に対抗する決意をしておれは
瞼の裏側から赤、オレンジ色、紫を追放する
おれが求めるのはしずかな暗闇
眼球を星空のように落ち着かせる藍の先にあるもの
イラクの少女アヤは、6歳の時にがんになり片足を切断した。今は12歳になって、9月から中学校に行く年頃の少女になっている。その間彼女の成長に合わせて、義足の支援を続けてきたが、一方で、足を失った子どもたちはイラクにたくさんいて、彼女だけしか支援できない僕たちが情けなく、後ろめたくもあった。
震災が起きて、6ヶ月経ったが、震災直後に彼女からもらった手紙があり、ローカルスタッフにどんな事が書いてあるの? ときいても、「日本への感謝だ」ということであまりきちんと訳していなかった。改めて、アラビア語が堪能な加藤君というのに頼んだところ、ああ、あの小さな少女がこんなに成長しているんだと感動したので、全訳を皆さんにも読んで欲しい。この6ヶ月、イラクと、東北を歩いて感じたのは、戦争も、震災も、人びとが受ける苦しさは、全く同じだ。「地震や津波は必要だった」という人はいない。しかし、イラク戦争は、「必要だから支持した」というのが政府の見解だ。イラクの人たちの苦しみを、今始めて僕たちも実感できたのではないだろうか?日本の責任は大きい。期せずして911からも10年が経った今年、日本が復興して目指す国は、世界に平和をもたらす国になって欲しい。
* * *
バグダード陥落
2003年3月20日、アメリカがイラクを占領するためにやってきた。国を壊すために、そして市民を制圧するために。イラク市民をアメリカの下にしばりつけておくために。陸も、海も、空も、イラクのすべてが取られてしまった。混乱の中でイラク市民は相争うようになってしまった。2003年4月29日、バグダードは攻め込まれた。バグダードは暗い墓場のようになってしまった。あの時から「アル・カーイダ」がイラクに入ってくるようになった。彼らのために爆発やテロ行為がたくさん起こるようになった。お年寄りや女性、そして子供がたくさん犠牲者になってしまった。放射能が原因で、爆発の煙が原因で、戦争のゴミが原因で多くの子供が犠牲になってしまった。
私もその中の一人。6歳の時、右足にガンを患った。放射能が原因だ。でも私の国には治療がなかった。薬や治療に必要な道具は盗まれてしまっていた。でも日本の支援のおかげで隣の国に治療を受けに行くことができたの。神様のおかげ、そして日本のみんなのおかげで治療を終える事ができた。ハムドリッラー。
地震と津波
日本で第二次世界大戦以来と言われる程とっても酷い悲劇が起こってしまった。これまで世界の国々に支援の手を差し伸べてきた日本が今、災害に見舞われている。神様にお願いするわ。日本のみんな頑張れるように。私はイラクの子供達の代表として、日本のみんながこの試練を乗り越えることができるようにお願いする。かつてイラクの子供達が辛い戦争や病気の時を乗り越えたように。
私達は日本のみんながこれまでイラクを、特にイラクの子供達を助けてくれたことに本当に感謝しているの。インシャーアッラー、悲劇が過ぎ去り、安寧がこの平和な国を包むでしょう。世界中の人々に優しさを届けてきたこの国を。だから世界中にお願いするわ。みんなですべての力でもって、そして手に手を取って素晴らしい友人である日本を助けてあげてって。彼らが困難を乗り越えられるように。
気がつくといつも月末になっていて、それまでに書くことは沢山あったはずなのに、いざ机に向かうとなぜか決まって頭の中に深い霧が立ちこめてきます。毎朝早く、朝食のパンを買いついでに息子と散歩していると、日の出がみるみる遅くなって、朝日も秋らしい乾いた黄金色に変わってきた気がします。
拙宅はミラノのナヴィリオ運河近くにあって、時折ネズミの親子が連れ立ってベランダで遊びにくるのも仕方ないかと、さほど気にせず暮らしておりましたら、壁伝いにネズミがやってきて困ると苦情を言われてしまいました。家の半分ほど覆っていたつる草を一気に剥ぐと、見通しこそ良くなり広く感じられますが、いきなり髭を剃ったときの気恥ずかしさがあり、土壁のつる草には可愛らしいクロウタドリも巣を作っていて心配していたのですが、こちらはどうやら難を逃れたらしく安心しました。
ブーレーズの「エクラ・ミュルティプル」を勉強していて、今月は作曲者の素晴らしい自作自演を聴きに出かけてきました。「エクラ」だけでなく「プリ・スロン・プリ」の名演にも立ち会えて、両作品の美しさはもちろん音楽的な作曲者の指揮に深く感銘を受け、特にフレーズやアウフタクトも思いがけずクラシカルに感じられたりもして、本当に目から鱗が落ちる思いでした。自分がどこまで出来るかわかりませんが、何れにせよ現在も健在な”名演奏家で大作曲家”と向き合うのは簡単ではありません。
ブーレーズの真似をするわけにもいかないし、真似をしないわけにもいかない。真似をしたところで彼ほどの演奏ができるわけがありませんし、真似をしなければ、彼の演奏に触れた意味もなくなるどころか、作曲者の意図に近い演奏に接したいはずの聴衆を欺くことにもなりかねません。ただ、作曲者の演奏ばかりを追い求めても、演奏を重ねるなかで変化してきたものもあるだろうし、作曲者のみに許される解釈もあるはずです。
作曲時と現在とで演奏の理想が違うこともままあるかもしれませんし、何が正しいか一概に言えないにせよ、少しずつ自分のスタンスを見つけていかなければなりません。それには譜面を地道に読みこむことだろうし、たぶん普段より読みこまなければいけないのだろうと思います。あと半世紀もすれば、ブーレーズもマーラーのように扱われる日が来るかもしれませんが、マーラーの当時と今とでは環境もずいぶん違いますから、たかが半世紀後であれ、やはりまた違う環境で演奏されているのではないでしょうか。その頃どんな風にわれわれの現代作品が扱われているのか、ちょっと見てみたい気もします。
先日、補完したドナトーニの出版譜2冊を初めてリコルディから受取り、13年ぶりに楽譜を広げてみました。今ならこんな風には直さない、こう書いただろうと嫌なところばかりが目に付き、自分がこれほどロマンティックだったかと呆れもしましたが、自分の主観に基づいて、生きている作者の作品に公けに解釈を施したというところが今回のブーレーズに少し似ています。
ドナトーニが糖尿病の発作で倒れ、朦朧とする意識の中で書きなぐった音符をどう解釈し繋ぎ合わせるか、出版社から頼まれていた締切りぎりぎりまで、全く手がつけられなかったのを覚えています。初めて作曲者に書き直した楽譜を見せたとき、彼が目の前でぼろぼろと子供のように大粒の涙をこぼしているのを、やり切れない気持ちで見つめました。自らの身の上に起こったとは思えない目を背けたくなるような現実を目にして、無言で立ち尽くして自身をきりきりと苛む姿にかける言葉もなく、大きな老人が、まるで子供のように小さく見えました。
あれから出版まで作品と付き合ったけれど、なんとなくそのままになってしまい、出版社に楽譜をほしいと言ったことはなかったのです。今になってコンピュータで清書された楽譜を手に取っても、自分が携わった実感が沸きませんでしたが、ページを捲っていって無残に残された無音の小節を見たとき、途端に気持ちが塞ぐのがわかりました。どうにもこじつけようがなくて、結局手稿通り残した休符が暴力的に並ぶさまは、自分にとって荒涼とした光景以外の何でもありません。あちこち紫色に変色し、腐り始めた糖尿病末期の身体や、喉から飛び出していた数本の透明なチューブ、むっと鼻をつく病人の臭いと掠れた呼吸音。びっしりと記憶がはびこった小節たちは、息をひそめて、じっとこちらを見つめていました。
片岡義男さんの短編集『木曜日を左に曲がる』の出版を記念して、詩人の小池昌代さんとの対談が千駄ヶ谷のブックカフェ「ビブリオテック」で開かれた。9月10日、まだ秋が始まったばかりの土曜日に片岡さんの話を聞くために出かけて行った。
イベントの案内には「ほんの一歩、それが小説。さらに一歩、それが詩。一歩から物語が生まれる。一歩とは希望。でも、自分は自分でしかないのに、どうしたら自分の外へ踏み出す一歩の言葉を作り出せるのか? 「一歩」の言葉が生まれる時間と場所を、こっそり教えます。」とある。小説の1歩と詩の2歩。小説も詩も両方書く二人の間にどんな会話が交わされるのか、期待を胸に出かけた。
以前小池さんが紀伊国屋書店の名物フリーペーパー「じんぶんや」で、片岡さんの『日本語の外へ』を大切な1冊として推薦しているのを見た時、意外なうれしさを感じた。詩人というものが言葉に対してもっているこだわりと、片岡さんが言葉に対してもっているこだわりは、違う世界の話のように感じていたからだ。
対談の中盤、小池さんの新しい詩集『コルカタ』に登場する少年の話になる。インドのコルカタに住む「純粋な光を放っているような少年」(と片岡さんは紹介していた)が詩を書いている。そして、その”ひみつ”をやすやすと姉によって明かされてしまった少年は、自分の部屋にまっしぐらに逃げ帰ってしまう。「見せたくなくて、逃げるという事は自分にはなかった。」と片岡さんが言って、そこから対話は核心に入っていったのだった。片岡さんは、その最初の作品から、人に読ませるための文章を書いてきたと言う。商品として成り立つ文章、読まれないと完成しない、共感があってはじめて完成する職業人としての文章を書いてきたというのだ。
安っぽい謙遜ではなくて、本気で、誰にも見せたくないという思いを持って文章を書く少年は、何のために書くのだろうか…。たぶん、自分のためにではないか。自分が世界を理解するために、世界をしっかり掴むために。書いて、世界を言葉で確かめているということではないだろうか。この世界にぴったりあてはまる言葉、時には、目に見えないものの存在を指し示す言葉。当然書かれたものは、納得できるまで充分に彼独特なものとなるはずだ。言葉は、時に通常の使い方とは違った使われ方をして、そのことによって役割を果たす。そのように書かれた言葉は、独特の手触りを持った言葉になっているような気がする。そして、その独自性、いびつさが、誇らしくもあり、とてつもなく恥ずかしいということではないかと思う。
小池さんは、「詩には、私のほんとうのほんとうの部分が残り続けている」と言い、「僕はそうなれない」と片岡さんは言う。一流の言葉遣いの二人が、言葉の持つ表裏一体の魅力について語っていて印象的だった。
「他者性と間接性が大切だ」と片岡さんは繰り返し語った。片岡さんは、言葉に固有の意味を付加するという事をしない。片岡さんにとって言葉は、「レゴの部品」のひとつひとつのようなものだと言う重要な発言も聞かれた。では、彼の書くものが無味乾燥なのかというと、そんなことはないと思える。
言葉は人と共有できるくらい、充分に洗練された道具として、既に充分魅力をもっているのではないか。手作りの、ごつごつとした手触りを持った言葉ではなく、人々を媒介する道具となりきった言葉の魅力について、片岡さんは承知しているような気がする。片岡さんの作品の持つ清潔感というか、空気の乾いた空間の気持ち良さのようなものは、この言葉の扱い方から来ているのではないかと思った。もう少しよく考えてみなければならないのだけれど。
片岡さんには、スーパーマーケットの棚の魅力について書いている文章があったけれど、ちょっと共通するイメージとしてそのことを思いだしたりもする。
9月16日にバンドンで行われたジャワ神秘主義実践者らの集まりで踊ってきた。というわけで、今回はインドネシア、中でもジャワの信仰について書きたい。
インドネシアでは宗教と信仰は別とされていて、前者は宗教省の、後者は観光文化省(認定された時点では教育文化省)の管轄下にある。普段は略して「信仰」と言っているけれど、正式には「唯一神への信仰」と言う。ちなみに宗教として公認されているのは、イスラム教、キリスト教・カトリック、キリスト教・プロテスタント、仏教、ヒンドゥー教、儒教の6つである。儒教はスハルト退陣後の華人文化の復権に伴って再公認された。
信仰は各地に土着的なものがたくさんある。以前は、信仰を表す語はクバティナン(内面的なるものの意)だったけれど、前・信仰局長の話によれば、信仰を表す語はクプルチャヤアンに統一されたので、クバティナンは今は使われていないとのこと。
私はジャワ以外のことはほとんど知らないので、ここではジャワのことだけ書く。ジャワで実践されている信仰は、特にクジャウェン(ジャワ的なるものの意)と呼ばれ、ジャワ神秘主義と訳される。彼らは占や暦を信じ、霊的な力の強いとされる日に、霊的な力を得られるような場所(聖人の墓、巨石のある場所、川など)で瞑想やみそぎなどの修行をしたり、断食をしたり、霊が宿るとされる石やクリス(剣)を大事にしたりして、霊的な力を得ようとする。また、一定以上の霊的な力を得た人は、そういう力で以って他人を施術することもある。
そういう信仰を実践している人たちは、自分たちのことをプングハヤット・クプルチャヤアン(信仰実践者)と称する。インドネシアには、似たようなカテゴリの人を指す言葉として、パラノルマル、ドゥクンという語があるが、信仰実践者を自称する人達は、彼らと一緒にされることを喜ばないので、注意が必要だ。
パラノルマル(英語のparanormal)とドゥクンはどちらも超常能力を見につけた人のことを指し、特に、失せ物・失せ人探し、事業の予言、病気治療などを得意とする。ただし、インドネシアでは、どちらもネガティブな響きを持つ単語だ。特に、少なくともジャワでは、ドゥクンという語を耳にすることはない。そこには、呪術師のようないかがわしい感じの響きがある。パラノルマルの方がまだしも耳にするし、王宮広場のイベントで「パラノルマル大集合!相談コーナー」という企画もあったので、ドゥクンほど否定的な響きはない。それでも、一般の人たちにはこういう人たちのことをオラン・ピンタール(賢人の意)と呼んで、パラノルマルやドゥクンという語を口にしないことが結構ある。
パラノルマルやドゥクンは信仰実践者と違って、その能力によって生計を立てている。信仰実践者が一緒にされたくないと考えるのも、それが一因だ。信仰実践者は何らかの職業で生計を立てながら信仰し、そこからお金を得るようなことはしない。信仰の実践として他人に施術することがあっても、お金を受け取らないのが普通なのである。
パラノルマルの人たちは、卓越した能力があるかどうかだけが問題なので、その能力の由来する宗教はまちまちだ。クリスチャンのパラノルマルだって大勢いる。そして、××教徒であることと、パラノルマルであることとは矛盾しない。
けれど、信仰実践者の場合は少し違う。ジャワではイスラム教は土着信仰と混交してきたので、イスラム教徒であることとクジャウェン信仰が矛盾しないと言う人も少なくないが、いずれの宗教の信徒であることも拒否する信仰実践者も少なくない。インドネシアでは2006年、前・信仰局長の時代になって初めて、信仰実践者はKTP(身分証明証)の宗教欄を空欄にしたままでよいということが法律上で認められた。それまでは、いずれかの宗教に属していなければならなかったのだ。
それでも、社会的には信仰実践者というのはマイナーな存在のようだ。私が出演した信仰実践者の集まりはバンドンにある国営ラジオ局で開催されたが、信仰実践者の集まりに場所を貸すことに反対する勢力が根強くあって、開催までスッタモンダがあったと聞いた。前・信仰局長の話でも、信仰実践者の集まりに招待されて出かけたら、その会場の周囲をイスラム教徒の反対デモが取り囲んでいるというようなこともあったらしい。
似たような存在だと思われているけれど、信仰実践者とパラノルマルは、法的には別の存在である。今まで述べてきたように、信仰実践者に関することは観光文化省信仰局の管轄だ。しかし、パラノルマルは、実は、最高検察庁(Kejaksaan Agung)の管轄下にある。また、信仰は観光文化省信仰局の管轄下にあるといっても、これは信仰実践者団体を管轄しているだけで、個人の信仰までは管轄していない。そして信仰団体とは、教義を持っている団体のことなのである。(そうなると、別に宗教と信仰を分けなくてもいいと思うのだが…。)パラノルマルは個人の活動なので教義は必要ないという点でも、信仰局の管轄から外れてしまう。
そういえば、私が毎週欠かさず見ているTV番組のあとに「THE IDOLM@STER(アイドルマスター)」という作品が放映されておりまして、流れでそのまま見ているのですが、どういう内容かと申しますと、いろいろな個性を持つ新米アイドルたちの日常(仕事・レッスン・交流)や、彼女たちを売り込んだりしてスターに育てていくプロデューサの奮闘を描いていく、アイドル事務所のお話なのです。
ぼーっと見ているときは、だいたいささいな妄想も伴っているのですが、このあいだふと思ったのは、こういうアイドル事務所的な〈翻訳家事務所〉は、ありえるんじゃないかな、ということで。つまり、所属する翻訳家のキャラと能力を前面に押し出して、そのための宣材を作って営業をかけて――というような。もちろんそれと同時にレッスンやら、事務所や控え室での翻訳家同士のわいわいがやがやとした交流なども含むわけですが。
もしかすると、足りなかったのはこういうものなのかな、という考えもありまして。というのも、ある意味では翻訳業界とアイドル業界は通じるところがあるのです。とりわけ1990年代、ご存じの方もおられるとは思いますが、一部の女性翻訳家がアイドル視されることがあったわけで、しかも成功したキャリアウーマンとして、女性たちの自己実現の対象として目されました。しかしもちろんそこには裏があるわけで、そこへの憧れや欲求をあおることで、語学業界はたくさんの教本を売り、翻訳学校におおぜいの生徒を集めた、という寸法。
こうして90年代以降、多くの翻訳家志望者を生んだのですが、ところが問題になるのは、そういった人々が抱いていたイメージと、翻訳業界の実体にギャップがあったことです。彼女たちは翻訳学校を卒業後、その運営母体である翻訳会社にフリーランスとして登録されたりするのですが、そこから回ってくる仕事は基本的には縁の下の力持ちのような、名前の出ないもので、くすぐられた自己実現とはほど遠いもの。翻訳会社にしても、喧伝するのは〈自社〉であって、いかに安く早く何でもできるかというようなこと、個々の翻訳家なんてどこにも見えず、生徒を集める際に説明したあれやこれやの形もありません。
また文芸翻訳家を目指すにしても、卒業後は自助努力で、もちろん地道に出版社でのリーディングを経て訳者の地位にたどり着く人もいますが、苦労して得ようとするそれも、何というか強いコネさえあればその過程は理不尽なほど簡単にすっとびますし、ましてや有名人・芸能人なら。(このあたりの事情から〈翻訳家を目指さないことが翻訳家への一番の近道〉という逆説に気づいた私があれやこれやし始めるのは別の話。)
と、いうようなことを踏まえたとき、下地としては90年代から00年代を席巻した〈アイドルを目指すブーム〉と下部構造がどことなく似通っているわけなのですが、向こうにあってこっちになかったものは、やはりアイドル事務所的なものなのではないだろうか、と妄想したりもするのです。つまり、せっかく育てたのに、その人をちゃんと売り出すようなところがなかったのではないか、少なくともエージェントでもあれば現状はいろいろと変わっていたのではないか、と。しかも、今や語学教育の若年化が進んでいるのですから、おそらく翻訳の教練もそれこそ中学校どころか小学校から低年齢から行える(私は中学からですが)、可能性として翻訳姫・翻訳王子のようなアイドルを誕生させることさえありえて、インターネットの普及した今であればそういった人たちを売り出していく事務所も割と現実的に作れるのではないか。
なーんてことを大した真剣味もなく考えていましたら、先日学会に出た折、そんな妄想も冷めてしまうようなことが耳に入りまして。なんと、今の子たちは翻訳に対してもっともっとドライに考えているというのです。もはやアイドルや自己実現としての翻訳家イメージは影も形もなく(というのは言い過ぎかもしれませんが少なくとも以前ほどではなく)、翻訳はあくまでもスキルのひとつ、社会へ自分を見せるための売りのひとつにすぎず、翻訳を学習する人も、翻訳家になりたいというよりは要領よく効率よく技術を身につけて利用したいと考えているのだとか。
ひょっとすると、承認欲求をあおるよりもそっちの方が健全かも。実際に、スキルとしての翻訳の技術や知識は、いろいろなところで必要とされているようですから、無理に目指して路頭に迷っちゃうよりも。言われてみれば、00年代で大きくプッシュされたアイドル翻訳家なんてあまり思い出せませんから、そもそも抱きようがないのかもしれませんね。正直、社会的には文芸翻訳よりもビジネスにおける翻訳の方が、支えるものとしての重要性は高いわけですし、そういうものを毛嫌いしたり下に見たりする風潮もどうかと思いますし(翻訳家の偶像視はそういう点でも悪影響だったかも)。
まあ、でも今の私は、翻訳業務だけでなく営業も経理も宣伝も編集も鍛錬もみんな自分でやっているわけなので、個人的に事務所はほしいかも、なんて。とはいえ自分がアイドルとして売り出されるとなると…………あははは、演技としてなら結構嬉々としてやりそうな気がする、私。
最近、いろいろといらっとすることが多い。別のタイトルでもっと刺激的な話を書こうかとも思ったが、全ての根源が「矛盾」なのだと気付いたのでこのタイトルにしてみた。先月も吐露したが、私の見方は万事が万事、斜め向きである。斜めで見たときにこんな見方もあったのねと温かい目で見てもらえれば幸いです。
例えば、自然エネルギーと言ってもなにを示しているのかよくわからないのだ。日本は恵まれているといわれる水力にしても、過去からの歴史は綿々たる自然破壊の歴史であった。多くの自然環境がダムの下に沈み、多くの遺伝子資源が失われてきている。以前から矛盾に思ってブツブツ文句を言っていた東京電力の「尾瀬で自然保護」キャンペーンだが、もともと東京電力は尾瀬にダムを建設するために付近の土地を買い占めた背景がある。幸いにしてというか、東電の思惑が外れたというべきか、尾瀬は自然保護運動などの結果残っただけの話で、別に自然保護のために東電がナショナルトラストよろしくCSR(企業の社会貢献)の一環で購入したものではない。逆に言えば、水力を再開発するといえばすぐに尾瀬で開発計画が進められる(すでに土地は購入済み)し、全国で尾瀬のような話が噴出するに違いない。
もともと自然科学の世界の人間だったので、そうでなくても、小規模な砂防ダムの建設で世界唯一の生息地をなくしたと見られる植物の話はいくつもできる。結局のところ、自然エネルギーなどといっても所詮は人工物を作る限り、どのようなものを作っても自然を破壊することには違いない。例えば、何回かの推進策で一時はブームのようににょきにょき建設された風力発電所だが、結局は作ったけれども回らない風車が続出し、環境問題や経済問題(投資資金が回収できない)、景観問題などを引き起こしたことを大都会の人たちは知らないのだろうか。都会の人工物の中なら風力発電の風車は気にならないのだろうが、自然景観の中でみる風車は異様の極みでさえある。
また、海上に建設するともいうが、海洋動物、特に音波を重要なコミュニケーションに使う海獣や鯨類に対する問題が生じないことを確かめているとも思えない。最悪こうした問題に関する研究を行い、環境アセスメントを行えば、建設までに数十年単位の時間が必要になるに違いない。ただし、「自然エネルギーがいい」と主張する人たちからそうした問題に対する対応策のひとつも聴いたことはない。まあ、だいたいにおいて、火力で代用などと、少しまで大騒ぎだったダイオキシンだの、CO2だの満載の手段を持ち出してくるのだから考えているはずもないのかもしれない。要は、大局的に見ていないその場しのぎの思いつきに過ぎないのだろうけれども。
「何とかムラ」なる言葉もよく一方的な呼び方だ。本来、発電所で作られる電力の恩恵など全く関係のないところに都会に作るのだから、その迷惑料も含めて利益還元するというのは妥当なのではないだろうか? そうでなければ、誰も直接利益の得られないモノを引き受ける引き受け手も現れないように思う。そうであれば、補助金漬けなどと批判せず、「どうもありがとう」「いつもお世話になっております」と頭を下げればいいように思う。少なくとも電気問題では、発電所を持たない、電気を多少なりとも使っている人たちは謙虚になるべきだろう。そういう関係がいやなら、エネルギー不要の生活をして見るか、自分で自分の分のエネルギーを作り出してみればいいのだ。
全体的に「なんとかムラ」「御用なんとか」と他人にレッテルを貼りたがる人間の話は信じないようにしている。しかし、そうして見直すとなんとも社会に出回っている情報の空虚なこと。
また、いたいけな少女に「正常な子供を生めますか?」なる質問をさせた下種な大人がいたらしいが、相手が学者であることを念頭においてこうした質問を発したとすれば相当な策士だと思う。「正常な」をどのように理解するかが問題だが、先天的な障害だと理解すれば、何もなくとも先天的な障害を持った子供が生まれる可能性があることはわかっている。専門家であれば、そうした可能性を考えて「絶対に大丈夫」とは言えないはずだ。そういったことまで考えて、回答に窮する質問を組み立てているのであれば、なかなかに策士だと思う。ただし、人間としては下種な部類だ。(主義貫徹のためには手段を選ばないという面で)
しかし、私は専門家ではないので、「はい。大丈夫です」と言ってしまおう。理由は、通常時に、妊娠に際してもともと先天的障害を持った子供ができる可能性がある程度あるにしても、それを問題にして妊娠を悩む親は滅多にいないからだ。そうでなくても、生まれた子供は親にとっても社会にとっても大切な子である。そこに「正常かどうか」などという概念を持ち込むこと自体が人道として許されないことだろう。だからこそ、悩むべき問題はないのである。
実際には、放射線の被曝が原因で遺伝上の問題が生じるという仮説は、長年の広島、長崎の被爆者に対する綿密な追跡調査の結果から否定されている。「ピカがつく」と称して、被爆者に対して婚姻などで差別する長年の風評被害があったと聞くが、それ は単なる思い込みであり、正されるべき悪癖である。それを本来、良識があるはずの人道的に原発被害を心配しているする人たちが主張しているということは実に矛盾に満ちている。今回、子供だけでそうした考えを持つとは思えないから、そうしたことを吹き込んだ大人は、福島のひとのほかに、全ての風評と戦った広島、長崎の被爆者に対して、己の不徳を恥じて懺悔をすべきではないだろうか?
それとも、長年の追跡調査の結果からヒバクシャを風評の呪縛から解き放した研究結果を否定し、御用なんとかと称して、無視を決め込むのだろうか? 結果として、信じてしまった妊婦がせっかく授かった命を中絶するような事態になったとしても平気でいられるのだろうか?
こんなことを考えていると、全国でなくならない「いじめ」の根っこが透けて見えるように感じられてならない。ストレスを感じるとなんとなく自分と異なるもの、弱い立場にあるものを攻撃したくなるのだろう。それがいじめを呼び、被爆者差別を呼び、いま新たな原発事故の二次被害を生んでいるのだろうと思うと非常に悲しい。
無責任に情報を垂れ流すマスコミを含めて、いま、大人は自分の行動を冷静に見直すべきではないか?
あの大震災から半年が過ぎた。
タイにしばらく行っていたのだが、今回、滞在中にインフルエンザにかかってしまった。暑い国ではインフルエンザはないのかと思うと、鳥インフルエンザを始め、各種ヒト・インフルエンザがあることはあるのである。しかも、今年はタイも春から異常気象で、乾季も終わらぬうちから雨が毎日毎日降っていたので、体の調子を崩す人も多かったらしい。
昨夜まで元気にしていたのに、明け方目覚めると、いきなり高熱が出ている。連れも高熱。連れも同時に一緒に倒れると、大変なこと極まりない。だれも面倒見てくれる人がいないじゃないか。誰かに来てもらうとインフルエンザが感染するし。宿はアパートメントホテルなので、飲料水は一階の自動販売機まで容器を持って買いに行かねばならない。
「み、水・・取って」「自分で取ってよ〜、あ、もうない・・」
こういうときに人間の本性が出る。「水を買いに行かなあかんで・・」「うう、なくてもだいじょうぶ・・(シーツをかぶる連れ)」「はああ?」
高熱で倒れているときに水がなかったら死ぬだろう・・。けっきょく、倒れてから三日間、わたしが水を買いにいくはめになった。熱は周期的に上がったり下がったりするので、下がったときをみはからってそろそろと買いに行く。一階までいくと、もうすこし歩けそうなので、通りに出ると向こうからバナナ売りの屋台を引いてくるおばちゃんが。天の助けとバナナを買い込む。二日目に、さすがにバンコク在住の友人に食糧を買ってきてもらったが、思ったより味のついたものは食べられない。
こうして、丸四日間、ほとんど水とバナナで過ごすことになった。食事の面から見れば、まるでバナナ断食である。そして、やっと治って、外にごはんを食べに行ってみると、これがまたいつものお店の料理なのに、ひと口食べると「しょっぱい! 味の素が気持ち悪い・・」苦行のように飲み込む。道を歩いても、空気がまるで毒のよう。住んでいるところは、もともと空気がかなり悪い地域なのだが、今までは慣れてしまっていたのだろう。もう道を歩きたくないほど苦しい。次からはもう少し空気のましなエリアに引っ越そうと真剣に考える。
インフルエンザや風邪で高熱が出ると、治ったあとにはいろいろ身体から悪いものがウイルスと一緒に排出されて毒出しされ、身体が軽く、すっきりしている。ちなみに日本では風邪やインフルエンザで熱が出ると、すぐに解熱剤や咳止めなど風邪薬を大量に飲んだり、病院に行ったりするが、わたしは風邪薬を飲まない。人間の身体は熱を出してウイルスを殺す、という免疫システムになっているからだ。
それにしても、今回の毒出し感はなにか強烈。なぜだろう? 思い当たることといえば、このとき水にゼオライト鉱石から作った「ゼトックス」という液体を加えて飲んでいたこと。放射能汚染が広がるなかで、身体に入れないよう防御するということも大事だが、身体に入ってしまった有害物質を排出することも大事である。免疫力をつけること以外に、もっとすぐに効果のあるものはないのかな? と、いろいろ調べているうちに鉱物のゼオライト(ZEOLITE)に辿り着いた。これまで日本では水の浄化、ペットの消臭材としてしかあまり利用されてこなかったが、福島第一原発で放射性物質吸着剤として使われ、その重金属吸着作用がやっと注目されている。
ゼオライト鉱石は、その分子構造とイオン交換作用から、重金属を吸着する。人体にゼオライト鉱石を取り込むと、有害な物質を吸着し、数時間後には人体からその有害物質をかかえたまま排出されるのである。しかも人間にとって必要なミネラルは吸着しないという、ものすごく人間に都合のいい性質を持っている。さらにゼオライト鉱石がいろいろな重金属の中から優先的に取り込むのはセシウムなのだ。
安全性については、日本ではすでに添加物としての認可があり、アメリカではFED(食品医薬品局)の認可があり、食品として安全とされている。というか、欧米ではゼオライト鉱石は福島原発事故よりずっと前から、人体における重金属や化学物質の毒出し効果が認められていて、パウダー状になったものが、薬局でデトックスのサプリメントとしてごくふつうに販売されている。
というわけで、アメリカ製のサプリメントや、出雲のゼオライト原石などいろいろ取り寄せて試してみた。
★アメリカ製サプリメント「ZEOFORCE」ゼオフォース。なんか効き目ありそうな名前だ。毎日の健康維持に一日二錠、集中デトックスには一日六錠から二十錠・・。カプセルはとても大きい。大きすぎて飲みこめないので、カプセルを解体してみると、中にはいっているのはゼオライト(クリノプティロライト)鉱石のパウダー。水に溶けば飲めるかと、コップ一杯の水に溶いて飲んでみた。う〜ん、石の粉の味ですね。三回飲んでいやになった。もう飲めない。
★出雲産ゼオライト(モデルナイト)鉱石の石粒。洗って、ひとつかみを水のポットに入れて一晩置いておくと、水がとてもおいしくなった。ゼオライト鉱石は水を浄化すると同時に、硬水を軟水に変える作用もある。過剰な重金属を吸着するわけだから、なるほど・・。硬水で、しかも安全性に疑問のあるタイのアパートの飲料水に使ってみると、水が格段においしくなったばかりか、お茶もかなりおいしく入れることができた。硬水ではお茶はおいしくはいらないので、悩みの種だったのだが、う〜ん、これはいい。
★出雲産モデルナイト鉱石のパウダー。これも直接飲むのはおいしくない。畑でもあればまけば土壌改良になるらしいが・・。タイで、旅行中に水にほんの少し粉を入れてみると、お茶がおいしく入った。石粒を旅で持って歩くのは重くてジャマくさいので、携帯用にいい。大匙一杯の粉を一リットルぐらいの水に溶き、しばらく置いておいて上澄みを使うことにしてみた。沈殿するのは粒子が大きいゼオライトで、粒子は小さいほうが吸収力は高く、ざらざらしないので使いやすい。お風呂に入れてみる。これはなかなか温泉みたいでいい感じ。汚染の可能性のある野菜などを洗ったりするのに、洗い桶に水を入れてこの上澄み液を少し入れ、ちょっと浸しておけば外側に付いた有害物質はかなり取れるのではないかと思う。
★アメリカ製でNCD(WAIORA)ワイオラという液体の飲料用のもの。飲みやすく、吸収力を高めるよう粒子をナノ加工した液体。一回三滴、一日三回。飲んでみた感じはいいとは思うが、日本国内では直接買えず、個人輸入しなくてはならない。購入はかなり面倒だ。販売方法もアムウエイくさい。
★日本製の「ゼトックス」という液体の飲料用のもの。これもナノ加工してある。無味無臭で、子どもでも違和感なく飲める。スプレーになっていて、一回三スプレーを一日三回が基本。いろいろ試した結果これが一番、飲みやすく、使いやすく、入手しやすい。二か月間試しているが、いい感じ。コップ一杯の水にスプレーして飲む。水分を必ず一緒に取ること。お茶やスープなど食事に入れてもいい。50ml.入りのボトルが3800円で二ヵ月近く持つ。飲む期間は二週間から四週間が目安。何か月おきにドクダシするといい。汚染地域の人は毎日飲んだほうがいいだろう。
放射性物質の排出に有効とうたうと薬事法に違反するので、ネットショップなどでは書いていないけど、セシウム以外にも水銀とか鉛とかいろいろ排出してくれるので、内部被曝だけでなく有害金属について不安のある人は試してほしい。汚染地域の子どもたちにはぜひ飲ませたい。
ちなみに、有害物質やセシウムを排出するといっても、自分で出たと分かるわけではないから、何がどう効いているのかよく分からない。しかし、ドクダシ作用が効いているかどうかは、排出系の変化で分かる。変化には個人差があるが、汗がよく出る、おしっこがよく出る、便がよく出る、というのが主な変化。中には鼻血が出たという人もいたが・・。
日本では、デトックスというと、美容やダイエットというイメージがあったが、いまや日本中で真剣なデトックス=毒出しが必要になっている。じぶんの身体はじぶんで守らなければ、だれも守ってくれない。
ゼトックス公式HP http://zetox.jp/
●はじめに
ひさしぶりに鎌倉の吉田秀和さんを訪ねて、自伝を書かないのかと訊かれた。いまは日本の外で日本の音楽家たちについて知りたい人たちも出てきた、日本語を読める研究者たちもいる。でも武満のほかにあまり資料がない。そうかもしれない。これから書こうとしているのは、でもそのためではない。
いままでは個人的なことを書かないようにしてきた。記録もとっておかなかった。いま薄れていく記憶が失われないうちに、いくつか書き留めておいてもいいかもしれない、音楽について語り合った人たちのことを、いまはもうない場所のことを。そこであったことと、いま思い出される姿のあいだには、時間が「反省」の薄膜をかけている。くりかえし書いたこともある。それでも思い出すたびに、ちがうかたちで現れる。
●クセナキス
最後に会ったときは、病気で5分前の記憶もなかった。作曲はもうできない。新しい友だちの顔もわからない。それでも古い仲間はおぼえている。「1950年代にひとつの音のイメージが浮かんだ。それまできいたことのない響きだった それから40年間それによって作曲をつづけた。でもいまそれは終わっている。なにかちがうものが顕れようとするのを感じる。」
その後、パリに電話をした。「しごとをしているか? こちらもだ。」作曲はもうしていない。立つ、歩く、座る。自分の作品が演奏されてもわからない。それでも良い演奏はわかったらしい。壁にきみの写真がかかっている、とだれかに言われた。
臨終に立ち会った知り合いからメールをもらったが読まず捨てた。最後の数日間を書いた小説ももらったが、読まずにだれかにあげた。
むかしパリのアパートに居候していた時、テレビでその1年前に亡くなったヘルマン・シェルヘンの追悼番組をやっていた。ドアがあいてクセナキスが帰ってきた。画面をちらりと見ると、だまって寝室に入った。
シェルヘンが亡くなるすこし前クセナキスの「テッレテクトール」を指揮するのを見る。指揮者が中央にいて、オーケストラが聴衆といっしょに客席一面にひろがっている。シェルヘンは小さなメモを手にして八方に向きを変えながら演奏者に合図を送る。
『ピソプラクタ』はシェルヘンが初演した。不規則にばらまかれた音の雨がしずまると、長く伸びる響きを背景に不規則に打つ音が聞こえる。それは冬のパリでゆるんだ蛇口から滴る水のリズムから思いついたらしい。題名の「ピソ」は確率的、「プラクタ」は行動の意味。
西ベルリンにいた頃、シェルヘンがシェーンベルクの「オーケストラのための5つの小曲」を指揮するのを見る。指揮棒をもたず、前に置いたスコアも見ない。かすかな身振りにつれて響きが目覚めて立ち上がる。演奏の後クセナキスといっしょに楽屋に行く。小さなピアノで何か弾くように言われ、シェーンベルクのピアノの小曲を弾くと、シェルヘンが言う。「この正確さ、これでプロイセンは世界を征服したんだ。しかし……」夏にイスキア島にくるよう誘われたが、行くカネがない。
パリの古いアパートは歓楽街のはずれにあった。屋根裏に泊まったが、それはクセナキスがパリに来た時最初にいた部屋だ。ベッドしかなく小さな窓から夜空が見える。部屋の外に共同便所がある。
西ベルリンではクセナキスの生徒という名目で奨学金をもらっていた。クセナキスは時々しかベルリンに来ない。まず出版されたばかりの自分の本をくれた。次にはワルシャワに行くフランスのアンサンブルのために作曲して、その作曲方法を説明するのが課題だった。その曲はワルシャワでは演奏されない。次にピアノ曲を書くと鉛筆をくれて、それで余計な部分を削る。
その後はクセナキスの演奏者となり、ヨーロッパやアメリカでピアノを弾き、韓国と日本では指揮もするピアノでは『ヘルマ』『エオンタ』『エヴリアリ」『シナファイ』を弾き、『オレステイア』『ヒケティデス』『エリダノス』『キアニア』などを指揮する。
クセナキスはコンピュータ音楽スタジオを作るための場所を探していた。その準備のために呼ばれて西ベルリンやストックホルムやアメリカのインディアナ大学に行ったが、計画は実現しない。ハジダキスが指揮していたアテネのアンサンブルにも誘われたが1967年のクーデターでそれどころではなくなった。
「日本に帰ってしごとをつづけるほうがいい。」とよく言われる。ギリシャと日本には古代からつづく伝統があると思っているようだ。クセナキスは政治亡命者でギリシャには帰れなかった。ギリシャを通る飛行機には乗らない。本棚のいちばん上の棚に「血の本」がある。地下武装組織の死者名簿だ。ナチスとその後のイギリス軍と戦って死んだ同志たち。かれらのために音楽を書いていると言う。
京都のホテルにいたクセナキスをホセ・マセダと訪ねる。マセダは後で、クセナキスはヨーロッパ的なピッチ支配から逃れたいのだろうと言った。「アジアでは5つの音でじゅうぶんだ。」
クセナキスの『キアニア」とマセダの『ディステンペラメント(平均律の解体)』をおなじコンサートで指揮する。マセダはクセナキスの音楽は暴力的だと言う。クセナキスにコンサートの録音を送ると、マセダの音楽は奇っ怪だという返事。
クセナキスに初めて会ったのは草月アートセンターのコンサートで武満の『ピアノ・ディスタンス』を弾いた時だ。その後秋山邦晴の勧めで、クセナキスにてがみを書いてピアノ曲を委嘱した。やがて送られてきた曲が『ヘルマ』だ。鍵盤の上であちこちに跳ぶので、すこしずつ分けて練習して30日かかる。5連音と6連音が両手で同時に進行する。このリズムの演奏が不正確だと後で若い世代のピアニストから非難される。でも楽譜は、確率計算した音の出現時間を1/5と1/6の格子ですくいあげて、規則的なリズムでは書けない音楽をぼんやり映し出している。そこから思いがけないフレーズを、演奏する手が浮き彫りにする。ゆっくりうごく面と速く飛び散る線の二つの響きの層が同時にきこえてくる。
指は10本あるからそれぞれ独立にうごくだろうと言われたが、そんなことはない。注意の焦点をちがう指にすばやく向け変えることはできると思った。いまはどちらもちがうと思う。孤立した音がまずあって、組み合わせて音楽にするというのは、社会契約論のような近代思想に似ている。伝統のなかでは演奏される音楽がまずあり、音階や構造理論はそれについての後からの仮説にすぎないと言えるだろう。
それでもメロディーを連続した線ではなく、それぞれ独立した断層の重なりのように弾くことができる。これはクセナキスの思いつきで、「シナファイ」を弾く前にためしてみると、音の強さとリズムの微妙なずらしによる効果で空間の奥行が出てくる。このやりかたはバッハを弾くときにも使える。音は点でもなく線でもなく、音色の複雑なシステムになる。ここには1920年代までの個人主義でもなく、それ以後の原典主義でもない演奏スタイルのヒントがあるようだ。和声でも対位法でもなく、音階も音列も、主題も構成もない作曲も想像できるかもしれない。
クセナキスは1960年代にコンピュータを使って作曲するプログラムを作った。その後は確率を使ってランダムなノイズを発生させ、一部を切り出して循環させながらピッチのある音を作るというプログラムを書いて実験をつづけていたが、コンピュータの出す音は人が楽器で作るような変化のある音にはおよばなかった。どこか空虚な固定された響きになるので、組み合わせで変化をつけるために音楽は複雑になる。最後に会った時、クセナキスは長年つづけていたコンピュータ音楽の実験はもうやめたと言った。「いま興味があるのは大きなオーケストラだけだ。」
その頃のオーケストラ曲もだんだんすべての半音が同時に響き、別々のリズムでずれていく音楽になっていた。『キアニア』もそうだった。シアンとおなじヒッタイト語から来たタイトルは、どこか遠い青い土地を意味しているらしい。極端におそいテンポでからみあうフォルテシモのたくさんの層でできている。打楽器を含まないオーケストラだが、リズムもピッチも感じられない、響きの持続だけがある。マセダが感じたように、暴力的に聞こえるかもしれない。
ニューヨークの空港の騒音のなかで話したことがある。「人間は自分の作り出した時間と空間のガラス箱に閉じ込められている。この迷路から出れば、この瞬間には過去と未来のすべてがあり、ここは20億光年の彼方でもあるだろう。」クセナキスは最先端テクノロジーを使いながら、その合理主義の限界の向こうにある不死の夢を古代哲学のなかに追っていた。プラトンの『エルの伝説』によるレーザーと電子音響のスペクタクルを創ったのも、日本の禅に興味をもったのもその手がかりをさぐっていたのかもしれない。でも現実には、啓蒙主義の生み出したカテゴリーの壁のなかでますます複雑になる響きをつむぐことしかない。
京都で、忘れていたギリシャの火渡りの儀式のイメージが突然よみがえり、それを話そうとするが、ことばが出てこない。長年の苦しい作業で生まれた自分の音楽を忘れて、わずかに残された心は遠い故郷に帰っていく。
渋谷の道玄坂を中途半端にあがり、円山町のホテル街へ歩いて行くと、流行らなくなった古い連れ込み宿をカフェなどにしている若いヤツらがたくさんいる。坂根はそんなカフェの中から、落ち着けそうな店があるとふたりと立ち寄る。
いまどきフリーのグラフィックデザイナーなんて、商社の御用聞き営業よりもクライアントのご機嫌伺いばかりだ、と坂根は自分の仕事を卑下している。写真を右に五ミリ移動させろだの、ロゴマークのシアンをあと十パーセントあげてくれだの、言いがかりのような修正に丁寧に対応しなければ仕事はなくなる。この不景気、企業の広報担当者だって、暇で暇で仕方がないのだ。だから、どうでもいいことに言いがかりを付けて、終業時間までの暇つぶしをする。帰る前に、無理難題をメールでこちらにぶつけて席を立ち、明日の朝出社すれば、自分のふっかけた無理難題がきれいに形になって仕上がっているという次第だ。
ここしばらくそんな仕事の振られ方ばかりしていて、坂根の生活は昼夜が逆転しかけている。埼玉のマンションに強い日差しが照りつける昼前に目を覚まし、うだうだと身支度をして外出し、午後と夕方の狭間のこんな時間にうろうろとカフェ巡りをするだけが、坂根の楽しみだ。いや、楽しみだった時期は過ぎて、すっかりそれが生活のようになっている。言い換えてみれば、夕方、仕事に本腰を入れるまでの時間を楽しむ術を知らないと言った方がいいのかもしれない。
それでも、ごくたまに本当に過ごしやすいカフェを見つけると得をしたような気持ちになり、夜の仕事を思い出さずに時間を過ごせる。自分の部屋にいると、どうしても仕事のことを考えて、気持ちが滅入ってしまう。フリーのデザイナーなんてみんな同じじゃないかと坂根は思う。
渋谷の円山町界隈は、最近ラブホテル街としても廃れている。それはそうだろう。東京に住んでいる若いヤツらはほとんど一人暮らしだ。それに、飲んだ勢いで飲み屋のお姉ちゃんを、なんていうヤツはどんどん減っているらしい。四十を過ぎて厄年を迎えた坂根でも、それほど女をモノにしたいという欲求を感じたことがない。知らない女とややこしいことになるくらいなら、一人でゆっくりと眠りたいくらいだ。
そのおかげで、最近は真新しいきれいなホテル以外は経営が立ちゆかなくなっているようで、昔ながらの木造の連れ込み宿は内装を変えて、おしゃれなオフィスなどに商売を替えている。その小さなオフィスの一室に、坂根が昔から一緒に仕事をしているフリーのライターが事務所を開いたのだった。おかげで、週に何回かは道玄坂をあがり円山町へやってくることになった。まだまだ、見知らぬ町だから駅までの行き帰りにいろんな道を歩いてみるだけで楽しい。坂根は打ち合わせの書類が入ったバッグを肩から吊し、軽い足取りで円山町のあちらこちらを寄り道して歩いた。
坂根が見つけたのはごく普通の民家のような顔つきをしたカフェだった。入り口だけはガラスの引き戸に変えられているが、全体はいわゆる木造モルタル造りで、子どもの頃に自分が住んでいた家と同じような作りだと坂根は思い、妙な気持ちになった。
引き戸をあけると、先客は一人だけ。若い夫婦が経営しているようで、清潔感のある若い女の方が先客に注文された珈琲を出している。先客もまた若い男で、その服装から普通の会社員ではなく、どちらかというと自分に似たような仕事だろうと坂根は値踏みする。
メニューをざっと見て坂根も珈琲を注文する。
「珈琲をひとつお願いします」
女が丁寧に奥のキッチンにいる男に注文を通す。すると、それを待っていたかのように先客の男が女に話しかける。
「このお店はいつオープンですか?」
女がにこやかな笑顔で答える。
「まだ二月しか経っていないんです」
すると、男がまるで小学校の学芸会のようにわざとらしく店内を見回して、
「なんかすごく落ち着きますよね」
「ありがとうございます。古いお宅をお借りしてるんです。店内は改装させていただいたんですが…」
その辺にしておけ、と坂根は思うのだが、二人の会話は意外にも弾み、終わりが見えなくなってきた。おかげで、何も話していないのに坂根にはこの店の生い立ち、経営しているのが確かに夫婦で、結婚したのが三年前、旦那がリストラされたのを機会にカフェを始めたのだということも、全部聞かされてしまった。それだけじゃない。旦那の両親がこのカフェをオープンする資金を出してくれたこと、奥さんのお父さんがいまでもカフェに反対していること。そんなこんながたった十数分珈琲を飲んでいる間に、全部わかってしまったのだった。
早過ぎるよ、と坂根は思う。そういうのは、何度も通いながら、数週間、数ヵ月かけて、少しずつ話していく感じでいいんじゃないか、と坂根は思ってしまう。
デザイナー臭い先客は途中から坂根が聞いてると言うこともわかった上で、話しているように思えて仕方がない。自分が坂根よりもカフェに通じているということをアピールしたいように見えるのだ。時折、坂根に向けられる視線、同意を求めているように聞こえる語尾の上げ方。すべてが気にくわない。坂根のイライラは次第に募ってくる。この男はどうにもカフェの楽しみ方がわかっていない。いくらカフェというものが、スタッフとの何気ない会話も楽しみの内だといいながら、ここまであからさまに話し込んでしまっては、他に客に迷惑だ。さらに、質問攻めにしてそこから見えてくる真実は日常ではなく非日常的なレポートに等しいじゃないか。
そんな思いに坂根は内心憤然としているのだが、もちろん、そんな気持ちは表には出さない。それを出してしまうのはカフェという空間には一番似合わないことだと坂根は思っている。あくまでも、カフェという空間を愛するものとして、そして、おそらくは同業である先輩格の男として、毅然として悠然として珈琲をすする。
大丈夫だ。もう少し待っていれば、この無粋な客はいなくなる、そうすれば、もっとゆったりと店主と会話を交わそう。あからさまな私生活を聞き出すのではなく、この店の行く末やこだわりといった、彼らの「仕事」について言葉のやり取りをしよう。坂根はそう気持ちを引き締める。
しかし、だ。一時間が経過しても、先客は帰らない。それどころか、先客の仕事仲間が四人来店した。
「お待たせ」
「いやいや、大丈夫。こちら、このカフェの経営者の遠藤さん」
「あ、どうもです」
「こいつらはぼくのデザイン事務所のデザイナーたちです」
「デザイナーだなんてすごいですね」
店主の奥さんは本気で目を輝かせる。
「いえ、たいしたことないです。一生懸命やってるだけで」
あっという間に、後からやってきた四人も会話に加わり、さらに楽しそうな雰囲気を醸し出す。互いに挨拶をしたり、名刺交換をしたり。店のホームページを無料で作ってあげましょうなんて話まで出てくる。
坂根の気持ちがまた揺れ始める。デザインの楽しさを伝えるのはいい。でも、それを無料でやってあげる、なんて安請け合いはプロとしてすべきではない。少なくとも、おれを育ててくれた先輩はそう教えてくれた。いくら安くてもいいから、料金を発生させる。それがプロの心意気だろう。
坂根はそう心の中で檄を飛ばすが、結局、楽しそうに話はまとまり、今から早速ウェブデザイナーを呼びますよ、なんて話になっている。
どうやら彼らはこれからどこかの画廊のオープニングパーティに参加するらしい。そこに行く前にカフェに集合しようと、あちらこちらに電話を入れたりメールを打ったりしている。そして、円山町のどこに潜んでいたのか、五分もしないうちに一人、二人と人が集まってくる。結局、十数人が集まり、狭い店内は満席になった。悠然として、毅然としている坂根は自ら相席を申し出て、立ったままでもかまわないという若くオシャレなウェブデザイナーを座らせる。いつもなら、相席などさせないのだが、立ったままでもいいという理由が「立食パーティに慣れているから」というのが引っかかり、無理矢理相席で座らせたのだった。
こうなったらもうカフェという空間をゆっくり楽しむことは不可能だ。坂根は方向を変えて、カフェももう一つの楽しみである人間観察に専念しようと決めた。
目の前にいるウェブデザイナーはまだ二十代の前半だろうか。四十を迎える坂根がチノパンにカラーの襟のあるシャツという一昔前のカジュアルを絵に描いたような格好をしているのに、ウェブデザイナーはアンシンメトリーでオシャレなシャツときれいにラインの出るパンツを履きこなしている。
立食パーティに慣れているというのも、嘘ではないかもしれない。そう思った途端に坂根は手に汗をかいている自分に気付いた。よくよく見れば、ウェブデザイナーだけではなく、他のヤツらもそれぞれに個性的な格好をしていた。
おそらく、ここにいるなかで、いちばん安い服を身につけているのが自分だろうと坂根は思った。服は値段じゃない。自分に合っているかどうかだと思い直したが、思い直した途端に、つい先月も青いシャツを買おうとして、散々迷ったあげく結局安い方を買ったのだということを思い出した。
若いウェブデザイナーが楽しそうに他のデザイナー達と話すのを眺めながら、坂根は自分を嫌悪した。こんなシチュエーションは俺の好みじゃない。坂根はそう思った。そして、同時に、坂根はいま抱えている仕事のクライアントから言われた言葉を思い出してしまう。
「坂根さんの好みはどうだっていいんですよ」
クライアントの広報担当者は、坂根が作ったサムネールを見ながらそう言ったのだった。
「いや、私の好みというわけじゃなく…」
「うちの商品の良さがちゃんと伝わるかどうか。そのためだけにクリエイティブを発揮して欲しいんですよねえ」
坂根よりも十は年下の担当者はため息混じりにそう言ったのだった。違う、と坂根は言いたかったのだが、その後につながる言葉が見つからずに黙り込むしかなった。
いつだって話すべき言葉が見つからない。だから、坂根には黙り込んで担当者の要望を一言残らずノートにメモするくらいしか出来ないのだった。こういうことがある度に、グラフィックデザイナーなんて辞めてしまおうと本気で思うのだった。それでも、この仕事を辞めることなんてできないということは坂根自身がいちばんよく知っていた。それは自分が本物のグラフィックデザイナーではないからだ。豊かな才能があって、デザインという仕事を極めた者だけが、「他の仕事を」などという新天地を考えることができるのだと坂根は知っている。
思い切ってデザイン賞に参加したこともなく、新しいクライアントを求めて営業をしたことさえない。友人が働いていた会社が仕事をくれると言いだして、それをきっかけにたった半年だけ働いたデザイン事務所を辞めて独立したのだった。
その時の友人がその会社を辞めてからも、運良く仕事だけは継続して、いまに至っている。だからこそ、担当者ともめて命綱のような仕事を失うのが怖いのだ。
そんなことを考えながら、目の前の若者達を見ていると、最初の勢いは消えて、自分だけがこの場所に似つかわしくない人間のように思えてきた。
坂根はそそくさと仕事道具の入ったバッグから財布を出すと勘定を支払った。金を受け取り、お釣りを渡すこの店の若い奥さんの視線は、目の前の坂根よりも若いヤツらへと注がれている。まるで自分がここにいないかのようだと坂根は思ったが、それを認めることが嫌で、
「おいしかったですよ」
などと感想を言ってみるが、
「ありがとうございます」
と心ここにあらずの返事をされてしまう。
坂根は逃げるようにして、客席の若者達にも気付かれないように店を出ようとしたのだが、最初からいた男が坂根に会釈する。しかたなく坂根も頭をさげる。なぜ、自分が年下のこの男に頭を下げているのか釈然としない。
カフェから出て、渋谷にいたのだということを坂根は改めて思い出した。それほど、この一時間ほど、気持ちがざわめいてどこにいるのかさえ忘れるほどだった。
さあ、どこへ行こう。今日はもう仕事をする気持ちなどなかった。気分転換にもう少し散歩を続けようかと思ったとき、坂根は声をかけられた。
「とりあえず、僕も一緒に行きますよ」
さっきのウェブデザイナーだった。
「一緒に行くって、どこへ」
坂根はそう聞いた。聞きながら、ウェブデザイナーが意外に背が低いことに気付いた。そして、仲間から離れて、年上の坂根と正対していることでウェブデザイナーは少し緊張していた。
「えっと、次のパーティも出られるんですよね。みんなは少し打ち合わせがあるっていうんで。僕は道を知らないんで、先に行かれるんなら一緒に連れてっていただこうかと」
もちろん、坂根はパーティにも出ないし、その場所など欠片も知らない。どうやら、勝手に坂根をヤツらと懇意にしているデザイナーだと思ったらしい。
「あ、場所を知らないんですね」
坂根の中に、この若いウェブデザイナーに対する妙に底意地の悪い心が芽生えていた。「それじゃ、一緒に行きましょう」
坂根は自分でも思っていた以上にするりとそう言うと、気持ち胸を張って歩き始めた。
「名前はなんて言うの?」
「立花です」
坂根の問いにそう答えると、立花はカフェで見せたよりも心細い表情になった。
坂根は立花のそんな表情を見ただけでもっと困らせてやろうという気持ちになっている。
「お名前はなんとおっしゃいましたっけ」
今度は立花が聞く。しかし、坂根は答えない。答えないまま歩き続ける。その後も、立花はときおり坂根に話しかけるのだが、坂根は次第に歩く速度を速くする。道玄坂を降りきったあたりで、人通りが激しくなる。人と人の合間を縫って歩いている内に、だんだんと坂根と立花の距離が開くようになった。間が開き、また縮まり、しばらくするとまた遠くなった。
立花は少し息を切らせながら、坂根を追いかける。坂根は坂根で、歩く速度を上げているのがばれないように、歩いている人たちの合間をうまくすり抜けていく。後ろから見ていた立花は、ふいに姿が見えなくなる坂根を必死で追いかけているような格好になっていた。
渋谷駅前のスクランブル交差点に差し掛かったときに、ちょうど信号が青に変わった。坂根は斜め斜めに横切りながら、さらに立花との距離を開ける。
立花は後ろから「待ってください」と声をかける。その声が聞こえないふりをしながら、坂根は振り向きもせずに歩き続ける。声をかけられたことで、坂根は急に自分のしていることが恥ずかしくなる。
坂根の息は乱れている。人混みの中で足下がおぼつかなくなってくる。不安になって、足下を見ていると、ふいに落ちている子どもの運動靴を見つける。次々と人々が足を踏み出す混雑の中で、すぐに見えなくなってしまったのだが、確かに子どもの運動靴が片方だけ落ちていた。黒と赤でデザインされた小さな運動靴だった。
その運動靴を見つけた瞬間に、坂根は子どもの頃のことを思い出した。新しい運動靴を買って欲しくて、わざと自分の靴を近所の空き地に捨てたのだった。その時、母親は何も言わずに新しい靴を買ってくれたのだが、それが逆に母親に攻められているように思えた。
坂根は見失った子どもの運動靴を探した。しかし、前後左右からやってくる人々の行く手を遮るような格好になり、何人かの男達から罵声を浴びせられた。見ず知らずの子どもの運動靴を探しているのか、自分が捨てた運動靴を探しているのかわからなくなった。
「すみません、すみません」
そう謝りながら、坂根はあちらこちらに押され、転倒しそうになる。それを支えてくれたのは立花だった。
「大丈夫ですか」
立花は心配そうな表情で、坂根を見つめている。
坂根は一瞬、どこにいるのかを忘れていたように、じっと立花の顔を眺めた。
「とにかく、信号が変わっちゃうんで、渡っちゃいましょう」
立花が屈託のない笑顔でそう言った瞬間に信号が赤に変わった。堰き止められていた車が一斉に交差点になだれ込んでくる。
立花は坂根の腕を取り、走り出す。もたもたとしている二人にクラクションが容赦なく鳴らされる。立花は片手でそんな車に拝むような手つきをして、もう片方の手で坂根の腕を引っ張った。坂根は足をもつれさせるようにしながら、必死で立花の後について走った。ちょうど、信号を渡りきった場所にいた警察官が、警笛を鳴らしながら、二人を手招きして、周囲の車を停止させた。
「さっさと渡りなさい」
警官は大きな声で二人を促した。あと数歩で歩道に着く、と思った瞬間、立花の手が坂根の腕から離れた。立花が小さく「あっ」と声をあげた。それを聞いて、坂根は「大丈夫だから」と答えた。そして、もう一度、さっきよりも大きな声で「大丈夫だから」と言うと、坂根は全速力で歩道へ走った。立花も歩道に向けて走った。歩道に着いた途端に立花は立ち止まり、息を整えようとしている。坂根はそんな立花の横をすり抜け、そのまま走り続けた。警察官が何か声を発し、警笛まで鳴らしている。それでも、坂根は振り返らずにそのまま表参道のほうへ走り続けた。振り返ると、警察官も立花も追いかけてきてはいなかった。坂根は速度を落とさずに、そのまま走った。もしものことを考えて、小さな路地があれば入り、ビルとビルの間の通路を見つけては走った。
犬に吠えられ、積みかさねられた段ボールに行く手を阻まれたりしながら、坂根は走った。息が上がり、膝が震えた。持っていたはずのバッグはもうすでに持っていない。通路を走ったときにぶつけたのか、肘からは血が滲んでいる。坂根は走るのをやめて歩き始めた。
気がつくと、坂根は人通りのまったくない住宅街の真ん中を歩いていて、それがどこなのかわからなかった。
「大丈夫だから」
坂根は誰もいない住宅街の真ん中でそうつぶやいてみたが、誰が見ても大丈夫な様子ではなかった。そして、別に急ぐことはない、と思いながら坂根は少し気持ちを落ち着かせて、周囲を見渡してみた。小さなマンションの一階にオープンテラスのカフェがあった。いつも行く田舎風のカフェではなく、パリにあるような本格的なカフェを再現したお店だった。
疲れ切っていた坂根は、とにかく座りたかった。何でもいいから水分がとりたかった。バッグはなくしていたが、ポケットを探ると小銭が何枚か出てきた。五百円玉も混ざっていたので、カフェオレくらいは飲めそうだった。坂根は店のドアを開こうとした。しかし、そこで止めてしまった。
ドアに映った自分の姿が汗だくであまりにもみすぼらしかったからだ。肘には血が滲み、服は所々汚れ、バッグさえ持っていない。どう見たってカフェにふさわしい格好ではなかった。カフェが好きだからこそ、こんな格好では入れない、坂根はそう思った。