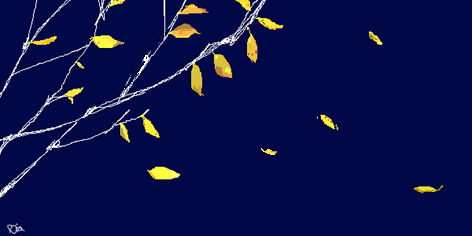11月のミラノは文字通り毎朝深い霧に覆われていて、息子を小学校に送りがてら、日本語では霧は深く、イタリア語では濃いと表現する、と教えたりしました。雪と霧だったら、霧が素敵だと言います。雪だとところどころ白が剥げてしまうけれど、霧だったら風景が真っ白になるから。霧の深い朝はびっしりと冷気が身体に張り付いてきて、全身がかじかみますが、日が昇ったとき、辺り一面が一瞬深秋らしいまばゆい黄金色に染まり、すぐに透通る青空へ変化するさまは、見ていて心が洗われるようです。
息子と言えば、先日山に行った折には、アルプスの頂に小さな雲が一つ低く影を落としているのを、あれはきっと神さまの雲だから、あの雲の中には神さまが坐っているに違いないと目を輝かせ、朝の散歩の途中、夜明けの星を指差しては、人は死ぬとお空の星になるから、きっとあれも誰か亡くなった人なんだと説明してくれました。親が死んだらお化けでも良いから会いたくないかと尋ねると、こわいから止めてほしいと断られてしまいましたが、確かに空の星を眺めて故人を思ってくれた方が、逝った方ものんびり骨休みができて好いかも知れません。
地球が果てしなく広く、日本がどこまでも遠く感じることもあれば、地球のどこに居ても同じ空を見て、同じ月や夜空を見て、同じ海を目の前にしていることに感動を覚えることが、震災後多くなった気もします。夜、空を見あげてこれは数時間前に日本を過ぎた夜空だと思い、朝焼けを見てこの太陽も、数時間前に日本に昇った同じ太陽だ、そんなこと当たり前のことを思うのです。
年末、安江さんが前に書いた打楽器曲を再演して下さると聞いて、全て書き直そうと決めたのは震災と無関係ではありません。この作品はナイジェリアの石油開発で環境を破壊された少数民族出身の作家が、絞首刑に処される直前に残した宣言文を基にしています。
初めにこの曲を書き下したとき、自分なりのアプローチを試みたつもりでしたが、それが図らずも不誠実な結果となったことに落胆しずっと封をしておくつもりでしたが、震災があって心変わりし、自分にけじめを付ける為にも一から書き直さなければと思っていた矢先のことでした。
もちろん化石燃料に反対したいのではなく、我々がいつも恩恵に浴していながら、忘れてしまいがちな事実を、自分は彼の言葉で聞かなければならない、そんな自戒が込められているだけです。自らが故郷の汚染地図に毎日一喜一憂しているとき、他人の環境破壊の言葉を、あんなにも気軽に扱った自分に情けなさと憤りを禁じえませんでした。端的に言って偽善でした。
さきほど、漸く安江さんに書き直したウードゥードラムの楽譜を送りましたが、これは宣言文を予め決めた規則に則り転写しただけのもので、使うリズムも音も限定されてモールス信号のようなものになります。聴きてを飽きさせてしまうかもしれないけれど、元来この宣言文はおよそ聴きてを喜ばせもしなければ、飽きさせぬよう書かれた内容でもなくて、このテキストを使うと決めた時点で仕方がないと諦めました。
文字に記された思想や感情をリズムに転写し、それを音に転化させれば、初めの思想や感情が相手に伝わることは、原始的なアプローチだけれども、もしかしたらあるかも知れないし、ただの音に過ぎないかも知れません。作曲とは愉しみの行為であるべきとドナトーニに言われて、努めてそのように作曲との距離を量ってきましたが、今回の作曲とはいえない文章の転写作業は、自分にとって思いもかけない辛い体験で、時に小さなウードゥードラムが、作家の声を自動再生する小型スピーカーに見えて、背筋が寒くなったことすらあります。音楽は煎じ詰めればコミュニケーションの手段だと仮定するなら、たとえばモールス信号が音楽ではない根拠はどこにあるのでしょうか。同じナイジェリアのトーキング・ドラムだと話は違ってくるのでしょうか。
前回の恣意的な内容に辟易した反動から、作曲行為の放棄ながら、自己を極力排し自動書記的に作家の言葉に耳を傾けつつ、通信と音楽の間の差について考えていました。文章は信号には変換し得ても、音楽には転化できないのでしょうか。そもそも、その昔、音楽はどのように生まれたのでしょう。神と交信する必要もあっただろうし、喜びの踊りや弔いの歌は欠かせなかったかもしれない。音とは常に人間を超越する存在だったのかもしれないけれど、そこには、われわれ人間の意志を伝える必要性もあったと思います。トーキング・ドラムはその名残ではないでしょうか。
では人間と音楽をつなぐ、記譜や演奏は何を意味するのでしょう。イタリアに住んで、ヨーロッパ人と日本人の根本的な音楽観の相違に気づきましたが、音に込める感情というのが、どうも彼らと我々では違う場所にあるようなのです。限られた表音文字、アルファベットの配列組み替えで感情を表現する彼らにとって、各アルファベットに対し特に何の感情も沸かないのと同じように、音符は彼らにとってアルファベットのような存在なのかも知れません。音符から音が発せられて初めて、そこにふっと感情が宿るような気がするのです。
我々は表意文字の文化で生まれ育ちましたから、「音」という漢字を見て、観念的に「音」や「音」の周りの曖昧模糊したものまでひっくるめて連想します。だから発音される前の音符に思いを込めることもできるでしょうし、無意識にそうした傾向はあるはずです。それがヨーロッパ人の意図と同じではなかったとしても、個人的にどちらが正しいとも間違っているとも思いません。ただ、少し音に対する感受性が違うだけだと思います。
作曲も同じで、彼らが音符を書く作業を我々よりずっと理知的に徹することができるのは、自分の身体からいかに恣意的な感情、不条理な部分を剥ぎ取り、他者との共通言語上で論理化しスタンダード化できるかが、つねに西洋音楽を発展させる原動力だったからかも知れませんし、そんな彼らが、音を使って電信を発明したのは、当然の結果だと言えるでしょう。
元来トーキング・ドラムは、遠方まである程度「緩やかに」内容を伝える通信手段だったと聞きます。ですから、直接言葉では表現できない内容も、太鼓に託すことはあったといいます。日本から離れて暮らしていて、言葉では無防備に発することの出来ない感情や、言葉にすら出来ない感情や願いを音で伝えなければと思うとき、太古の昔から我々の「音」の根源は、さほど変化していない気がしてきました。
夕べ注文してあったパリの千々岩くんのCDが届きました。エネスコやイザイ、平さんやクセナキスなど、その昔パリで活躍した外国人の作曲家を中心に集めた無伴奏ヴァイオリン作品集で、最後をストラヴィンスキー編「ラ・マルセイエーズ」が飾っていて、千々岩くん、こういうのはずるいよと思いながら、思わず目頭が熱くなりました。
(11月30日ミラノにて)