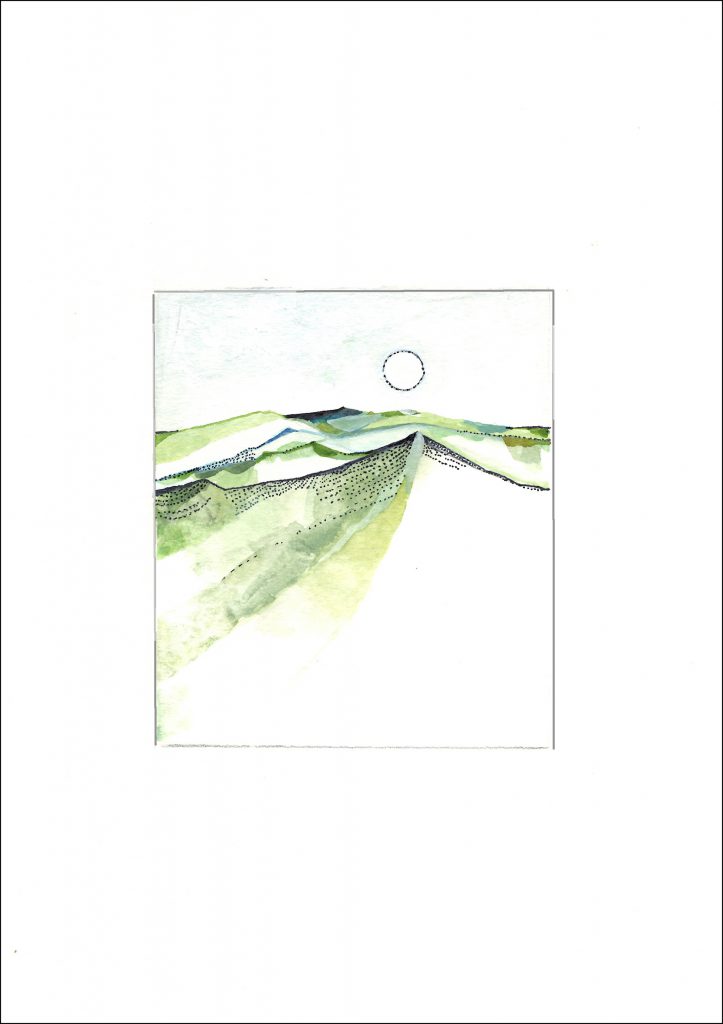息子と連れ立ってフランクフルトへ向かう機中です。羽田空港の国際ターミナルに着いて、運行便の電光掲示板の9割以上が「運航中止」と書かれているのは思いの外衝撃的な光景で、普通の日々からは程遠いのを実感させられます。
店舗もレストランも軒並み休業していて、空港内は閑散としています。係員の女性曰く、以前は喫茶店など文字通り全て店を閉じていて、当時のトランジット客は文字通り路頭に迷い大変な経験をしていたそうです。
羽田からの機内は意外に乗客が多く、6月末にミラノから乗った便とは随分様相が違います。尤も、この便に決定するまで、2度も別便がキャンセルになりましたから、その振替え客で混んでいるのかもしれません。世界にはりめぐらされた動脈は、すっかり干乾びきっているのです。
…
8月某日 三軒茶屋自宅
早朝明薬通りの祠を通りしな、改めてまじまじと眺めると、像の右上に赤字で貞享二年と彫りこんであるのに気がつく。1685年だから大バッハの生まれた年に、ここに石像を建てていた。百年前程度の石像と思いこんでいたが、急に崇高に見えてくる。以前近所で植木に水を撒いていたおばあさんに、石像について尋ねると、よく知らないようだった。お稲荷さんかねと笑っていたが、お稲荷さんには見えなかった。
東京の新感染者数472人。昨日は463人。どうなるのか。広島のライブハウスや、尼崎の劇団で集団感染。
夜半一柳先生よりお電話を頂戴し、26日の演奏会開催について意見を聞かれる。
毎日のように主催者やマネージメント、オーケストラと話し合いを重ね、可能な限り万全な感染症対策を準備しているが、今後感染爆発や医療崩壊が起きて、政府から公式に自粛要請があれば万事休すでしょうとお答えする。
個人的には、是が非でも開催ありきではない、とはっきりお伝えした。感染爆発に慄きながら数ケ月を過ごせば、誰でもそう考えるようになるはずだ。
8月某日 三軒茶屋自宅
朝5時半、何時ものように世田谷観音にでかけると、僧侶の家族と思しき小学生ほどの兄妹が、題目を唱えながら梵鐘をついていた。
低く尾をひく鐘の音を聴きながら境内を後にすると、梵鐘の下を走る道路に、一人じっと目を閉じ、手を併せて立ち尽くす老人の姿。
オルフィカの各パートは演奏がむつかしい。少し速度を落としてもよいか悠治さんにたずねる。
「クセナキスの曲の演奏からもわかるかもしれないが、演奏不可能だからテンポを落とすというのは まちがった考え方だと思う
古典ギリシャ語を習うときにすぐ出てくるのは プラトンが「ソクラテスの弁明」に書いたことばです
「試練のない生は生きるに値しない」 能力を超えた難しさに直面して 不可能とわかりながら試みることで 書かれた音を忠実に再現するのではない 演奏の創造性が生まれる
これは クセナキスの書いてくれた曲の演奏だけではなく ケージの曲 あるいはフェルドマンでも それぞれに 物理的不可能を文字通り(つまり新即物主義的)ではなく 楽譜の示唆によって創造的に 意識を超えて行為しながら 身体的疲労を通して生まれる覚醒 演奏者たちをそこへ誘うためには 指揮者(あるいは調整者)は「音楽的に」表現しようとせず 冷静にハードルを提示する役割に徹する これはシェーンベルクやクセナキスや(おそらく)ノーノを指揮したシェルヘンの方法でした シェルヘンが言っていたのは プロイセン的精密さ(近代主義)は世界にひろまったが それとはちがうなにかがあること それを若い時シェーンベルクの指揮で『ピエロ・リュネール』のヴィオラを弾いていたころ学んだのかもしれない 18世紀の啓蒙主義的知でもなく 19世紀的・ロマン主義的自己超越とは似ているように見えても まったくちがう古代的智 クセナキスは「無神論的苦行」と言っていましたが それはオルフィズムの あるいは禅の あるいは老子の「無為」 に近い身体の使いかたとも言えるのだろうか」
8月某日 三軒茶屋自宅
早朝世田谷観音に出かけると、僧侶は未だ読経中で、開いたままの本堂の格子から観音像を眺める。町田の両親から、昨日もいで糠につけたばかりのキュウリ2本が届く。この異様な暑気に糠漬けはよい。スカイプで久しぶりに母の顔を見たが、思いの外元気そうで安心する。
「仰ることの意味は、頭ではよく理解できる気がします。「6つの要素」をリハーサルした経験からもそう思いますし、実際「オルフィカ」には「6つの要素」のようなパッセージが出てきます。
まだ身体に入っていないので判りませんが、そのメタ感覚に近いものを、大集団と共有するプロセスについて考えています。
案ずるより産むがやすしかもしれませんし、楽観はいけないかもしれません。策を巡らせてばかりいれば、本質からずれてきそうです。尤も、これは毎度のことで、今回は特に編成も大きく、個々が複雑なので余計そう思うのでしょう。勉強をしていくうちどこかで吹切れて、これでやろうと思うものが、自ずから生まれてくると信じています。
クセナキス作品に比べ、悠治さんの作品はより演奏が難しいと思います。やはり悠治さんが演奏に係わっていらっしゃるからでしょう。クセナキスは音と身体の生理が隔絶しているので、精神的に扱いやすい部分がありますが、悠治さんの作品は、身体的運動と音楽が、より具体的にせめぎあう気がします」。
8月某日 三軒茶屋自宅
午後から読響の藤原さんと、オーケストラ配置打ち合わせ。その前に本條さんと悠治さんと「鳥も」リハーサル。悠治さんもお元気そうだ。近所に住んでいてやり取りもしているのに、今回会うのはこれが初めて、と笑う。
本條さんの唄に、相聞歌のより女性らしい心情をひたひたと感じたのは気のせいか。毎回お会いする毎に、本條さんの唄の息が長くなっていると思う。フレーズのような稜線ではなく、凛とした佇まいの絹糸が、本條さんの処まで伸びていて、そのずっと先のところで、彼は糸を繰り続けているようにも、撚りをかけているようにも見える。
8月某日 三軒茶屋自宅
モーリシャスでタンカー座礁。ランバンサリのリハーサルに内幸町まで自転車で出かけたのはよいが、溜池を折れた辺りで通行止めになっていて、迂回路を行くうち道に迷う。
店員に道を尋ねようとコンビニエンスストアに駆け込むと、無人操業になっていて愕く。これが未来のコンビニエンスストアの姿なのか。未だ実験段階だとばかり思っていた。感染症対策にも少子化にも好都合なのだろうが、在留外国人のアルバイト先減少と、航空会社の客室乗務員の副業許可のニュースを読んだばかりで、どこか納得がゆかない。オーケストラも閉鎖されてしまうのではないか、とふと恐ろしくなる。将来は無人オーケストラか。今回の感染症で、ピアノコンクールのヴィデオ審査が広がったが、家人曰く、今後コンクール審査は、参加者はデジタライズされたピアノを弾き情報として記録して、審査員は在宅のまま、家にその情報を読み取れるピアノを用意して、デジタルピアノが演奏する参加者の演奏を審査するようになるという。
閑話休題。ガムランを振るのは甚だ不自然ではあるが、響きは楽しいし、子供の頃から憧れていた。本番中の会場での舞台転換を最小限に抑えるため、ガムランは置きっぱなしになるので、金属楽器の反響を調べる。座布団を中に敷いて吸音すると、ほぼ反響が抑えられた。
最近めっきり見かけなくなった右翼の街宣車が、「宇宙戦艦ヤマト」を高らかとかけて、内幸町のあたりを走り回っていた。
8月某日 三軒茶屋自宅
明薬通りの石像は、庚申尊の青面金剛だとわかる。どういうわけか石像には滋養強壮剤が供えてあった。青面金剛の憤怒の相は、最早すっかり滑らかに削られていて、角ばった顎あたり以外は判然としない。朝、世田谷観音に出かけ、特攻観音に手を併せた瞬間、梵鐘が鳴った。
山根作品は、一見単純な繰返しに見える和音を、一つずつ書き出して読み返すだけでも、随分印象が変わる。不安定で思いがけない内声の動きは、ていねいに一音ずつ読まなければ手触りまで行きつけない。落着いた動きのようだが、思いの外すばやい動きの、凸凹のある表面が浮かび上がる。
予約していたミラノ行きフライトキャンセル。
8月某日 三軒茶屋自宅
イタリア新感染者数574人。死亡者数3人。ICUには1人のみ。信じられない。結局生活習慣の違いはあまり関係なかったのだろうか。
楽譜というのは面白くて、作曲者側から眺めるのと、演奏者側から眺めるのとでは、まるで違ったものになる。作曲者にとってごく単純な事象であっても、演奏者は、記号を読み込み咀嚼し、思索を巡らせても到達しえない、複雑で奇怪な存在になったりする。
8月某日 三軒茶屋自宅
朝、慌ただしく大きな段ボール数箱が宅急便で届き、夜、富山より家人と息子が三軒茶屋帰宅。半年ぶりに会ってそれぞれ感慨は覚えているのだろうが、ごく自然に三人の生活に戻る。息子に背が伸びたか尋ねられたが、背丈より寧ろ、雰囲気が大人びたように感じる。背が伸びた分以前より痩せて見えるが、中学生の頃は、こちらも随分痩せていると笑われたから、自分も似たようなものだったのだろう。
8月某日 三軒茶屋自宅
朝から森作品リハーサル。関係者一同、感染症予防に最大限の配慮。演奏者の使用する椅子や譜面台に、それぞれ名前が振られていて、共有はしない。演奏者がそれぞれ自分の名前の書かれた椅子や譜面台をとって、定位置にセットする。机なども気が付けばすぐにアルコールで消毒して、換気にも充分気を配りながらのリハーサル。
皆で演奏できる喜びを、それぞれ噛みしめながら音を紡いでゆく。独奏をつとめる山根君と上野君が、とても深く咀嚼し自らの音楽としてあって感嘆する。作曲者と独奏者二人は、素晴らしい共同作業を実現していた。音を鳴らすだけの次元よりずっと深い部分で、互いに音という言葉を交わしている。迸る瑞々しい才気。
三軒茶屋自宅
権代作品リハーサル。先日から録音した通し稽古を聴いていただき、権代さんから助言をもらっていた。
作曲者から直接アドヴァイスをいただける倖せ。主旋律と信じていたものが装飾句で、装飾と信じていたものが主旋律だったりして、自らの読譜力の低さを恨めしく思う。実際、権代さんの助言通りに演奏すると、まるで違った風景が浮き上がる。それまで断片的な情報の並置だったものが、突如として有機的な相関関係を浮彫りにし、作品全体に一貫した意味をもたらす。
今日は権代さんがリハーサルにいらして、久しぶりにお目にかかる。大学時分、留学中だった権代さんから、海外に出るよう強く勧められて現在に至る。表参道の喫茶店で、彼と話さなければ、留学はしなかったかもしれない。日本でずっと過ごしていたら、全く違った人生だったに違いない。
8月某日 三軒茶屋自宅
ここ数日、メトロノームをかけながら、日がな一日繰返し「オルフィカ」を練習している。最初は指定の速度の倍の遅さですら、音が全く目に入ってこなかった。繰返しさらいつつ少しずつ速度を上げてきて、漸くほぼ指定の速度でも目がついてくるようになった。今まで4つぶりで頭の中の音を鳴らしてきたが、今日から思い切って、悠治さんの希望通り、2つぶりで練習を始めた。
安達元彦さん制作のパート譜には、4分音符120と指定されているが、悠治さんは2分音符60だと言っていた。現存するオリジナル総譜には、速度も拍子も書かれていない。初演当時に使われたパート譜には、今も演奏者の猥雑ないたずら書きがそのまま残る。
子供の頃よく聴いたレコード録音は、今回全く聴いていない。聴いても分からないし、第一、録音と実際聞こえる音がまるで違うのは経験上分かっている。そうして少しずつ見えてきた音風景は、驚くほど雄弁で、振る度に感激していた。
録音は素晴らしい産物だが、実演とは根本的に違う意味を持つ。録音は写真と同じく、ある瞬間を永遠化するものであり、実演は瞬間毎に新しく創造する作業だ。どちらも等しく意義深いが、ベクトルはまるで違う。
8月某日 三軒茶屋自宅
ドミューンにて放送イヴェント。話すのは苦手なので、このようなイヴェントは本当に困る。しかしながら、楽屋で悠治さんと話し込み、長い間の懸案だった「たまをぎ」再演の目処がついたのは素直に嬉しい。「たまをぎ」合唱部分は明治学院大学に残されていたが、オーケストラ部分は何年探しても出て来なかった。だから、今回は悠治さんのご協力をえて、録音から再構成版をつくることにした。1月24日まで時間がない。
初演は、方陣を組んだ100人ほどの合唱が走り回る、縦横無尽なシアターピースだったが、現在の状況で実現不可能だ。今回は合唱も楽器も小編成の演奏会形式でやり、楽譜をしっかりと用意しておき、将来もとのような形での演奏が可能になったら、あらためて実現を目論みたい。本当に間に合うのか。
ドミューン楽屋で、一柳先生と悠治さんと3人になったとき、一体お二人が何を話すのか興味津々だった。先日悠治さんが弾いたばかりの「告別」について、どこの箇所がむつかしいよね、などと、盛んにベートヴェン談義が愉しそうに話題にのぼっていて、感銘を覚える。
8月某日 三軒茶屋自宅
「アフリカからの最後のインタビュー」演奏終了。「黒人の命は大事」運動の盛上りのなか、この作品をサントリーで演奏すると、また別の意味を持つことになった。
息子も息子の友人の中瀬君もペンライト演奏で参加。今朝、シェル石油が日本撤退のニュースを新聞で知る。サロウィワは何を思うだろう。
久しぶりに「東京現音計画」の皆さんと再会し、演奏にも接してみて、あらためて素晴らしいバンドだと思う。初演より格段と演奏の強度が増していて、何より演奏から音が伝わって来ないのが良い。音ではなく、もっと堅固な何かが我々の喉元に突き付けられる。信念のようでもあり、メッセージのようでもあり、それは実は情熱なのかもしれない。
サントリーの天井にうつろう、ペンライトの茫洋とした光が印象に残っている。
8月某日 三軒茶屋自宅
「オルフィカ」リハーサル。悠治さんリクエストメモ。
強音は身体をゆるめ、楽器の一番良く鳴る音にまかせて出すこと。むしろ弱音の方がよほど演奏がむつかしい。
5連音符、6連音符で書いてあるのは、確率で決めたもの。正確な計算ではない。だから、演奏するとなお不正確になる。あまり拘らなくてよいですね。
音の始まり。その前には音がなく、ピアニッシモであっても、そこから音が始まる。そして余韻を残さずに音を止めることで、各人にあてがわれた別々のパートの各音が、ばらばらになる。
音の終わりは閉じてほしい。管楽器なら、息を残さないこと。弦楽器なら弦の上で弓を止める。どこでそれをやるかは、各自自分が一番いいと思われる部分で音を出してほしい。
それぞれ別だから指揮者を頼ることもできない。
指揮は、2拍子を何回かやれば、だんだんだらしなくなってくるので、テンポを動かしてほしい。予測つかないみたいになりたい。ああこのテンポだと思ってやっているとそうならない、という風にやってほしい。結局、指揮者がいるが、いろんな音が勝手にでてくる風になりたい。
グリッサンドは最初の音を確定してから動き出すのではなく、最初から動き出す。弦楽器であれば、上がる場合は左手をアッチェレランドしていけば均等に聞こえるし、降りる場合、早く降りてゆっくりおわると均等になる。
揺れる音は、毎回揺れかたを変える。だんだん、死んだようになってくるから、テンポや幅を変えてほしい。自分のアイデアで変えてください。全体の音が聞こえていて、自分からは誰とも違う響きがでていることを意識する。
できなくてもいいんです。整然といくより、できなくて、いろいろなことがでてくることがいいんです。
始まりと終わりなんですけど、楽譜とあんまり関係ないことなんですが、はじまりかたは、はじまるときに、全く何もない空間から、突然と出てくるような感じがほしい。ちょっと一瞬静まったときに、どこからともなく出てくるような、不思議な感じがほしい。
一番最後なんですけど、ちょっと緩めてください。揺れながらふうっと消える。
8月某日 三軒茶屋自宅
読響との演奏会終了。「鳥も」では指揮せず、銅拍子と鏧子など小道具を演奏し、曲名を言うだけなのに、特に銅拍子は本当にむつかしい。さわりを残さなければいけないと言われても、なかなかうまくいかない。無心になってやるものなのだそうだ。鏧子も、チーンとならせば良いのかと思っていたが、高い倍音を消すように、緩く向こう側に少し撫でるように叩かなければならない。われながら、煩悩の塊だと妙に実感する。
本番、本当に無心になって初めて銅拍子がとても美しく響き、さわりがいつまでも消えなかった。余りに無心になっていて、次に「島」というはずの題名を「鳥」と言い間違えてしまった。もう一生銅拍子は叩きたくない、と思っている。仏具はそれに見合った人格者が触らなければいけない。尤も、演奏は本條君が実に見事に歌い上げてくださったし、オーケストラも彼に美しく沿ってくれたから、全く文句をつけるところではない。自分自身の煩悩に嫌気がさしただけである。
読響とのリハーサルは、リハーサル前の準備段階から、感動させられることばかりだったし、学生時代の仲間に会えたのも本当にうれしかった。たとえば山根さんの作品で、コンサートマスターの長原さんが、第一ヴァイオリン後方で第3パートを先導して下さっていて、オーケストラの細やかな心配りと采配に密かに感動していた。第1パートの小森谷さんと合わせて、実に見事な演奏だった。
オルフィカの冒頭、悠治さんの希望の何もないところから顕れる音を体現して下さったのは、小森谷さんだ。本当にオルフィカなど、自分では何もしていないが、オーケストラの一人一人が、それぞれの音をとても濃密に演奏して下さった。読響の音の印象は、濃密な音と音楽の深さだった。
マスクで苦しそうにしていると、藤原さんがアイスキャンディーの「ガリガリ君」を差し入れて下さったり、悠治さんの難題に四苦八苦していると「そんなに気にしなくても大丈夫ですよ」なんてオーケストラのM君から声をかけられたり、不思議なくらい人間臭いお付き合いがあってこその渾身の演奏だったのかもしれない。指揮者など、実際のところ本当に何もやっていない。深謝。
8月某日 三軒茶屋自宅
リハーサルは午後からなので、思い立って、朝湯河原まで墓参に出かける。子供の頃から数えきれないほど通ったからか、小田原を過ぎたあたりから、強烈な郷愁に襲われるのは、相模湾の匂いと海の色のせいだろうか。
英潮院の墓地へ昇りながら、振り返ると、深い色を湛えた海が眼下に広がる。何度ここを訪れても、子供のころから変わらない感動に襲われる。ただ、目に飛び込んできた祖父母の墓石に、これだけ激しく心を動かされたのは初めてだった。来てよかったと思う。
「自画像」リハーサル。鈴木さんが振ると、音楽が溌溂としてくる。
最初に通すと、書いた金管セクションが、想像通り世界を飲み込んでしまって、人生最大の失敗作かもしれないとも思う。成功など目指していないから、失敗にもならないが、もっと普通にオーケストラ曲を書けば良かったのではないか、との疑問が頭をもたげかける。
「アフリカからの最後のインタビュー」を、コロンビア大で聴かせたとき、何故こんなに明るい作品なのか、とアフリカ系の作曲科教授ジョージ・ルイスから投げかけられた素朴な問いが、未だにずっと脳裏に残っている。Black lives matterが全世界的に広がりを見せる、ずっと前の話だ。
もちろん、明るい内容で書いたわけではなく、当該地域の讃美歌をそのまま使ったので一見明るい音の素材になっただけだが、彼の指摘以来、どこか音楽的に成立させるために素材を利用してきたような、後ろめたさを引きずってきた気がする。
特に題材が特殊であれば、音楽的に書くほどに表面的な音楽になる危惧を覚えていた。
オーケストラは、やはり基本的に後期ロマン派までの作品を演奏するために形作られた社会体系だ思う。オーケストレーションは、オーケストラを一つの楽器にみたて、さまざまな響きを作り出すために作曲者がつくるものであり、オーケストラ一人一人の顔は浮かばない。それでいいとも言えるし、自分が同じことをしなくてもよい気もする。
8月某日 三軒茶屋自宅
朝5時半。澄み切った明け方の空に、くっきりと輪郭を浮かび上がらせる、湧き立つ積乱雲。夜半したたか雨が叩きつけたのか、道はまだ濡れている。
川島君の作品を、漸く最初から最後まで見学できた。素晴らしい!お互い多分高校生くらいから知っていて、彼の印象は当時から今まで全く変わらない。自分には到底真似できない情熱とカリスマがあって、一方的にとても尊敬してきた。確固とした技術と叡智があるから、彼の音楽はどんなに破綻していても純粋に愉しめる。自分が瞬間ごとに忘れてゆく気質だからか、彼のように、知識や経験がすべて蓄積されて、ますます極めてゆく姿に、素直に感銘を受けている。
一柳先生の新作は、闊達で瑞々しい。音楽は縮こまらず、のびやかで、甘くだれたりすることもない。それはご自身の人間性とまるで瓜二つで、いつも自由で本当に不思議な方だ。前に二重協奏曲を演奏したときも、一柳さんと彼のピアノ協奏曲を演奏した時も心底そう思った。どうやったら、あのように尖った、新鮮な感覚を持ち続けられるのだろう。カーターがお好きであったり、悠治さんと音楽の趣味が一致するのだから、もちろん頭では理解しているつもりだけれど。
リハーサル後、鈴木さんと少し話す。互いの子供の話とか、反抗期についてとか。高校のとき、彼は東ティモール問題について論文を書いたという。別の機会に学校でインドネシア大使館を訪れた際、東ティモール問題について大使館員に疑問を投げかけたというからおどろいた。
大使館の方は、学生からの質問に備えて、反駁するために膨大な資料を机に堆く用意して待っていた。鈴木さんはデンハーグの国際裁判所にも親しい友人がいる。
8月某日 三軒茶屋自宅
「自画像」リハーサル。学校でオーケストラについて習うとき、やってはいけないと習うことばかりを集めて書くと、こんな風になるだろうと思う。
こうやったら聴こえない、とか、こうやったら効果がない、ということばかりを集めてやる。聴こえるように、効果があるように書く意味とはなにか。オーケストラは重ねれば聴こえるようになる。背景を消せば、明瞭になる。リズムをそろえれば、一体感が生まれる。
世界中に埋もれ聴こえない声は、聴かなければよいかも知れない。わざわざ賑々しい席で、普通であれば目を背けたくなる現実に、わざわざ目を向ける必要もないかもしれない。
これは作曲とは言えない、とは書き始めた当初から思っていた。最初から最後まで、ストップが極端に限られた古いオルガンのように、音量の強弱も、曲線を描くフレーズも皆無のまま、20分間近くただひたすらドミナントペダルの上に、事象ばかりを連綿と紡ぎ、そこには弛緩も呼吸も存在しない。そんなものは音楽ではない。無情に時間だけが刻まれてゆき、2020年にそれが止まるのみ。
では、音楽を書けばよいのか。自分が無事に日本に戻れるかどうかすらわからず、毎日何百人という人が亡くなり、アパートに防護服姿の看護師たちが救急車で駆け付ける日々のなか、今書いておかなければいけないと思ったことは、書かなければ一生後悔しただろう。今後、書く機会も、書く時間もないと思っていたし、今もそれは変わらない。
オーケストラは、本来皆で一つのハーモニーを紡ぐための社会体系だった。理想論と笑われようが、世界も、本来は皆で一つのハーモニーを紡ぐものであってほしかったが、実際はこの50年間だけ顧みても、一時たりとも世界が平和になった瞬間はなかった。
最初に各国の国歌を書き取り、大きな表に並べてみた時、見えてきた音に思わず鳥肌が立った。あまりに惨く響いて、これを書くべきかどうか、ひと月ほど悩んだが、毎日信じられないほどの人が世界で死んでいく毎日のなか、やはり書かなければ後悔すると思うに至った。
そのとき、聞こえてきた音そのままの音が、目の前で鳴っている。
せっかくオーケストラを使うのなら、もっと希望があって、演奏者も聴き手も心地良く、満足感の得られるものを書くべきだろう。オーケストラを書く力がない、ともいえるし、西洋的なオーケストラを書く行為を放棄しているともいえる。演奏者には聞こえない無力感を与え、希望の象徴であるはずの国歌は、無残に戦禍に塗れて、まるで亡骸にこびりついているようだ。
8月某日 三軒茶屋自宅
自画像演奏会終了。 鈴木さんと東京フィル、文字通り渾身の演奏に聴き入る。自分の作品として聴き入るというより、走馬灯のように駆け抜ける50年の恐ろしさに、そして、鬼気迫る演奏者の姿に、ただ圧倒された。
演奏者は、互いに聴きあって一つの音楽を紡ぐのではない。セクションごとにまるで、それぞれが国となったかのように見える瞬間もあった。演奏者自身もそう感じていたのではないか。
良い作品とは到底思えないし、成功したとも思えないが、少なくとも当初頭に浮かんだ音そのままが、演奏者一人一人の燃え盛る情熱に駆り立てられて浮かび上がり、曲尾のオーケストラがユニゾンで合奏する部分は、本当にベルガモの谷のまにまにいつまでも木霊する弔礼ラッパのように響いて、ますますやりきれない心地に襲われた。
こんなに達成感や満足感のない新作も生まれて初めての経験なので、どう捉えてよいのかわからなくて戸惑っている。ただ、必要だったという思いだけが、いつまでも反芻している。
付き合わされる演奏者や聴衆に甚だ申し訳ない気もするが、世界をとりまく現在の特別な世情を鑑みれば、ある程度は理解してくれるかもしれない。
この状況で実現された音楽祭は、関係者全員の努力の賜物以外の何物でもない。その努力に力を与えてくれたのは、関係者と聴衆の「希望」ではなかったか。3月4月くらいは、無事に日本に帰れるかどうか分からなかったし、曲が最後まで書き上げられるか分からなかったし、演奏されることなど想像もしていなかったし、自分がそれを聴くことができると期待すらしていなかった。
万が一のことがあっても、家族に作曲料が入って生活の足しになれば、と思ったのと、そんな状況なら、書かなければ後で後悔することをやっておこうと思った。それ以上でもそれ以下でもない。
舞台裏で、笑顔で気軽に挨拶してくださる方がいて、知合いの評論の方かと思いきや、マスクを外すと、思いがけず鈴木雅明さんで大変恐縮した。マスクは、顔の情報を半減させてしまう。
演奏会後、久しぶりに悠治さん、美恵さんと喫茶店でしばらく四方山話。悠治さんの波多野さんとノマドのために書いている新作。原発に関する藤井さんの回文。
2度や7度のようなぶつかる音は今まで散々使い古されている、ともいえるが、それらを異様に排除しようとするのもどうなのか。日本の文化とスペクトルとの融和性か、それとも穢れを排除する風土故か。
8月某日 ミラノ自宅
フランクフルトの空港は、6月に東京に戻った時よりずっと賑わっているようにも見えた。
機内のアナウンスでは、「このような状況にも関わらずご利用いただきまして、まことに有難うございます」「Covid 感染症対策のためXXXは閉鎖されております」という言葉が長々と続く。
フランクフルトの手荷物検査で、タブレットをリュックから出すのを忘れて止められた以外は、滞りなくミラノまで辿り着いた。ミラノへの機中に、渡航歴に関する書類を提出させられ、体温検査をやっている以外、目新しい検査もなく家に着き、拍子抜けするほどだった。
久しぶりの家は、我々が帰ってくるのを待っていたように見え、半年ぶりの帰宅に思わず息子は興奮して歓声を上げた。機中、二人掛けの座席に息子と隣り合って座っていたが、すっかり身体も大きくなった息子が、窮屈そうに身体を曲げ、小さい頃のようにこちらに肩を預けて寝込む姿に、以前彼と訪れた旅行を思い出していた。
(8月31日ミラノにて)