海の底で目が覚めた
先程まで水槽のような部屋で眠っていたのに
桜色の鯨が行き先を訊いてきた
光の差す方へ行きたい
海の中は暗いから
鯨は唄いながら私に教えた
陸も墓のように暗いが
光の束が行進している
黒い影に向かって
何かを止めようとして
灰にも塵にもならない沈んだ船と共に埋もれる前に
地上を探して浮き上がる
水面から見た地上
空は黒く煙が噴いている
陸には小さい光の束
祈りながら歩いているそれは
輝く星のような人の行列
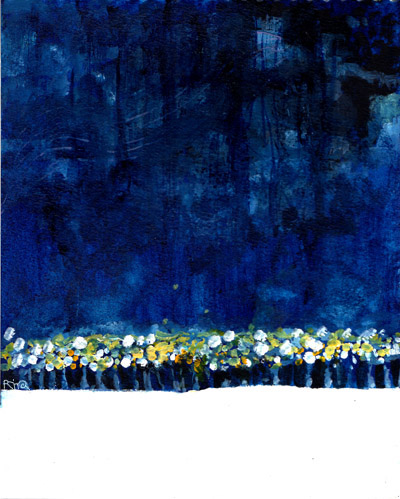
海の底で目が覚めた
先程まで水槽のような部屋で眠っていたのに
桜色の鯨が行き先を訊いてきた
光の差す方へ行きたい
海の中は暗いから
鯨は唄いながら私に教えた
陸も墓のように暗いが
光の束が行進している
黒い影に向かって
何かを止めようとして
灰にも塵にもならない沈んだ船と共に埋もれる前に
地上を探して浮き上がる
水面から見た地上
空は黒く煙が噴いている
陸には小さい光の束
祈りながら歩いているそれは
輝く星のような人の行列
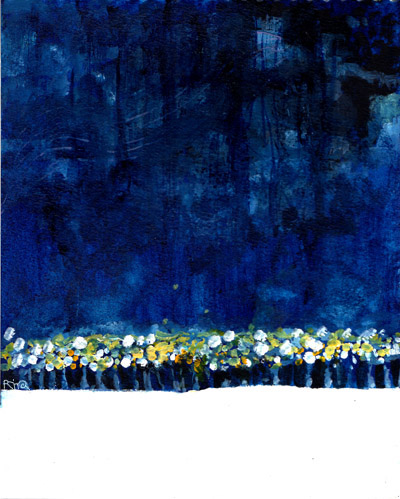
6月29日、丁度、ヨルダンについたら、金曜日だったので、デモを見に行くことにした。「アラブの春」の影響を受けてヨルダンでも毎週金曜日は、キングフセインモスクの前でデモをやっている。今回のテーマは、公共料金の値上げに反対するというもの。
モスクの前だからイスラム政党が仕切っているのかと思いきや、旧ソ連の国旗のようなTシャツを着たグループもいて、結構みんな楽しそうにみえる。ヨルダンのデモは公道を遮断して、道一杯にデモ隊が繰り出すから迫力がある。ヨルダンでは、当局の言論統制がさほど強いわけではなくても、「こんなこと言ったら当局にひどい目に合わされる」という風に思い込んで、自重してしまうことが多かったそうだが、「アラブの春」以降はみんな自由に主張できるようになってきたとか。
時を同じくして、日本でも、大飯原発再稼動に反対するデモが官邸前で行なわれていた。こちらも毎週金曜日に集まるようになっている。先週は4万5千人あつまった。そして、なんと20万人?が集まってきたというからすごい。日本はたくさん集まっても歩道しか解放してくれないから迫力に欠けるけど、さすがにこれだけ人が集まったらすごいだろう。なんだか遠くにいてもエネルギーをもらった気がする。ツイッターやフェイスブックの力は侮れない。誰かが、「アジサイ革命」と呼んでいるそうだ。
そしてシリアはどうだろう。6月28日に、ヨルダンのシリア難民がシリア大使館前に集まってデモをした。国家の替え歌がうたわれる。新しい曲を作るのではなく、替え歌というのが引っかかるが。最後には、大統領の大きな写真を持ってきてみんなで踏みつけるパフォーマンス。
僕は、1994年から2年間、シリア政府の工業省で働いていた。協力隊員として派遣されたのだが、ハマの国営タイヤ工場で生産されるタイヤの品質改善を行なっていた。やる気のない公務員たちと働くのは、厭だったが、彼らを観察するのはとても楽しかった。だから、今のシリアが信じられない。バッシャール大統領は、父親から政権を引き継ぎ、民主化に向けた改革を自ら行なおうとしていた。クリーンなイメージがあったのに。
しかし、今は、デモを極上の暴力で押さえ込もうとしている。
昨年4月29日、13歳の少年、ハムザ君が、デモに参加し、父親とわかればなれになってしまい、シリア当局に拘束され、拷問を受けて遺体となって戻ってきたという事件があった。電気ショックやタバコを押し付けた後があり、性器も切断されていたという。
このニュースを聞いた時、私は吐き気がした。こんな国の政府で2年間も働いていたのだ。大統領の写真を踏みつけたい気持ちだ。僕は当時東北の復興支援で走り回りながらも、怒りに震えながら、この記事をリツイートしたのを思い出す。
しかし、最近出版された、元在シリア日本大使を務めた国枝昌樹氏の『シリア アサド政権の40年史』(平凡社)には、シリア政府は、ハムザ君は、4月29日のデモで銃撃され死亡したとし、身元がわからぬまま3週間たってしまったこと。検視報告書によると、弾痕以外の損傷はなく、死亡後に、遺体が朽ちて損傷し、性器も腐り落ちたと説明しているという。だからといって、アサド政権の弁をどこまで信じていいのかわからない。
しかし、国枝氏の本は、アサド寄りに書かれていて、僕はかなり共感した。なぜならば、アサドがデモを怖がり過激な暴力で鎮圧することには、意味がない。なぜならば、暴力がネットで流れてしまうことのほうがもっと怖くて、政権にダメージを与えるのはわかりきっている。ネット時代。実際にそうなってしまっている。そんなことを、アサド政権は自ら好んでやるのだろうか。外国からの介入で真実が歪められている気がしてならない。政権側も、反体制側も信用できないのだ。
事態が深刻なのは、暴力がエスカレートし、犠牲者が増えていること。何とか、犠牲者を救済しようと、張り切って、ヨルダンに来て見たものの、お金もさほど集まらない。「何をしてくれるんだ」というシリア人の期待に、そえない自分にいらだつ。それならば連帯だと、差し出される、「自由シリアの旗」。僕は、感情的には、昔のシリアを懐かしむあまり、「政治的には中立」をたもち、旗を振る彼らを冷ややかに見ざるをえないのだ。
六月がもうすぐ終わる
ほんのり青い曇天を
つば広帽のように深くかぶって
ここで いま
夏休みを待ちこがれる妹のように
花を咲かせる
青いあじさい
赤いあじさい
この世のものとは思えない
夕映えのなか
全車線に広がる
新しいものに水がみちて 重さをまして
殺処分された生き物たちが
還っていく 深く 地に染みて
ふわふわと
はがゆいもの吹く 微風のなかで
赤子を抱いた若い父は
今日も生きていく
そう 生きていくのよ
去年のいまごろ
まだこの世にいなかったきみだって
静かに 確かに 息をしている
埃っぽいアスファルトの道に
広がり 連なり
見えない地球の裏に
目を凝らして
賢しらなことばをほどき
愚直なことばを結ぶ
営みそのものが試されていく
あすは すいみつ にゅうどうぐも
台風最接近のはずがそれて、大雨、洗濯ものが乾かないため今年初めてのクーラー稼働。
慰霊の日、糸満あたりではハーレーがあるユッカヌヒーに梅雨明け。
クーラー、暑くて昼間からスイッチを入れるともう切ることはできない。窓を開けるとぬめ〜っとした風が忍び込み扇風機では太刀打ちできない、長い夏のまだ途中。
家のまわりはコンクリートとアスファルト、木陰は皆無。リゾートとはかけ離れた錆びれた街中、活性化のためのイベントの案内はほぼすべて土日。平日休みの人間には縁が無い。
この十年くらい海に行っても木陰がある涼しいビーチなんてなくなってしまい、砂をよそから持ち込んだ人工ビーチ。陰が欲しければお金を払い、ビーチパラソルで少しばかりの陰を買うしかない。沖縄でサミット開催が決まったとき、会場になったところは昔ながらの砂浜と木陰があったけど、サミット前から工事が始まり、ホテルと会議施設ができ、自然の砂浜、木も無くなり、陰のない人工のビーチになった。なにか持ってくると、べつのなにかが壊される繰り返し。
今からちょうど150年前の7月4日、30歳の若き大学人は、その友人、そして同じ大学の(今でもその編纂した古典語辞書が重宝されている)高名な学者の娘三人と連れだって、川へピクニックに出かけました。途上、彼は真ん中の姫にその子を主人公とした不思議な話を物語り、少女にねだられそれはのちお手製の本としてプレゼントされます。その冊子こそ、有名な『不思議の国のアリス』の元となった”Alice’s Adventures Under Ground”です。
唐突ですが、私は今月で30歳になります。独身です。実は曖昧なことよりも論理の方が好きで、またどういうわけか、現在高等教育機関で講師業をしており、ひそかに人へお話を物語っていたりします。なぜか生意気な子に好かれます。それから波長の合う子となら、即興で言葉遊びなどをすることも。
基本的には「――だから?」という問題ですし、私もことさらに偶然の一致を必然のように語ろうとしているのではなく、実際ふたりのあいだには差違は様々あり、私はカメラを全然用いないどころか、少女よりも少年になつかれ、そもそもアリスのような特別な相手もいません。ただ私は彼の生まれた150年後に生まれ、そしてほんの少し似たような道を歩もうとしている、ように見えなくもない、と、それだけのことで。
翻訳というものがひとつの芝居でもあるならば、たとえ翻訳者がどのような人物であっても、巧みでさえあればどんな人物になれるのかもしれませんし、演者と役が似ているか似ていないかなんて、どうということもないのかもしれません。上手ければ障害となるものなど何もないのであると。
しかしここで私は、知人が”Le Petit Prince”について言っていたことも思い出すのです。「この作品が、心に傷のないやつに扱えたものか」――つまり、たとえば自意識ばかりが肥大した若者や、安定し幸福な立場にある老教授に、この作品が本当に訳せるのか、という、疑問というより心情に近いものでしたが、研究者としての私は否定したくても、個人としての私にはうなずけるものでもあり。
確かに、”The Great Gatsby”は、翻訳の技術を手に入れた円熟のハルキ・ムラカミよりも、「まだ訳せない」と思っていた頃の若い村上春樹に訳されていてほしかったし、あるいは生前広くは認められなかったH・P・ラヴクラフトやフランツ・カフカが、今をときめく人気翻訳者に訳されようものなら微妙な気持ちにならざるをえず、どこかごく少数の人にしか認められず毎日をもがきながら生きている、そんな(おそらく私ではない)誰かに訳されていてほしいと願ったりするおのれもいるわけで。そこまで行かずとも、とかく翻訳では年の功や経験が強調されがちですが、若書きの作品はやはり若訳しされてもいいのでは。
これはどこか良心に属するようなものでもあると思うのです。ふと自分と誰かが似ているなと感じたとき、または、何か偶然の状況が自分の背中を推してくれているような気がするとき、翻訳者の歴史を研究している自分は、やはりここで先に見えている何らかの道を、ちゃんと選んでおかなければならないのではなかろうか、と。
「アリス」はこれまで様々訳されていても、こういった形でキャリアの重なる人間に訳されたことは、もしかして今までなかったのではなかろうか、もしそうだったとすれば、自分がこの選択を取らないことは、先人にとって(あるいは翻訳の神様にとって)たいへん失礼なことではないのだろうか、と。少なくとも今自分は、30歳の大学人という文体をたまたま手にしているのだから、これを生かさなければ、と。
むろん、日本のアリス翻訳史を振り返ったとき、そういった意味では幼妻と一緒に訳したという高橋康也先生の存在はたいへん大きなものなのですが、しかし神様や倫理を持ち出さずとも、自分に正直なことを言ってしまえば、「これは何だかすごく面白いぞ」ということであって、心と身体の底から盛り上がり湧き上がる何かがあるわけでして。
そんなわけで、アリス150周年のこのときに、30歳の私は”Alice’s Adventures Under Ground”を訳し始めようと決めたのです。そして(当時に同じく)3年後の7月4日までに、”Alice in Wonderland”を訳し切ろうと。
私にとって、「翻訳」行為そのものは、本が出版されるとかされないとかとはまったく別次元のところにあって、商業の都合で何かが訳されたり訳されなかったり、訳したり訳さなかったり、そんなことよりも、今自分が挑戦できる翻訳に取り組みたい、そういうものであるのです。
だから、訳します。7月4日から。その途中経過(不定期連載)はたぶん、復活したaozorablogで。
ほんものですかと聞いた。東京・駒込にある東洋文庫ミュージアム。2階に上がって薄暗い中に浮かび上がるのは、写真や映像でしか知らないイギリスやストックフォルムやウィーンの図書館や司馬遼太郎記念館を思わせる天井まで続く書架。「モリソン書庫」とある。北京に暮らしていたオーストラリア人のジャーナリスト、ジョージ・アーネスト・モリソンが集めたおよそ2万4千冊を1917年に岩崎久彌が一括購入、その後、自身の蔵書などと合わせて1924年に財団法人東洋文庫をたちあげた。2011年秋に建物の改築に伴ってミュージアムを併設し、展示室(といっても実際の出納もおこなう)としての「モリソン書庫」を完成している。
文庫全体の蔵書は現在およそ100万冊。ミュージアムができたことでさまざまな企画展として蔵書が公開されるようになり、研究者でなくても閲覧できるようになった。取材で貴重書のいくつかを見せていただく。温度湿度を自動管理された部屋ながら緊張してヘンな汗をかく。実際のところ、それぞれの資料のどこがどう貴重なのかほとんどわからない。でも、浮世絵の紺や赤のグラデーションのなんて鮮やかなこと、明の時代の漢籍の紙がなんて白く朱や墨のなんて艶っぽいこと。文庫の方が熱い思いを淡々と延々と話されるのを聞きながら、『東洋文庫の名品』(平成19年 東洋文庫)にあった、収集と保管、研究に寄せるたくさんのひとの執着や情熱を思い出して、ひとの一生では過ごしえない時間と知りえない世界を渡り歩いてきた本たちへの、ねたみみたいなものを覚えてしまった。
このミュージアムはフラッシュを使わなければどこで撮影してもかまわない。「モリソン書庫」をバックに自分撮りするひとが多いようだ。もちろんわたしも。どの1冊もまともに読んで理解することはできないのに、すべての本が”わたしのもの”でもあるように感じるのはどういうわけか。本は読んで理解できたら最高だが、理解できなくても読めなくてもそれでもいい。しあわせなやつだな、本って。
クラスノヤルスクのホテル6階の窓から外に目をやると、夕陽がエニセイ川を真っ赤に染めています。眼下の350年記念広場では、思い思いにドレスアップした若者たちが互いに記念撮影をしていて、高校生の卒業パーティーでしょうか。広場にはいつも2頭ほど馬が佇んでいて、子供をのせて歩く風景もみられます。大きな噴水の向こう側、川への階段を降りきったところでは、コーヒー牛乳の瓶を、斜めの板に載せただけのゲームが結構賑わっていて、日本のヨーヨー釣りのようなものでしょう。垂れた釣糸の先につけられた輪で瓶の首を引っ掛けて立てるだけの素朴な遊びで「釣れたら4000ルーブル」と破った段ボールの切れ端にマジックで書いてあります。30分ごとに時報の短いチャイムが鳴るのも独特の風情で,子供のころによく聞いた短波ラジオのインターバル・シグナルを思い出します。
—-
6月X日11:20 ミラノ・Lスタジオ
昨日録ったOさんのシェルシを聴き返す。野性的で直情的な音楽は、時に日本の子守唄のようなひびきで、耳にねっとり残る。
家人が一年間通ったイタリア語クラスの打上げに息子を連れて顔をだす。小学校隣にある社会センター、ここは共産党系の自習施設のようなもの。普段は学校帰りの中学生たちが一緒に宿題などをやっている。この語学教室は、息子の通う小学校で開かれた外国人の母親のための無料のイタリア語教室で、市が主催している。7割がアラブ人、エジプト人女性なのだが、普段彼女たちを街で見かけても、別段明るい印象も持っていなかったのが、ここでは別人のように活き活きとして、喜びがみなぎっていることに心を打たれた。修了証書と記念写真を一人ひとり受け取るとき、アラブの女性たちは舌をふるわせ歓声をあげる。みな、見違えるように嬉しそうだ。
そこのイタリア語を教師フランチェスカのパートナーと話しこみ、「暗やみでお食事を(Cena al buio)」の話しになる。イタリア視覚障害者協会がずいぶん前から開いているイヴェントで、窓をしめきり文字通り真っ暗ななかで、視覚障害者に手伝ってもらいながらフルコースの食事をするだけなのだが、それは素晴らしい体験だという。
自分が部屋のどこにいるのかも勿論わからなければ、何を食べようとしているのかもわからない。何を食べているのかすら、時としてわからない。水やワインをグラスに注ぐことなど、神業のように思えるそうだ。殆どすべて視覚障害者のひとに助けてもらって、彼らにとってごく自然な形で食事をとることで、助ける側と助けられる側が逆になった、新しい世界観がひろがる。
と、教室の外で遊びに興じていたアラブの子供たちが、口々に甲高い声で叫びだした。誰が一番うるさいかを競っているらしい。途中で一人の子供が耳をいためて大声をあげて泣き出した。
何でも息子は校長先生から呼ばれて、学校登録にきた日本人の通訳をしたと大得意だ。校長先生自ら、授業中の小学1年生を呼び出して通訳させようとする発想がイタリアらしい。
6月X日 22:40 自宅にて
「カジキマグロや」亭にでかけ、パリからやってきた作曲のS君とOさんに会う。S君には数年前からあってみたいと思いつつ、機会を逃してしまっていたが、会ってみると控えめでまじめな青年だった。彼の曲を聴くと、洗練された響きの部分よりむしろ、そこに浮上る一見不器用そうな部分こそ独特で魅力的だった。アムランのピアノが好きだという言葉が印象にのこる。Esaの譜割りがなかなか終わらない。
補講にでかけると、隣の教室から聴こえてきたピアノに思わず聞惚れてしまう。ベルガマスク組曲全曲と、感傷的で高貴なワルツ。ペダルは極力抑えてあり、悪趣味なルバートもなく、和声感が美しく、こんな素晴らしいピアニストが学校で教えていたのか誰だろうと隣の教室に入ろうとすると、生徒たちが静まってレコードを聴いているところだった。ベルガマスクの出だしを何度もくりかえしていた以外、止まらず間違えもせずさすがに妙だと思ってはいたのだが。しかし誰の演奏だったのか。ベルガマスク組曲があれほどすばらしいと思ったことはなかった。隠れていたバロックのひびきが浮上る。
6月X日 23:00 自宅にて
夏のフェスティヴァルで演奏するドナトーニのプログラムを書くことになり、途方にくれている。ドナトーニが書いたプログラムノートが殆どないことがわかり止むに止まれず。朝晩息子をサマーキャンプに送り迎えにローモロ駅に通いながらバスのなかでシューベルトの5番を読み返し、ドナトーニの本を捲っている。
家に帰るとクラスノヤルスクで大学2年生のときに書いた拙作を演奏するため慌てて譜読み。自作の譜読みはいつも一番最後、申し訳程度にしかやる気がおきない。楽譜を広げて思い出されるのは、大学2階奥の広い教室で、明るい日差しのなか、せっせと授業中に書いていたこと。当時は横へ音楽を紡ごうとしていたことを思い出す。
6月X日 23:30 三軒茶屋自宅にて
翌日日本経由でクラスノヤルスクへ出掛けるという段になって、プログラムにドヴォルザークのセレナーデを足してくれと言われる。とにかく楽譜を荷物に放り込んで家族と一緒に日本に発ち、機内で息子を寝かせた上で、毛布をテント状にして読書灯を遮りつつ譜読み。これほど混乱したスコアなのは原本のせいか、校訂者のせいか。日本海に差し掛かるころ、ようやく最後まで粗読みを終えて少しだけ眠った。
セレナーデの流れが納得できず和声分析を一からやり直してみる。音がわかっていても、コンテキストが繋がらなければ音楽は流れない。単純な和声と高を括っていても、実は全く分っていない。人体を素描するとき、ただ表面をなぞるのと、骨格や筋肉の厚さを理解し表面を描く違いとはこんな感じなのかもしれない。
6月X日 23:15 クラスノヤルスクホテル
モスクワ経由でクラスノヤルスクに着く。時差5時間のモスクワに10時間弱かけて飛び、5時間近く日本方面に戻ってクラスノヤルスクに着くと、日本との時差は1時間になっていて、狐につままれた気分だ。ここはヨーロッパではなく中央アジアだという至極当たり前の第一印象。英語はあまり通じないが、みなとても親切で温かい。熱く滾るような演奏は想像通りだが、思いがけず繊細な部分にもふれて感激する。招待してくれたオーケストラのディレクターは、クラスノヤルスクからは、モスクワ、パリ、ベルリン、ミラノ、東京、どこに行っても今や距離感は一緒だと力説しているが、そんなものなのだろうか。ドヴォルザークは、不可解なリタルダンドなどは無視して、フレーズを大きくつくることに腐心。展示部と再現部で楽譜に矛盾はなはだ多いためだ。
6月X日 00:20 クラスノヤルスクホテル
今日の練習会場はスリコフ記念美術館。スリコフの聖母と聖ガブリエルの絵には目を奪われる。ワシーリー・スリコフ(1848-1916)はクラスノヤルスク生まれの、ロシアの代表する画家だが、彼の受胎告知は官能的としか形容できない。聖天使ガブリエレは、屈強な男性像で、対する聖母は戸惑いを隠せないあどけない少女だ。イタリアで見る構図とは正反対でこちらも当惑せずにはいられない。マリアの位置づけがロシア正教でまったく違うのだろう。ガブリエレは白色の大きな光を放ち、内に秘めた情熱が放射するようだ。性向も世代も違うが、スクリャービン(1872-1915)の悩ましげな響きが立ち昇ってくる。ここでは魂が素材に宿されているのがわかる。裡へと内向する情熱に圧倒される。ヨーロッパの、少なくともイタリア絵画とは、根本的に一線を画している。ナボコフのロリータが頭を過ぎった。
6月X日 23:50 クラスノヤルスクホテル
ガイドの女性と通訳の妙齢と連れ立って、街を歩く。ソ連時代のアパートは寂しい感じ。元共産圏を訪ねたのは初めてで驚くことは多い。街を走るバスは、一番古いものがロシア製、それから韓国製、新しいものはドイツ製の払い下げ。白と水色の教会の前で、ガイドの女性は、ここが中心の教会です、とだけいって通り過ぎようとしたが、正教会をどうしても訪れたくて中に入れてもらう。思いもかけないほど低い天井で、全体的に暗くて神秘的だ。鈍い金色に輝くイコンが所狭しと並んでいて、あちらこちらのロウソクの光が美しい。天井が高く広々として、さんさんと光が差しこむ、ローマ・カトリックのイメージとはかけ離れている。女性は揃ってみな頭にスカーフを巻いている。信者たちは熱心に祈っていて、ふと頭をあげてため息をもらしつつイコンを見つめる眼差しの情熱には、当惑すらおぼえた。
ガイドの女性は、ここに日本人抑留地だったことは一切触れない。レーニンがクラスノヤルスクに流刑されたため、レーニンに纏わる史跡は多い。
6月X日16:50 クラスノヤルスク・フィルハーモニーホール
フィルハーモニーホールの練習室で、ソプラノのEを待っている。練習室には巨大なバラライカが2本立てかけてあり、小型のバラライカケースには古くなった譜面台が入っている。汗が噴き出すほど暑い。窓のすぐそばに見えるエニセイ川のほとりに旧レーニン博物館があり、現在は美術館だ。そのエニセイ川を眺めながら、もうすぐ本格的再稼動になる大飯原発についてぼんやり思う。ここに来る前にクラスノヤルスクという街の名前は、地図には載らなかった秘密都市クラスノヤルスク26の軍用核施設と、橋本=エリツィンのクラスノヤルスク会談で耳にしたくらいだった。93年の核燃料再処理施設爆発事故、いわゆるトムスク事故があったのは、ここから600キロ近く離れた、クラスノヤルスク州に隣接するトムスク州トムスク7だった。
いつも離れず着いている通訳の妙齢に言わせれば、レーニンもスターリンもみな嫌いなのに、この街がレーニンにあやかろうとするのは奇妙だという。ゴルバチョフもエリツィンも彼女ら若い世代にとって全く無関係の存在のようだ。そんな時代は終わったが、ホテルから一人で出掛けてはいけないと繰り返し念を押される。彼女のボーイフレンドも演奏会に来ると聞いたので紹介してねと言うと、「それは駄目です。わたしは常に杉山さんと一緒にいます。これはわたしの仕事です」とすげなく断られる。
日本人抑留者記念墓地にでかけて手を合わせたいが、墓地は駅のあちら側にある。フェスティヴァルの最大限の好意は身にしみていて記念墓地訪問は少し切出しづらいが、あちらは案外気にもとめないかもしれない。どこかで時間を見つけて出掛けられれば良いのだが、今日は練習のあと演奏会に4つも出席しなければならないそうだし、明日の夜はホテル着は夜半過ぎ2時と聞き冗談かと思ったほど。
街並みを眺めていると、もしかすると当時日本人が作ったものも混じっているのかも知れないと思う。韓国や中国の人の裡にくすぶり続ける蟠りの片鱗を、少しだけ垣間見た気がした。
67
歌手としてもっとも有力なのは樹齢二世紀のカクタスだった
月が南中するたびに青い歯を見せるのにセニョーラは気づく
レゴのブロックを32個組み合わせて霊のための祭壇を作った
スーツのだぶつきがギャングのようで神父が焦げた眉をひそめる
集団を群れから解放するために国境と雨雲が必要だった
蟻たちは神学を欲しがって蜜蜂に交換条件を提示する
欲望とミルクを比べると倒れるのはいつも日時計だった
落雷を飼い馴らそうとクローバーで餌付けを試みる
ふたたび経済理論を学ぶために羊飼いはひそかに出国した
丘がふらふらと夜市をさまようので景気が破滅する
岩陰に魚を拾いにゆくとどれも焦げたいるかばかりだった
ときどき海が見えるたび塩の節約が議題になる
本のページをマッチで燃やすと文字は蛍光色で発光した
茹で卵は地球ゴマの回転で自由を表現する
火山が「私はきみよりも永続的だ」とヒマワリにむかって自慢した
ひまわりはたちまち百万本に増えて火山の麓を包囲する
68
貧血を優先して庭園がイギリス式迷路に作り替えられた
女王は揮発性の飛行機を使って月と金星の往復を試みる
燕の飛跡が占いに用いられる古代的な慣習があった
整列した樹木は遊びとして倒立と屈伸をくりかえす
ちくちくと皮膚を刺すのはアルパカの悪戯だった
未舗装の道が泥のように流れはじめるのをみんなで待っている
爆弾という言葉が低気圧に初めて応用された
競走馬が競馬の是非を美学的に議論し始める
「話を聞かれているときだけ声変わりするみたい」と小鳥がささやいた
村がアイスクリームのように溶けて地面がべたべたする
「雲の白が純白ならおれの心は何だ」と白熊が嘆いた
干潟の蟹の穴から永続的なシャボン玉が生まれている
白い崖よりも希望に近いのは柱状列石しかなかった
平野の空の一面がアスペラートゥスという名の雲に覆われる
Hail Maryよりも早くhailが急襲した
レタスとA菜のどちらも祖母は加熱してから食べる
69
くりかえし訪れる夢は万葉仮名で書かれていた
反復が赤道のように肌に皺を刻む
Sundanceとは太陽そのものの歩行に過ぎなかった
もぐらの人道的配慮は地下通路を封鎖させる
ガラス玉を丁寧に磨くと闘牛士のための義眼となった
回遊という性格により魚群が象を前世に追いやる
噴水はその姿よりもむしろ音響装置として機能した
年代の観測に年輪と砂時計が併用される
出漁の直前に二枚の板で小舟が設計された
トウモロコシの皮を画布として100号の作品が描かれる
干したトビウオのように身を殺がれつつやはり生きていた
城から北から城から南へと遠隔的に存在する
指先から蛇が出てゆき背骨にカクタスのような棘が生えた
洞窟の壁画に直接かつての野牛を埋めこむ夜がある
Reality TVをはめこむことによって現実は流れ星に近づいた
すべての海のエッジで存在とムネモシュネーがアネモネのように躍る
70
祖母の粗末な家は実際に鯨塚の真横にあった
砂まじりの米がランチボックスを光でみたす
瞼で炎が燃え猫の目が金星のように笑った
色彩とかたちにはどうしても等価交換が想像できない
「鳥」という鳥の不在がカモノハシの独立宣言だった
蝙蝠傘をひらいて地面の上昇に対抗する
風が蜘蛛を大量に飛ばすので合金が沸点に達した
トルティーヤをドレスのように着て彼女はくるぶしを回す
大広間の暗さに比べて玄関は氷山のように明るかった
傷ついた燕の傷を犬がやさしく舐めている
Porcupineは知っていてもcoatiは見たことがなかった
洞窟絵画に描かれるスラップスティックのように神妙に生きている
祖母は身長135センチで105歳まで生きた
フロリダを四十日かけて縦断する計画を立てている
ぼくの犬はみずから毛布にくるまる技を覚えた
人さし指と中指をそろえて架空の礫を飛ばせ
71
ブラスバンドが踊りながら海溝へと落ちていった
煉瓦とパスタの粒状性はそれぞれに離合集散をくりかえす
白い石膏の砂漠が満月にみたされた海になった
夜の中でブーゲンヴィリアが絵はがきのように揺れている
知識の代価としてきつねが木の葉をさしだした
とれなくなった指環が祈祷と羨望の対象になる
スズメバチが準備した効果音がロケットを発射させた
サッカーのゴールは写生よりも遠い風景に届く
魚たちの行列が巡礼への参加を希望した
波間にときどき屑鉄が浮かんでいる
窓に鐘楼を描くとやかましく鳴り出した
美しさと鏡とは別の周期表に属している
庭で無くしたサンダルにはノスタルジアと書かれていた
鹿よりも猪よりも四肢の進化を期待する
目の高さで凧をあげるのは伝統的なフラの動作だった
だが伝統とマグマは海岸のテーブル上で噴火をくりかえす
72
線路の音がハンナ・モンタナに世界市民主義を自覚させた
個々の生の破壊により生命の連続的広大さにめざめる
きみの心から人口流出がつづき過疎化が進行した
おれはおれとしてひとつのbutteを形成する
古い本を書き写すことをやっとボノボが覚えてくれた
民族博物館は多数の干し首を無垢の軍勢として所蔵する
太陽をめぐる一神教はそれ以外のエネルギーを断固として拒絶した
ぼくの犬が「うるさいよ」と耳をふさいで寝ている
雲の底から雲が湧き出したちまち夜のように暗くなった
ハープシコードが勝手に鳴ってアフリカの旋律を叩き出す
極東シベリアの町でも小学生の喫煙が習慣化した
マグネシウムの粉をまぶしてかれらを驚かしてやりたい
神はかたちがないから神であり物理的にはまるで無力だった
ひとひらの雪の中に海があるとしてすべての雪はいま潜在している
きぬいとがきれることなくどこまでもつづいていた
朗読が生物学的に禁じられてボノボが激しく怒っている
「きまぐれ飛行船」は、1974年3月から1986年9月まで、片岡義男さんが13年間パーソナリティーを務めたFM東京のラジオ番組だ。毎週月曜日の深夜1時から3時まで。番組スポンサーは角川書店1社のみで、片岡さんによれば「CMを取り払うことが可能で、そうすると1時間57分ほどを、番組そのもののために使うことが出来た」という事だった。
片岡さんが作家としてデビューした『野生時代』が創刊され、片岡さんを”売り出す”ために角川春樹氏が企画したのがこのラジオ番組だった。ラジオと並走するように、赤い背表紙の角川文庫が次々と書店に並んだ。ラジオの最終回で片岡さんが言っているように、13年間というのは、高校生でラジオを聴き始めた人が大学生になり、社会人になり、結婚して子どもが生まれるという長さを持った時間だ。
私は高校生だったある日、新聞の番組欄できまぐれ飛行船の「ビートルズ特集」を見て、初めて片岡さんのラジオ番組があることを知った。ほとんど最終回に近い頃にやっと追いつくことができて、数えるくらいしか聞くことができなかったのだけれど、忘れることができない番組となった。深夜1時に、静かに流れていた番組に、ファンは多い。この珠玉のラジオ番組についての覚書を残しておきたくて、今、小さな冊子を作っている。
13年間交代することなくディレクターを務めたのは、柘植有子さんと佐野和子さん。交代することなく、2人の女性が担当したというところが、なんだか片岡さんらしいとうれしくなってしまう。
柘植有子さんにお会いして、当時の事を少しずつ聞いている。柘植さんは片岡さんと同い年。柘植さん自身も「ユア・ヒットパレード」というラジオ番組が大好きだったという。ラジオドラマが作りたくて文化放送に入って、7年半務めた後、フリーになって「きまぐれ飛行船」のディレクターを担当することになった。
番組については、ディレクターが一番覚えているのではないかと思ったが、収録中は、時間内に入るのか、放送禁止になるような事を話していないか(田中小実昌さんがゲストの時などは新宿ゴールデン街の話になったりするので)その後の編集のことが気になって、ゲストの話をじっくり聞いている余裕などなかったそうだ。
「FMfan」のバックナンバーで、オンエアされた曲や、どんなゲストが来たのかを知ることができる。番組の宣伝として、掛ける予定の何曲かと特集のテーマを事前に提出していたのだという。オンエアのリストを見ながら、具体的な話を聞いていく。「ラジオ番組で落語のレコードを掛けるというのは珍しいことでした。志ん朝から、お礼の電話が入ったことがありました。」そんなエピソードが聞けた時には本当ににっこりしてしまう。
13年間いっしょにラジオ番組をつくり続けていながら、柘植さんは片岡さんのプライベートの事をほとんど知らない。片岡さんが、なぜあんなに洋盤(輸入レコード)を持っていたのか、片岡さんのおいたちに立ち入って聞くという事もなかったようだ。そんな事ひとつとっても、とても良いなと思ってしまうのだ。
あ、すみません。満月バー行けませんでした。なにせ、ドクターストップで禁酒状態なのです。お酒好きなのになあ。いろいろなお酒をちょびちょびっと味わうのが好きなんですが、でも、当分はお預け状態です。
さて、6月になって1年半ぶりにウチの植木が帰って来ました。家の改築で、がばっと土地を削ってよう壁をやり直した関係で植木の置き場がなくなり、ほんの一部だけ植木屋さんに避難していました。昨年の正月に引越しし、人間はその夏に戻ったのですがさすがに猛暑に植物を戻すわけに行かず、その後、造園をお願いしてずっと待っていたのがようやく終了した次第です。ようやく、殺風景な庭の風景が一気に落ち着きました。
いやはや、お願いするも梨のつぶてで、一時ははどうなるかと思いましたが、梅雨に入って戻して頂きました。良く取れば、タイミングを見計らっていたんでしょうね。結局、預けていて無事に戻れたのがボケとモクレン、それにドウダンツツジ。特にボケとモクレンは母の実家から移したものなのでもう70〜80年くらい経っています。
新しく追加した木は大きいものだけで、エゴノキ、アオハダ、それにカツラと雑木林の住人ばかり。それにズミとアセビを加えて、暖温帯〜温帯にかけて生育している木ばかりにしました。要するに、ウチの近所にもともと生えているような木を選んだわけです。基本的には手間いらずで、すぐに根付いてくれることを期待しています。まあ、低い植物も似たようなものなのですが、草の話はまたそのうち、おいおいと。そうそう、むかしむかしに携わった落葉樹の冬芽図鑑を植木屋さんに差し上げたところ、とても喜んでいただきました。
ところで、植木屋さん、今度は費用の請求が来ないんですが。。。
ルスマン(1926〜1990)はソロ(スラカルタ)にあるスリウェダリ劇場(ワヤン・オランという舞踊劇を上演する劇場)のスター舞踊家で、ガトコチョを当たり役とする。ちなみに、ルスマン全盛期のスリウェダリ劇場は、毎晩の公演が満員になるという黄金期だった。列伝(1)、(2)で取り上げてきた人達が舞踊も振付も手掛けるのに対して、ルスマンは舞踊だけ、それもガトコチョ一本である。昔の踊り手は、その人のキャラクターと一致した役柄1つを極め、今のようにいろんな舞踊を踊ることはしなかったという。しかし、そういうタイプの舞踊家は、学校での芸術教育全盛の現在では、もう出現しないような気がする。
ルスマンの奥さんもスリウェダリ劇場の踊り手で、ダルシという。彼女はスリカンディが当たり役だが、もちろん、ルスマンと組んで踊る「ガトコチョとプルギウォ」は人気演目だ。これはガトコチョがプルギウォに恋して追いかけまわす舞踊で、結婚式でもよく上演される場面。そのダルシさんとは、実はその昔(1996年末)、スリウェダリ劇場の前座でガンビョンを踊ったときに、楽屋で会ったことがある。その娘(といっても、もう定年前くらいの年齢)がインドネシア国立芸大(ISI)ソロ校で舞踊をおしえていて、ルスマンについて修士論文を書いている。
ルスマンはスカルノ大統領に気に入られ、大統領官邸でも何度も踊り、大統領の芸術使節団にしばしば選ばれている。ルスマンがスカルノの前で最初に踊ったのは、1948年7月、ジョグジャカルタでのことらしい。当時、インドネシアは独立戦争中で、首都がジョグジャカルタに移されていた時だった。1961年、日本に初めてインドネシアから大統領芸術使節団が来て、そのときにルスマンも来日している。この公演にはインドネシア各地から踊り手が集められていて、美女が多いにも関わらず、ルスマンが公演ポスターに採用されているから、やはり別格のスターだったのだろう。この公演に出演したソロの踊り手(私の舞踊の師匠の義妹に当たる)も、スターと一緒に出演したというのが嬉しかったらしい。芸術使節団に参加した他地域からの踊り手たちのインタビューを聞いても(これはリンドセイという研究者に見せてもらった)、ルスマンの舞踊はすごかったという話が多い。
ルスマンの魅力は、まずはその朗々として艶のある声にある。ルスマンの歌声はロカナンタ社のカセット(ACD-011)の「ガトコチョ・ガンドロン」に収録されている。このガトコチョの舞踊には途中で歌うシーンがあって、切々とプルギウォへの恋心を歌いあげるから、ここで下手だとだめなのである。ただし舞踊に関しては、もちろん上手くスターのオーラもあるのだが、宮廷貴族の美意識には合わないところがあったようである。ルスマンはサブタンと言われるポーズなどで、宮廷舞踊の通常では右足を上げたら左手を上げて左右の均衡を取るところを、右足、右手を同時に上げるようなポーズを取るため、「犬が片足を上げて放尿するポーズ」に見えると言って、貴族たちは嫌ったものらしい。
荘司和子訳
「アメリカのギターはめちゃ高いなあ」と、わたしはこぼす。
ふとそのとき、ブッシュ大統領の顔が浮かんできた。あいつは嫌いだ。現世で同時代になるような因縁でもあったものか。もしもアイ ヘート ユー、ブッシュと書いたシャツがあれば買ってきて、3日3晩脱がずに着続けてやるのだが。
駅は人の往来で込み合っているが、昔と同じように泰然とそこにある。10年前わたしの友人のひとりがヨーレイ(浄霊)教(訳者:オーム真理教)にはまっている信徒の前に立ったものだ。ウィラサックだ。催眠にかけられたかのような表情をして立っていた。一方その若者はといえば、奇妙ないでたちで、日本の時代物映画で見たことあるような竹で編んだ平べったい帽子をかぶっている。何か日本語で呪文をつぶやきながら掌をウィラサク向けてこころを鎮めようとしているかのようだ。
東京のような肥大した社会では一風変わったことに次々と出会う。定住する家もなくてなんだかごちゃごちゃと物を抱えて歩き、公園のベンチに身を横たえる者たちがいる。こういった連中の過去には興味深いものがある。聞いたところではイデオロギーとか主義主張を持っていたタイプの者がいるという。かつては教師講師の類だったかもしれない。それがついには何にも拘泥されない生活を選ぶことになった。わたしもかつてそういうことを考えたものだ。
タイでも髪は伸びてぼさぼさ、いろいろなものを抱え込んで歩くアホとか化け物と呼ばれる路傍の旅人、苦しみも幸せもない人、について、わたしは考えたことがある。何か深いところで気づかせてくれるものがあるのではないか、と。彼らの空こそが涅槃なのではないかと。
けれどこの国のホームレスはタイのいろいろなものを抱え込んだアホというのとは違う。彼らは自分の世界が多々あるかのように黙して語らない。周囲に人がいないかのようにゆっくりと歩き、話さない、努力しない、交流もしない。いかんせん話しかけるのが難しいのだ。
カッ、カッ、カッ。
近くから、12チャンネルに録音された1人の人間の足音が聞こえて来て、まだもう少し寝ていたいと思いながらも、目が覚めた。彼女を救わなくては・・・
カッ、カッ、カカッ・・・カカカッ、カッ・・・・カ・・・
あれ? どこだ?
そうか、私は電車に乗ったんだ。渋谷での仕事を終えて秩父行きの終電にギリギリ間に合ったのだ。
1両目には運転室があり、そこには車掌がいるのだが、突然運転室の扉が開き、車掌は12人の作業員を運転ルームに入れ始めた。
作業員達は運転室から外へ出るための扉を開けて外(トンネル内)に下り始めた。
「そうか、もう電車が通らないこの時間から作業員達は仕事を始めるんだな。しかしこの夜の暗いトンネルで、それもこんな真夜中から仕事なんて大変だ・・・。」
とは言えトンネルはいつでも暗いし、湿度がある。
いつも夜みたいだ。
・心の中ではポトシ銀山で死んでいった、あまりにたくさんの奴隷たちの事を想っていた。
ふと気がつくと目の前の通路に、白い液体がダラッとこぼれていた。
「うわっ!何だこれは、汚いじゃないか、きっと私が寝ているうちに誰かが牛乳をこぼしていったのだろう。困ったなあ・・。」
牛乳はエアコンによって暖められた車内の空気と混じったせいか、少し粘り気を出して、足で踏むとベタベタと言う感触がする。
12人の作業員達は一列になり、順番にその扉から電車の外のトンネルへと下りて行った。
作業が始まるのだ。(一体何の作業なのかは一般の乗客には知る由もなかった。)
アナウンスが入った。
「・・・乗客の皆様、電車は停車しておりますが、まもなく発射致しますのでご注意下さい。」
停車していたせいなのか、電車は一度少しだけ後ろに動いた後に前へ向かって動き出した。 やけにゆっくりと・・・。
「ああ、トンネルと言うのは暗くて嫌だなあ、早く外に出たい。」
仕事で疲れた体を動かしながら通路の牛乳に目をやると、牛乳が固まりのようになっていたので自分の目を疑った。
それはどこかの海の中にぼつんと浮かぶヨーグルトのようだった。
「ああ、きっと疲れているんだ。とにかく早くこのトンネルの外へ出たい!
それに、一体何なんだこの牛乳は。気持ちが悪い上に恐くなってきた。」
「何だこれは、こんなものは見た事がない・・・。」
カツカツ、カツ。カツカツ。足音が聞こえる。
トントン、トン。トントン。と何かを叩く音と聞こえるはずのない笑い声が確かに聞こえる。
電車は次第に速度を上げて、出口へと向かった。
私はその時の光景を今でもはっきりと、明確に記憶している。
しかしまだ誰にもそれを喋った事がない。恐怖と、喋っても信じてもらえないのではないか、と言う不安からだ。
電車はそのまま出口へと近づき、やっとの事でトンネルを出るその瞬間、
通路にぶちまけられていた牛乳が真っ黒な牛になったのだ!
牛になったと言うのが正しいのか、牛に戻ったと言うのが正しいのか、言い方はともかくとして・・・とにかく真っ黒な牛になっていた。
「ああ、あの白い牛乳が、とうとう黒い牛になった・・・。」
トンネルを出た瞬間に牛の姿はどこかへ消えて行った。
(牛はどこかへ生まれていった。)
一方、その電車はトンネルの外に出たが、私はまだ電車の中で出口を見つけながら移動している。
いや、もうすでに死んでいるのかもしれなくて、ただそれに気がついてないだけなのかもしれない。
とにかく、わからない。
どこまで遠くへ歩いても、その足音や血液が体内を循環し続けるごく短い時間内において、歩く行為は自らの記憶の種子へと回帰してゆく。
牛は牛の足音の中を、私は自分の靴の足音やカバンの夢の中で異性を探し彷徨って電車の通路にこぼれている牛乳ように・・・
誰もいない夜の電車で座って(こぼれて)いた。
ブリオッシュという名をつけられた仔犬を飼いはじめたのに、高原は一度もその名を呼んだことがなかった。チビだのシロだの明らかに見た目でわかるような名前をその時々で呼んでいるうちに、その仔犬は高原が「おい、お前」と声をかけた時にだけ、高原のほうを振り返るようになった。「おい」に反応しているのか、「お前」に反応しているのか。前半分だけ呼んでみたり後半分だけ呼んでみたのだが、仔犬は見事なほどに反応しない。そして、少し諦めかけた高原が「おい、お前はなあ…」とつぶやくと、その瞬間に仔犬は小さくのどを鳴らして高原を振り返ったのだった。
その日から、といってもほんの三日ほどしかたたないのだが、高原は仔犬の名を呼ぶことをやめて、まるで人に話しかけるかのように「おい、お前」と仔犬に呼びかけるようになったのだった。
相変わらず、この犬を我が家へ放り込んでいった娘と孫は週に一度は様子を見にやってきて、身勝手にかわいがり、一緒なって遊ぶと帰っていく。いま、この犬を「ブリオッシュ!」と正式な名前で呼ぶのは幼稚園に通う孫だけだ。すっかり妻に似てしまった娘などは最初の二文字だけを楽しそうに「ブリちゃん」と呼んで、あとは省略してしまう。妻にいたっては高原を呼ぶのと同じように犬に向かって「あなた」と言う始末だ。おかげで妻が高原を「ねえ、あなた」と呼ぶと仔犬も一緒に駆け寄ってくるようになった。そして、「あなたはどうしていつもそうなの」と妻が仔犬を叱っていると、なぜだか高原も同じように所在なげにしていたりするのである。
そんな高原の様子を面白がって、
「父さんと母さんは、ブリちゃんを真ん中に置いて、うまく会話してるのよね」
と娘は言う。
確かにそう言われてみれば、光景を見ずに言葉のやり取りだけを聞いていると「おい、お前」「ねえ、あなた」と少し枯れた夫婦の会話だけが思い起こされるだろう。
今日も高原は仔犬を連れて散歩に出る。ときどき前を歩く仔犬の背中が右へ左へ、上へ下へと揺れるのを眺めながら「生きているということは揺れるということなのか」などと考えてしまい、その仔犬の背中に「なあ、お前」と声に出して呼びかけてしまう。すると、いかにも若々しくて未発達な、そしてだからこそ立ちのぼるような血の熱さを伝えていた背中の躍動が、高原を圧倒するように大きく見え始めた。高原はその揺れの熱さに呼応するかのように気持ちをゆさぶられ歩くこともままならなくなり道ばたの電柱の陰にそっと寄り添う。飼い主が自分についてきていないことをリード越しに察すると、仔犬は立ち止まり高原を振り返る。その刹那の大儀そうな迷惑そうな表情を見ていると、高原はいつか近いうち何かに引きずられるように、この犬を「ブリオッシュ」という名前で呼ぶことになるのだろうなと思い知らされるのだった。
蘂をめぐり 運命の花瓣よ
一萼のうえに並ぶ 一枚
たてまつる 水を受けよ
音無くて また一瓣を抜けば
悲鳴を吸い上げる 受けよ
地上の盥 すべてひらけ
かなだらいより 瓜子
這い出よ 包め芯
つよい鞭毛が 落花よりも
はやい足で あの人形を救え
その人形を拾え 客神よ
(なお一言――〈子供たちを見送った後の屋上に立つと、決壊した堤防から昇る朝日に照らされ、変わり果てた荒浜が見えた。「壊滅」とはこういうことなのだと知った〉と、多田智恵子先生の手記である。給食用の野菜を納めてくれた方、米作り、シジミ獲りを教えてくれた方、酷暑の日も、強風の日も、路上で子供たちの安全を見守ってくれた方。学校がお世話になった方々……(『世界』別冊〈二〇一二・一〉より)。「壊滅」という言葉を多田の手記から記憶しよう。念願の六年生の担任を「終え」て、離任式もなく荒浜小学校を去る一教諭の手記から、宗教人類学者山形孝夫は「実存的で真摯(しんし)」という、強い印象を受け取ったという。この「実存」そして「真摯」という語も拾っておこう。)
意識が薄れると自意識はなく感覚だけがある。視野が暗く遠くなり耳は聞こえているが音は現実のものではないかもしれない。雪のなかで転んで気がつくと知らない店先に座っていた。次の瞬間にはだれかの家で寝かされている。白い天井が回り薄暗い空間に透明な壁が立ち上がり膨らんだり縮んだりする。
昼間窓から吹き込む風が紙を床にばらまく。拾おうとして足が滑り気がつくと椅子に座っている。だれかが話しかけているが声が聞こえにくい。近所の医者に手をひかれていく。家に帰って寝かされ次の朝は熱もなかった。
熱が下がらないときは医者に行ったが階段から降りられない。タクシーに乗せられ眼をあけると病室で2週間経っているようだ。点滴を6時間おきに換えられて天井を見ていると夜が来て朝になりまた夜になる。たらいの湯で足の裏をこすられているとき身体があるという感覚が起こり昼がありまた夜があった。
指が何本かしびれている。触るものの表面が膜に包まれている。
病気は周期的に来ると感じる根拠はあるのか。予想外の偶然を説明しようとしているだけか。身体に弱い部分があるのは強い部分がありバランスをとるからだろう。変化するアンバランスと言ったほうがいいかもしれない。健康が安定した状態という幻想がある。健康も病気も変化するバランスの静止画像だとすれば自分の力で維持しさらに身体を鍛えればバランスの変動を妨げてやがて全体の崩壊速度が加速することもありえないことではない。
バラバラな要素を組み合わせて全体を構成する分析と統合の方法はその全体を一つの原理で説明し操作できるという世界支配の信仰だったのか。全体は幻想でこの樹はあの樹と似ているがすこしちがう。樹ということばは樹ではなく似ているという感じを言い表しているだけだとはだれも言わないがそれを知らなければこの樹からあの樹に歩いては行かれないだろう。
あの樹がこの樹のクローンではなくちがいがあり間には距離がありそれが森という空間になるのではなくこの樹がある前に森はそこにあったと感じることもなく言うこともなく森が見えそのなかを歩くこともできるのはなぜかとだれも言わない。
同じものが二つとない世界のなかにいてふしぎとは思わず毎日がすぎていく。この樹を見てあの樹を見るから空間があり時間もあり朝が来て夜になりまた朝が来る。
日常の音楽は音楽をする日常ではなく日常の音をもちこんだ音楽でもないだろう。この朝があの朝とはちがいそれでも朝であるように連続と断絶の間の薄い膜のなかにすべての音が星座であり偶然の飛沫であるような音楽。