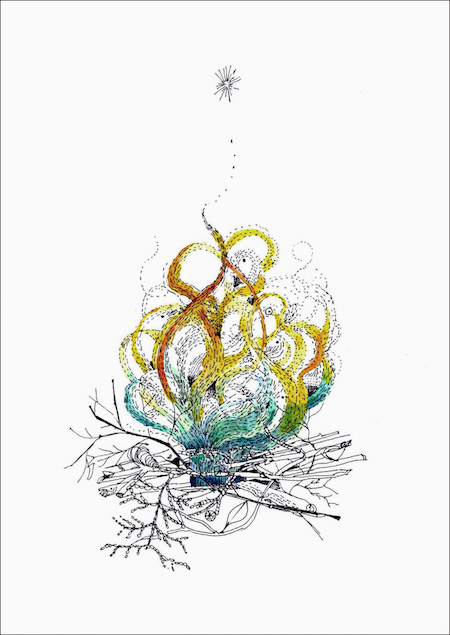谷川俊太郎*李政美*高橋悠治コンサート
ー暮らしの中に平和のたねを蓄えるー
2019年1月13日(日)
【開場】13:30【開演】14:00
【会場】東京・両国シアターΧ
【料金3,000円(席は埋まりつつあります)
主催 憲法いいね!の会 kenpoiine@uni-f3ctory.jp
*
空気のように
少年時代
戦争の罪深さと
憲法のかがやきを知った
大人になるにしたがって
憲法はいつのまにか
空気のような存在になった
あることを意識などしない
あって当りまえ
それでいいだろう
憲法が暗雲のように
ぼくたちの頭上に重くのしかかっては
困る
憲法は権力者の上にのしかかって
暴走に歯止めをかけるものだが
勝手な解釈を押し通して
今や憲法も虫食いだらけ
さらに大きく作り替え
ぼくたちの上に
重しを
のせようとしている
憲法が在ったって
私たちは疎外されている
憲法は私たちを守ってくれない
でもそれは、
憲法が悪いわけではない
憲法を疎んじる人たちと向き合い
声を上げることをあきらめない
不断の努力(第12条)が
求められている
象徴的な場所が沖縄だ
権力者に都合のいいように
一字たりとも
変えさせない
空気のように
日々の暮らしの
かたわらに
あることさえ意識などしない
あって当たりまえ
このままで
いい
*
ひろがりを求めて
悠治さんに相談して
僕にとって高橋悠治さんは、最初から、著名なピアニストとしてではなく、水牛楽団の高橋悠治さん(以後、悠治さん)として出会った。
水牛楽団は、タイの抵抗歌を日本に紹介するために、1978年に結成された。その後、タイの歌にとどまらず、ポーランドの禁止された歌を歌ったた。その後、タイの歌にとどまらず、ポーランドの禁止された歌を歌ったり、「カオル(東山薫)の歌」や「よね(小泉よね)の歌」、「管制塔の歌」など、三里塚の歌も作った。
僕が悠治さんとパートナーの八巻美恵さん(以後、美恵さん)と出会ったのは、いつだったのか正確には思い出せないが、1978年頃、東京の三里塚関係の集会の控え室で、前田俊彦さんから紹介された様な気がする。それから、何度か水牛楽団の演奏会を見させてもらった。
水牛楽団が、日本に紹介したタイの抵抗歌の代表的な曲は「人と水牛」で、カラワン楽団の歌だ。カラワン楽団は、1974年に4人の若者によって結成され、タイの民主化運動の象徴的な存在となった。1976年のクーデターでジャングルに逃れたが、1983年、バンコクに戻り、カラワンは再結成された。
カラワンは、水牛楽団の招きで1983年に来日し、コンサートツアーにのぞんだ。その年に三里塚の反対同盟は分裂したが、分裂後のぼくが属していた熱田派の集会に、悠治さんや美恵さんがカラワンを誘ってくれて、全国集会の壇上で「人と水牛」や「カラワンの歌」などを披露してくれた。リーダーのスラチャイの話によると、機動隊も拍手していたと言う。
その後の経過は省略するが、1984年の秋から冬にかけて、3ヶ月間、ぼくは「カラワン農村漁村キャラバン」と銘打って、北は秋田から南は石垣島まで、都市ではなく地方の36カ所を車で移動し、カラワンの生の歌を届けた。つきあってくれたのは、カラワンのスラチャイ・ジャンティマトンとモンコン・ウトックの2人だ。よくぞ3ヶ月間もつきあってくれたと思う。そしてこの旅に欠かせなかったのは友人で社会学者のロバート・リケットさん、通訳兼運転手としてツアーを共にしてくれた。この旅の計画の相談にのってくれたのは美恵さんだ。タイにいるスラチャイ達への打診や航空機の手配、ツアーが休みの時は、悠治さんと美恵さんの家にカラワンの2人が滞在した。
この「農村漁村キャラバン」が動きだすこ頃、水牛楽団は活動を休止していた。というか、5年間も「たたかう音楽」に情熱を注いだのだ。そして終止符を打った。ぼくも、このキャラバンから5年後、「闘いという言葉を/忘れようと/思う」という詩を書いた。
悠治さんは1978年に『たたかう音楽』(晶文社)を出した。ぼくも構成員だった三里塚ワンパックグループも1981年に『たたかう野菜たち』(現代書館)という本を出した。ぼくも悠治さんも、場所は違っていても「たたかうこと」を中心にして生きた時代があった。そしてその後、そのことを生きるという言葉でくるんで(ぼくなりの言い方だが)生活してきた。
いつのことだったか忘れてしまったが、ぼくは悠治さんに「いつか一緒に仕事ができれば」と話したことがあった。悠治さんは「そうだね、いつか」と言ってくれた。そのことを悠治さんは覚えていらっしゃるかどうか分からないが、その言葉を頼りに、ぼくは悠治さんに電話をした。
悠治さんと会うのは久しぶりだった。僕より10歳上、今年80歳になるのに、受ける印象は変わらず若々しかった。悠治さんと会う約束の時間の少し前まで、同じ場所で、憲法いいね!の会の相談会をしていた。3月3日に開催した「憲法いいね!憲法をたたえるつどい」の反省会と今後の取り組みについて話し合った。その中で、今後の取組みについて、ぼくはこんな提案をした。
「この会として、今まで3回の集会を開いて、どの会も、参加者からも評価され、僕たちも学ぶことが多かったけれど、これからどうするか、もう少しひろがりを求めるようなことを考えたい。70名前後の人々の参加を得て、どの会も成功した。しかし、憲法の問題に強い関心を抱いている人を集めてはいるけれど、それ以上のひろがりはない。それで次は、言葉で語る集会ではなく、コンサート風な千人規模の集まりを考えたいのだけれど、どうでしょうか」。
今から思えば、千人規模の集まりとは、大風呂敷を広げたものだと思うが、その時は勢いで、そう言ってしまった。そして、その時、出演者の候補として、ピアニストの高橋悠治さん、詩人の谷川俊太郎さんの名前を上げた。もう1人ミュージシャンの人は決められないでいた。ぼくの提案は、皆さんの大いなる賛意を得た。「実は、この後ここで、高橋悠治さんと合う約束をしていて、悠治さんに出演のお願いをしてみようと思っているんです」と打ち明けた。東京にたびたびは出てこれないので、出てきた機会を活用したかった。僕の提案がいいね!の会の皆さの同意を得られなければ、悠治さんに謝るしかなかっだが、ほっとした気持ちで、悠治さんを待つ席に座った。
悠治さんは1人でいらっしゃった。美恵さんと会うのも楽しみにしていたのだが、残念ながら、家を留守にできない事情があったとのこと。早速、本題に入らせてもらい、いいね!の会で提案した内容を話した。悠治さん家はずっと、循環農場の会員であって、憲法いいね!の会の大体のことをご存知だ。それどころか、ありがたいことに、悠治さんと美恵さんで運営しているウェブサイト『水牛のように』上で、「憲法肯定デモってどうだろう」などの文章やチラシを載せてくれていた。
悠治さんはぼくの相談に、「いいよ。ピアノさえあれば」と言ってくれて、それだけで感謝なのに、さらに「谷川さんとは5月に会う機会がある」と教えてくれ、また、歌い手については「在日コリアンのイ・ヂョンミ(李政美)がいいよ」と名前を上げてくれた。あまり日常的に歌を聴く習慣のないぼくは、失礼ながら、イ・ヂョンミさんのことを知らなかった。家に戻ってから、ネットで探して聞いてみると、美しい声と豊かな声量、そしていつもは気付かずに過ごしている胸の、奥の奥に届くものを感じた。
悠治さんのおかげで、こうしてコンサート風な集いの輪郭が見えて来た。いいね!の会の皆さんに、このことを報告し、谷川俊太郎さんとイ・ヂョンミさんに日程と場所は未定のまま、内諾をいただく方向で進めてみようということになった。規模は、一気に千人は冒険すぎるので、300人が入るホールを探そうと言うところに落ち着いた。
日本近代文学館主催の5月の『第93回声のライブラリー』に高橋悠治さんと谷川俊太郎さんの自作朗読会が予定されていることを知った。司会は詩人の伊藤比呂美さん、定員は80名と言うことで、これは谷川さんに直接会えるチャンスと思って申し込もうとした時には、すでに定員に達していた。少し落胆している時に、悠治さんからメールが届いた。こちら側の事情は知らないのに、そこにはこう書かれていた。「来られるなら 招待券を受付におきましょうか。
谷川俊太郎さんのこと
悠治さんの有難いお誘いで、「声のライブラリー」の関係者席に座ること出来た。開演の前に悠治さんを見かけたので、谷川さんにお会いしたいとお願いした。「そうだね。じゃあ、こっちに来て」と控え室に案内された。
悠治さんがドアを開けると、部屋の中央に20人ぐらいが囲めそうな大きなテーブルがあって、谷川さんは向かって右側の端の方に、Tシャツ姿で座っていらした。ぼくは若い時に一度、谷川さんの詩の朗読会に参加したことがある。その時も確か、谷川さんはTシャツ姿だった。
悠治さんがぼくのことを簡単に紹介してくれた。開演前の大事な時間なので、ぼくの方から手短かに自己紹介と憲法いいね!の会のこと、そして出演のお願いをすると「出演者が3人だと楽だね」とおっしゃって「このファックス番号に、集会の趣旨などを書いて送ってください」と言ってくれた。
悠治さんの自作の朗読は、劇作家、演出家の如月小春さんへの弔辞、作家、矢川澄子さんへの弔辞などを読まれた。矢川澄子さんはカラワンの「農村漁村キャラバン」の石垣島でのコンサートに同行してくれたのだが、キャラバンの最中のことなので、ゆっくりお話を伺うことは出来なかった。
谷川さんは現在86歳だが、姿も朗読の声も、その年齢を感じさせないものだった。詩の朗読の最後に「今日、憲法の話があったので」と前置きして『中央公論』2017年5月号「特集ー憲法の将来」に寄せた「不文律」と言う詩を読んでくれた。
「不文律」は是非、次のコンサート風の集いで読んで欲しいと思っている。その前半を紹介する。後半は当日のお楽しみに!
憲法は言葉だ 言葉に過ぎない
誰の言葉か? 国家の言葉だ
そこには我々日本人の言葉も入っているが
〈私〉の言葉は入っていない
私はこういう言葉では語らないからだ
憲法の言葉は上から降ってくる
下から湧いてこない
だから私の身につかない
だが憲法が言っていることを
私は日々の暮らしで行っていると思う
憲法の言葉が行いになるのではない
私の中には言葉のない行いがあるだけだ
そこが憲法の有史以来の古里だろう
私は実は国家というものが苦手だ
国家のおかげで生活しているのは確かだが
ぼくが、谷川さんに出演して欲しいと思ったのは、直感だ。悠治さんと谷川さん、2人の組み合わせは、憲法いいね!の会を始めてから時々、頭をもたげていた。
谷川さんに会う前に、全く直感だけでは申し訳ないと思ってあれこれ調べ「不文律」の存在を知った。その時は、それが文章なのか、詩なのか分からなかった。だが、不文律と言う言葉から、ぼくは1998年の朝日新聞に載った鶴見俊輔さんの談話の中の「私の憲法」を連想していた。
「私の憲法をもつこと。慣習法としての憲法で、人を殺したくない、平和であってほしいと願うなら、そのことを自分の憲法にし、心にとめておいたらいい」
憲法いいね!の会を始めた頃にこの言葉を見つけて、ぼくは随分救われた。理論の鎧をまとうことが嫌いなぼくにとって、この言葉から受けたものは大きい。
慣習法も不文律も同じような意味を持つ。法律が成文化される以前の社会の暮らしの中で、お互いに了解し守りあっていた決まりごとを指す。
市立図書館で「不文律」の詩を読み、憲法に対する接し方が鶴見さんも谷川さんも同じだと感じ、ぼくの直感が当たっていたと思った。自分で黙読した時より、会場で谷川さんの朗読を聴いた時の方が気持ちよく胸に響いてきた。谷川さんの朗読の力なのだろう。
その後何日かして、谷川さんから教えられたファックス番号に、講演依頼のお願いを送った。そうすると数日も置かずに谷川さんからファックスが送られてきた。
「お誘い有り難う。歳をとって体調が不安定になることもあるので、先々の約束をすることに不安はありますが、内諾という形でお受けします。(中略)わざわざ図書館で詩を探して読んでくれてありがとう」
「図書館で詩を探してくれて」とは、ぼくが「不文律」を図書館で見つけたと、講演依頼の文章に書いたことによる。わざわざそのことに配慮してくれて恐縮した。そして何よりも、内諾をいただいたことがありがたかった。
もう少し谷川さんのことを知ろうと調べていたら、『現代詩手帖』2015年9月号に対談が載っていて、その中でこう話していた。
『日本が戦争に向かって行っても、自分はあえて反戦詩も書かない。でもその代わりに「地上から戦争はなくならない」事を前提に「自分の中の戦争の芽を摘む詩」を書く』
戦禍の中で生きることを余儀なくされているイラク子どもたちの絵に、谷川さんが詩をつけた『おにいちゃん 死んじゃった イラクの子どもたちと せんそう』(2004年、教育画劇)という本がある。その本の存在とそのあとがきに書いた谷川さんの言葉を、憲法いいね!の会の仲間の人が教えてくれた。彼女は「やまゆり園事件追悼」の市民集会でこの詩に出会ったと言う。そして自分が働く保育園の「園だより」に載せた。その一部を紹介したい。
「戦争をひとのせいにしないで、じぶんのせいだと考えてみる。
ひとをにくんだり、さべつしたり、むりに言うことを聞かせようとしたり、
じぶんのこころに戦争につながる気持ちがないかどうか。
じぶんの気持ちと戦争はかんけいないと考えるかもしれないが、
それでは戦争はなくならない。
まずじぶんのこころのなかで戦争をなくすこと、
ぼくはそこから始めたいと思う」
「あえて反戦詩も書かない」との立場をとることで、より人の胸にとどく言葉が産み出される。「自分の中の戦争の芽を摘む詩」こそ、反戦詩に求められるものだと思うのだが「あえて」と言うところに、谷川さんの覚悟のようなものが感じられる。
鶴見俊輔さんが谷川さんのことをどう見ていたのか。「忘れることの中にそれがある」(『鶴見俊輔集』10巻、筑摩書房)という文章を見つけた。その中で「事件」という谷川さんの詩を引用している。
事件だ!
記者は報道する
評論家は分析する
一言居士は批判する
無関係な人は興奮する
すべての人が話題にする
だが死者だけは黙っているー
やがて一言居士は忘れる
評論家も記者も忘れる
すべての人が忘れる
事件を忘れる
死を忘れる
忘れることは事件にならない
そしてこう続ける。
「これは『政治』と特定されている活動が政治についてどんなに無力かを照らし出す。しかしこの詩は、政治に背を向けているとは言えない。では、どのようにしてこの人は政治に参画するのか」
「それは明日の新聞に出るような政治行動ではない。しかし、たゆみなく、ある方向に、歩みつづける1つの道は、ひらけてゆくはずだ。家庭の中にさえ、1つの道はある。そういう認識は、戦前の日本人の政治観にはふくまれていなかったし、戦後もどれだけふくまれているかわからない」
「家庭をつらぬいて流れ、町をつらぬいて流れ、私をつらぬいて流れる生命。それにそうて政治を見るという、気の長い視点が、この詩人にはある」
引用が長くなったけれど、ぼくがぼんやり感じていたものを、鶴見さんがその輪郭を描いてくれたので、つい頼ってしまった。
谷川さんは若かりしころ石原慎太郎、江藤淳、大江健三郎、寺山修司、浅利慶太、永六輔、黛敏郎、福田善之ら若手文化人らと「若い日本の会」を結成し60年安保に反対したと言われている。
高橋悠治さんも先に述べたように『水牛楽団』として日々舞台に立っていた。
お二人ともその後「新聞に出るような政治行動」からは離れ、独自の道を歩んで来られた。お二人とも「政治に背を向けている」わけではない。そこから教わることは多い。
『谷川俊太郎 李政美 高橋悠治 コンサート』のサブタイトルを「暮らしの中に平和のたねを蓄える」とした。谷川さんや李政美さん、高橋さんを迎えるのにふさわしい言葉、憲法いいね!の会がこのコンサートに込める思い、それを言い表した。
鶴見さんの言葉を再び借りるとすれば、日常の暮らしや生命にそうて「政治を見るという、気の長い視点」を持って、かつ、現実の政治の動きにも具体的に対応しながら歩を進めて行きたい。
李政美さんのこと
オフィシャルホームページ『李政美の世界』を開くと、その中に「李政美の世界を深める」というページがある。そこでは政美(ヂョンミ)さんを知るための3冊の本が紹介されている。ここでは『永六輔の芸人遊び』(小学館)をひもといて政美さんの世界を見つめてみたい。
政美さんは1958年、東京の葛飾区に生まれた。両親は2人とも済州島の出身で廃品回収業を生業にしていた。「私は、皆に可愛がられて育ちましたが、小学校にあがる頃には、リヤカーを引いて歩く長屋の人たちと道ばたで会うと、恥ずかしくて逃げ出すような女の子になっていました」と言う。
政美さんは必死に勉強して音大に進んだが、それは「長屋」から逃げ出し、「別の」自分になろうとしていたのだと振り返る。音大の入学前後、韓国の民主化に連帯する集会などで、誘われるままに韓国のプロテスト・ソングを歌い「在日のジョーン・バエズ」と呼ばれたりもしたが、本人はとても恥ずかしいと感じていたと言う。高橋悠治さんの水牛楽団と一緒に歌ったのもその頃だった。
音大でオペラを学んでいた時も、集会でプロテクト・ソングを歌っていた時も「どんなにきれいな声で、うまく歌えても」違和感とむなしさがあったと言う。それから自分の声、自分の歌をさがす歳月が流れる。
私生活では、結婚、出産、そして娘さんが3歳の時に離婚を経験し、夜は定時制の高校で「朝鮮語」の講師、昼間はゴンドラに乗ってビルの窓拭きの仕事に従事し「もう再び歌うことはないかもしれないと」思っていたと言う。
転機は、詩人の山尾三省さんとの出会い。三省さんが朗読してくれた「祈り」という詩に心を大きく動かされ、その詩を歌にして歌いたいと思ったことだ。
「そもそも歌の始まりは、人々の祈りだったんじゃないかと感じたんです。それなら私は、私自身の深い祈りを歌おうと」
「ありのままの自分を表してあげればいいんだよ」と三省さんに教えられたような気がすると政美さんは言う。そうすると、たくさんの歌が湧き出るように生まれたと言う。代表曲『京成線』もその頃生まれた歌。逃げ出したいと思っていた「長屋」こそ、自分のふるさとなんだと。そうして、こう語る。「異質なもの、役に立たないとされて蔑まれているものの中に、私の命の根っこ、歌の根っこはありました」
永六輔さんは政美さんのことを「僕が思う日本でもっとも美しい声の歌手」とこの本に書いた。たくさんの歌い手を知っている永さんがそう言うのだ。また、高橋悠治さんが「政美がいいよ」と推薦してくれて、このコンサ
ートは動き出した。
永さんも、悠治さんも触れたであろう、政美さんの歌の深いところにあるもの、政美さんが依って立つところは何なのか、どこなのか、それを知りたくて、この文章を書き始めた。
最初、悠治さんに勧められて『京成線』を聞いた時のこと。歌が終わったかと思われた時に「アリラン」の歌が流れてきて、ぼくは涙を止められなかった。京成線の走る葛飾「ここもまた ふるさと」と歌い、一呼吸置いて、「アリラン」の歌が流れたので、葛飾もふるさとなんだけれど、心の中のほんとうのふるさとは「アリラン」が流れる朝鮮半島なんだと、望郷の想いが込められていると感じられたからだった。しかし、それは、ぼくの勘違いだった。
政美さんの歌の根元にあるものは民族的なものではない。そもそも「アリラン」に歌われる峠は、伝説上のものでどこにも存在しない、架空の峠だと言う。
「国籍という峠、民族という峠、人の心の光と闇の間にある峠、この世の中のあらゆる峠を、軽やかに超えてゆく歌、聴き手の心をそこへといざなう歌、そんな歌を歌っていきたいなあ、と思います。私の『京成線』も、『アリラン峠』を越えて走っていく歌なのです」
政美さんを知るための3冊の本のうちの1つ『誰が平和を殺すのか』(佐高信著、七つ森書館)の中では、こう語っている。
「私は日本で生まれて国籍は一応韓国なんですけど、日本からも、韓国からも、どの国からも守られているという実感がない。ジョン・レノンが歌っているように、私もやっぱり国家なんかなくて良いと思うんですよ」
ジョン・レノンの『イマジン』は政美さんの持ち歌の1つとなっている。韓国で日本で、多くのファンを惹きつける政美さんの歌の魅力は、歌と歌声の深部にある、国家を越え政治を越えた、命の尊さ、命への感謝、命への祈りのようなものにあるのだろうと思った。