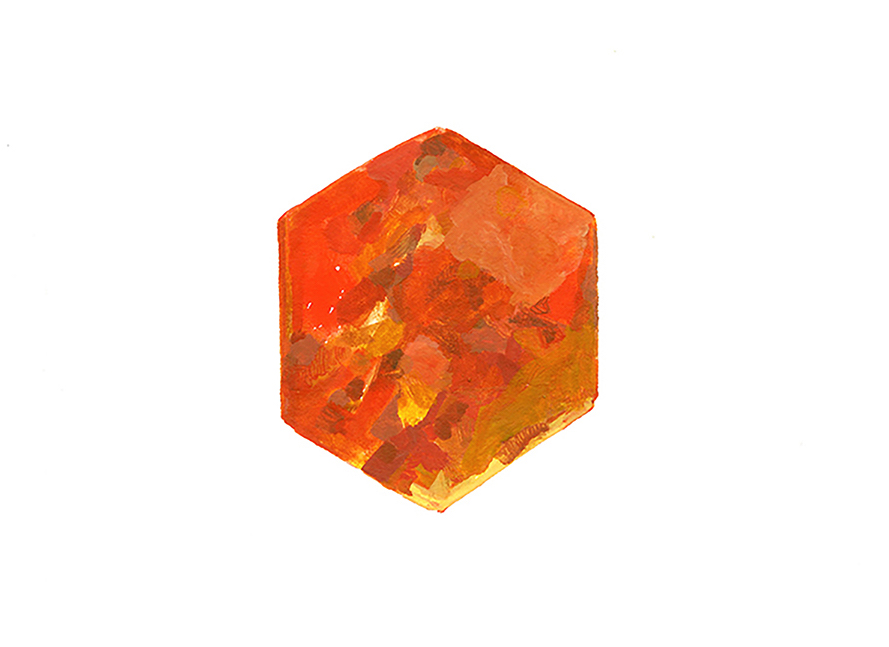カタロニアの独立宣言を東京で知り、かなりの衝撃を受けています。イギリスのEU脱退と同じか、それ以上に驚いていますし、絶対に回避してくれるに違いないと信じていたところもあります。今月はイタリアでも国民選挙があって、北部の自治権拡大を強く支持する結果になりました。ただ、「北部同盟」のように北イタリア独立を求める声は、少なくとも周りにはありません。
一等地に住むアリストクラシー以外、現在でもミラノに住んでいる、生粋のミラノ人など、全体の何パーセントなのでしょう。周りを見回してもあまり思いつきません。教えている学生たちも、大体親の世代に南から移住してきた家族が目につきます。南には仕事がないので、北に移住してくるのです。
ミラノでも、少し離れたブリアンツァの小都市に出かければ、恐らく今でも土地の出身者はそれなりの数住んでいるのかもしれません。
カタロニアの事情は分かりませんが、少しは近しい部分もあるのかも知れないと思いながら、移民者の一人としてニュースを読んでいます。
—
10月某日 ミラノ 自宅
今月末で家人の滞在許可証が切れるので、更新に必要の書類作りに奔走。驚いたのは、現在まで10年も滞在許可証を貰っていて、市役所に戸籍登録されていなかったこと。最初は何かの手違いだったのだろうが、今となっては原因は分からない。改めて戸籍登録をして事なきを得る。
最初はミラノの市役所に出かけて、該当する人物は見つからないと言われ、あなたと子供さんだけモンツァから転出されてきている、きっとあなたはモンツァに奥さんの戸籍を忘れてきたのよと笑われ、朝一番の列車でモンツァの市役所まで出かけて尋ねると、「スギヤマ」は何人か登録されているが、該当する「スギヤマ」はいないようだと言われ、狐につままれた思いで帰宅した。
日本で、外国人不法滞在者や不法移民が話題に上ると、決まって自国へ早急に送還すべきと言われるので、正直なところ、内心穏やかではない。日本の滞在許可申請について明るくないが、申請書類を準備するのに思いがけず時間がかかったりして、全く不可抗力的に滞在許可証が切れ、再発行手続きが間に合わないことも考えられる。事実イタリアでは、以前は滞在許可証が切れても何日以内かに申請すれば、更新手続きとして受領して貰えたが、現在どうなっているか分からない。保育園や小中学校の子供の声は近所迷惑で、育児休暇もむつかしく、子連れの外出も憚られ、出生率は当然低下しつつ、外国人は風紀を乱すし、外国人でもクリアしなければいけない専門職の試験は、我々でも分からないむつかしい日本語が並び、近隣諸国は嫌いだとすると、これから日本の国力はどうやって上げてゆけるのだろう。
まあ、怪しげな移民の立場では偉そうなことも言えない。
10月某日 パドヴァ ホテル
ヴェニス行き特急に乗り、ヴェニス一つ手前の停車駅、パドヴァ駅で降りる。この街には、今から20年以上前に、一度だけパドヴァ大学の演奏会にやってきた。当時は伊政府給費が突然止められた時だったから、文字通り無一文で、作曲の先生だったゴルリがそれを見かねて、自分のアンサンブルの演奏会の折に、アシスタントとして雇ってくれた。何をするわけでもないのに、一緒についてゆき、ホテル代も出してもらっていた。リハーサルを聴いて、バランスや音間違いなどをチェックした程度だったに違いない。本当に彼のお陰で生き長らえたと改めて思う。パドヴァ大の演奏会で、確か「主のない槌」がプログラムにあったような気がするが、間違っているかもしれない。場末のホテルにチェックインした時、彼がホテルに出した身分証明書にアレッサンドロ・ゴルリと書いてあって、初めて本名はアレッサンドロで、通名がサンドロと知った。あの時は、とても寒くて、暗い印象ばかりが残っている。実際にその通りだったのかもしれないし、鬱々とした毎日を過ごしていたのかもしれない。
食べるものにも事欠く状態だったはずなのに、食事に関してはあまり惨めな印象が残っていないのは、市役所を罷めて八百屋を始めた友人がいたからだ。
相変わらず曇り空で肌寒いパドヴァ駅で、そんなことを想う。
10月某日 パドヴァ ホテル
いつもリハーサルに出かけるとき、忘れ物がないかととても不安に駆られる。幸い楽譜は揃っていたが、本番用の黒シャツを詰めるのを忘れていた。
パドヴァ駅の案内所で男物の洋品店を尋ねると、駅の向かいにあると云う。そこは中国人が経営する所謂場末のアウトレットだったが、黒シャツもちゃんと一種類置いてある。17ユーロ。一体、どこで誰が、どんな状況でこれらの製品を作っているかと思う。昔モンツァの集合住宅に暮らしていた頃、隣の部屋は階下の中華料理屋の使用人たちが暮らしていた。とても狭い部屋に一体何人暮らしていたのだろう。何度か警察がやって来たのを覚えている。或る日突然、その部屋の玄関が開け放たれ、中はがらんともぬけの殻になっていて、仰天したことがある。警察に捕まったのなら、調度品など残っていそうなものだから、夜逃げしたのだろうと家人と話した。
捕まっていなければいい、理由はないが漠然とそう思った。夕方になるとランニングシャツ一枚の中国人が、へろへろの外に突き出た通路にもたれて煙草を吸っていて、イタリアは好きかと聞くと、寂しそうに笑って、「家に帰りたい」、とたどたどしい伊語で答えた。
今回パドヴァでリハーサルするプログラムに、カン・ヘスンを独奏者に迎えて郭文景(Guo Wenjing)のヴァイオリン協奏曲があるのを思い出し、マオカラーの黒い国民服みたいなシャツはないか尋ねてみる。一瞬怪訝な顔をしたが、果たしててらてらの中国生地のシャツがあって、15ユーロ。どちらが本番服に合うかわからないので、二つとも購入して計32ユーロ。安い製品を購入するのは、搾取される労働力に幾何か還元する唯一の道なのか、さもなければ奴隷扱いに等しい経済構造にただ拍車をかけるだけなのか。
10月某日 パドヴァ ホテル
パドヴァ・ヴェネト州立室内管リハーサル。古くはヴィオラのジュランナ、暫く間までピアノのアシュケナージが音楽監督だったが、現在のアンジュスに替わって以来、近現代作品を演奏する回数が飛躍的に上がった。ジュランナとグッリと録音したモーツァルトの「協奏交響曲」の名演が忘れられなくて、このオーケストラと現代作品を演奏する現実感が伴わない。練習会場は、郊外の宗教施設に併設された古い劇場で、時には映画も上映していた風情も漂う。外のインターホンにはオーケストラの名前が書かれていたし、2階には事務所と楽譜庫があったから、今は専らリハーサル会場として使われているようだ。
愕いたことに、リハーサルが始まる14時から15時半まで、一帯が工事停電する、と今しがた通告されたと言う。どうしましょう、とステージマネージャーは困り果てた顔をする。最初のリハーサルは、筝の後藤さんを迎えた岸野さんの作品だったが、左右舞台脇の出口の扉を開け放して、外からの寂しい光を頼りに練習を始めた。
光が多少は入ったところで、映画館のような漆黒の空間に差し込む二筋の太陽光では、到底オーケストラが練習できる筈もなく、暫く試してすぐに頓挫。冗談みたいなことを、真剣に出来ると思う不思議。イタリアに歴史に残る天才が数多く残る証かも知れない。
夜、散歩中に見つけた「狙撃隊」というヴェネト料理屋に入る。「肉が食べられないのですが、何かありますか」と尋ねると、烏賊の煮込みとカジキマグロのパスタを用意してくれる。一杯くらいワインはどうかと言われたので、疲れていたので、珍しく頂くことにする。白ワインか赤ワインかと尋ねられ、一旦は白をと答えたものの、ウェイトレスの後姿でふと思い返し「でもここは赤ですよね」と声をかけると、嬉しそうに「そうです」とこちらを振り返った。
10月某日 ヴェニス ホテル
ホテルからすぐのサント・ステファノ広場あたりのバールで朝食を摂ろうと、散歩を兼ねて早朝ヴェニスを歩く。一軒開いていたバールは、覇気のない若い夫婦がやっていて、注文しようと幾ら待っていても目もくれない。ところが、後から入ってきた近所の老人が、菓子パン頂戴と声を掛けるとすぐに出したので、こちらも注文してよいかと尋ねると、「別の用事してんだから待ってなさいよ」と酷い剣幕で言うので、「常識知らずのヴェネチア人、恥を知ればよい」とだけ応え店を後にした。若い夫婦の顔色がさっと変わるのが分かった。
ヴェネチア人が観光客を嫌っているのは、本人たちから何度となく聞いて知ってはいるが、彼らにどこか食堂を紹介してくれと頼むと、「この何某亭に行ったら、馴染みのヴェネチア人に紹介されて、後で待遇がどうだったか確かめて、悪ければ文句をつけに来るそうだ」と脅迫染みた文句まで言わなければ相手にされない、と聞き呆気に取られる。そこまでして、ヴェニスで外食したいとも思わない。
尤も、フランチェスコと昼食を摂ったガリバルディ通りの郷土料理屋は親切で、何より美味だった。フランチェスコは8歳までヴェニスで育ち、それから親の仕事の都合で、嫌々フィレンツェに引っ越した。ヴェネチア人は実はとても優しく話も通じるが、フィレンツェ人はどこまでも攻撃的なので身も蓋もない、と確かに身も蓋もない言い草をする。フィレンツェに引っ越した当時、ストレスからか突然字が書けなくなったそうで、「繊細だったんだろう」と笑う。
観光ガイドに、お薦めの郷土料理屋のリストが載っているのか、観光客相手のレストランには閑古鳥が鳴き、地元の小料理屋にばかり観光客が群がって、文字通り「観光客相手の料理屋」になっている。
10月某日 ヴェニス ホテル
大くんの「ホルン協奏曲」。大くんと初めて会ったのは随分昔にベルリンで、KNMが彼の作品を紹介した時だった。それからは京ちゃんと3人でイタリアをツアーしたり、会っては話し込む機会が続いていたのだけれど、ここ暫くご無沙汰していた。
楽譜を広げると、一瞬単純そうに見える明快な譜面だけれど、演奏は難しいだろうと覚悟していた。実際練習時間は他の曲よりずっと多く取らなければならなかった。
昔から大くんはメジャーコードが好きだと言っていたが、和音をピアノで弾いてゆくと、一つ一つの和音に表情があって、翳ってみたり、くぐもった顔をしたり、光が差し込んできたり、後ろを振り返ってみたり、その変化がとても美しいと思う。
その和音が響かせるためには、オーケストラは互いに耳をそばだてて聴きたい音を探してゆかなければならない。オーケストラが耳を開くと、それが巨大な花びらのように広がってゆき、その中心に独奏の福川くんの音が沁みとおってゆく。
オーケストラで使われる楽器はどれも禁欲的だし、禁欲的な姿勢を強いると思うけれど、ホルンはその最たるものではないか。その佇まいに美しさを見出したところが、大くんの、もしかすると、ヨーロッパ的ではない視点が働いていたのかも知れない。福川くんの音は素晴らしかった。
尤も、今回大くんとは音楽の話より、寧ろ彼が凝っている「腸内細菌」についてばかり話し込んでいた気がする。
10月某日 ミラノ行車中
朝4時半に起きチェックアウトをして、冷え込みの厳しい夜明け前の路地を伝い、5時の水上バスに乗る。
昼間の喧騒が嘘のように静まり返っていて、ただ聴こえるのは波の音と、時たま通る汽船の低い警笛、それにエンジン音くらいだろう。ぽつりぽつりと水面に尾を引く橙色の街灯が、波に揺れていて美しい。
早朝の水上バスは、意外に利用客もいるが、大方が、荷物を抱えて駅に向かう労働者のようにも見え、何人か外人も交じっていた。どういう事情か分からないが、ヴェネチア本島に住んで、メストレ方面に働きに出かける労働者がいるかどうか。
昨晩の演奏会の後、食事を摂りながらヘソンと話していて、彼女が韓国を後にした時の話になった。当時は海外に出るのがとても大変で、それも姉妹で留学したので、親はとても苦労したと言う。何時でも整った身なりをしていて、一見澄ました雰囲気も醸し出しつつ、完璧な演奏をしていた。リピッツァー賞の審査員をした時、日本のヴァイオリン奏者のスタイルが以前とずっと変わっていて驚いたと話していた。韓国より、長く暮らしているフランスの方が暮らしやすいと言う。母親とは気軽にインターネットで連絡が取れるようになったし、でもずっと離れていると、会話の内容が一辺倒になってしまっていけない、と笑った。元来フランスは移民の国だが、それでも最近はフランス人への優先度が高くなり、外人への門戸は途端に狭くなり、留学してくる自分の生徒たちが大変だ、と話す。
10月某日 ミラノ 自宅
息子は吐気と眩暈で布団に突っ伏している。中学時代の自分にそっくりで、何故こういうどうしようもない処ばかり遺伝するのか、息子に申し訳ない思い。親の心子知らずと言うが、両親はどう思っていたのだろう。尤も当時のは明らかに自律神経失調症で、息子に関しては、自律神経なのかウィルスなのか、さもなければ神経なのかも良く分からない。実際に巷では酷い吐き気を伴う風邪が流行っているということで、病院からは吐気止めを処方されたが、効果は見られない気がする。
食べられないので体力も落ちるのだろう、自転車に乗りたがらない。道路を走っている途中で、いきなり力が入らなくなる時があって、恐いのだそうだ。
勿論、それを見越してリハビリも兼ねて乗らせているので、心配しないで乗ればいいのだが、夜半中トイレに立って吐き気と戦っているのを見ると、とても強く励ます気は起こらない。
10月某日 ミラノ 自宅
7月に息子が退院してすぐ、思い立ってサンタゴスティーノの自転車屋へ走った。朝、息子が混んだ路面電車で転んだので、その日の午後から、息子を後ろに乗せて走れるような自転車が必須だった。どういう自転車が必要かと言われたので、12歳の息子を乗せて走れる自転車なら何でもよいと伝えた。
「失礼ですが、一体どういう訳で」と我々くらいの年代の店主に尋ねられたので、事情を説明すると、実は自分も昨日病院から出てきたばかりだと言う。
「私は実は癌でしてね。ちょうど昨日、やっと化学療法が終わって、退院してきたのです。ですからほら、髪の毛も身体中の毛も、すっかり抜け落ちてしまいました。息子さんが癌じゃなくて本当によかった。でも大変ですね。一緒に頑張ろうと伝えてください」。
あれから、自転車が丁度サンタゴスティーノあたりでパンクしたので、店主のところへ持ってゆくと、髪もすっかり生え揃って、見違えるように活動的な姿になっていて、思わず「本当にお元気になって嬉しい」と言うと、そんなことを誰もが思い出してくれるわけじゃない、有難うと、手を取って顔をくしゃくしゃにして答えた。目には涙がたまっているように見えた。
7月、丁度この黒い婦人用Delmaの自転車を購入したばかりの頃、家の玄関先で、アルフレッドに会った。正確な年齢は知らないが、60はとうに過ぎた、ミラノでは名のある建築家で、このマンションの最上階のペントハウスに、何時もケリーブルーテリアを散歩させている、小さな可愛らしい奥さんと住んでいる。このマンションの建築も彼がサンドロと一緒に手がけた。
アルフレッドに声をかけられたと言っても、最初挨拶された時、すっかり痩せこけていて一瞬誰だか分からなかった。
「君のところの息子さんの具合はどうだい。実は僕は癌でね。君と同じように、ニグアルダで治療しているんだ。ちょうど化学療法の治療期間が終わったところでね。ナディアから息子さんの事情は聞いたよ。大変だったね。でも癌じゃなくて本当に良かった」。
台所で家人と二人、夕食の準備をしていると、見かけない黒い車が庭先に止まった。胸騒ぎがして窓を開けて外を見ると、木棺が車に積み込まれるところで、傍らには、いつもより小さく見えるアルフレッドの奥さんの姿があった。彼女は棺が車に収まったのを見届けると、糸の切れた凧のように歩きながら、別の車に乗り込んだ。
二日ほど後、道でいつものように犬を連れている彼女に会って、かける言葉もなくただ肩を抱くと、「本当に、とても辛かったわ」と絞り出すように声を出した。化学療法は途中で肺炎を起こして中断し、再度検査すると、癌はもう手の施しようもない状態になっていた。
10月某日 三軒茶屋 自宅
期日前投票に出かける。自分だったら可能な限り投票したいと思うが、何故投票率がこれだけ低いのか。
イタリアで如何なる投票権を持っていないので、投票権に切実な意義を感じるのかも知れない。何時でも投票用紙が送られて来ると、案外なおざりにしたくなるのかも知れない。三軒茶屋の食卓にスコアを広げて仕事をする。どうこれから譜読みをこなすのか途方に暮れながらも、「一度には一つの事しか出来ず」「急がば回れ」と言い聞かせてみるが、言い聞かせる口調も悲壮なので、余計心臓に良くない気がする。
窓際に、何時も仕事に出かけるときに持ち歩いている、息子がずっと小さかった時に書いた「さいごまでよくがんばったね」というイラスト付きの紙ぺらを飾る。片面には、両親の笑顔が赤ペンで描かれていて、「よくさいごまでがんばったね」と吹き出しの中に書いてあり、その裏にはずっと大きな字で、「でぷろま よくピアノをがんばったね」とある。小学校の時に使っていた、日本の通信教育の冊子の影響だろう。
湯浅先生の新曲「軌跡」の楽譜を読みながら、ドナトーニの「prom」のオリジナルの楽譜を渡された時のことを思い出す。
どちらも似たような大病の直後の作品で、表現力、訴求力の方向性が少し似ているような気がする。強靭な精神力と、生命力を感じる。
音の意味を一つ一つ嚙締めながら、読んでゆく。
10月某日 三軒茶屋 自宅
インターネットが出来たとき、行ったことのない土地の人と話し、世界中の図書館にアクセスすることが出来る、夢の世界の誕生だと言われた。
1971年に作曲され、子供の時分から一度は聴いてみたいと思っている曲があって、思い立って9月半ばから探し始めた。出版社に連絡すると、もう取り扱っていないし、素材も一切残っていないと言われる。楽譜は残っていなかったが、作曲者から初演者の名前を教えてもらった。初演した指揮者は鬼籍に入っていて、初演したオーケストラは破産したと言う。この指揮者の死亡記事を書いた音楽ジャーナリストに直接便りを出して、探している楽譜があって、もしかしたら家族のもとにあるかも知れないと書いたが、返事はなかった。日本でも演奏されたことがあって、テレビでも放映されたという。78年のことだから、自分が9歳くらいの時のことだ。
日本で演奏したオーケストラには楽譜は残っていなかったし、番組の制作会社にも楽譜はなかった。当時のヴィデオは見られるか尋ねたが、もしVTRが残っていたとしても、簡単に再生できないので、とてもお金がかかるだろう、といわれる。
初演はアメリカ西海岸の話だったので、サンフランシスコの劇場で働いている幼馴染に連絡したり、邦楽器で活動している知合いにお願いして、ロサンジェルスのオーケストラのライブライアンと連絡を取ったのは、ロサンジェルスのオーケストラで演奏したという記録も見つけたからだ。
ライブラリアンはとても親切で、ここにはその楽譜は残っていないが、その指揮者の残した資料は、遺族がスタンフォード大に寄贈して、コレクションになっているので、連絡したらどうかと助言してくれる。スタンフォードのコレクションのカタログには、確かに初演時の写真の記録と思しきものもあったので、司書に連絡すると、この写真は別の演奏会のものだった。
実は写真ではなく、楽譜を探していると伝えると、楽譜は全く別の場所に保管しているが、取り寄せて調べてくれると言う。数日して連絡が来て、丁寧に残した楽譜を調べてみたが、該当する楽譜は見つからなかった。ただ、全世界の図書館検索にかけると、ニューヨーク公共図書館と、ドイツの図書館にコピーがあると言う。
ニューヨークに住んでいた作曲の友人に頼んで、この楽譜が閲覧、複製できるか、何度となくやりとりを繰返してもらっている。
物凄く長い旅をしている気がするけれど、会ったこともない人たちとも、もちろん忙しい友人たちにも、本当にとても親切にしてもらっていて、楽譜探しの旅は、人間の温もりを実感する旅のようだ。
10月30日 三軒茶屋にて