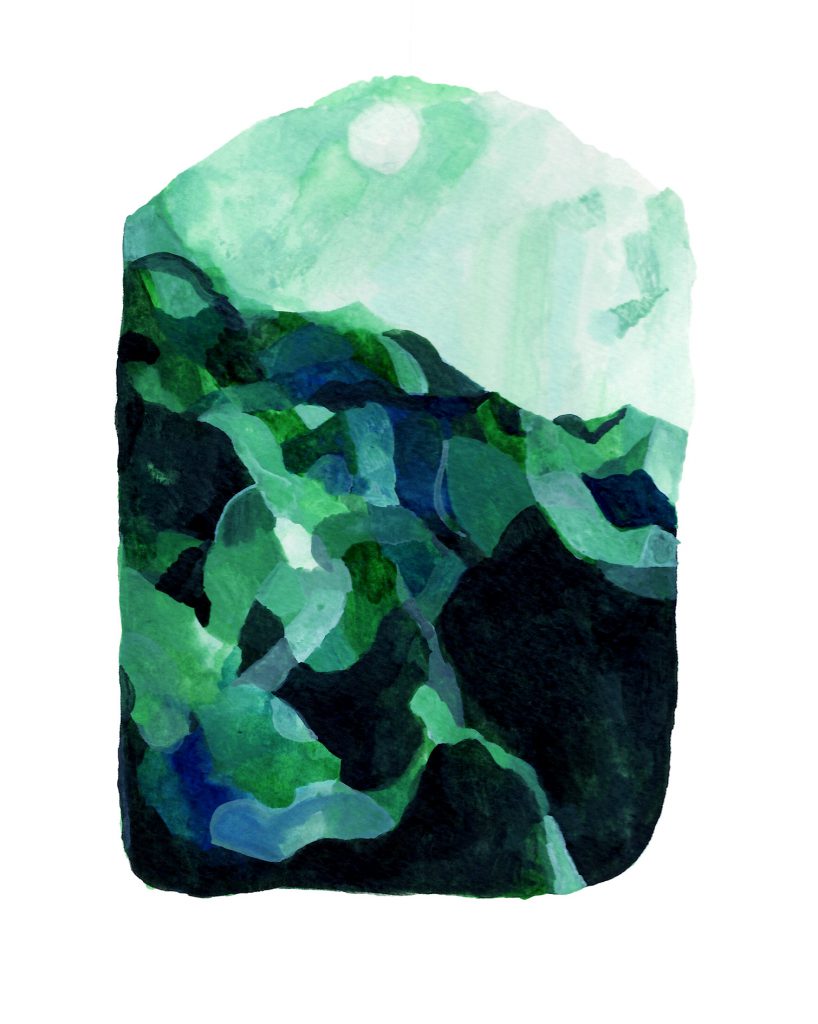世の中には「編み込み派」と「地模様派」というのがある。編み物の世の中のことです。編み込みは、さまざまな色の糸を使って複雑な模様を作っていくことで、地模様は、色は一色のままで、編み物の表面に縄だの溝だの格子だのでこぼこを作っていく技法だ。
編み込み派はさらにフェアアイル閥、北欧閥、橋本治閥などの分派に分かれ、地模様派にもアラン閥、ガーンジー閥、各種レース支部などがある。私は元来、編み込み派のどこかに属したかったが、色彩感覚がだめなのであきらめ、結局、地模様派・アラン閥/ガーンジー閥のかけもちということに落ち着いた。
大造りにいえば、編み込み派は世界を色で把握し、地模様派は立体感で世界を把握している。私の属する地模様派は、糸のループを互いにからませたり重ねたり、交差させたりしながら凸凹を操っていく。基本は一つのループ、つまり一目にすぎないが、それを何重にも組み合わせた結果、「ふるいつきたいような」模様編み、「そそってそそってたまらない」「狂おしいような」模様編み、というものがこの世に生まれる。
例えば「枝先にボッブルをつけた生命の木」とか、「中を2目かのこで埋めたダイヤ」とか、「1目×2目の交差を左右対称に並べてウイングみたいにしたやつ」、「ホースシューの両サイドをモックケーブルあるいはハニカムの1列だけを配置」……などと、編み物をしない人には何のことかわからないと思いますが、書いていくだけで脳内にその手触りが再現されてアドレナリンが出るし、実際、こうしたふるいつきたい模様編みが上手に編まれ、着られているのを道で見かけ、その人の後をずっとつけたこともあった。
あれは子供のころ、地表のいろんなものに思わず触れたかった衝動と何も変わらない。ぽこぽこした、ぷつぷつした、ざらざらした世界のテクスチャーの、問答無用の牽引力だ。こんもり、みっしりと地上に盛り上がってどこまでも続くシロツメクサの畑、枝先からあふれる百日紅、馬酔木の花や山葡萄の房の連なり方とばらけ具合。ナラの木の根元に散らばったどんぐりの笠の粒々、大木の根元で盛り上がって入り組んだ細い根っこたち。また、草の茎の途中でふくらんでいたカマキリの卵のあぶく、セミの羽根に透けて見える波模様。規則性と不規則性、世界の粒立ちと波打ちとうねり具合。毎年まっさらな顔をして現れては輝いていた、何でもないぽこぽこした、ぷつぷつした、ざらざらしたものたち。
それらに近いものを手と糸と針で作り出せるというのは、ちょっとうっとりするようなことだ。
たぶん最初に魅了されたのは、「かのこ編みと縄編みの組み合わせ」だったと思う。かのこ編みとは編み物の表面を一様に細かくざらっとさせる手法で、縄編みは「ケーブル」というやつ、量販店のセーターに最もよく出現するあれです。でも、手編みの縄編みと手編みのかのこ編みを組み合わせると、縄の盛り上がり方がぐぐっとアップするので、「これがほんものの……こんもり・くっきり・ふっくらというやつ!」と静かに興奮する感じになる。
このたまらなさ、何かに似ていると思っていたが、最近になって気づいた。あれは、私が大学時代に一応専攻したことになっている考古学で扱う縄文土器、特に縄文中期の土器の表面ではないのかと。
縄文土器の表面の模様は、自然界にあるさまざまなものを利用してつけられる。植物の繊維を縒ったもの(縄)を転がす。それを棒に巻いたものを転がす。または刻み目を入れた棒、貝殻のぎざぎざの縁、それから竹を半分に割ったもの。
竹を半分に割ったものを粘土板の上でぐっと強く引くと粘土のひもができる。そもそも縄文土器自体が、粘土のひもを巻き上げたり、積み重ねたりして作ったものだ。そして、粘土ひもを渦巻きにしたりうねらせたりして、細かい網目模様で埋めた土器の表面に貼りつけると、私の好きな「かのこ編みと縄編みの組み合わせ」そっくりになる。写真が載せられないけど、「加曽利E式土器」などのワードを入れて検索してみてください、私の言ってることがわかるかもしれないから……。
こうした装飾を土器の縁に積み上げたりして、縄文土器の立体感はどんどん開花暴走していく。その頂点が火炎土器だろう。一方、弥生土器ではごつごつした凹凸は消え、全体の美しい曲線的なフォルムが特徴だ。その上に彩色したり、部分的にあっさりした刻み目模様を施したりする。
どうやら人類には、世界の表面を引っかいたり穴をあけたり何か貼りつけたりして凹凸を作りたくなる人たちと、世界の表面をすべすべにしてその上に模様を描きたくなる人たちとが、いるみたいだ。日本列島で作られた土器はこの順番で現れたが、どっちが進化してるというわけでもない。
それと同じく、編み物における編み込み派と地模様派のどっちがえらいわけでもない。えらくはないが、テクスチャーを作り出す地模様派には、なかなか奥深いところがある。
昔、一世を風靡した編み物デザイナーの戸川利恵子先生という方がいて、その方が「2目×2目の縄編みを、6号針でゆるめに編むのと7号針できつめに編んだのでは、同じ糸でも色が違う」といったことを本に書いていらした。これもまた編み物をしない方には何のことかわからないにきまっているが、これは真実だ(真似したのでわかる)。
なぜ色が変わるかというと、実に微妙な手かげん一つで、編み目の盛り上がり方が変わり、結果として同じ光を浴びても影のできの方が変わるためだと思う。つまり大げさにいえば、編み物でテクスチャーを作り出すのは、光と影を支配することだ。
地模様派の人は、そんなに広くないセーターの表面に何種類もの柄を並べようとして、その並べ方に苦心惨憺する。並べ方を変えるたびにそれぞれの模様への光の当たり方が変わり、全体の景色が変わるからだ。ほんとに、どの模様の隣に置くかによって、好きな模様のテクスチャーがぐっと引き立ったりまるでだめだったりするのだ。
それは、縄文土器の模様の組み合わせを工夫していた何千年も前の人たちの仕事と多分、あんまり違っていない。縄文土器もアランセーターも、空間恐怖症みたいに「素」の面積が少なくて、複数の模様がびっしりと表面をおおっている。世界のテクスチャーを選びとり、配置して、光と影の塩梅を見る。箱庭を作って俯瞰している小さめの神みたいでもある。
俯瞰できる面積は狭い。一枚のセーターとか一個のかわらけとか。セーターは破れる、土器は割れる。生きているうちに目の前で壊れるものの表面を、ぽこぽこした、ぷつぷつした、ざらざらしたもので埋め尽くしたいという欲求は、何か圧倒的にきりがなくて、個人の力量を超えている。
なので私は、もう模様配置の開発はやめてしまった。ほぼ理想に近い箱庭が二種類できたので、今はそれを反復して編んでいる。でも、道で、ふるいつきたい模様編みが上手に編まれ、着られているのを見かけると(以下略)
俯瞰できる面積はほんとに、圧倒的に狭い。自分が今歴史のどこにいるのかが、結局、すっきりと一望できないのと同じように。だから箱庭の中を歩いて、世界の疎と密を手で触って確かめるしかない。そしておりがあれば、自分の箱庭から出て歩いていくしか。
視覚障害者は、晴眼者が見て気づかない編み間違いに、指で触ってすぐに気づくと聞いたことがあった。