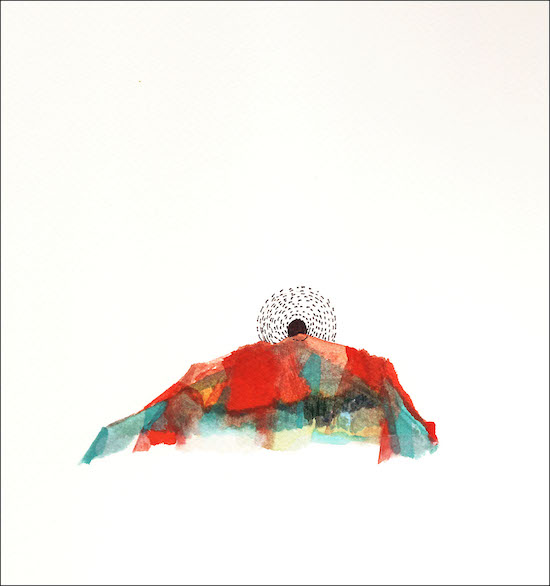ボローニャはマッジョーレ広場から程近い宿でこれを書き始めました。今までマッジョーレ広場で、国営放送局のインタビューを受けていました。隣のフランス人観光客の家族が騒いだり、物乞いが「空腹!お恵みを」と書いた段ボールを持って近づいてくるので、その度に録りなおしになったりして、格闘一時間半。明るい夏のボローニャの広場の夕刻は、人々の笑顔が印象的です。
….
7月某日 ミラノ自宅
寝不足と暑気が重なり、体調を崩した。吐き気が止まらず、手首辺りから先が麻痺している。椅子に坐っていられなくて、思わず床に倒れこむ。顔が真っ赤だが一体どうしたの、と母が驚く。
地下鉄サンタゴスティーノ駅のキオスク店主が、客と話し込んでいる。こんな仕事、本当に何の愉しみもない。月給6000ユーロ貰っても辞めたいと言う。
7月某日 ミラノにて
12世紀サレルノ医学校で編纂された養生訓をテキストにした西川さんから頼まれた新曲を送付する。12世紀だというのに、過労死への警句がまず最初に書いてある。ストレスという単語はまだなかったかもしれないが、あまり今と変わらない。
ウナギやクルミがいけないのは、消化に時間がかかるからだろう、との見解を読む。イタリア人が風呂好きなのは、古代ローマ時代から連綿と続く文化。医学が体系化されてゆくのは、この養生訓が書かれたこのサレルノ医学校で、世界の叡智が結びついてからのことだ。
ヨーロッパ全土をなめつくしたペストの大流行の前に書かれているが、この後すぐに訪れるペスト流行とは少し違った意味で、「死」との距離は非常に近い。彼らにとって、生命とは今よりずっとシンプルなものだった。生きるか、さもなくば死ぬ。
サレルノ養生訓
「12世紀、世界で最初の医学校が、南イタリア、ナポリの少し南にあるサレルノに生まれた。当時サレルノを含む南イタリアは、ビザンチン、アラビア、ラテン文化が混ざり合う文化の宝庫で、才能豊かなシチリア王フェデリコ2世のもと、アラビア人、ユダヤ人など世界各地から叡智が集った。サレルノには、各地の医者が諍いなくそれぞれの知識をあわせ、近代医学の体系を整えようとしていた。このサレルノ医学校を認可し、医者の資格をこの医学校を修了した者に与えると決めたのも、フェデリコ2世だった。当時の医者たちがうつくしい詩の形で書き残した養生訓集から抜だしたものに、フェデリコ2世時代シチリアの賛歌、Congaudentes jubilemus 冒頭の旋律を使って作曲を試みた。西川さんからVox humanaのためにと新作をお願いされ、まず頭に浮かんだのは、ラテン語のテキストを使うこと、望月さんのオペラで演奏者としてVox humanaの皆さんとご一緒した経験から、一人一人の卓越した技術と個性を際立たせることを思いつき、そしてささやかながら、さまざまな異文化のより豊かで平和な共存が実現するよう、願いをこめた」。
息子はCongaudentes jubilemusによる主題が気に入って、厭きずにずっとピアノで弾いている。
Regimen sanitatis salernitanum
サレルノ式養生訓
1
Triste cor, ira frequens, bene si non sit, labor ingens,
Vitam consumunt haec tria fine brevi.
Haec namque ad mortis cogunt te currere metas.
Spiritus exultans facit ut tua floreat aetas :
Vitam declinas tibi, sint si prandia lauta.
Si fluxum pateris, haec ni caveas, morieris :
Concubitum, nimium potum, cum frigore motum.
Esca, labor, potus, somunus, mediocria cuncta:
Peccat si quis in his, patitur natura molestis.
Surgere mane cito, spaciatum pergere sero,
Haec hominem faciunt sanum, hilaremque relinquunt.
かなしみ、くりかえす怒りは、よくありません。度を過ぎた仕事も。
この3つは、生命をたちまち燃えつくします。
死と出会いのを早めるだけ。
愉快なこころは、あなたの齢に花をさかせますが、
豪華な食事は、あなたから、瞬く間に一日を過ぎさります。
熱があがり、血のめぐりがわるく、性生活も控えず、
酒をのんで、動きまわっていると、死にます。
食事、仕事、酒、眠り、どれもほどほどがよいでしょう。
このどれか欠ければ、おのずと不愉快が増します。
朝早くおきて、夜散歩にでかけると
人を健康にし、快活にします。
2
Vitam prolungat , sed non medicina perennat;
Custodit vitam qui custodit sanitatem.
Sed prior est sanitas quam sit curatio morbi ;
Ars primitus surgat in causam, quo magis vigeatis.
Qui vult longinquum viam perducere in aevum,
Mature fiat moribus ante senex;
Senex mature, si velis esse dici.
薬は命をのばしますが、永遠にのばせるわけではありません。
命を守る人は、健康を守る人のこと。
病気を治すより、まず健康であることが大切です。
この芸術は、健康であるほど、あなたの役に立つでしょう。
老いらくまで長生きしたいなら、
生活習慣を成熟させることです、老人になるまえに。
すぐに老けますよ、あなたが望めばね。
3
Lumina mane manus surgens frigida lavet unda.
Hac, illac modicum pergat, modicum sua membra
Extendat, crines pectat, dentes fricet; ista
Confortant cerebrum, confortant caetera membra.
Lote, cale, sta, pranse vel i, frigesce minute.
朝ベッドから起きたら、つめたい水で目と手を洗いましょう。
しばらく歩いてから、四肢もすこしのばしてください。
髪をとかして、歯をみがきましょう。すると、
頭がすっきりして、身体のあちらこちらに元気が湧いてきます。
風呂で身体をあたため食事をとり、少し休むか散歩をして、ゆっくりほてりを冷ましましょう。
4
Sit brevis, aut nullus somnus tibi meridianus.
Febris, pigrities, capitis dolor, atque catarrhus
Quatuor haec somno veniumt mala meridiano.
tibi proveniunt ex somno meridiano.
昼寝はほんの少し、いや、とらなくてもよいでしょう。
発熱やなまけ癖、頭痛やカタル。
これが昼寝の四悪です。
午後の眠りのあと、あなたに訪れます。
4
Post pisces nux sit; post carnes caseus adsit.
Unica nux prodest, nocet altera, tertia mors est
Post pisces nux sit, post carnes adsit.
魚のあとのクルミはよいでしょう。肉のあとにはチーズ。
クルミ一個はよいのですが、もう一個食べると身体にわるく、三個たべれば死にます。
三つのうち、一つだけなら身体にとてもよい。
5
Vocibus anguillae nimis obsunt, si comedantur;
Qui physicam non ignorant hoc testificantur.
Caseus, anguilla mortis cibus ille vel illa,
Si tu saepe bibas et rebibendo libas,
Non nocet anguilla vino si mergitur illa.
ウナギを食べて、声がおかしくなるのは
道理を理解する人なら、証言してくれるはずです。
チーズとウナギを一緒にたべれば、死にます。
しばしばワインを口にし、またのんで、ちびちび舐めていれば
ウナギは差し障りありません。ワインと一緒にたべるのならね。
6
Cur moriatur homo cui salvia crescit in horto?
Contra vim mortis non est medicamen in hortis.
Salvia confortat nervos, manuumque tremorem
Tollit, et eius ope febris acuta fugit.
Salvia salvatrix, naturae consolatrix !
Salvia dat sanum caput et facit hoc Adrianum.
なぜ人が死ぬと、庭でサルヴィアが育つのでしょう。
人の命に対する薬は、庭にはありません。
サルヴィアは神経をやわらげ、手から震えをとり、
高熱もサルヴィアのおかげで消えてしまいます。
ああ、生れながらにして心やさしき、救世主サルヴィアよ、
サルヴィアは頭を健康に、聡明なハドリアヌス帝のようにしてくれます。
7
Coena brevis, vel coena levis fit raro molesta,
Magna nocet: medicina docet, res est manifesta.
Numquam diversa tibi fercula neque vina
In eadem mensa, nisi compulsus, capienda:
Si sis complulsus tolle quod est levius.
Si sumis vina simul et lac sit tibi lepra.
O puer, ante dabis tibi aquam post prandia dabis
Omunibus assuetam jubeo servare diaetam.
Ex magna coena stomacho fit maxima poena.
Ut sis nocte levis, sit tibi coena brevis.
Si fore vis sanus, sit tibi parca manus :
Pone gulae metas ut sit tibi longior aetas;
Ut medicus fatur parcus de morte levatur.
手短にすます食事、軽い食事が、身体に悪いことはまずありません。
食べすぎは身体にさわります。医学でもそういいますし、明白です。
無理強いされないなら、あなたをそそのかす豪華な料理や数々のワインは断ること。
無理強いされるなら、そのなかで一番軽いものを選んでください。
牛乳とワインを一緒にのむと、湿疹がでます。
ああ少年よ。食事の前後に、水をのむことです。
この養生訓をみんなにつたえましょう。
ぜいたくな夕食は、胃をたいへん痛めます。
心地よく夜を過ごすため、夕食は軽くしてください。
長生きするため、食道楽はやめましょう。
医者のいうとおり、慎ましさが死を遠ざるのです。
これを書き出しながら、何か記憶の奥底で反響するものがある。悠治さんの「エピクロスのおしえ」だ。書き出すまで、サレルノのさまざまな民謡を繰返し聴き、私設動物園でキリンを飼っていたフェデリコ2世のまわりの音楽を繰返し聴いた。
ラテン語の詩は、響きもとてもうつくしい。友人が、ラテン語は、イタリア語のように回りくどくなく、単刀直入に言い切るのが気持ちよいと言っていた。ラテン語に通じているわけでもないが、少し気持ちはわかる。
7月某日 ミラノ自宅
藤木大地さんと福田進一さんのための新曲を送付する。
没後500年のダヴィンチが残した「鳥の飛行について」手稿の一部をテキストにし、リラ・ダ・ブラッチョの名手で、優れた歌手だったダヴィンチの残した「音判じ物Rebus musicali」から断片を一つ使って作曲した。「音判じ物」は、楽譜の音名を辿ると、テキストが浮かび上がる謎かけ。「レラソミファレミレ」と音符が書かれ、”Amore la sol mi fa remirare”「あの愛はわたしを振り返らせるばかり」と読むもの。ウィンザー手稿に収録されている。歌いまわしは、ヴィンチ村のあるトスカーナ地方で盛んな民謡、Stornelliを参考にした。
Il Volo degli Uccelli Leonardo Da Vinci
Fig. 19
Quelle penne che son più remote dal loro fermamento, quelle saran più piegabile. Addunque, le cime delle penne dell’alie senpre saran più alte che li lor nascimenti, onde potren regionevolmente dire che senpre le ossa dell’alie saran più basse nell’abassare dell’alie che nessuna parte dell’alia; e nell’alzare, esse ossa d’alie saran più alte che nessuna parte di tale alia. Perché senpre la parte più grave si fa guida del moto.
付け根から離れるほど、羽はより曲げやすくなるようだ。翼の羽の先端は、翼が付け根より高い位置にあるから、翼の骨は翼をさげれば他の部分より低くなり、翼をあげれば、翼の他の部分よりも高くなる。なぜなら、より重たい部分が運動を先導するから。
Fig.27
Quando l’ucello si vorrà voltare alla destra o sinistra parte, nel battere dell’alie, allora esso batterà più bassa l’alia onde esso si vorà voltare, e così l’ucello si torcerà il moto dirieto all’inpeto dell’alia che più si mosse.
鳥が右や左に曲がるとき、曲がりたい方の翼をより低く羽ばたかせ、向きを変える。このようにして、翼をより羽ばたいて推進力を得るより、翼の後ろの風の勢いをねじる。
Fig.28
Quando l’ucello, col suo battimento d’alie, si vole innalzare, esso alza li omeri, e batte le punte dell’alie in verso di sè, e viene a condensare l’aria, che infralle punte dell’alie e ‘l petto dell’ucello s’interpone, la tensione della quale si leva in alto l’ucello.
鳥が翼を羽ばたかせ上昇するとき、肩を上げ翼の先を自らの身体へ向け羽ばたかせる。すると翼先と鳥の胸の間の空気が圧縮され、鳥を上へ押し上げる力が生じる。
Il nibbio e li altri uccelli, che battan poco le alie, quando vanno cercando il corso del vento, e quando il vento regnia in alto, allora essi fieno veduti in grande altura, e se regnia basso, essi stanno bassi.
風の気流を探すあいだ、トビやその他の鳥は、あまり翼を羽ばたかない。風が高い位置を支配するとき、鳥はとても高い位置を飛ぶだろうし、低い位置を風が支配するとき、鳥は低く飛んでいる。
Quando il vento non regnia nell’aria, allora il nibbio batte più volte l’alie nel suo volare, in modo tale, che esso si leva in alto e acquista inpeto, colo quale in peto, esso poi declinando alquanto, va lungo spazio sanza battere alie; e quando è calato esso di novo fa il simile, e così segue successivamente; e questo calare, sanza battere alie, li scusa un modo di riposarsi per l’aria, dopo la fatica del predetto battimento d’alie.
風が凪いでいると、トビは、より多く羽ばたいて高くまで上昇し、しっかり推進力をたくわえたところで、その勢いを使って翼を動かさずに長い距離をかけて降下する。そうして降りきったところで、ふたたび同じ手順を繰返すのだ。羽ばたきを使わない降下により、疲れた身体をやすめることができる。
Tutti li uccelli che volano a scosse di levano in alto col lor battimento d’alie, e quando calano, si vengano a riposarsi, perché nel lor calare non battano le alie.
翼を羽ばたかせて急上昇する鳥が、降下で身体を休められるのは、降下で翼を羽ばたかないから。
Fig.29
Senpre il discenso del obbliquo delli uccelli, essendo fatto incontro al vento, sarà fatto sotto vento, e ‘l suo moto refresso sarà fatto sopra vento.
向い風で鳥が降下するとき、鳥は風の下にもぐりこみ、上昇するなら、風の上に身を置くだろう。
Ma se tal moto incidente sarà fatto a levante, traendo vento tramontano, allora l’alia tramontana starà sotto vento, e nel moto refresso farà il simile, onde, al fine d’esso refresso, l’ucello si troverà colla fronte a tramontana.
しかし北風に乗って東へ下降するときは、北向きの翼を風の下に入れる。上昇も同じだが、額は北へ向ける。
Ed è di tanto vilipendio la bugia, che s’ella dicessi be’ gran cose di dio, ella to’ di grazia a sua deità; ed è di tanta eccellenzia la verità, che s’ella laudassi cose minime, elle si fanno nobili.
たとえ神の偉大な逸話であっても、偽りは実に卑しむべきであり、虚偽は神性からも歓びを奪い去る。真実こそが何物をも超越した存在であり、些細な事実であれ、高潔な誉れが与えられる。
Sanza dubbio, tal proporzione è dalla verità alla bugia, quale da la luce alle tenebre; ed è essa verità in sè di tanta eccellenzia, che ancora ch’ella s’astenda sopra umili e basse materie, sanza conparazione ell’eccede le incerteze e bugie estese sopra li magni e altissimi discorsi; perché la mente nostra, ancora ch’ ell’abbia la bugia pel quinto elemento, non resta però che la verità delle cose non sia di somo notri mento, delli intelletti fini, ma non di vagabundi ingegni.
疑うべくもなく、真実と虚偽は光と闇の相違に等しい。どれほど慎ましく貧弱な物質であれ、真実がそこに介在するとき、不確実性やどんな高邁な説法を振りかけられた偽りをも、真実は掛け値なしに超越する。たとえ偽りが人の思考の一部を成していても、物事の真実こそが、洗練された思考、驚くべき知性の偉大な滋養であることは変わらない。
Ma tu che vivi di sogni, ti piace più le ragion soffistiche e barerie de’ palari nelle cose grandi e incerte, che delle certe.
でも夢に生きるお前なら、確実で当然で我々の理解を逸脱しない事実より、むしろ大袈裟で不確実な事実に怪しげな推論を立て、言葉巧みに貶める方が、よほど好きではないのかね。
1505 marzo-aprile Firenze
実際の写本は、これらの言葉の傍らに、鳥の動きのスケッチが書かれている。ダヴィンチの言葉は、イタリア語が未だ現在のような形になる前の姿を現していて、響きも独特な味わいだが、詩ではない散文調で、当初音に載せるのにずいぶん苦労した。
7月某日 ミラノ自宅
ボローニャで作曲コンクール審査。1位と2位はイタリア人、3位は中国人だった。4位と併せて特別賞を得たのは、ブラジル人だった。中国、韓国、日本の他、イランやトルコから複数、ブルキナファソからも一人の応募があった。
審査の途中でソルビアティとドナトーニの話になる。In Caudaの初演時、ドナトーニは純白なシャツを着ていた。演奏会直前、喫茶店でカンパリをこぼして、胸のあたりに大きな赤いシミを作って、ニヤリと笑ったと言う。「彼はわざとやったんだ、自分が呼ばれるときに、あの服でスカラ座の舞台に上がりたかったのさ」。理由は分からないが、妙に説得力のある逸話ではある。
7月某日 ミラノ自宅
ミラノ滞在中の母とわが息子が「わらび餅」を作った。美味。
母曰く、戦時中お八つと言えば、笹の葉に包んだ梅干をちゅうちゅうと吸うばかりだったそうだが、そんな話を息子はどう聞いているのか不思議に思う。
スキエッパーティ宅での息子のレッスンを見学。特にチェルニー練習曲がどんどん音楽的に、立体的になってゆくのに瞠目。和声的なアプローチも、こういう時こそ役に立つと知る。タッチについても、他の曲よりずっと細かく教えてゆく。レッスンにベートーヴェン「サリエリの主題による変奏曲」も持って行ったので、サリエリ、ベートーヴェン、チェルニーと師弟が揃った。こうして聴くと、意外なほど明確に親和性、関係性が浮き彫りになる。言葉ではなく、自らの指でピアノ史の重要な一ページを読んでいるのは、聴いていてとても羨ましい。
7月某日 ミラノ自宅
吉澤さんから8月15日演奏会のリハーサル録音が届く。ダヴィンチがミラノに滞在していた時期のミラノ・スフォルツァ家の音楽家たちの作品5曲を、賢順らが初めて西洋音楽に接したときを想像しながら、邦楽四重奏で書き直した。届いた録音は、失礼を承知で演奏があまりに上手過ぎると正直に感想を書く。あくまでも西洋文化も、西洋音楽も見たことも聞いたこともない人間が、自分の知っている言葉を使って、それらしいものをやろうとする。おそらく縄文弥生の時代から、日本人の典型的な姿であったであろう、外来文化への尊敬と真摯な姿勢の原点をそこに見る。現在はコミュニケーション技術が過度に発達して、結果が先に見えてしまっているから、こうすればよい、という方法論ばかりが論じられる。良しも悪きも日本的な精神論は、結果へ到達しようとするその過程を補填してきたわけだから、その部分が抜け落ちてしまうと、これから我々の文化はどうなってゆくのかと不安にもなる。
ともあれ、送っていただいた録音の演奏は素晴らしいので、すっかり気に入って何度も聴き入ってしまった。傍らで息子もすっかり聴き入って、珍しく神妙な顔をして「感動した」と呟き、「何だか中国の民族音楽みたいだ」と言葉を継いだのには、内心妙に感心したものだ。
ルネッサンス音楽と邦楽は想像通り、実に親和性があった。もっと邦楽でルネッサンス作品が演奏されるとよいと思う。恐らくそれは、邦楽の古典の先入観を払拭し、自らの演奏スタイルを見つける助けになるはずだと信じている。
7月某日 三軒茶屋自宅
ヴォクスマーナリハーサルより帰宅。一言、自らが書いた音の目指している方向を示すだけで充分だった。西川さんも歌手のみなさんも、皆揃って音の感受性が豊かで、表現の幅が深く広い。だから練習はとても楽しい。聴いているこちらも、鄙びた田舎ののど自慢大会に参加している気分になる。ちょうど土用のウナギの日に「ウナギを食べると死にますよ」と歌うのは愉快な経験であった。
7月某日 ボローニャ・ホテル
朝早くにミラノをでて、ボローニャにて8月2日作曲コンクール演奏会リハーサル。オーケストラとは、10月のクセナキス以来。再会を喜ぶ。
ホテルでヒジャブの妙齢とエレベーターで乗り合わせた。彼女は同行の年配のイタリア人婦人と英語で話していて、彼女たちと同じ階でエレベータを降り、歩き出したとき、かちゃかちゃと不思議な音がして、無意識にその音の方に目をやると、義足がアディダスを履いていた。
7月31日 ボローニャ・ホテルにて