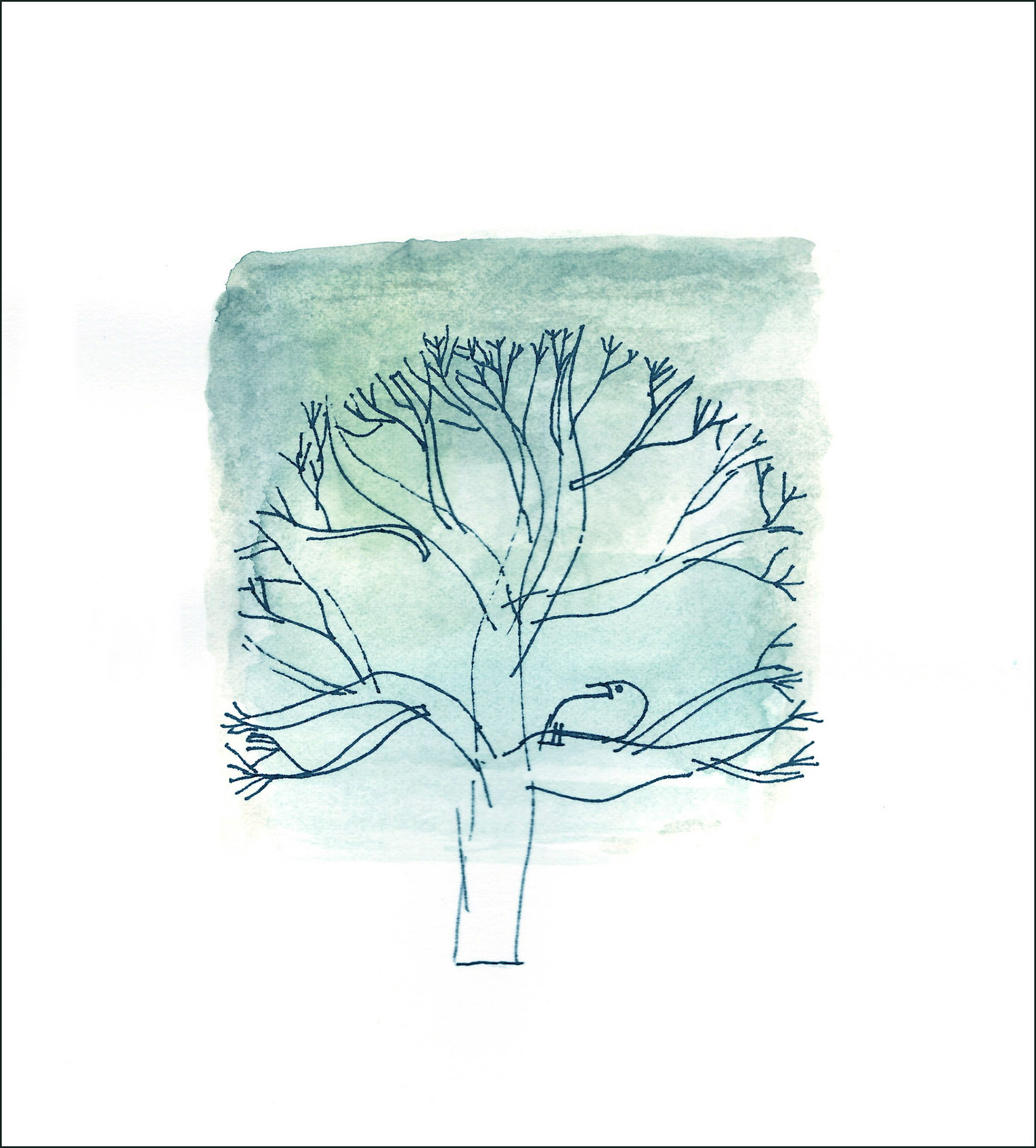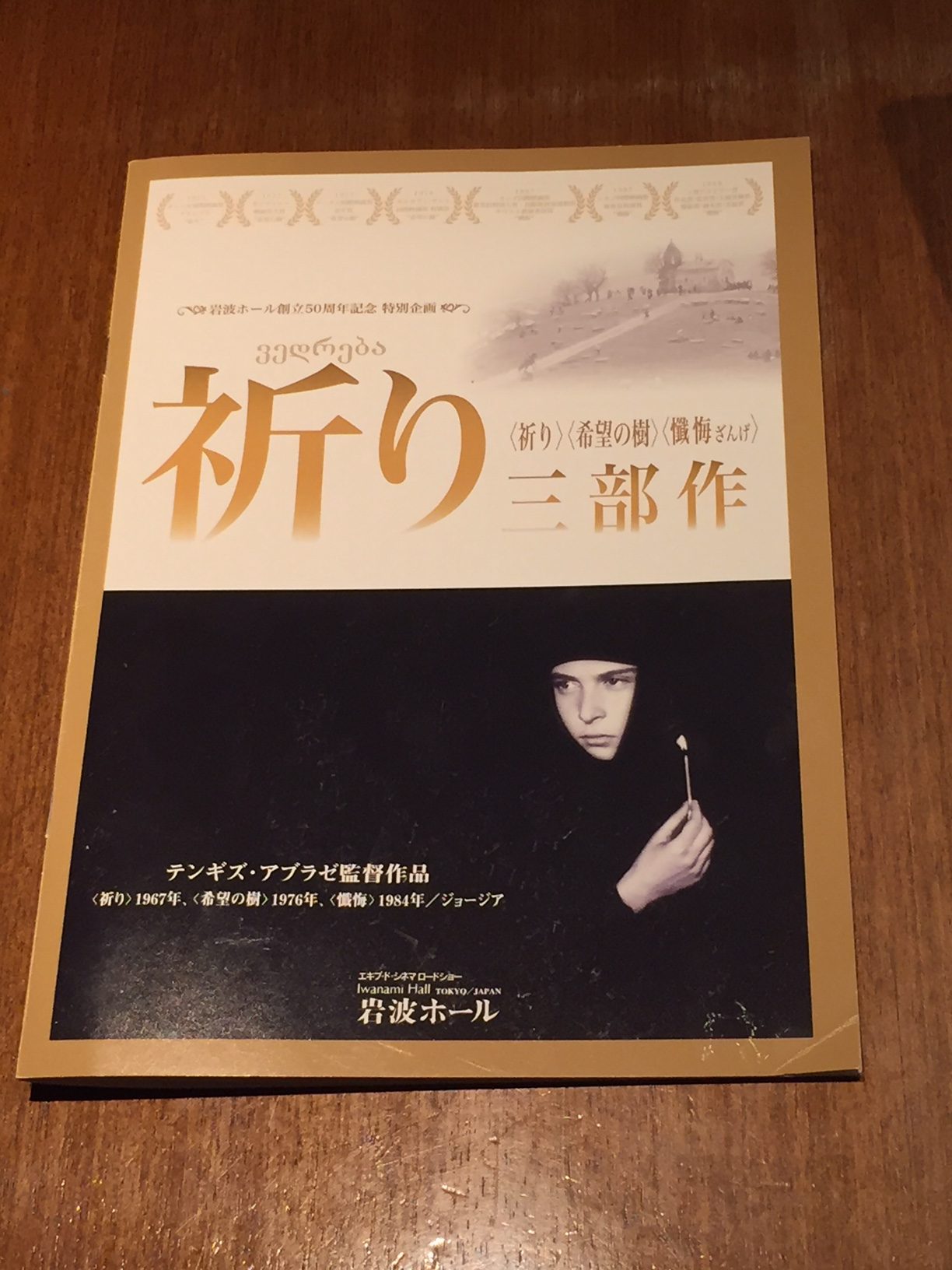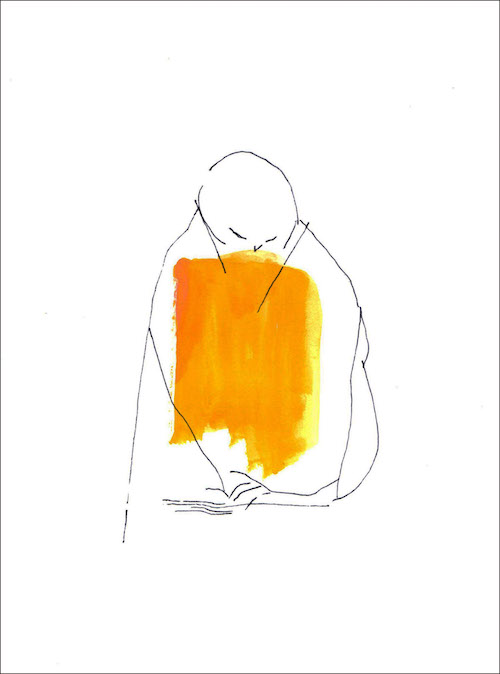日本からの留学生A君の耳の調子がよくないと連絡を受けて心配していた矢先、相変わらずの持病で自分も眩暈と吐気で寝たきりになり、36時間文字通り何も喉を通らない状態になっておりました。先一昨日から家人も日本で、明日からボルツァーノで新作の練習が始まるのでどうなることかと思いつつ、不死身のようにモソモソ起き出して仕事を始めているところが、不思議というか、我乍ら不気味と言うか。傍で心配そうにしている息子に申し訳ないと思いつつ、こればかりは、身体の方に優先権をやらなければ、後でまた酷い仕返しをされそうで、黙ってひたすら寝ておりました。36時間寝ているうち5キロ程一気に体重が落ちて、丁度良かったと喜んでいると、夕べくらいから食べ始めてすぐに1キロ戻ってしまいました。昔はいくら食べても太れなかったのが嘘のようです。
—
2月某日 ミラノ自宅
仲宗根さんから、打楽器と十七絃のための拙作についてメールをいただく。
「…すみれさんと一恵先生おふたりの音と時間が、深いところでつかずはなれず鳴っているように感じました…」。
今日から後期授業。新しい器楽学生クラスのイヤートレーニング授業が始まる。毎回一番最初の授業は、まず三和音を一音ずつ三人が目の前に並んで音を出していると想像させる。ドミソであれば、たとえばドソドソとかドソミソという風に、視覚化し抽出して聴く訓練をする。最初はこんな子供騙しみたいと笑っていた顔が、その和音がドミソシbレファ#ラレラド#と、八人が奏する八和音に膨れ上がると、学生たちは困惑の表情に変化する。音も多い上に真剣に音を聴こうとすると、教師は耳で音を聴いてはいけないと言うからだ。
どういうわけかイタリアの文部省によって必修扱いになった30時間のイヤートレーニングについて、他学校の教師が何をやっているか良く知らないが、元来指揮科と作曲科の生徒用に個人的に考え細々と教えていた課題を器楽の生徒にも、もう少し易しくしたものを映画音楽科の学生にも出しているのだが、それは音を耳で聴かない習慣の訓練に終始する。
音の姿を視覚化できるようになると、次第に音の質量や重量が感じられるので、それを自在に操れるようにするのが理想だ。そのためには、頭に鳴る音に耳を傾けてはいけない。自分の分身を造り上げ、分身に対しどうしろと指示を出す要領、とも何度となく言う。
例えば、八和音から四五個の音を無作為に抽出して、その音を歌わせてみると、最後の一つの音がどうしても聴こえなかったりする。
そんな時は目の前に縦に並んだ五つの窓を想像させ、歌えた音の窓を一つずつ閉じる。そして閉じられた窓を揃え、ぐっと遠くへ押しやらせる。例えば下から二番目の音が聴こえなければ、丁度君の鼻先あたりに音が飛び出てくるから見ていてご覧と言うと、意外なくらいすんなりと音が歌える。
メトロノームをかけ、わざとメトロノームとずれるようにした簡単なリズムパターンを弾かせるのも、リズムパターンとメトロノームの空間の間に、柵状のテンポが横に流れてゆくのを視覚化する訓練に他ならない。遅くから始めて、極端に早い速度まで柵が流れてゆくのを目で追えるようになれば、中庸の速度の揺らぎが明確に知覚できるに違いない。恣意的でない音楽的ルバートには有益だろう。正確に言えと、柵を横に一定の速度で流すところでも、本人の意志が使われている。
つまり、頭の中をそのまま目の前の空間に投影する感じかもしれないが、段々と音が見えるようになって来ると、当人たちには生れて初めての感覚らしく、とても面白がる。目を閉じて聴くのに集中するのも逆効果だ。耳に聴こえるのは、既に頭に残されている音だけで、新しい音はなぜかこの状態では入ってこない。耳が緊張していれば、聴こえるものも聴こえないという至極単純な理屈だが、緊張している耳を自らの意志で弛緩させるのは、そう簡単ではない。
簡単ではないが、たとえば時計をもたせ、ある一点を2分間黙ってながめているだけで緊張が解けることもあるし、指揮のレッスンなら、手袋を生徒の頭に載せて落ちないようにして振らせるだけでも、緊張した耳がすっと解けたりする。要するに、耳の緊張を別の場所に向けて、身体の無意味な動きを止めるだけで、焦点の精度が上がるようだ。
先日ブラームス2番を持ってきた生徒に手袋を載せて振らせると、最初はこんな状態で振るのかと文句たらたらだったのが、終いにはもうこれがないと振れません、と言うものだから、一同捧腹絶倒になった。彼はミラノの学校を終え、ジュネーブ音楽院に通っている。
音の重量を明確にするために、黒板に即興で和音の連なりを書き、それを生徒たちに弾かせて、生徒に振らせる。ドミソ・ソシレ・ドミソをハ長調で演奏させて、次には同じ和音をト長調で振ってもらうだけでも、結構むつかしい。ドミソのあとに、レファラドを足してやると音の間の稜線が少し繋がる。出来るようになったら、またそれを抜いてやらせる、という簡単なことから、連綿と転調が繋がる長いフレーズを振らせたりもする。
同じ課題を弱音でやってみたり、トレモロにして最強音でやってみたり、慣れてくれば、短音で休符を挟んで和音を繋げてみたりもする。音通し常に何某かの関連付けが必要であって、音の流れを起こすため、隣り合った和音間には、いくらか重量の傾斜が必須となる。その稜線を知覚し滑らかに繋げてゆく課題も、もちろん音の視覚化の一環で、これをが見えていない上で、いくら正しく振っても音は流れない。音はこの稜線の上をしなやかに伝いながら進んでゆくからだ。
2月某日ミラノ自宅
江戸時代初期に生まれた歌舞伎が瞬く間に人気を博し、ちょうど宣教師と一緒に日本を訪れていたスペイン人やイタリア人、ポルトガル人らが持ち帰り、それぞれ自国で大人気となった。ヨーロッパ各地の宮廷で日本人歌舞伎作者や演者を雇い入れることが流行し、彼らはもちろん日本語で上演していた。各地の宮廷では、土地の音楽家や作家たちもこぞって日本人教師について歌舞伎の作曲や台本の書き方を学んだので、程なくヨーロッパ中の芸術家たちは、流暢な日本語で作品を残すようになった。団十郎や近松の名前は神格化され、勧進帳や曽根崎心中は、ちょっとした文化人なら世界中の誰でもそらで言えるほどだった。江戸時代の各地の歌舞伎養成所には、世界各国から歌舞伎を志す若者がひしめきあっていた。
江戸時代後期、香港生まれの坂本龍馬らが倒幕を目指していたころ、正岡子規の近代歌舞伎は討幕運動の象徴とまでいわれ、日本中から熱狂的に受け入れられた。ちょうどその頃欧州留学中だった漱石や鴎外は、古典歌舞伎に端を発する全く新しい欧州歌舞伎を見出し、大きな衝撃を受ける。
大政奉還、王政復古を経て明治維新が成立し、それまで江戸や京都、大坂ばかりで新作初演されてきた事実に甘んじていた尾張が、ここぞとばかりに新時代の歌舞伎日本初演を名古屋で実現したいと名乗りを挙げる。近代歌舞伎の芸術監督で名を成した漱石とともに、市長自らロンドンやベルリンに赴き、名古屋公演実現に奔走した記録が残っている。漱石は、正岡子規の新作歌舞伎をパリで公演して大成功に導いた。
漱石の監督下で実現した欧州歌舞伎は、それまでの日本の宗教観生活観とかけ離れた欧州神話に基づく。既存の概念を大きく変えた名古屋、欧州歌舞伎公演は、新時代の訪れに湧きたつ民衆から熱狂的に受けいれられ、瞬く間に各地で公演された。歌舞伎名古屋公演には、目立たぬように子規も駆けつけ、感想を出版社の友人らに書送っている。
大成功に気をよくした名古屋は翌年早速、また別の欧州歌舞伎の演目を上演したが、その初演は惨憺たるもので「近松万歳」を叫ぶ聴衆の怒号にかき消された。もっともそれは、古典歌舞伎を支持する一派が切符を独占して、意図的に起こされた失敗談であり、翌日の公演からは前年と同じ喝采に包まれた。以降、名古屋は欧州歌舞伎の新演目を立て続けに初演することで一躍注目されるようになる。
数年後には、以前から長らく欧州歌舞伎に興味をもっていた坪内逍遥も、名古屋での新演目初演に関わり大成功を収め、逍遥はその後に大坂に開いた新劇場で、欧州から歌舞伎のみならず最先端の芸術全般を紹介するようになる。同じころ東京では、古典歌舞伎そしてその後欧州歌舞伎にも強く影響を受けた近代歌舞伎、欧州歌舞伎がまじった、華やかな歌舞伎文化の興隆をみるようになり、それが現在のミラノやパリの歌舞伎座の伝統に繋がる。後年、子規も欧州歌舞伎に大きく影響を受け、鴎外と子規も親しく交わるようになり、二人によって生み出された傑作も数多い。欧州歌舞伎は芥川龍之介はじめ、後代の芸術家にも大きな影響を与えた。現在も世界各地の歌舞伎座では古典歌舞伎、近代歌舞伎、欧州歌舞伎が人気演目であり、日本生れの芸術監督は大切な存在だ。申し訳程度に現代前衛歌舞伎などが公演されている…。
…
イタリアに初めて紹介された頃のワーグナーについて原稿を書き始めるが、噴飯物で断念。言わずもがな欧州新歌舞伎はワーグナーで、明治維新はリソルジメント運動を経たイタリア統一。香港生まれの龍馬は現仏領ニース生れのガリバルディ将軍。マリア―ニやボイトを漱石と鴎外、マルトゥッチを逍遥としたので、ヴェルディが子規になるあたりから話の辻褄の合わせようもない。
イタリア統一と明治維新はほぼ同時期で政治的な流れは通じる。ただ、イタリアはダンヌンツィオが19世紀終わりに生まれ第二次世界大戦のファシズムにも繋がった。日本のダンヌンツィオは三島由紀夫に相当するのだろうが、確かに三島がダンヌンツィオと同じ頃に活躍していたら、日本の芸術運動全体も政治も違った発展を見せたに違いない。
今朝フランス国際放送ラジオをつけると、首相の書いたナンとか推薦文のニュースが流れている。
2月某日ミラノ自宅
身体の麻痺が快癒して、息子はハノンの指の練習やら身体の柔軟体操にすっかり夢中だ。幼少時からバレエが好きだったのは義妹の影響もあるだろうし、今でも一番ペトルーシュカが好きなのは、劇場で黙役をやったからかも知れない。
バレエ音楽を聴かせろと余りにせがむので、指揮を勉強し始めた頃繰返し聴いたマタチッチの「ライモンダ」を久方ぶりにかける。丁度今年から指揮クラスに入ってきたウクライナ人のアルテンは、イタリアに来る前キエフの劇場でヴァイオリンを弾いていた。数えきれない程演奏しても「ライモンダ」は誰もが大好きだと言っていた。グラズノフの書法が複雑すぎるのはよく分かっているが、ヴァイオリン協奏曲と「ライモンダ」には心を奪われた。それに輪をかけてマタチッチとフリッチャイの音楽にどれだけ憧れたか知れない。何年振りに聴いても自分にとって相変わらず程遠く、距離は縮まっていないことに落胆する。
週に一度は実家に電話を入れていても、何かしら瑣事は起きる。最近は母の首が動かないとサポーターを嵌めていて仰天させられたばかりだが、その母から息子に緑と白の毛糸で編んだ綺麗なマフラーが郵便で届き、同日実家よりメールで首のレントゲン写真が届いた。「年齢的に骨がつぶれており、しかたがありません」とあり、「痛みはほんの少し残っていますが、だいじょうぶ」と結ばれている。
2月某日ミラノ自宅
大学前課程の作曲科の後期授業にやってきたフェデリコは、祖父と父と共に代々ピアチェンツァの教会つきオルガン奏者で、オルガンの演奏に役立てるため作曲を学び始めた。
戦前までオルガン奏者と言えばミサの伴奏はもとより、数多くのオペラアリアを集めた演奏会を催して、市民のオペラ人気を支えた。ヴェルディのオルガン編曲など数えきれない程残されているのはその為で、オルガンはどんな片田舎にもあるオーケストラだった。ジョヴァンニ・クイリチ(Giovanni Quirici1824-1896)などの「ミサ終了後の田園行進曲(Marcia Campestra per dopo la Messa)」、「軍隊小ポルカ(Polkettina marziale)」など、フェデリコから教わるまで、怪しげな表題の存在すら知らなかった。オルガンの世界では常識なのかも知れないが、二十数年住んでいて、19世紀イタリアオルガン音楽については、全く触れる機会がなかった。実際、街でよく聴かれるオルガン演奏会で取り上げられるのは、ルネッサンスからバロックまでのオルガン作品ばかりだった。
「イタリアのオルガン音楽の伝統は、フランスとは全く違うんです。あんな上品な代物ではなく、当時のヴェルディ人気を反映してか、ロンバルディアの19世紀のオルガンの多くに、大太鼓、シンバルや鉄琴が作りつけられていて、オペラのアリアやらマーチを賑々しく演奏して民衆を喜ばせてきたんです。あの手のレパートリーを弾くのは全然好きじゃないですよ、あんなどんちゃん騒ぎは邪道です。好きなのはもちろんバッハです。メシアンとかデュルフレとか、しっかりした現代オルガン音楽だってフランスにはありますし。もちろん色物の楽器は典礼での使用は禁止されています」。確かに、パイプが並んでいる上あたりに、外から見えないように大太鼓とシンバルが吊るしてある写真も見た。ちゃんと「大太鼓」と書かれたペダルがあって、それを踏み込むと、ドーンと大きな音がする。鉄琴は小さい音栓の前あたりに吊るしてあって連動する仕掛けになっている。街の教会にオルガンが奏でる「軍隊小ポルカ」を聴きにゆく、19世紀の民衆の光景が目に浮かぶ。
ピアチェンツァ生まれのダヴィデ・マリア・ダ・ベルガモ(Davide Maria da Bergamo通称ベルガモのダヴィデ神父1791-1863)というオルガン作曲家はより痛快だ。無数のオルガン作品を残しているが、どれもヴェルディ様式のオペラそのもので、凡そ神父の書いたオルガン作品とは思えない上に、しばしば彼の作品にはシンバル、大太鼓、鉄琴が活躍する。曲名も「血なまぐさい三月の日々、もしくはミラノの革命(Le sanguinose giornate di marzo, ossia la rivoluzione di Milano)」や「槌打つ鐘と理想の大火(Incendio ideale con campane a martello)」と奮っていて、イタリア統一前夜、混乱のるつぼに飲み込まれる市民の姿を、鉄琴やシンバルを雑じえてダイナミックに描写する。ヴェルディが統一運動の興奮と緊張漲る市民たちの心にどのように息づいていたのか、まざまざと実感させられる。すると、オルガンが今までとまるで違った輝きを放ちはじめるのだった。
2月某日ボルツァーノ・ホテル
2月末になると、毎年エミリオの長男ロレンツォに誕生日の便りを書く。それも、決まって一日遅れで。彼に最後に会ったのは、未だ家族でパリに転居する前だから、もう10年以上前になる。近況を尋ねると、すぐに返事が届いた。28歳の誕生日を中央アフリカ共和国で迎えたこと、家族から離れてこんなに早く時間が経ったことに愕いていること、現在はフランスの非政府医療団体ALIMA (the Alliance for International Medical Action)で働いていること、夏からは赤十字国際委員会で働く、などが書いてある。一昨年まで国連派遣でコンゴで働いていたが、いつ中央アフリカに移ったのか。28歳と言えば、自分が最初にエミリオに会ったころの齢だ。
Non credo, purtroppo, che il mio lavoro abbia una portata universale, ma, ad ogni modo, mi piace ed è utile.
この仕事で世界中のすべての人を助けられるわけではないけれど、好きだしね。何某か役に立っていると思う。
(2月27日ボルツァーノ)