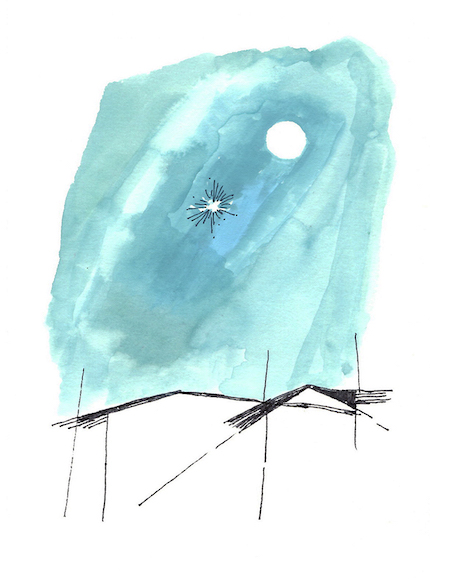この一か月ほど、週末の夜になると、線路の向こう側の運河沿いの駐車場で、屋外コンサートが開かれています。最初はアフリカン・ポップスなどやっていて、楽しんで聴いていたのですが、何しろ大音量で日付が変わる頃までやっていて、演奏中はこちらも落着いて仕事できる状況にないので少々困っていて、息子に愚痴ると、他の人は皆喜んでいるからでしょう、とあしらわれてしまいました。
まあ、尤もな話ではあります。
—
6月某日 ヴェローナ宿
ヴェローナのサン・ゼノ教会の傍ら、サン・プロコロ教会でブルーノ・カニーノのシューベルトD960を聴く。先月終わりに東京で会ったとき、このソナタを演奏するのは人生で2回目、本当に難しいとしきりに話していたが、それだけ作品に愛情が深いことがよく分かった。今度何時聴けるかも分からないので、思い切って家族連れでヴェローナへ出かける。一楽章が始まった途端に聴きながら涙がとまらず、何故涙が流れるのだろうとしきりに自問してみたのだが、答えが見つからなかった。倍音の豊かさ、和声感の充実、弱音の明瞭なキャラクターが際立つ。気が付くと外で鳥が甲高い声で啼いていて、まるでピアノとやり取りしているように聴こえる。シューベルトがいなければ、西洋音楽史は大きく変化していたに違いない。ブルックナーやマーラーの交響曲もなければ、プーランクの歌曲もピアノ曲も生まれなかっただろうし、ブラームスに至る和声の発展もなかったに違いない。誰に対して感謝しているのか分からないが、ともかくシューベルトという人がこの世に生を受けたこと、そして彼の音楽を我々に残してくれたことに深い感謝を覚えるばかりだ。
6月某日 ミラノ自宅
ヴェローナの宿で朝ベッドでラジオをつけると、べンバ元副大統領が国際刑事裁判所で無罪となったことに絡み、コンゴの賛成反対両意見をラジオフランス国際放送が流している。コンゴと言えば、エミリオの長男が国連で働いているので、コンゴの状況がニュースで流れると思わず気にかかる。
天気もよく、歩いてヴェローナの記念墓地まで歩く。入口で仏花を買おうとすると、お墓に供えるのかと尋ねられて、ここまで自宅用の花を買いに来る人もいると知る。ドナトーニの墓の花さしがとても小さいので、枝を短く切ってもらい、水がなくなってもそのままドライフラワーになりそうなものを選ぶ。最初の墓地を通り過ぎ、Piis lacrimus と書かれた神殿の教会の傍らから裏の墓地へ廻る。ドナトーニの墓は、ちょうどコインロッカー状に並ぶ一番奥の墓地の一番左、そこを入って左奥の右上、ちょうどとても暗いところにある。息子は大分昔に一度ここへ連れてきたときのことを覚えていた。
花を活け、積もった埃をウェットティッシュで拭った。ロウソク型のオレンジ色の電灯が切れていて、電球が緩んでいるのかとガラスの蓋を外すと電球が入っていないので愕く。ドナトーニの墓は、とても高い処にあって、梯子で昇ってゆくのだが、ここに墓を備え付けるのもさぞ大変だろう。墓の蓋には、重さのない重力、gravità senza pesoという、ドナトーニの好きだった言葉を表題にして、彼の曲名を散りばめて作られた詩が刻み込まれている。息子も梯子を上ってみたいと言うのでやらせてみると、salve! やあ!と声をかけ半分ほどで怖がって降りてきた。
この区画の前あたりには、「何某家の墓」と書かれた、立派な家づくりの豪奢な墓地が並んでいる。日本の公衆便所くらいの厳めしい石造りの建物が、刈り込まれた美しい芝生の上に点在している。そこに一つだけすっかり蔦に覆われた緑の墓地があって、近くで作業をしていた庭師にこれはどういうことか尋ねると、10年来一度もこの墓主は手入れに来ないのだそうで庭師たちはすっかり怒っていた。彼らは毎日頼まれた墓の掃除に来ているのだと言う。
入口裏の事務所に顔を出すと、墓地の管理事務所らしく、黒い服に身を包んだ中年の女性が一人残っていて、電球が外されているのは、契約を破棄したか、料金が未払いだから事務所が故意に外したものだと言う。年に18ユーロだと言うので、それならここで支払うと言うと、契約を取交した本人でなければいけないと言う。そのままIngenio clarisの神殿の石碑を訪ね、ドナトーニの名が刻まれている辺りに、供えきれなかった残りの花を手向けた。
駅に戻ると、まだ少し時間があったので、タクシーを拾って、ドナトーニ広場へ出かける。想像通り、タクシーの運転手はドナトーニ広場など知らなかったので、うろ覚えで、作曲家の名前の道ばかりが並ぶ音楽家界隈の、ヴェルディ通りとポンキュエルリ通りに挟まれた小さな広場があるだろうと言うと、犬に用を足させるような広場しかない、あんなところに本当にお前は行きたいのかと何度となく念を押される。
果たして、アパートの立ち並ぶごく普通の一角に、よく手入れの行き届きた小ざっぱりとした芝生に、小さな滑り台とブランコがあるだけの広場があって、確かにgiardini Donatoni, compositore, maestro di musicaと銘板が立っていた。もう18年前に亡くなった恩師で、ミラノに長く住んでいたが出身はヴェローナで、記念墓地のingenio clarisの石碑にも名前が刻まれているのだと言うと、それならせめてヴェローナのどこかの広場に名前をあげればよいものを、とタクシーの運転手に言われる。
ここは正確にはヴェローナ市内ではなく、サンタ・クローチェという地域だそうで、現在のインターネット地図でも、ドナトーニ広場がある場所はただ「無料駐車場」としか書かかれていない。ドナトーニらしくて悪くはないが、少し寂しい。昼食時だったからか、人気がなかった。
ミラノに着いて、マリゼルラに墓の電灯のことで電話をすると、それは恐らく急逝したドナトーニの長男名義になっていたのかも知れないと言う。そんな話から、ドナトーニは当然ミラノの墓地に埋葬されるはずだったのが、ふとマリゼルラが生前ドナトーニが死んだらヴェローナに埋めてくれと言っていたのを思い出して、急遽ヴェローナに場所を拵えた話やら、息子が7月、一週間ダブリンに出かけるのだが、ドナトーニの妻だったスージーがダブリン出身で、ウィスキーのjamesonの創業者の家の出だったことについて話し込む。スージーは、子供のころ住んでいた城のような家の写真を何度か見せてくれた。晩年のスージーは片時もウィスキーのグラスを手放さず、すっかり中毒になっていたが、或いはアイルランドの家が懐かしかったのだろうか。
家に着くと、息子はすぐにピアノを触っている。しばらくクレメンティのソナタを弾いていて、厭きたのか今度はフルートでマルチェルロのソナタを吹く。息子は日本風に一音ずつ感情を込めて弾いたりしないので、旋律はとてものびやかに響き、少しばかり羨ましい。
6月某日 ミラノ自宅
息子と連立って2年ぶりのべレグアルド運河を訪れる。それぞれの自転車を携えてサンクリストーフォロからモルタラゆきの電車に乗り込むと、周りには多くのアフリカ人が屯している。車掌が近くで検札を始めると、無賃乗車をしていたのか、彼らのうちの何人かは、辛うじて開いていた扉から外へ逃げ出してしまった。目の前に残った一人は、廻ってきた車掌に、切符を買う時間がなかったと言い、ここで切符を買うと言い張るが、差し出したクレジットカードにお金が入っていないと車掌に指摘され、次の駅で降ろされてしまった。
無賃乗車を容認するつもりは毛頭ないが、例えば彼らが船でアフリカから渡ってきた難民、もしくは移民だとしたらどうなのだろう。難民が鈴なりになった船が難破した、というニュースは数えきれない程聞いた。人道的見地から、つい最近までイタリアは彼らの上陸を許してきて、最近になって、イタリア政府は方向を転換したわけだけれど、彼ら難民が上陸を許され自由になった後どうしているのかは、よく知らない。
ラジオでは連日トランプ政権の不法移民政策のニュースをやっている。幼い子供たちが親から引離され泣き叫ぶ姿に際し、女性報道官は「サマーキャンプにゆくようなものですから大丈夫です」と応えなければならない。仕事とは言え、気の毒な気もする。
各国の難民、移民政策に意見を言える立場にはないが、政権が変わり政情が大きく変化したなら、自分だって「一週間以内に一億円税金を納めなければ不法滞在と見做す」と言われる可能性もある。二十年前に二年の約束で伊政府給費を取ってイタリアに留学した時も、政府から一方的に一年で給費が打ち切られた。そうして路頭に迷って食い繋いで暮らしてきて挙句、結局未だにミラノに残っている。当時奨学金が打切られた理由は何も知らされていない。だから、何時また「不法移民」と呼ばれる日が来るかもしれない、と覚悟している。無賃乗車のアフリカ人を嘲ることなど到底できないし、アメリカで家族が引離されたと聞けば、他人事とは思えない。ラジオを聴きながら、思わず涙がこぼれた。
間もなくアッビアーテ・グラッソの駅に着く。2台の自転車を下ろしていて、列車のドアが閉まりかけた。駅から自転車で5分も行けば、ベアグアルド運河沿いの自転車専用道路に出る。周りは見渡す限りの水田とトウモロコシ畑。澄み切った青空が心地よい。
昨年の今頃は、ずっと窓も開けられないニグアルダの小児病棟に入院していたから、こうして息子と二人でサイクリングが出来る日が訪れることなど、想像すら出来なかった。二年前と比べてすっかり成長した息子の姿を後ろから眺めつつ、思わず感慨に耽る。朝買ってきたピザとキッシュを水辺で齧りながら、息子は船着き場に腰を下ろし、足を運河の水に浸して喜んでいた。
後ろから息子の足の具合を注意深く眺めつつ、どこで引き返すべきか必死に見計う。彼に自信をつけさせたくて、体力の許すところまで頑張って走らせたいが、失敗して途中でリタイヤすることになれば、精神的に立ち直すのに時間がかかるのも分かっていて、慎重に後ろから様子をうかがう。息子は「疲れた、家に帰りたい、帰ろう」と繰返していたが、モリモンドの修道院に寄って、それからまた運河沿いに進んでカッシーナ・コンカの牛舎を訪れる。2年前に来たとき、ここで息子が牛の鳴き声を真似しているうち、乳牛たちが集まってきた。
ベザーテ辺りで休憩し、アッビアーテグラッソに向かって来た道を戻り始めると、息子の左足がするりとペダルから外れてしまう。足が疲れて力が入らなくなった時の典型的な症状で、こちらは内心生きた心地がしなかったのだが、気が付かない振りをしていた。
針の筵の思いで暫く走って彼方にアッビアーテ・グラッソの街が見えてきたところ辺りから、突然彼の身体は見違えるように活力を取戻した。魔法でも見ているようだったが、彼はすっかり元気になって顔つきも精悍になった。
果たして首尾よく駅にも戻ると、あろうことか乗るつもりだった列車が、突然運休とアナウンスが流れるではないか。次の列車まで1時間以上あるので、近くの喫茶店で時間でも潰そうと提案すると、息子はそれなら家まで自転車で帰りたいと言う。ここからミラノまで20キロ弱あるし、もう6時間近くサイクリングしたのでやめるべきと説得するが試してみたいと言い張るので、こちらも腹を決め、水と菓子パンを買い込んでミラノまで走ることにする。
極力早くならないよう先導しつつ、適宜休憩をとりつつのんびり走る。飽きもせず作曲家のしり取りをしながら走っていて、気が付くと目の前にミラノの街並みが迫っていた。信じられない思いで、すっかり逞しくなった息子に目を見張る。
真っ黒に日焼けした顔に満面の笑みを湛え、無事に家に着いて最初に息子が発した言葉が「また明日もまたベアグアルドにサイクリングに行きたい」、だった。
今月の初めには、学校に行きたくないと駄々をこねる息子を一喝して、パジャマ姿の息子を雨の中を抱きかかえ、トラムまで無理やり連れていったこともあった。トラムに一度は無理やり乗せたが、二人とも裸足のままだったで、息子も観念して学校へゆくと約束したので、一度家に戻ることを許しトラムを降りたところ、どこかのおばさんが、これをお履きなさいと靴下を渡してくれた。
父親に羽交い絞めにされながら、息子は誰かが警察に通報してくれると思っていたらしいが、こちらも腹を括って連れ歩いていたから、年度末でこの父親も余程必死なのだと誰もが理解してくれたようだ。
その一件のあって息子も学校にゆくようになったが、こちらは数日全身が筋肉痛に悩まされ、あの日はその後こちらも学校へ出勤し、一日授業をした挙句に夜はリハーサルまであった。ドナトーニのリハーサルに出かけて楽譜を開くと、持参したのはグリゼイの楽譜だった。
息子は今月、劇場の合唱団のインスペクターをやっている彫刻家のキアラの工房に足繁く通っている。まず最初に訪れた際に龍を作り、無心で土を触る時間が余程気に入ったのか、次に出かけた折には竪型ピアノを、そしてその次にはピアニストを作った。ピアノを作った時にもその精巧さに感心していたが、その後でピアニストを作った時には心底感嘆した。父親には到底できないのはさることながら、息子がピアノを弾く時に伝わってくる情熱と同じものを、息子のピアニスト像に見出したからだった。これはどういうことなのだろう。
6月某日 ミラノ自宅
マスターコースのテーマにミヨーを選んだ。本来はハイドンの中期の交響曲の続きをやるはずだったが、学生たちの集めたお金でオーケストラを借りるので、予算がぐっと少なくなった。もちろんオーケストラの弦編成を減らせば良かったのだが、せっかく編成を減らすのならば、本来その編成のために書かれた作品をやる方が、学ぶことも多いに違いない。今回はいつも一緒にやっている現代音楽アンサンブルが一緒にやってみようと話してくれたので、それならばと考えたのがミヨーだった。自分が今まで何曲か演奏した中で、演奏が決して易しくなかったが、作曲家として魅力的だと思ったので、小交響曲以外はどれも実際知らない曲ばかりだったが、アンサンブルが提示してきた予算に見合う編成の楽譜をレンタルした。
1918年、ちょうど100年前に書かれた小交響曲2番「牧歌」と1921年に書かれた3番「セレナーデ」。1番「春」は子供の頃から好きだったが、ハープあってフルートも1本多いので却下した。1919年作の「農機具」と1920年作の「花のカタログ」。それからマーシャ・グラハムバレエ団のためにアメリカで1944年に書いた「春の遊び」。1968年から69年に書けて書かれた「グラーツのための音楽」。「春の遊び」と「グラーツのための音楽」に関する資料は、殆ど見つからなかったし、実はもう1曲、「家庭のミューズ」室内オーケストラ版をぜひ演奏したかったのだが、アメリカの出版社が倒産していて、こちらは楽譜の所在が見つからなかった。
これだけミヨーの楽譜を続けて読んだこともなかったが、本当に素晴らしい作品であることに驚く。それぞれがまるで違った内容で、特に1920年前後の作品は視覚的、絵画的だ。ちょうどピカソやミヨーが一緒に仕事をしていたレジェのキュビズムを思い出せばよいかもしれない。もっと正確に言えば、ピカソはこれより10年くらい前にキュビズムの世界に到達していて、ミヨーが「小交響曲」やその他の作品を書いたころには、これらのキュビズムは既にダダに到達しかかっていた。ストラヴィンスキーの「火の鳥」が1910年、「ペトルーシュカ」が11年、「春の祭典」が1913年だから、キュビズムの時代は正確に言えばこれら3大バレエの時代でもある。
南仏の美術館で息子がピカソの絵を前に得意げに説明してくれたところによれば、キュビズムは、重力の解放と視点の多角化だと言う。その意味に於いて「小交響曲」などは、文字通りキュビズムの絵画そのものではないか。特に重力から解放されたコントラバスの面白さなど、合点のゆくことばかりだ。
多調とか複調、ブラジル音楽などと表面的に総括してしまうと、ミヨーの音楽の核心を全く捉えていない。本来の素材を、視覚化し、切り出し、別の色を付けて、別の視点から再度貼りこむ。絵画として二次元の素材を切り出して、3Dプリンターにかけ、視点や遠近法に変化を与えて、三次元の彫刻として再構成しているようにも見えるし、時には、その再構成した彫刻の断面図を切り出して見せているようにも見える。
端を丁寧に揃えたりして妙に体裁を整えたりせず、もとの素材の新鮮さを、出来る限り生かそうとする。そのちょっとしたぞんざいさが、魅力的だ。その意味ではダダの時代性との繋がりも感じる。順次進行する長いパートは、拡大された経過音だろう。
ただ残念なのは、完成した作品を視覚的に把握できるのは本人だけなのかも知れない。彼が自分で指揮している演奏では、どんなに音がぶつかる復調であっても、それらが円やかにブレンドされて響き合う。他人が演奏すると、往々にして耳障りな音に響く。これが音楽作品として成立する上での限界か。
作品が「六人組」の仲間にそれぞれ献呈されている「農機具」は、農機具博覧会で目にした「草刈機」「結束機」「播種機」などの、機能や構造説明、使用用途、性能や値段について書かれたテキストを歌うソプラノに、アンサンブルは機械的を模するオスティナートや、歌と無関係なロマンティックな旋律で軽妙洒脱に応え、社会の近代化、現代化への共鳴が明るく伸びやかに謳われる。
1919年のイタリアと言えば、ムッソリーニが社会主義に見切りをつけて、地方の農家を支持基盤に「戦闘ファッショ」を組織してファシズムへと駆け出した頃で、その後、イタリアでは未来派のダイナミズムに影響された、重厚な音楽ばかり聴かれるようになるのは対照的で興味深い。個人的には5曲目の「耕作機」が、「大地の歌」の「青春について」を揶揄しているように聴こえて仕方がない。冒頭のファゴットの旋律には、わざわざ「chanté-歌って」と註がある。
「農機具」と「花のカタログ」をプログラムに入れ「春の遊び」と演奏会にタイトルをつけたので、ミラノ市の公共公園事業部から後援が取れたとか。
(6月30日 ミラノにて)