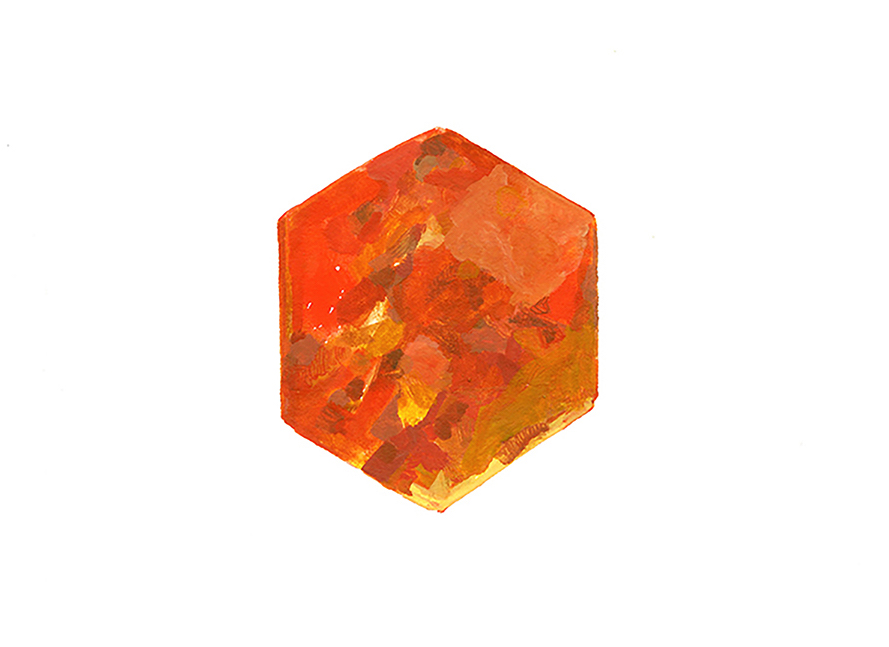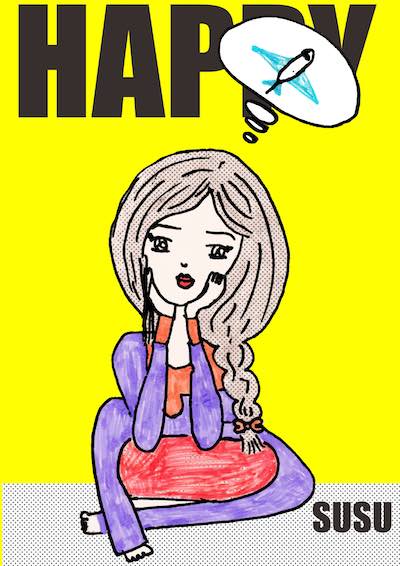ねえ、また家を手に入れましょうよ、と母が言い出した。それはとても唐突で、私はぐっと足を突っ張ってしまい、目の前に座っていた父の足を蹴ってしまった。出したばかりのコタツが持ち上がった。
がたんと音がして、私と父は母をじっと見つめた。母はさっき言った「ねえ、また家を手に入れましょうよ」という言葉が嘘ではないということを私たちに信じ込ませるように今までにないくらいに柔和な笑顔を浮かべていた。
今朝、私は学校へ行き、教室の入り口ですれ違った神谷先生に「お早うございます」と挨拶したときに、「お前、なんか大丈夫そうだな」と言われた。私は「はい、大丈夫だと思います」と答えた。私が小学生の頃、父がこんなことを言ったことがある。「うちはね、母さんが笑っていれば大丈夫なんだ」と。そして私は、母の笑顔で父が笑えるようになったら、父も大丈夫なんだ、とその時思ったのだった。
誕生日を迎えた六月からこの十二月まで、東京はオリンピック関連のイベントがあちこちで開かれて、なんだかそんな東京を引っ張っていくぞ、と先頭に立っていた都知事の人気が急に上がったと思ったら急に地の底にまで落ちた。安部さんのスキャンダルはものすごくうやむやになって、奥さんが校長をしていた小学校は知らない間に潰され、安部さんのお友達が作ろうとした獣医さんの学校は無事に作られる運びになった。潰されたほうと、作られるほうにどんな違いがあるのか私は知らない。私ならそんなスキャンダルまみれの大学になって絶対入りたくないと思うけれど、たぶん同級生に獣医になりたい、という子がいたら「別にその学校に罪があるわけじゃないから」とか言って、偏差値さえあえば、平気で受験しそうな気がしてものすごく嫌だ。
それはたぶん、マクドナルドのハンバーガーを「いったい、どこの肉を使っているのかわからないし、農家や牧場の人の仕事を値切りまくって、こんな値段にしてるんだよ、きっと。だって、百円バーガーなんて、まともな材料使ってたら、出せなくない?」なんて話しながらも、「安くて、そこそこ食べられるから」という理由だけで、平気で通っている私の行動と実は地続きだと思うから、私自身はえらそうには言えない。言えないけれど、そのことは忘れずにいたいと思う。そして、そのことを忘れないために、私は今日からマクドナルドにはいかない。今までも、他の同級生たちに比べればあまり行かなかったと思うが、今日からは絶対に行かないようにする。どこまで続くか解らないけれど、いま私は私自身にそのことを高らかに宣言したのだった。そして、もし、今日クラスの誰かが「帰りにマック行く?」と誘ってきたら、なんといって断ろうと考えている。いまの政府に意義をとなえるためにいかない、なんて言っても誰もわかってくれないと思うし、なんとなく政治的な話をしないように穏やかに暮らしたいと思うから。私の毎日は愛ではなく優しさでできているのかもしれない。何が優しさで何が愛なのか、その境界線もよく知らないけれど、うちが貧困層だということを知り、神谷先生と話している間に、同級生たちと私との間には優しさばかりが満ちあふれているのだ、と感じる瞬間がたくさんあった。手をさしのべてくれる人はほとんどいないが、優しい笑顔で対応してくれる人はたくさんいる。
そして、コタツは我が家の優しさだと思う。少し寂しかったり、少し落ち込んだりした私を救ってくれるだけの温かさがある。そして、母がその冬コタツを出すタイミングは、すべて母に一任されていて、私たちが母に「そろそろコタツを出して」と言ったことはない。そう思う前に、というか、そう思った瞬間に必ずコタツは出されていた。いつも、ああ、今日は寒かった、と思いながら家に帰るとコタツはリビングにどんと置かれていた。それを見ると私は一瞬身動きがとれなくなってしまう。このコタツにこの冬もやられてしまうのか。コタツを中心とした家族のなかに今年も足を入れるのか、という妙な思いがわき上がって、その温かさを躊躇してしまう私がいる。
でも、私がコタツに抗えたことは一度もない。本気で抗ったことさえない。いつも、一瞬躊躇した後、私はその躊躇をなかったことにして、足を入れる。なんなら、誰よりも早くそこに足を入れようとする。だって、コタツに入って話をしながら、みかんを食べたり、笑いながら同級生の話をしたり、お茶を飲んだりすることこそが家族だと私は思っているからだ。
神谷先生から、大丈夫そうだな、と言われ、家に帰るとコタツがあり、制服姿のままそこに足を入れていると母が帰ってきて、みかんとお茶を用意して一緒になって食べていると、父が「ああ、神田の古本屋まで歩いて行ってきたよ」とドアを開けて、私が「神田の古本屋って、歩いて行けるの?」と驚いていると、父が「歩けるよ、地続きなんだから。二時間かかったけど」と笑い、母があきれた顔をして、「一緒にみかん食べましょうよ」というと父は「鯛焼き買ってきたよ」と茶色い紙袋をひょいと見せて、コタツに入って、三人家族がコタツに揃ったのだった。
そこで、母が言ったのだ。
「ねえ、また家を手に入れましょうよ」
その言葉に、私と父は気持ちが明るくなった。十二月の寒空の下だけれど、コタツがあって家族が揃って、また母が新しい家を手に入れようと提案したことで、神谷先生が言ってくれた「大丈夫そうだな」が「もう大丈夫」に変わった気がした。私たちは大丈夫だ。いつもの冬と同じように、コタツに入って足が触れあった瞬間に私たちは大丈夫になった。父がコピーライターという仕事に絶望し、母がお気に入りの家を出たことに絶望し、親の絶望に私が絶望してしまった時間をなかったことにはできないのだろうが、コタツがあれば大丈夫なんだと私は思ったのだった。家族が揃ってコタツに足を突っ込むことができるのなら絶望にのまれてしまうことはない。
私はいつものように鯛焼きを頭から食べている母と、しっぽから食べている父に聞いてみた。
「ねえ、今度はどんな家に住みたいの?」
母は鯛焼きをもぐもぐと食べながら、しばらく考えて答えた。
「そうね。今度はさつきが気に入った家ならそれでいいわ」
しっぽを食べていた父が笑った。(了)
投稿者: yamaki
ツインピークス再び
若松恵子デビッド・リンチ監督の連続テレビドラマ「ツインピークス」の新シリーズが、25年ぶりに制作されて、日本でもWOW WOWで7月から18回にわたって放送された。
毎週土曜日の夜9時からの放送を楽しみにして、夏が過ぎ、秋が来て、冬も深まってくる11月の終わりに最終回を迎えた。
かっこつけて言ってるわけじゃないけれど、わけのわからない世界をテレビで見るなんて、ほんとに久し振りで感激だった。謎は謎のまま投げ出されて、パチンと電気を消すように最終回が終わってしまった。あの時ああなったあの人はその後どうなったのだろうなんて気になるけれど、ほったらかしである。
細部を何度も見直して、謎解きすることもできるのかもしれないけれど、大人をも怖がらせる映像に触れただけで、まずは満足だった。邪悪なものは心底邪悪で怖かったし、毎回最後に登場するバーでのバンドの演奏シーンは、この世のものとは思えないあやしさを秘めていて魅惑的だった。
25年経って、ますます異端なデビッド・リンチの感性に感心した。あるいは、映像技術の発達によって、彼の頭の中の映像化が過激に可能になったのだとも言えるのかもしれない。
世の中は快方に向かっていない。邪悪な者が相変わらず動き回っている気配がするのだ。主人公のクーパー捜査官を演じたカイル・マクラクランも、25年後のローラを演じたシェリル・リーもいい具合に老けている。この間の世の中の厳しさを反映して、顔に年月が刻まれている。そんな感じも良かった。
別腸日記(10)冬の客(前編)
新井卓北へ向かう衝動は、なぜ、いつも突然にひらめき胸を締めつけるのか。冬の旅には、そくそくと迫る寂しさと仄白い希望のようなもの、それらがないまぜになった静謐な感情がある。
今年も、遠野に冬が来た。寒波の到来は例年よりも早く、まだ十一月というのに、土淵や附馬牛など、すこし上がったところの村々は一面の雪景色となった。
この時期、心待ちにしていた酒が、酒屋やスーパーの冷蔵庫に並びはじめる。酔仙酒造の「雪っこ」は、酵母が生きたまま封入された濁り酒で、気温が高い時分は発酵が進んで破裂するおそれがあるため、晩秋から翌春までの期間に限って出回る季節限定の酒である。
二〇一〇年ころ初めて旅してから、山深い自然と人々の心のあたたかさにすっかり魅了され、何十回となく遠野に通ってきた。宿に困っていると、いつもにこやかに家に迎えてくださる藤井家を訪れるとき、冬ならばいつも、この「雪っこ」の一升瓶を提げていくことにしている。藤井さんの家は遠野からすこし南東の、気仙郡住田町にある。いつ、どうして「雪っこ」を手土産にするようになったのか忘れてしまったけれど(たぶん自分で飲みたかっただけだろう)、緑色のさっぱりした瓶を差し上げたときの、奥さんの満面の笑顔は、どうやらこの酒が一家にとって特別な存在であることを物語っていた。
藤井家の広々とした客間、あるいは数年前に農機具置き場を改装してしつらえた宿泊所に荷物を下ろしてほっと一息つくと、もう夕餉の支度が調っている。藤井さん夫婦と息子さん夫婦、孫のルイ君(八歳くらいの頃はよくコタツの中で裸になっていたが、最近はすっかり立派な中学生になった)、そしておばあちゃんとの食卓はとても楽しい。おばあちゃんは気仙語を話す。遠野言葉に少し慣れてきた耳でも、南部と伊達の違いなのか、山あいと海辺の隔たりなのか、その言葉を聞き分けることはたいへん難しい。なぜかわたしのことを「先生」と呼ぶのは、いつか農繁期によく来ていた大学の先生と間違えているらしいことが後で判明したが、まあいいか、と思い先生のふりで通すことにした。それに当時はアルバイトで大学の非常勤講師もやっていたから、とりあえず身分詐称にはなるまい。
「雪っこ」は、おばあちゃんの好物でもあった。──「雪っこ」さ、まづ、先生に。しづかに、飲んでください。
わたしはこの、しづか(静か)に、という言葉がとても好きだ。気仙語なのかどうかは確かめていないが、しづかに、という確かめるように一端沈み込む語と、ぐい飲みに首をかがめ黙して酒をすする感じが、いかにもぴったりしているし、何か儀礼的な所作の趣さえ出てくるではないか。そして、細かいことだが「まづ」は絶対に「づ」であり「ず」ではないのである。
(つづく)
しもた屋之噺(191)
杉山洋一庭に鎮座している背の高い樹があって、10年以上住んでいて未だにちゃんと種類を調べていないのですが、夏の暑い盛りは青々と茂る葉で家をすっぽり日陰に隠してくれ、秋から冬は同じ樹とは見紛うほど、葉を落とした姿はふと見上げると思いの外頼りなく見えます。今目の前を見上げると、か細い骨の向こうに、美しい橙色の満月がてらてら光っています。冬らしい深い漆黒の夜空の背景と相俟って、その光景が妙に心に突き刺さるのはなぜでしょう。
—
10月某日 三軒茶屋自宅
練習を始めて1時間くらいすると、まるで手の力がすっかり入らなくなる。恐らく先日までのんでいた抗生物質をやめたばかりで、体力が落ちていたからだと思うのが、力が入らないのが、これだけ怖いものかと愕く。
息子がここ暫く自転車に乗らないのは、道の途中ですとんと力が入らなくなるからだそうだが、右足で適当に漕げばよいと思っていたが、それほど簡単ではなかった。力を入れようとしてもぐにゃりとして入らないというのは、恐怖以外の何物でもなかった。このまま倒れるのではないかという恐怖が先に立ち、神経が引き攣る思い。オーケストラの皆さんにも申し訳ない。
それでも、本番はこちらが倒れてもオーケストラの皆さんが何とかしてくれると信じて、何が起きてもよい積りで指揮台に立つことができた。演奏者を信頼できるということは、これほど有難いことはない。
堤先生のどこまでも誠実な音楽と、新鮮な響きの成田くんが織りなす音楽の深さ。緊張で倒れそうになっているこちらを、いつも温かく励まして下さる木村さんの優しさ、どこまでも音楽を深く掘り下げようと練習の度にさまざまな提案をしてくださる児玉さん。共演者の音楽の技量の深さに助けて頂いた。
二重協奏曲では一柳先生の音楽の深さには圧倒され、「クロノ」に、会場を突き抜けて飛び出してゆく湯浅先生の火の玉のような「コスモロジー」を目の当たりにした。
10月某日 三軒茶屋自宅
日本で医者をしている家人の友人が、杉山は指の足りない左手をいつも隠していると家人に話したそうで、余計なお世話だと憤慨していたが、別に本人は特に隠そうと思っているわけでもなく、指がない姿など自慢するものでもないし、殊更誰も見たくもないはずだから、あまり人の目に触れないようにしたいと無意識には思っているかも知れない。
成行き上、曲がりなりにも指揮などさせて頂くことになり、それも現代作品に関わる機会が多くなってしまうと、左手を隠してなどいられない。否が応でも左手でキューサインを出すことは多く、その度に内心醜くて申し訳ないとは思っているが、無い袖は振れない。
キューサインのみで7分ほど音楽を作ってゆく箇所があって、リハーサルで両脇の演奏者から左手のキューサインが何本出ているか見えないと何回か言われると、単に見づらかっただけに違いないけれど、心の底から消え入りたい心地に駆られそうになる。リハーサルからの帰途、自分が今の息子と同じくらいの頃、息子よりずっと酷い対人恐怖が続いていたことをぼんやり思い出す。自分でも嫌な心地に自分が飲み込まれてしまう感じとは、確かにこんな感じだったと思う。
まあ、当時に比べれば良くも悪くもすっかり太々しくなって、お陰で何とか生き長らえている。
11月某日 三軒茶屋自宅
町田の実家に戻った折、期せずその昔買った水牛楽団のカセットブック「休業」を見つける。カセットは思いの外良い音で、美恵さんや悠治さん、それに楽団の皆さんの若々しい声が記録されていて、思いがけず再会した忘れていた時間を前にして、感激に震える。今の自分の歳とほぼ同じ頃の録音だけれど、今自分がやっていることは、当時の彼らのように、何某か意味を残せるものなのだろうか。渋谷のユーロスペースに「水牛楽団」を見に行った時、目の前に黒マントを羽織った時代がかった妙な男性が居たなあ、と父が笑う。言われてみれば、そんな気がしてくるから不思議なものだが、確かにあそこに黒マントの男性が居ても、全く違和感はなかった。
母は、小学校5年から3年くらいひばり合唱団で歌っていたが、中学に入って酷い熱を出してやめたそうだ。続けていれば良かったと思っていたが、孫がミラノで歌っているのを見ると何か繋がっている気がして嬉しいのと言う。
11月某日 三軒茶屋自宅
林原さんの演奏会を聴きにゆく。お世辞を言う間柄ではないのだけれど、実に素晴らしく、忘れ難い演奏会だった。林原さんがチベットの子供たちへの教育支援をしているのを聴いていたこともあり、「馬」というチベットの民謡をもとにした小品を書いたので、それを聴きに行ったのだけれど、会場にはチベット関係者が沢山集ってくださり、ニマさんには純白のカタまでかけていただいた。演奏も素晴らしかったし、思いがけずチベットの皆さんと触れ合えたことも嬉しかった。
それに輪をかけて、林原さんと吉田さんの演奏が、素晴らしかった。別に素晴らしいでしょう、と見せる演奏ではないのだけれど、音の向こう側にある林原さんの人の温もりが、そのまま伝わってくる演奏会で、このような演奏会は誰にでも出来るものではないと思う。
目の前で微笑むチベットの皆さんが、それぞれどんな経験を経て今自分の目の前にいるのかと思うと、思わず胸が一杯になった。一月に日本へ戻る際の再会を約束して、会場を後にした。
11月某日 ミラノ自宅
自分は日本人だし、イタリア語を学校で聞くだけで気分が悪くなると言っていた息子が、随分元気になって、学校にも毎日通うようになり、友達と電話で話すようにもなった。息子が神経質になのは家が静かすぎるからだ、等と周りから文句を言われたが、確かに家にはテレビもないし、ラジオを付ける以外は必要以外音楽も殆ど聴かない。家の中が静かであるほど、頭でいろいろ音楽も聴こえるし、あまり飽きることはないというのは、こちらの言い分であって、家人に言われると亭主関白が過ぎるらしい。
そういう気質のせいか、日本の生活は本当に音に溢れていると思う。消防車も救急車も、サイレンを鳴らした上に、マイクのボリュームを上げ、反対車線を走ったり、信号無視して通過することを詫びながら走る。こちらでアナウンスしながら走る緊急車両は見たことがないし、第一緊急車両が詫びるというのは、どうもしっくり来ない。反対車線を走ることを伝えなければいけないのなら、サイレンは要らない気もするし、サイレンを付けて緊急車両が通るのであれば、両車線共に道を譲るべきではないのか。
電車のホームのアナウンスも、発車を知らせるジングルのメロディーも、動く歩道の終わるところで無表情に流れ続けるwatch your stepのテープ音声も、渋谷のスクランブル交差点のように、何枚もの電光掲示板から同時に大音量の広告が流れているさまも、まるでパチンコ店から洩れてくる音の洪水のように見える。
それなのに電車に乗れば、殆ど誰も話もせず、話し声はとても低く抑えられていて、今年くらいに漸く気が付いたが、リュックは後ろに背負うのではなく、前に抱えて持つことで、スペースを節約できるので奨励されていた。こちらでリュックを前に抱える場合は、特にスリを警戒している場合くらいなので、それに見慣れていると、皆がリュックを抱えて電車に乗る治安の良い東京の姿は初めは異様に映った。
地下鉄のホームで行き先が分からなくて困っているお年寄りがいて、助けてあげたいけれど、全く東京の地下鉄は分らないのでどうしようもなく、無人化された長いホームで漸く見つけた駅員に尋ねようとしても、駅員は列車を定刻通りに発車させることに必死で、彼女は無下にされたまま話すら聞いてもらえない。
こんなことを感じるのは、20年以上外国に住んでいるからに違いなく、東京に住めば慣れてしまうことばかりだろうが、東京だって自動アナウンスを流すようになるまでは、目の見えない人に普通に手を差し伸べていて、「インフォメーションカウンター」まで行かずとも、駅員は誰でも気軽に乗客の相談に乗ってくれていた気がする。
地下鉄駅の光景にショックを受けたせいか、今回ミラノに戻って空港のバゲージクレームを出た瞬間、ざっと耳に入ってきた雑多な会話の響きに、言葉にできない安堵を感じた。そんな深い安堵を感じた自らに、改めて打ちのめされた。だから、単に無音を欲しているのではなくて、雑音で何かが見えなくなったり、聴こえなくなったりするのが厭なだけ、というのも、やはり亭主関白か。
11月某日 ミラノ自宅
未だに日本語を話すのは、とても苦手だ。息子が生まれてからずっと父子はイタリア語、母子は日本語を通して来たが、去年くらいから時々息子が何故父子でイタリア語を話すのか、イタリア語は苦手だと反抗するようになった。自分は先ず日本語で考えてからイタリア語を話している、と言い張るが、これは客観的に見ていて流石にあり得ない。彼がここ暫く病気と学校の事で辛かった時はこちらも日本語で返していたが、彼が元気を取り戻すと、何時の間にか会話もイタリア語に戻った。
こちらは日本語、特に仕事場で話す日本語はとても苦手だ。イタリア語、英語、日本語のどれが一番仕事が楽かと言われれば、これは断然イタリア語で、第一外人がイタリア語を話すというだけで印象は良いだろうし、それも敢えてこちらの作戦で、最初から相手の懐に飛び込んでゆくような、イタリア流の付き合い方をする。簡単に言えば敢えて馴れ馴れしく話すわけだ。20年以上も住んでいれば、馴れ馴れしくとも、下品でない言葉を選ぶことも出来るし、深い表現をしたい場合もある程度は伝えられる。第一馴れ馴れしくとも、使う構文の形式は至って丁寧だから、それだけで相手からすれば言葉へのリスペクトは感じられているはずだ。リハーサルで疲れてきた時などには下卑た表現を使って、相手を笑わせたりして、指揮者対演奏者という形を一切作らないように心を配っている。英語なら大して話せるわけでもないので、微細な表現の綾について心配する必要もない。相手がネイティブでなければ、お互い何とか通じればいいだけだし、相手がネイティブなら、この人は話せないから仕方がないと諦めてくれる。
日本語になるとこれはどうして良いか分からない。日本語の表現そのものもむつかしいし、日本人とのコミュニケーションもあまり上手ではないのかもしれない。イタリア人相手にやるように、馴れ馴れしく相手に飛び込んでゆくと誤解を生むことが良くあって、オーケストラの中の同級生や学校の友人から注意される。これはとても有難い。
最近は出来るだけていねいに、でも慇懃無礼にならないように気を付けながら話しているが、丁寧な言葉づかいを紡ぎつつ、相手の胸の中に飛び込んでゆけるような表現、人間関係を作るのはとても難しい。オーケストラで何時も助言してくれる演奏者がいて有難く思っていたから、こちらは尊敬できる友人のつもりで接していたが、相手は単に仕事相手として助言していただけで、誤解を受けたこともある。恐らく日本に住んでいたら、そんなことは当たり前なのかも知れないが、難しいものだと思う。そうしてリハーサルを積むなかで指揮者対オーケストラの関係に落着きそうになる時があって、必死に回避を試みる。オーケストラの一員になりたい、というとそれは無理と一蹴されるだろうが、それでもそれを目指してみる。オーケストラ全員を引き受ける責任など到底引き受けられない。結局どのみち無責任なだけか。
11月某日 ミラノ自宅
ミラノのドゥオーモ裏、大通りから脇に入ったコルソ通りにも、ファシズム建築の小さなガレリアがあって、どこまでも青空が澄み渡る朝、そこの2階でガブリエレと近代イタリア音楽について話し込む。
イタリアで1880年代前後に生まれた作曲家は「80年世代の作曲家」とまとめられる。レスピーギ、カセルラ、マリピエロ、ピッツェッティ、ザンドナイ、アルファーノの名前がよく知られているが、ガブリエレのところへわざわざ足を運んだのは、この世代の作家を取り上げるに当たって、自らを納得させたかったからだ。1943年に作曲されたカセルラの弦楽、ピアノと打楽器のための「協奏曲」作品69は、晦渋な音楽で、所々に驚くほど美しい旋律が浮かび上がっては、荒々しく断ち切られる。曲頭にダイナミズムが大胆に用いられていて、最初はこれこそファシズムのプロパガンダに迎合した作品かと訝り、随分悩んで何度も聴き返してみたが、聴けば聴くほど鳥肌が立つほど美しい。カセルラはファイズムに当初から囲み入れられていた作家で、悔いて改めて作品71「平和のための大ミサ曲」を書いたのが1944年のことだ。この第二次世界大戦の極限の状況下で「協奏曲」がどういう経緯で、カセルラや音楽家たちが何を考えて作曲をしたのかどうしても知りたかった。
「協奏曲」の最終楽章で現れ断ち切られる天啓のような美しい旋律は、まるで断絶された扉が空に向かって開かれたかのように「大ミサ曲」冒頭にそのまま受け継がれる。
ファシスト党がいわゆるローマ進軍を行い、政権を取ったのが1922年のこと、ムッソリーニがナチス・ドイツとPatto d’acciaioいわゆる「鋼鉄協約」を結んだのが1939年、それによって行きずり式に第二次世界大戦にイタリアが参戦したのが1940年。Tre asseいわゆる「日独伊三国同盟」を結んだのが1940年。連合国軍がシチリアに上陸したのが1943年7月10日、ムッソリーニが身柄が拘束され幽閉されたのが1943年7月27日。イタリア王国が連合国軍に無条件降伏したのは9月8日で、ムッソリーニがナチスに救出されたのが9月12日。ナチスの傀儡政権「イタリア社会共和国」いわゆるサロ共和国が建国されたのが、9月23日。そのままイタリア全土は内戦に突入し、イタリア国内に残ったドイツ軍と社会共和国軍が連合国軍を相手に戦争を続けた。
当時カセルラが滞在していたローマが連合国軍によって解放されたのは44年6月4日。まさにナチス・ドイツ軍によってローマが占拠されている中で「協奏曲」は書かれ、恐らく連合国軍によって解放された後、もしくはその前後に書かれたのが「大ミサ曲」となる。社会共和国、ナチスが連合国に降伏したのが1945年4月25日、現在イタリアの祝日「解放記念日」になり、ムッソリーニはその2日後に捕らえられ射殺された。
彼ら80年世代の作曲家たちが、どれだけファシズムに貢献したのかとを理解するためには、ファシズムとナチズムとの相違を明確にしておかなければならない。ナチスは先進的な芸術一般を「退廃芸術」と称し排除していたのと反対に、ファシズムは当初からイタリア未来派と繋がり、先進的、未来志向の芸術を歓迎していたし、カセルラやマリピエロなど当時国際的な芸術家とされていた作曲家に対して重要なポジションを与えて積極的に庇護し、文化活動の展開に務めたと言う。当時「国際的文化人」と理解されたのは、特にフランスでの活動が認められる場合だった。「ドイツとイタリアの関係は、実に複雑なんだ」とガブリエレは笑った。最終的にはムッソリーニがヒトラーに保護される立場となったが、ヒトラーが当初手本にしたのがムッソリーニであって、その反対ではなかった。
1904年生まれのペトラッシの作品を、カセルラが指揮したのがペトラッシ29歳の時。その直後33歳の時には、ペトラッシが既にヴェニスのフェニーチェ劇場の総監督に据えて「新芸術」を強く後押ししたのは、ファシスト党の意向を強く反映していたのだと言う。尤も、1939年に鋼鉄協約でヒトラーと結ばれるまで、ファシズムに対して明確に反体制を唱える文化人は本当に少なかったのだと言う。殆どが皆何等かの形でファシスト党に関わっていて、例えばダラピッコラでさえ少なくともファシズムを否定する立場には当初なかったのだと言う。
当時オペラから近代音楽までを一手に引受けていた大手出版社がリコルディ社で、1960年代まで長く保守系の経営陣が構えていた。そのため30年代頃から「現代音楽」に特化し、ダルラピッコラを始め、より先進的でファシスト体制に好意的でない作曲家が集まりだしたのが、ツェルボーニ社だったと言う。1950年代基本的に保守系で構成されたイタリア政府は、芸術文化一般を急進派で構成された諮問委員会に一任した。その影響は、例えばイタリア映画のネオ・リアリズム運動などを思い出せば分かりやすいだろう。
その音楽部門責任者が、先日亡くなった、パルチザンの闘士としてナチスと戦い名を馳せた音楽学者ルイジ・ペスタロッツァだった。彼は大臣などの役職は一度たりとも引受けなかったが、長くイタリアの音楽事情に深く関わった。1960年代に、リコルディの経営陣が保守系から急進系へと大幅に刷新されて、ツェルボーニの作曲家たちは、一地方出版社だったツェルボーニよりも、より契約体系の保証できた巨大出版社リコルディ社に移ったのだと言う。その中ではドナトーニは最後までツェルボーニで粘った一人だ、とガブリエレは笑った。
どうしてレスピーギは、特に政治的犯的に捉えられるのか、と尋ねると、恐らくそれは、余りに地方色が濃いからではないか、と言うので、少し意外だった。ガブリエレ曰く、カセルラやマリピエロのような「国際的作曲家」ではなく、少しばかりロシアに留学はしたものの、飽くまでもイタリア国内でしか活動していなかったレスピーギは、単に広い視点で捉えられることが少なかったのではないか、というのが彼の意見だった。
彼とずいぶん話したお陰で、靄がかかっていた思いがすっきり晴れた。ナチスがローマを占拠していた時のカセルラも、戦後解放されたマリピエロも、是非演奏してみようと思う。そこから何か当時の彼らの思いが、或いは見えてくると信じている。
(11月30日ミラノにて)
イカの日
璃葉夜明け前の空の下で、私鉄に揺られながら漁港へ向かう。四角い窓から見える空はまだ暗く、薄雲が広がっている。電車のなかでぬくぬく温まった体は、漁港へ着いてものの数秒ですぐに冷え切ってしまった。
友人Zの誘いによって、やっと実現したイカ釣りは、想像以上に楽しいものとなった。早朝に起きることに慣れさえすれば、漁港には何度でも訪れたい。
海から吹く風のつめたさにすっかり動作が小さくなったが、この日の気候はいつもよりも暖かいようで、集まった釣り師たちは、今日あったかいよねえ、などと呟き合っていた。
乗合の釣り船が沖へ動き出したとき、ようやく地平線から顔を出した太陽がゆっくりと空を昇っていく。太陽は雲の向こうから優しく海面を照らし、波は黄金色に呼応していた。船がスピードを上げるたびに水しぶきがかかり、心身ともに凍る寸前だったが、雲が去り青空が広がると海の色もたちまち碧くなり、体も芯から暖かくなってくるから、世界は太陽の力で動かされているのだと実感する。
私の釣りのセンスが皆無なのか運が悪いのか、なかなか釣れないままおよそ6時間が過ぎたころ、ようやく疑似餌に食いついたイカがゆらゆらと紺碧の水面の奥から浮かび上がってきた。その風貌はエイリアンのような、摩訶不思議なかたちである。このような方々がわんさか漂っていることを考えると、やはり海のなかは宇宙空間と同様なのかもしれない。
釣り上げたイカの透き通った乳白色が美しい。その半透明の体から勢いよく噴き出すイカ墨のどす黒さといったら! バケツのなかで墨を吐き出しながら暴れるアオリイカを眺めながら、一層美味しく食ってやろうと決意する。すっかり上機嫌になり、再び釣り糸を垂らすと、またもや竿が勢いよく曲がり、もう一匹釣れたかと心躍るが、姿を現したのは気味の悪い妖怪のような魚だった。アカヤガラという衝撃的なフォルムをした朱色の細長い魚は、刺身はもちろん、良い出汁が出ることでも有名らしい。周りの釣り師たちがニコニコ笑顔を向けてくる。私は潔く妖怪アカヤガラをZに譲った。
バケツの中のイカはすっかり落ち着き、底で怪しく動いている。私は何となく、このイカとずっと目が合っているような気がした。ぎょろりとしたその丸い目玉は、自身の行く末を解っているようだった。
友人3名で釣り上げた7杯のイカは、程なくして出張寿司職人の手に渡った。その宵、イカ達は信じられないほどの美味しい寿司と刺身になり、たくさんのヒトの胃袋のなかへ吸い込まれていったのだった。
能舞台に舞うジャワ舞踊
冨岡三智去る11月25日に奈良春日野国際フォーラム「甍」能楽ホールでジャワ舞踊を上演する機会を得たので、今回はその話。この上演は日本アートマネジメント学会第19回全国大会の関連企画「能舞台に出会う」の一環で、能舞台の魅力を引き出すというのがテーマだった。私自身、能舞台でジャワ宮廷舞踊を舞ってみたいという希望を長らく持っていた。能をインドネシアで紹介する事業を実施した(水牛2007年2月号参照)のも、両者の空間感覚に通じるものを感じていたから。今回その希望がかない、しかも学会のサポートもあって照明の使用などをホールに認めてもらうことができたのを嬉しく思う。
●『ブドヨ〜天女降臨〜』
これは今回の私の上演題目で、ジャワ宮廷女性舞踊『スリンピ・アングリルムンドゥン』の前半を1人で舞った。スリンピは4人の女性による宮廷舞踊、ブドヨは9人の女性による宮廷舞踊の種類で、演出や衣装が異なる。この曲は今ではスリンピだが、本来はブドヨとして作られた。振付やステップにブドヨの儀礼的な性格を色濃く残しており、かつ、ブドヨとしても最も古い時代のもので、演目としても「重い」。だから、今回はブドヨとして扱い、ブドヨの衣装であるドドット・アグンを着た。
能舞台で上演するならブドヨだと決めていたのだが、それは、ブドヨの起源が神代に天女が天界の音楽にあわせて舞ったことにあるとされているから。鏡板の松に降臨する天女が舞うとすれば、それはやはりブドヨだろう。ジャワの王はブドヨ上演を通じて王国の安寧を祈念する。それらの点が、天界の調べにのせて国土の繁栄を祈念しつつ、宝物を降らせながら昇天していく『羽衣』の世界に通じるように感じる。
ジャワ宮廷舞踊は四方舞であり、大地を踏むステップが多いブドヨには特に呪術要素が強い(水牛2004年4月号参照)。能と言えばその摺足歩行が注目されるが、たまに床をドンと踏みしめる音に私は惹きつけられる。ジャワ宮廷舞踊にも、床を踏み鳴らすステップがあるのだ(その音からドゥブゥッと呼ばれる)。このステップは民間舞踊にはなく、宮廷舞踊を特徴づけるものになっている。
●柱と床
ジャワ宮廷の儀礼舞踊は、プンドポと呼ばれる壁のない建物の中央の、四本の柱で囲まれたホールのような空間で上演される。この4本の柱(ソコ・グル)は高い屋根を持つ建築全体を構造的に支えているだけではなく、日本の「大黒柱」という言葉のように徴的な意味合いを持つ。4本の柱が四方:東西南北を象徴するとされるのは能舞台と同じである。高い屋根の梁には祖霊神が棲んでいるとされ、4本の柱は天と地=プンドポの四角い空間を垂直につなぐ。ジャワ王家ではソコグルは1本の巨木を4分割して採られるが、それは、世界は結局1つの軸でつながっていることを示しているかのようだ。ソコグルの柱の中には布で覆われ、供物が置かれているものがあるが、それはその柱に霊が宿っていることを示す。
能舞台とプンドポの空間感覚には通じるものがあると前に言ったけれど、少し違う部分もある。プンドポでは柱が重視される一方、能舞台では床面の方が重視なのではないかと今回感じた。舞台上では必ず白足袋を履くのも、床面の保護という物理的な理由以上に、清浄さを尊ぶからのように感じられる。ちなみに、プンドポの床面は王宮なら大理石である。そして、本来なら裾にバラの花びらを巻き込んで舞う。だから、裾を蹴り出すたびにバラの花びらがこぼれ舞い散って、まるで散華のように見えるのだが、日本だと能舞台でなくても室内でこの演出をするのは難しい。
能舞台の床面は想像以上に滑らかで、体重をかけると自然と滑り出してしまいそうだ。この床上で『安宅』や『石橋』のような激しい動きができることに驚く。ケンセルという横に滑る動きが、何のひっかかりもなく流れていく。もちろん、それは足袋を履いているからこそだが、長く引きずる裾(ジャワ舞踊の衣装)に載って滑る(無論、そんなことはしてはいけない)よりも、よく滑る。橋掛かりを退場する時に客席の方を向いてケンセルしたのは、天空を滑るような感覚が表現できそうに思ったからだった。
その橋掛かりだが、実際に見える以上に遠いと感じた。実際に歩いた時間は揚げ幕を出てシテ柱まで1分、そこから舞台中央前方まで30秒であり、ジャワ宮廷舞踊の上演時には5〜8分くらい入退場に時間をかける私にとっては、時間的に長いわけではない。けれど、思った以上に橋掛かりから観客も舞台も遠く、違う世界から1人で舞台に上陸していくという感覚が確かにあって、少し怖さを感じた。
●照明
今回の舞台で私がこだわったのは、地明かり以外に照明器具を持ち込むことだった。能では〜ジャワ宮廷舞踊でも同じだが〜、舞台全体をフラットに照らした中で上演し、スポットライトなどオプションの照明を使うことはしない。そこに、見せるための舞台芸術(ジャワで言うトントナン)ではないという古典芸能の矜持を強く感じる一方、世阿弥なら使ったかもしれない…と、不遜にも思うのだ。私は2007年にジャワでブドヨ公演をしたときにも照明を使ったことがある。舞踊の振付を分析すると、当時の演出家も照明やズームカメラ(映像なら)など様々な技法を使いたかっただろう…と確信できる点があったからだが、賛否両論の反応があった。今回も賛否両論あるだろうな…とは覚悟している。
今回照明をつけたのも、第一に振付自体に陰影を感じさせるものがあるからだが、第二に、空間的、雰囲気的(神秘的だとか)な奥行を作り出したかったからである。地明かり照明は舞い手の姿をはっきり見せる一方、空間をフラットに見せてしまう。しかし、能が描くのは幽玄な空間であり、ゆがんだ時空の裂け目に顔を出す非日常の世界なのだから、現代のような舞台技術があれば世阿弥もそれを利用するのではないか?と私には思えてしまう。
私は橋掛かりを通る時に鏡の間から一筋のように光を照らしてもらい、また、舞台にいる時は遠く上手から一筋の光を投影してもらった。このような使い方は意外だったようである。実のところ、私が照らしたかったのは自分自身ではなくて床だった。私は平面的な世界に影を落とす存在(天女だけど)として舞台に登場したかった。能舞台では柱よりも床が重要なように感じると前述したけれど、光が差し込み、地面で照り返し、それが対象物に当たって影ができてこの世が切り開かれていくような空間が能舞台には合うのではないかな…と私には思えた。それが成功しているか失敗しているかは見た人の判断によるのだけれど、少なくとも私自身が見たいと思う能舞台空間を演出しようと思ったことは間違いない。伝統芸能の舞台でも、演者の技量だけでなく空間自体を見せることを考えても良いのではないかと思っている。
ダンス現在
笠井瑞丈9月から『ダンス現在』と言う自主企画を始めました
天使館を会場とし電球とちょっとした照明で行う公演
この『ダンス現在』と言う企画名は15年前に笠井叡が
天使館での若手公演として使用していた名前です
父の作った事を少しづつ
自分なりの新しい形で
発信し引き継ごうと思う
花粉革命を踊る
それも同じこと
ダンスをする事
ダンスをする場
やりたいこと
実験的のこと
普段の公演では出来ないこと
照明の打込
音楽の演奏
作品を磨き
自分を磨く
踊る場所を探す
踊る場所を作る
少しづつ理想な形を作っていきたい
そんな公演
すこしづつ
すこしづつ
これから続けていこうと思う
少しづつ
少しづつ
地球に
侵色していけば
白の和紙に
色を垂らす
ダンス現在vol.1
小暮香帆とのデュオ作品『Duo』を上演しました。
ダンス現在vol.2
上村なおかソロ作品『Lief』を上演しました。
告知
ダンス現在vol.3 2018年1月14日 21日
『曉ニ告グ』
笠井瑞丈×鯨井謙太郒
どうぞおろしくお願いします
仙台ネイティブのつぶやき(28)思い出のブラウス
西大立目祥子 セーター売り場で、いかにもウール100パーセントという感じのざっくりと編んだセーターが目にとまった。いいなぁ、ウールって。思わず手をのばしたら、となりの30代前半とおぼしき女性2人の会話が耳に入ってきた。「これいいけど、ウール100でしょ。縮むからいや」
へぇ。確かに縮むし、虫食いにもあいやすい。でも、空気をふくんだ弾力感とか、細い繊維がより合わされて生まれる独特のやわらかさは、何ものにも変えがたい。私の中ではセーターの素材としては最上位にくる繊維だ。
とはいっても、このごろは高価なせいか、アクリルとかポリエステルとかの混紡が主流になってきた。衣服全体がそうだ。そういう服を着て育てば、繊維の質を気にとめることは少なくなって、それよりはデザインや色を重視するようになるのかもしれない。
振り返ってみると、衣服の素材の違いに気づいたのは10歳のころ。それは、母のお手製のブラウスを着せられていたからのような気がする。私の子ども時代は、既成の子ども服はそう多くなく、母親が家族のためにミシンで服を縫い上げることは、ごくごく普通のことだった。特に夏服はそうだった。婦人雑誌には型紙の付録がついていて、母はデパートの包み紙の上にその付録を広げ、ルレットという小さな歯車状の道具を転がして型紙をつくった。数日後、学校から帰ると、ミシンに掛けられていた目新しい布は私の夏の服になっているのだった。
おしゃれな母にとっては、ミシンを踏んで子どもたちの服を縫うことは大きな楽しみだったのだろう。夏休みの家族旅行のときはワンピースを、海水浴のときは砂浜で着るガウンをつくってくれたし、仲のいい友だちと二人で着るおそろいの服も縫ってくれた。
いまもよく覚えているお気に入りの夏のブラウスがある。襟先がギザギザと左右で4つに割れているデザインで、おもしろい襟だね、とよくほめられた。私が気に入ったからなのだろうか、同じ型紙で違う生地を使って母は何着か仕立ててくれた。シャリ感のある赤い木綿の半袖、白に緑の水玉模様の薄手の木綿、オリーブ色のウール地を使った八分袖…。袖の長さが違うだけで同じかたちなのに、薄い生地はよく風をとおし、少し厚手の木綿は体にまとわりつくことがなく涼しくて、ウールは断然暖かい。一方で化繊のワンピースは袖つけのところがチクチクする。袖を通し身にまとって1日を過ごす中で、子どもなりに素材による着心地の違いをかぎわけていたのだと思う。
さすがに裏地のついた上着とスカートは、母の手に余ったのだろう。幼稚園入園のときは、知人がオレンジとベージュの千鳥格子のウール地をツーピースに仕立ててくれ、小学校入学のときは連れられて近くの洋品店に行き、薄紫の生地でこれまたツーピースをつくった。
じぶんで縫った服も、よそで縫ってもらった服も、母は容赦なく批評をした。特に評価の低かったのが小学校の入学式にきた薄紫色の服で、「色選びに失敗した」とか「仕立てが田舎くさい」とか何度もいっていた。じぶんで縫ったブラウスにも「生地がぺらぺらで安っぽい、ああ失敗」とか「いい生地はやっぱり違う」とか、独り言のようにいうこともあった。
いまこうして文章を綴っていて驚くのは、数十年前の服のディテールをじぶんがしっかりと覚えていることだ。からだが大きくなる時期だから何年も着たわけでもないのに、生地の色味や質感、ボタンのかたちまでが鮮明に記憶に残っている。手ざわりや身にまとったときの感触を、からだが覚えているからだろうか。
服の組み合わせも思い出す。オリーブ色のウールのブラウスには、えんじ色のタータンチェックのスカートを合わせた。赤い木綿のブラウスには、茄子紺の麦わら帽子をかぶった。そして緑の水玉のブラウスには、小さな刺繍の入った紺色のプリーツスカートをはいた。
考えてみると、タータンチェックも、麦わら帽子も、プリーツスカートも(いまはスカートははかないけれど)ずっと好きできたものだ。中学生のころに買ってもらったツィードのコートやニットのアンサンブルも、いまだに好きなアイテムだし、何よりはっきりした色合を好むのは母譲り。母の好むものを与えられる中でそれを受け入れ、服に対する母のつぶやきを聞かされながら、いつのまにかじぶんの好みをかたちづくってきたということなのだろう。
こんなふうに書くといかにも仲のいい親子と思われるかもしれないけれど、そうではない。長じて私は生意気な娘となり、母とはことごとくぶつかり、共感を持って話をすることはほとんどないままにいまに至っている。
それでも、ハンカチ1枚を選ぶときでさえ、白やピンクといったやさしい淡い色合いのものではなく、黒と赤と黄のチェックというようなまさに母の好みの柄を探すじぶんに、苦笑してしまう。
先日、近くのショップで千鳥格子のコートを見つけた。わぁ、大好きな千鳥格子だ。エンジとベージュの柄に心が踊ったものの品質表示のタグを見てがっくりくる。ウールの混合率はわずかに10パーセント。これがいまの時代の肌触りなんだろうか。
誰もがサンタになりたがっている
さとうまき大学生だったころ、サンタクロースのアルバイトをやったことがある。某デパートのクリスマスプレゼントをサンタが届けるという。綿の付け髭が何とも安っぽい。こんなの信じる子どもがいるんかと。当時の僕は20歳。痩せていて貫禄もない。
しかしだ。ピンポーンとドアをあけると子どもがウルウルしている。
「お母さん、嘘つかなかったでしょ!」と得意そうな母親。高学年の子どもですら、サンタを信じているんだ。
軽トラの助手席でお弁当を食べるとき、付け髭を外していたら、「子ども達の夢を壊すといけないので、髭はつけたままにしてください」しぶしぶ、髭をすこしもちあげて、もぐもぐとお弁当を口にもっていって食べたのを思い出す。
僕は、小学校に入ったらサンタの存在はおかしいとさとった。うちには、当時お風呂を薪でくべていたけど、小さな煙突しかない。あんなとこから入ってくるはずはないし、玄関は戸締りが厳しかった。一度夜に泥棒がはいったことがあり、父ちゃんも、かあちゃんも爆睡していて誰も気が付かず、朝居間が足跡で荒されていた。それ以来、戸締りには神経質だ。
父ちゃんに町のお店で、「あの赤い車買ってほしい」といったらそっくり同じものがクリスマスに枕元に置いてあった。どう考えても、父ちゃんがおいておいたとしか思えない。そこで、ある日、「サンタクロースなんていないんでしょ。父ちゃんがやったんでしょ」と問いただした。親は、あっさりと認めてしまった。ちょっとがっかりだ。
なので、こんな子供だましのサンタなんかあほらしいな、子どももだませないなと思っていたが、意外と、子どもは素直だった。それ以来、いつか、本物の髭が白くなってサンタになりたいというのが私の夢となったのだ。
東日本大震災では相玉県の騎西が双葉町の避難所になっていて、炊き出しに行くのにサンタの格好をしてJIM-NETのがんの子どもが描いた絵を使ったチョコを配りにいった。しかし、全然受けない。子ども達が喜んでくれると思ったのだが、実は数日前に、ノルウェーから見るからに本物のサンタっぽい人がやってきたらしい。
そのままの格好で、2歳半の息子にプレゼントを渡そうと家に戻ってピンポンとおすと、息子が出てきて、「あ! パパがサンタの格好している!」と見破られてしまった。
その息子も小学校2年生。普段会えないので、誕生日とクリスマスのプレゼントはどうしても贅沢なものに。こないだは任天堂のスイッチがほしいというからいいよいいよといったものの、さすがに、4万円もする。もう少し安物で何かないかと元妻に聞いてもらった。
こないだ、本人に会ったときに、「クリスマスに何がほしいんだい? ただし、一万円を超えたらだめだよ」といったら、「上限をきめるって、パパがサンタさんなの?」って聞いてきた。いままで、パパの貢献をアピールするために、クリスマスプレゼントはサンタじゃなくて、パパからだ! のつもりだったのに、元妻は、サンタさんからといって渡していたのか! と思えば腹立たしいのだが、「こいつ、サンタを信じているのか?」と思うとちょっとほほえましい。
「サンタは、みんなにプレゼントをくばるでしょ。君だけに高いものを買えないんだよ」と分かち合いの精神を教えたつもり。
ぜひ、クリスマスのプレゼントにJIM-NETのチョコを忍ばせて、助け合いの精神を注入してください。
チョコの申し込みはこちら
https://www.jim-net.org/support/choco_donation/
一ダースの月
北村周一奥湯河原温泉にあそぶアーティスト河原温氏がえがく一月
崇高のひかりあまねくカーテンの隙間に踊りはじめる二月
震災が何かを変えたと思うまで絵を描くのみにすごす三月
絵空ごと熱しやすくて校庭のすみに小暗きタネまく四月
段階的明暗技法は身につかず気づけば嚏止まらぬ五月
『洗濯バサミは攪拌行動を主張する』の絵を新しく描きたす六月
バブル弾けても肩幅ひろきW着こなし夜明けまではしゃぐ七月
花煉瓦はなれんがためにふれ合うを意味をもとめて病める八月
置き去りにされしメールが和蘭のひかりの粒を夢みる九月
遮断機をくぐりし友が鉄道の錆びのにおいに噎せる十月
有名になる前のきみに逢いたくて階段駆け上がる十一月
駅頭に聖少女らが客寄せのベルをリンリンと振る十二月
音を手渡す
高橋悠治ジュリア・スーのために書いたピアノ曲『夢蝶』のおかげで莊子を思い出した 偶然見つけた陳育紅の詩『印象』は周夢蝶の病後の印象 やせほそり/線香/けむり/雨ひとすじ/柳の枝/芦の茎/冬の太陽のようにほそり という回復のプロセス そのなかの芯のしなやかさが 甲虫の触角のような世界へのかかわりと しっかりした骨組みを失わない この詩の呼び起こすイメージを音で想像してみるうちに 周夢蝶という名から莊子の斉物論篇の「蝶の夢」を読み返した 荘周と蝶はちがう世界を生きている そうした物の変化は 人が蝶になるように記憶をつみあげるのではなく 忘れることで別な世界が立ち上がる それを音楽とすると こんな曲もできるかもしれない
自分で弾かないで 他のピアニストに渡したのははじめてだと思う それからジュリア・スーの演奏を聞いたとき 自分の楽譜は見なかった ことばで説明もしなかった これも莊子の物化に倣ったと言えるかもしれない
拍のような外側の時間尺度にしばられず 相身互いですすむ楽譜にも その都度のやりかたがある ひところのように作曲家の論理で図形楽譜を作ることはしないで 演奏者が慣れた記譜法をすこし変えて使い お互いの音符の長さが合わないようにしてあれば 自然と拍から離れる senza tempo という指定もできるが 何も書かなくてもそうなれば もっといい
大きなアンサンブルでは そうはいかない 指揮者がそこにいる さてどうするか いろいろためしてみたが なかなかむつかしい 田中信昭のように長くいっしょにしごとをした人には何も言わない 一度演奏された曲は 他の人が再演しても やりかたの一部は受け継がれる そうでないと……
東京佼成ウインドオーケストラの委嘱で『透影』を書いた それぞれの楽器の音が聞こえるように タイミングをずらす 最初3連音や5連音を使って書いたが 拍の始まりだけがいっしょになるのと 楽譜が無用に複雑になるので すべて16分音符で書き 演奏者が自分の感じでタイミングを早めたりおくらせて ずれをつくり さらに指揮者がテンポを不安定にするように指定してみた
透影は几帳に映る人影 寝殿造の室内は足元の灯台しかなく 几帳は個別に置いていたらしい
最初の練習に参加して希望を伝えると 個々の演奏者については問題がなかったが 指揮者が管理をゆるめ きこえてくる音に反応してテンポを変えるほうは なかなかむつかしかった 指導をやめて司会進行役をつとめるのは職業倫理に反するのかもしれない 均等に書かれた楽譜を ロックのような16ビートにせず リズムやテンポをたえず崩していくのも そろって書かれている音符をばらばらにするのも 指揮する身体には耐えられないのかもしれない
オーケストラと指揮者は対面している 自立した音響体であるオーケストラに 指揮者が外部から介入して システムをかき乱す これはオートポイエーシスからまなんだやりかただが 数世紀の経験をもつ現実のシステムを変えるのは 別なシステムを立ち上げるよりむつかしい
それでも コントラバス・クラリネットやバストロンボーンの荒々しい低音 ピッコロ・トランペットや木鉦の切り裂くような高音をひさしぶりに聞いたのは クセナキスを演奏していた頃のような内蔵の快感ではあった
莊子秋水篇には「魚の楽しみ」がある 魚でないのに どうして魚の楽しみがわかるのか 論理ではない 感覚でもない 魚と荘周が近くにいて ちがう楽しみを生きている 直感も神秘もない
2017年11月1日(水)
水牛だよりひと月ほど前倒しになったような寒さがしばらく続いたので、一部だけ冬の衣服を出して、半袖はしまいました。日本では四季があり、ひとつの季節は三か月です。その三か月を前の季節から次の季節かけての移行と考えれば、三日ごとに次の季節に向けて移っていく。それなら、持っている衣服で100通りの組み合わせができればいいわけですが、計算は計算で楽しいけれど、そうは単純にいかないのが毎日の現実の気候ですね。きょうの東京の午後は温かく、少し歩くと、白い山茶花が満開でした。もう冬、です。
「水牛のように」を2017年11月1日号に更新しました。
はじめての登場は溝上幾久子さん。以前からの知り合いであり、彼女のエッチングの工房を見にいきたいと思って、実現しないままです。最近のSNSでおもしろい投稿を見て、書いてもらおうと思ったのでした。今月に限ってではありますが、溝上さんと璃葉さんの絵の色合いが似ているのは偶然ではないかもしれません。
冬になるとチョコレートがおいしくなります。さとうまきさんのJIM-NETのバレンタインチョコには最初から寄付してきました。生死にかかわる重いことがらですが、そこに軽さとパンクが加わると抽象性が高まって本質がよく見えてきます。チョコレートの原料はカカオで、カカオの学名はギリシャ語で「神の食べ物」を意味するのだそうです。
それではまた!(八巻美恵)
心象風景としての山
溝上幾久子このごろ、就寝前に「心象風景としての山」を画題とした習作を続けています。
実際に山にでかけるわけでもなく、山の写真を見るわけでもなく、その言葉どおり、こころに浮かんだ山を描いていく試みです。こころの山とは、記憶のなかの風景でもありますが、必ずしも記憶の再現というわけではありません。
画材は、クレパスにしました。クレパスはクレヨンよりも柔らかく、パステルよりも粘性があります。水彩用紙は凹凸があるので、クレパスをかなり強くこすりつけて描画します。そのせいなのか、紙の上で、色と色が混ざり合い、思いもよらなかった色が現れてくることがあります。
描き始めるときには、頂が紫色で、薄い群青の空ととけあっているような山の風景を描こう、などと一応プランはあるのですが、手を動かしていくうちにすぐさまその青写真は崩れてしまいます。必ずと言っていいほど、自分が何を描こうとしていたのかがわからなくなります。画面を思うようにコントロールできなくなり、谷底をさまようような心細さに見舞われてしまうのです。
それでも、意識はずっと「風景」におきながら、こころに浮かびつづける色と形を重ね、画面のなかで道をさぐるように描き進めていくと、やがて、画面が輝きだす瞬間がやってきます。そこではじめて、ひとここちついて紙の上の散策を終えるのです。そのときに絵は、すでに山ではなく抽象的な色と形の重なりにしか見えません。けれどそれは、わたしにとってはまぎれもなくわたしだけの山なのです。
心象風景をさぐろうとする試みは少しの苦しさと少しの喜びをもたらします。求めているうちは、まだしばらくは続けてみようかと思っています。こころがざわついているときには、この散策が気持ちを落ち着かせてくれると気がついたのは、思いのほかのことでした。誰の胸中にも山水があるというのは、ほんとうのことなのだと思います。
仙台ネイティブのつぶやき(27)山の暮らしを継ぐ
西大立目祥子先月、山形で地域づくり活動をする若い人5、6人とお酒を飲む機会があった。みんな30歳ぐらい。出身地をたずねて、ちょっと驚いた。山梨、長崎、神奈川、大阪…と東北以外からやってきた人ばかりで、もちろん山形生まれは一人もいない。
ざっくりとその理由を私なりに探ってみると、ひとつには1992年に開学した東北芸術工科大学の存在が思い浮かぶ。けっこう目的意識をはっきりと持った学生が集まり、地域と緊密なプログラムの中で学び、卒業後も山形に住み続けて仕事を起こしたり地域とかかわり続ける人たちが、少数とはいえいるのだ。
そして、もうひとつは「地域おこし協力隊」という制度だ。2009年に総務省が始めたこの制度は、地方の町や村が都市の若い人たちを住人として受け入れ、集落の人たちと暮らしてもらいながら、農作業の補助から生活支援、地場産品の開発や販売、都市住民との交流などのにない手を育てようとするもの。期限は3年で、生活費や活動費が支給される。
東京や名古屋、大阪などの大都市にますます人口が集中する流れの中で、あえて田舎暮らしを選択する人たちなのだから変わり種なのだろうけれど、それだけに都市の暮らしに限界を見て、自分自身の新たな生き方やこれからの社会のあり方を模索するのに一生懸命なのだろう。地域移住への足がかりにする人もいるし、任期の3年を終えたあと地域にそのまま定住する人もあらわれ、あちこちで活躍を耳にするようになってきた。この山形の飲み会でも3人が地域づくり協力隊、もしくはその出身者だった。
実際、地方の町、特に山間地では息子・娘世帯は家を離れて都市に移住し、年寄りの一人暮らし二人暮らしが目立ってきている。ジジ・ババたちは案外と元気にたくましく生活しているけれど、冬場の雪かきや雪おろしはかなり難しくなりつつあるし、ぽつりぽつり次世代が離れていく集落の行く末を案じていることは確かだ。そこに若い人が飛び込んでいけば大歓迎、懐深く受けとめていろんなことを教えてくれるようだ。
私の知人の息子も夫婦で子育てしながら、新潟のとある町の地域づくり協力隊となった。夫婦そろってミュージシャンである彼らは、家々の雪かきをこなし、自然農法の米づくりを見習い、地域の人が歌うときには生オケをつとめ、ときおり演奏に出かけていく。「地域づくり協力隊+アルファ」という生き方は、地域に根ざす生き方と自己実現という、これまで隔絶していた2つの価値をつないでいるように見える。
福島のある町に出かけたときは、小さなワイナリーの入り口のラックに地域づくり協力隊の女性がつくったニュースレターを見つけた。一色刷りの表裏イラスト満載の手描きのレターは素朴な味わいで、田舎暮らしを満喫することばでいっぱい。電車やバスの少ない里山を舞台に軽トラでのデートコースを提案したり、東京と移住してからのおサイフ事情を比較したりしている。それを読むと、移住してからの生活費は都会暮らしの約半分。都会は「お金をかせぎほしいものを買う貨幣経済」、田舎は「自給自足など直接的な方法で必要なものをまかなう自分経済」とあって、「いなかで暮らすと生きていく方法の幅が広がっておもしろい」と率直な思いが記されている。(「おにぎり新聞Vol.2」二本松市地域おこし協力隊ニュースレター)
豊かな中で生まれ育った若い人たちが都市と田舎を等価値に見て、むしろ人同士の付き合いが深く、モノのやりとりや知恵の出し合いをする暮らし方に共感を覚えているのが小気味いい。
思えばずっと東北の人々は田舎を脱して都会に出ることを夢みてきたし、なまりを恥じて、小さな町や村の出身であることを隠してきたとろもあった。たとえば、宮城県出身者なら、「仙台生まれ」と答えるように。
でも、彼ら彼女らは違う。山間の集落に入り込み、ともに田んぼや畑で汗をかき、収穫した野菜を農家の人からどっさりと受取りながら、土地で営まれてきた知恵と技を驚きをもって見つめ、人々の生き方を追いかけている。
その姿に、私は新しい世代が登場したんだと感じるし、集落にかろうじて共同体や自然を活かした暮らし方が残っているいまこの時期に彼らが登場してくれてよかったとも思う。ぎりぎり彼らがその文化を継いでくれるかもしれない。
山形で出会ったT君は、地域おこし協力隊になったのをきっかけに山形県鶴岡市の山間地にある大鳥集落に入り、マタギの見習いとなり、ひとり地元の人々に聞書きを重ねて『大鳥の輪郭』という民俗誌を仕上げていた。冬期間の積雪は3メートル。高齢化率は70パーセント。社会的には限界集落とよばれるこの地域の人々が、数百年にわたりどのように生業を保ち集落を維持してきたのか、60ページの一行一行に人々への畏敬と愛情とみずみずしい感性があふれていてすばらしい。それでいて、都会の人間が遠く自然の中で暮らす人々を外から眺めて礼賛するのとは明確に違う、内部に入り込まなければ決してつかみきれない圧倒的な自然の生々しさ、怖さも伝えようとしている。
何人ものT君が、全国の小さな集落を今日もめぐり、地域の人々のために働いて居るはずだ。こうした若い人たちの現れは、私たちの暮らし方、社会のあり方の転換点を示しているのかもしれない。私には、彼ら彼女らがほころび始めた集落の、いやもっと大げさにいえば社会の修復の役割をになっているように見える。
団扇と女優
北村周一私はことのほか団扇が好きで、汚れたり破れたりしても捨てることができずに大事に使って参りました。
団扇といっても、いまふうのプラスチック製のものではなく、骨組みが竹製の、少し大きめの団扇のことです。
私が子供の頃は、どの家にも目立ったところに団扇が一、二本は置いてありました。
夏はむろん涼しい風を起こしたり、蚊を追い遣ったりと出番が多いのですが、それだけではなく、台所や風呂のマキを焚きつけたり、炭や練炭の火を熾したり、ときには塵取りの代わりになったりと、用途はさまざまでした。
団扇には当時はやりの女優さんの顔が描かれていて、うらがわには、○○米穀店とか、△△酒造店とか広告が印刷されておりました。
団扇に描かれた、女優さんのまったりとした笑顔を見ていると、日常のよしなしごとがふと馬鹿らしく思えてきたことも、二度三度ではありません。
団扇そのものが醸し出す特別な雰囲気もありましたが、その団扇を手にしている人が、祖母であったり、父や叔父であったりと、持つ人によって場面が変わるのも興味深いことでした。
そしてなにより、風を送る相手があるときは、たとえば母が小さな子供を寝かしつけようと団扇をあおいでいるとき、また相手が、老いた病人のときなど、いろんな光景を思い出すことができます。
***
女優というお仕事に就いて、もうどのくらい経ちましたでしょうか。
長くこの仕事を続けていると、どこまでがほんとの自分なのか、わからなくなることがあるように思います。
ほんとうの自分といっても、それがどんなだかはっきりといいあらわすことはできませんけれど。
役を作っていくうちに、その一部が自分の中に残ってしまうことがあるのかもしれません。
自分自身が気づかなくても、まわりの家族が変だなと感じるときがあるようです。
私には三人の子供がいます。夫はすでに他界しております。
子供は、うえ二人が男の子、末が娘です。
長男は学校を出て独立しておりますが、した二人がまだ学生で、いまは三人暮らしというわけです。
私は仕事の都合で、いったん家を出ると帰りが遅くなりがちなので、朝食だけはみんなで摂ろうと決めて、子供たちも朝だけ一緒の食卓についてくれます。
とはいえ次男は、夫の死後ますます無口になってしまい、私がなにをいっても、軽く返事をするだけで、自分から話すことはめったにありません。
娘はといえば、思春期はとうに過ぎたというのに、学校へは行かず、たまにアルバイトに出かけているみたいですが、ふだんは夜昼逆転の生活をしております。
それでも三人一緒に朝食を摂るスタイルは変わりません。
娘も食堂にやってきて、テーブルにつくことはつくのですが、寝たふりとでもいうのでしょうか、目を瞑ったままじっとしているだけで、なにもものいわず椅子に座ったままなのです。
私が出かけた後にひとり食事しているのでしょうが、なんとももどかしい限りです。
そんなある日、風邪でも引いたのでしょうか、娘が自室から降りて来ず、次男と二人だけの朝食となりました。
あの娘、眠たければ、あんな寝たふりなんかしてないで、
自分の部屋で寝てればいいのに、
なんかあてつけがましいわよ、と次男にそれとなく話しかけてみました。
次男は黙って聞いていましたが、食事を済ますと、ぽつんとつぶやくように、こういいました。
あいつ、寝たふりしてるんじゃないよ。
ほんとうに寝てるんだよ。
みんな一緒になると、落ち着くんだってさ。
病人生活
璃葉ずいぶん息苦しい場所をさまよっていた。充分な酸素を得られず、ここがどこなのかもわからない…。宇宙のような、海のような感覚をただ泳ぎ続ける。
これが夢なのだと気付いて、じわじわと目を開く。部屋は真っ暗で、カーテン代わりにしている布の隙間からほんのり青い光が漏れていた。明け方なのか暮れ時なのかがわからず、一瞬戸惑う。
外では風が強く吹いているようだった。台風が去っていった後の朝だ。
ひどい風邪の原因は思い当たる。友人宅で夜通し酒を酌み交わし、そのまま泊まり翌日、二日酔いのまま嵐のなか選挙の投票に行き、自宅にもどって雨に濡れた格好でしばらく過ごしていた(部屋はとても寒かった)あの日。
布団をかぶりながら自分の馬鹿さを思い出しては、唸ってしまう。気付かないうちに、弱った体にすかさず風邪菌様が住み着いたのだ。憎らしい。
久しぶりの病人生活はすぐに飽きた。8割は寝て、目が覚めれば映画を見たり、読み途中の本を手にとってみたりする。最初は意外と楽しかったが、やっぱりつらい。わたしがいまできることは、死んだ魚のように横たわるだけだ。日差しが東から入り、西へ消えていっても、わたしは何も変わらずそこで眠るだけなのだ。
その後、台風はまたやってきた。光がほんの少ししか部屋に届かないので、昼間から白熱灯をつける羽目に。
布団に包まれ、窓硝子にバチバチと音を立てて当たる雨粒をずっと聞いていた。時々起き上がっては、やかんで温めた白湯をひたすら飲んだ。このまま焼酎で割ってやろうと酒瓶に手を伸ばすが、これ以上ヘマをしたくないので既のところで止める。
風邪は高熱でわたしを苦しめた後、咳だけを残していった。その咳がさらにわたしを苦しめるので、本当に泣きそうになる。
「咳やのどには絶対に蜂蜜」と友人に言われたことを思い出した。そういえば、幼い頃風邪をひいたときも、よく舐めた気がする。
明け方、むくりと起き上がり、灯りもつけないままキッチンを物色し、瓶にたっぷり入った「りんごはちみつ」を手にとる。
スプーンたっぷり一杯すくった蜂蜜を湯のみに入れ、お湯を注ぐと、ほの暗い部屋の中に甘い湯気が立ち昇る。
外では風はまだ強く吹いていたが、空は晴れている。昨日の嵐で、桜の葉はすっかり散っていた。
枝に残された葉はまさに蜂蜜の色そのもので、朝日に照らされ輝いていた。
アジアのごはん(87)ビルマの和え麺ナンジー・トゥッ
森下ヒバリビルマ(ミャンマー)の都市ヤンゴン8日目。久しぶりに日本料理屋に行って、和食を食べるつもりだったのだが、お目当ての店「SAKURA」は見事にお休みでシャッターが下りていた。しかし、ココロはすでに和食モード。この近所にないかな? 地図で探すと、もうしばらくマハバンドゥーラ通りを行けば「横綱」という店がある。うまいかどうかは分からないが、まあとりあえず行ってみよう。てくてく歩いて、辿り着いたらここもお休み。ああ、日曜日だもんな。
腹ペコで、もうなんでもいい。通りの反対側にYKKOという店があったが、ビルマに似つかわしくない、ピカピカしたファミリーレストラン風。う~む。その近くにかわいらしい手作りのタイ料理屋の看板があった。数日後にはタイに戻るのにタイ料理もねえ。とりあえず矢印にそって小路を入り店の前に行くと、その隣にもビルマ食堂らしきものがあった。
「バーマース・トラディショナルフード」とビルマ語の看板の下に英語で書いてあるのが読めた。半分開けっ放しの食堂に入ると、大きな黒板にビルマ語でメニュウが書いてある。作り置きのヒンと呼ばれる油煮込み料理がトレーに並ぶ、いわゆるビルマ定食の店ではないようだ。まあ、他の客が食べている料理を指させばいいだろう。
テーブルに座ると、少年が注文を取りにやって来たが、英語は通じない。みんな何を食べているのかときょろきょろしていると、マネージャーぽいおじさんが簡単な英語のメニューを持って来てくれた。おお、すばらしい‥しかし、読んでもどんな料理かほとんどわからない。
「う~ん、ナンジー・トゥッ?ライスヌードル・チキングレービーっていうのはどう?」「それ何?」「知らないよ‥あんかけ麺かな」マネージャーに聞くと、厨房とつながったカウンターに連れて行ってくれて、茹でておいてある白い米麺を指差した。おお、まるで稲庭うどんのような麺。こんなうどんのような太い米麺はまだ食べたことがない。
じゃあ、これね、と注文したところでカウンターに他の客の卵焼きのせご飯が出てきた。タイのカウ・カイジヨウとまったく同じだ。しかもトマトなんかも入ってすごくおいしそう。もうひとつはコレ~!と無事注文を終えて、まつことしばし。
先に麺が出てきた。あれ、あんかけじゃないのか。汁けのない和え麺である。ちょっと黄色いたれに絡まった麺の上にはゆで鶏肉の裂いたのと香草がのっている。付け合せに茹で卵とライムが添えられている。わたしは、鶏肉がどういうわけか5年ほど前からほとんど食べられなくなったので、これは相方の分である。このバージョンで豚肉とか魚はないのかと聞いたが、ないとのこと。ふうん?
「あ、これ‥!」ライムをぎゅうぎゅうと麺に絞ってかけ、かきまわして一口二口食べた相方が、ぱあっと顔を輝かせて叫んだ。「これ、スパゲティやわ、なんてったけ、ほらあれ!」「はあ?」何アホなこと言ってんの、と思いつつ一口味見してみた。「う、うまい。これはあれやわ、カルボナーラ!」「そう、それそれ!」
なぜ、米麺にチキングレイビーソースを絡ませたら、生クリームと生卵・ベーコンのカルボナーラ味になるのだ! もちろん、乳製品も生卵も入っていない。何か不思議な調味料でも入っているのか? ビルマの麺料理は奥が深い、深すぎるぞ。
日本に帰って、いろいろ調べてみたところ、最初に見つけたナンジー・トゥの作り方はこうだ。
太い米麺ナンジーを茹でる。チェッターヒン(ビルマのチキンカレー)の汁を絡ませ、チキンの身をほぐしてのせ、香草を刻んでのせ、ライムを絞る。
え、残り物のチキンカレーで作る料理ですか?
さすがに、それは家庭での話らしい。きちんと作るには、玉ねぎ、ショウガ、ニンニクを刻んでたっぷりの油で煮て、チキンを加えてパプリカパウダー、粉トウガラシ、ターメリック、魚醤(ナムプラー)を加えてさらに煮て水分を飛ばし、(つまりビルマチキンカレーを作り)それを茹でた麺と和え、焼いたひよこ豆の粉をふり、香草をちらし、ライムを絞る、という。
ビルマ料理の中核をなす、油煮込み料理のヒンは、カレーというにはスパイスをあまり使わない。なので、インドカレーに比べるとおだやかな味である。油分が多いのだが、この油にはうまみが濃縮されている。しかし、油になれていない日本人は食べ過ぎるとお腹を下すので要注意だ。ビルマカレーを食べるときは、上に浮かんでいる油はなるべく食べないように‥って残すのはもったいないしな~。
やっぱりナンジー・トゥッは残ったカレーの油っぽい汁の再利用から始まっているのかも。ひよこ豆の粉を加えることで、まろやかなコクがでて、カルボナーラみたいな味になるのかも。ライムの酸味も重要そうだ。そういえば、うちには、米粉と合わせて使うと風味が上がるので、ひよこ豆粉が常備してあるではないか。ほかには、入手困難なスパイスも使わないので、ナンジー・トゥッを再現できるかもしれない。
もちっとした太い米麺というのも、他のアジア諸国では見かけない。この麺だからこそ、スパゲティのような食感がでるのだ。ビルマの米麺には、ビルマ族が主に食べるインディカ米で作った米麺と、シャン族が食べるジャポニカ米で作る米麺、米粉を発酵させて作る中華系のビーフンの三種がある。インディカ米の麺は、モウヒンガーに使う細麺、中太麺、太麺、平麺、切り麺の種類があり、麺料理によって使う麺がだいたい決まっている。
ビルマの麺料理と言えば、魚の身をすり潰してスープに加えたカレー風味の米麺モウヒンガー、そしてココナツミルクの入った鶏だしスープの小麦中華麺オンノカウスエ、そしてシャン族の米麺シャン・カウスエが有名である。考えてみたら、これまでこの三種類の麺料理しか食べたことがなかった。ナンジー・トゥッのおかげでビルマの麺料理にはまだまだ広い世界があることが分かって、楽しくなってくる。
卵焼きのせご飯もやって来た。スープとキャベツの浅漬けが付いてくる。このキャベツの漬け物がまたうまい。ビルマの漬け物はどこで食べてもはずれがない。先日行ったシャン・ヌードルの店では、付け合せの高菜の漬け物がおいしくて友達の分ももらって三人前も食べた。う~ん、乳酸菌をたっぷり補充して満足。
市場に行くと、さまざまな塩辛の調味料が山積みされていたし、大きな桶に入った漬け物コーナーも充実していた。漬け物は米のとぎ汁と塩を入れて乳酸発酵させるタイプが多い。青菜、大根、たけのこ、ほか何種類もの野菜の漬け物桶が並ぶ姿を見れば、いかにビルマ人が漬け物好きか分かるというものだ。日本人はあまりしない利用法だが、乳酸発酵の漬け物は漬け汁ごとスープなどの料理にも使われる。その他、発酵させた豆の煮もの、魚の馴れずし、お茶の葉の漬け物ラぺ、などビルマは発酵食品の宝庫であった。
人口の7割を占めるビルマ族、そのほかタイ系のシャン、カチン、カレン、カヤー、チン、ラカイン、アラカン、先住民族のモーン、ピュー、インダーなどビルマには135もの民族がいる。多民族国家なのだ。長い歴史の中で、交流の多い民族間では食文化も互いに影響し合い、区別がつかないほど同化しているものもあるが、ビルマの国の食は民族のバラエティに富み、滋味あふれ興味が尽きない。
オタク的なサブカルチョコレート
さとうまき寒くなってくるとチョコレートの季節。
今日は、昨晩から新宿に泊まり込んで、駅の地下にあるベルクというお店にチョコを置いてもらうために、朝の5時30分から作業だ。夜明け前の新宿。血を流してへたりこんでいる若者がいる。ハロウィンの仮装だ。ガード下にはホームレスが寝ていて、こちらは仮装ではなさそう。
イラクの子どもたちの絵も展示してもらえるというので、今年の缶の絵を描いてくれたSUSUの絵を、加工したものを作った。1960年代のポップアートを2017年という時代に焼き直してみるというコンセプト。技術は進歩して、フォトショップを使って家庭用のプリンターで打ち出すだけでいい。
広告が氾濫するように、メッセージが氾濫してほしい。僕らは、イラクのがんの子ども達を支援しているわけだが、「もっと薬を!」みたいな支援を訴える広告性だけでなない。SDGsに絡めて、みんなが医療を受けられるようなシステムづくりといったアドボカシーや、劣化ウランを廃絶せよとか、核兵器反対、NO WAR などのメッセージを氾濫させる。フェースブックでも簡単に拡散できる時代だ。しかし残念なことに、流れに乗らないと誰も見向きもしてくれない。新宿のベルクは一日1500人のお客さんが来るから、否が応でも、一か月は僕たちのアートに触れてもらえる。
さて、今回使った絵を描いてくれたのがSUSU。アニメのキャラクターのような絵を描く19歳。イラク、バスラの貧困街で生まれ、10歳で卵巣がんになる。闘病中は絵を描いて過ごすした。がんを乗り越えるが、学校には行かず引きこもりに。2013年に私が彼女の家を訪ねたときは、ほとんど口もきいてくれなかった。
アニメのキャラクターのような絵でチョコを作るのは結構難しいが、イラクのがんの子どもの絵をパラパラ見ていると、ディズニーキャラはもとより、スポンジボムとか日本風のアニメもある。ピカソのようなオリジナリティあふれるものは実は少ない。
思えば、日本の文化で海外で評価されているのは、昔の、ソニー、キャノン、トヨタ、すごい!という時代は終わっていて、日本といえば、漫画やアニメやゲームのオタク文化であり、世界の潮流になろうとしている。日本語でゲームをしたいとわざわざ日本語を勉強する若者もいる。なので、今回はそういうオタク的なサブカルに挑戦することになった。
SUSUの協力が必須で、アルビルまで呼び出してきてもらった。お母さんが一緒じゃなきゃいやだというのはわかるが、マナール先生も一緒じゃないといやだという。まあ、バスラからアルビルは、飛行機もそれほど高くないからお安い御用ではあった。
2017年に再会したら背も僕よりも大きくなっていた。2013年の印象が強く、恐る恐る話しかけてみたら、結構明るくなっていた。病院を訪問し看護師やソーシャルワーカーに自分の体験を話してもらった。結構本人も感じるところがあったのか、お母さんも、「バスラにいるときとは信じられないくらい積極的」だったという。
その後JIM-NETのスタッフとして働くことになった。さて、そのSUSUがメッセージを書いて送ってくれた。
「それまでの私は、普通の10歳の子供と同じような人生でした。しかし、それから一か月もしないうちに、私の人生は完全に変わってしまいました。私の体調は非常に悪くなり、痛みもひどくなりました。
様々な検査を受け、癌という結果が出ました。そして手術を受け、手術は無事に成功しました。手術で私の体から腫瘍を取り除きましたが、医師の考えと検査結果から化学療法を受けなくてはならなくなりました。
私は自分の運命、未来を知りませんでした。癌とはどういう意味なのかさえも知りませんでした。癌は他の病気と一緒で薬を服用したり、注射をすれば治るものだと思っていました。
病院では毎日たくさんの子どもの患者が、私の眼の前で亡くなりました。そのことは私の人生の中で、最もつらい出来事でした。
化学療法は他の治療と違って、私の容姿と心を完全に変えてしまいました。痛みがあったり、時々食欲がなくなり、免疫が弱くなりました。そして家族は、私がもうすぐ死んでしまうのではないかと恐れていました。
さらにつらいことは、人々が私を死が近づいている子どもであると、憐れみの眼で見ることでした。また彼らは、癌は伝染する病気と考えていたため、私に近づこうとはしませんでした。
私は、彼らが私の髪の毛がないことを笑ったり、質問したりしたことを、今でも覚えています。そして学校にも行けなくなりました。
しかしながらこれらすべてのことは、私を強くしました。自分は気にしていないし、強いということを見せようとしました。そして徐々に強さと笑顔を見せるようになりました。
私は治療を終えましたが、癌が再発しました。それでも癌に打ち勝ち、2010年にすべての治療を終えました。
私は、私よりも強力な病気と闘って勝ったことを誇りに思います。私の体験談や、絵が多くの子ども達にちょっとした笑顔を与えて、たくさんの癌をやっつけてくれたらいいと思います。
私を優しく支えてくれた医師たち、家族、先生たちとJIM-NETに感謝しています。」
今回の展示ではSUSUだけだはなく、2009年に目のがんで亡くなったサブリーンが描いた絵もリメイクしている。実はSUSUの本名はサブリーン。2008年にSUSUが病院に来て初めてサブリーンに出会った時のこと。
サブリーンは、SUSUに、「この病院には、2人のサブリーンがいるのね。でも私はもうすぐいなくなるのよ」と言われて、当時10歳のSUSUにはよくわからなかったが、一年後にサブリーンが亡くなった。そして次は自分かもしれないとおびえていた。サブリーンが、イラクのがんの子ども達のために絵を描き続けたことを改めて知り、遺志を継ごうとしている。是非見に来てください。
ベルク 11月1日―11月30日(7:00-23:00)
「イラクとシリアのHappy なアート展」
さつき 二〇一七年十一月 第七回
植松眞人 母が仮住まいと呼んでいる青い屋根の小さな家に引っ越してきてから、まだ一ヵ月しかたっていない。それなのに、私はもうずっとここに住んでいるみたいに、この家に馴染んでいた。前の家にいるときよりも、その狭さが私と父や母との距離を縮めているからかもしれない。
でも、距離が近くなった分だけ、母がこの家を仮住まいとしか呼ばない気持ちもひしひしと伝わってくるし、父が引っ越しをはさんだ一週間ほどだけいなくなっていた理由もわかるような気がした。
そして、どうしたって、人は新しい環境の中でだんだんとそこに慣れていくのだ、ということを私は知ったのである。もしかしたら、父は少しでも早く、仮住まいに慣れることで、ここしばらくのごたごたをなかったものにしたいのかもしれない。そして、母は仮住まいに慣れずに抗うことで、微かな希望のようなものを見失わないように必死なのかもしれなかった。
北朝鮮は中途半端にミサイルを飛ばし続け、アメリカはそれを叱りつけ、日本はよく意味のわからない総選挙をして、十一月もそろそろ半ばを過ぎた。
選挙の日には選挙権のない私も一緒に投票所に行く、という慣例は今回も守られ、東京の帰りにファミレスに行って、ちょっといいメニューを頼む、というルールもいつも通り守られた。
私たちのルールはいつも通りだったのだけれど、選挙そのものはこれまでになかった政党を都知事が急に作ってみたり、そこに合流しようとした既存の政党が合流を断られたり、選挙権のない私が見てもてんやわんやだった。そして、選挙前に父が話していたとおり、お金持ちがもっとお金持ちになりそうな、お金のない人がもっとお金のない人になりそうな、そんな準備が整ったのだと思った。
あ、それからもう一つ、いつもと違うことと言ったら、今年の十一月がやたらと寒いということだった。選挙でみんなが熱を使い果たしたのか、どうしようもないくらいに寒い日が続いた。昼間の日差しがあるうちはまだましだけれど、朝なんて真冬のように起きるのが辛くて、布団に潜ったままでいたくなる。
また冬が来る。ただ冬が来るだけなのに、なにか今年の冬はいつもより寒くて厳しい冬になりそうだ、とまだ子どもの私にも予測できた。しかし、その対策を何一つ考えられないことが狂おしい。
家の中にいるのに、本当にこのまま凍え死んでしまうのではないかと思ってしまう。本当に気温が低いというだけではなく、仮住まいがいつまで続くのかとか、母はちゃんと持ちこたえるのかとか。ちょっと壊れている父はなんとか元に戻れるのだろうかとか…。
そんなことばかり考えていると、私は今年の冬の寒さが厳しくならないようにと祈るばかりだ。昔、ある漫画の主人公がおばあちゃんから言われていた言葉を思い出した。
「人には怖いものがいっぱいあるけど、いちばん怖いのは寒さやで。寒い、ひもじい、死にたい。この順番に不幸はやってくるんや。そやから、まず温かいもんを食べる。そしたら、とりあえず大丈夫や」
その漫画を読んだとき、まだ私は小学生だったけれど、なるほどその通りだとものすごく納得したことを思い出した。
「ねえ、今日は何時に帰ってくる?」
母が聞いて、私は
「今日は普通に授業があるだけだから、そんなに遅くないよ」
「だったら、晩ご飯の買い物に一緒に行こうか」
私は母の提案にうなずいてから、母と夕飯の買い物に行くなんて、もしかしたら、一年以上ぶりじゃないかと思い、驚いた。
*
夕方、母は学校の近くまで来て私を待っていた。以前、母が私に聞いたことがある。
「学校の友だちに、親を見られるのって恥ずかしくない?」
私は「そんなことないよ」と答えた。すると母はこんなことを話してくれた。
「私が子どものころ、親と出かけていて、大好きな男の子に見られたの。そしたら、翌日、その子に、『お前、お前んちのおばさんにそっくりだな』って。あたりまえよね。自分のをお母さんなんだから。でもね、なんかその時、私はがっくりと落ち込んじゃったのよ。そうか、私はお母さんと似ているのかって思っちゃったのよ。それから、妙に意識してしまって。私、お母さんと、つまりさつきのお婆ちゃんと、一緒に出かけるのを避けるようになっちゃったよ」
「母さんはどうして、お婆ちゃんと似ていることが嫌だったの?」
「わからない。大好きだったし、顔が似ているのも嫌じゃなかった。きれいな母さんだなあって思っていたし」
「うん」
「たぶん、他人に母と似ていると言われたことが悔しかったのかもしれない。もっと深いところでつながっていると思っていたのに、誰から見てもわかる顔が似ている。そう指摘されたことが嫌だったのかもしれない。ちょっとわからないよね」
「うん。そうだね」
「私もよくわからないんだけど、なんとなくそんな感じだったと思うんだ」
「でも、私はそんなこと全然ないよ」
「そうなの?」
「母さんや父さんと出かけるの好きだし、それを友だちに見られてもなんともない。大好きな男の子になんか言われたら…。う~ん、それはもしかしたら、内容によってはちょっと傷ついたり怒ったりすることもあるかもしれないけれど、まだ経験していないことをあれこれ考えても仕方がないし」
「そうだね」
母は、そう言うと少しのあいだ黙った。そして、気を取り直したように顔をあげると、私に「母さんもさつきを見習おうっと」と言うと、ちょっとわざとらしい気もするけれど、楽しそうに私の手を握って、私たちは商店街のある通りへと向かって歩き始めた。(つづく)
創作ダンス?
笠井瑞丈姪っ子からラインがくる
「学校の授業で創作ダンスの振り付け考えなきゃいけないんだけど
どうしていいか皆目検討がつかなくて
ざっくりでいいから考え方を聞いてもいいですか?」
確かに創作ダンスとはなんなのだ?
自分がやっている事なのに
いざ言葉で説明しろと言われると
かなり説明に困る。
よくダンスやってますと言うと
だいたい
「ヒップホップ」
って聞かれる
「いやそうじゃなくてコンテです」
そうすると
「それどういうダンス」
この時にもなかなか説明するのに困る
そもそもダンスと言っても
コンテポラリーダンス
モダンダンス
舞踏
ヒップホップ
バレエ
社交ダンス
等等等
たくさんあるし、これもひとくくりに創作ダンスと言ってもいい。
そして姪っ子に
悩んだ末
たたき出した五つ答え
創作ダンスとは
↓
1. 今までの人生でやったことのない動きを探す
2. カラダの自由を探すこと
3. 意味のない動きの連続性
4. 無意識で動かず意識的に動く
5. 自分がダンスと思わないことをダンスする
こんな回答でよいのだろうか!!
ちゃんと自分のやってる事を答えられるようになろう
これからも踊っていきます
しもた屋之噺(190)
杉山洋一カタロニアの独立宣言を東京で知り、かなりの衝撃を受けています。イギリスのEU脱退と同じか、それ以上に驚いていますし、絶対に回避してくれるに違いないと信じていたところもあります。今月はイタリアでも国民選挙があって、北部の自治権拡大を強く支持する結果になりました。ただ、「北部同盟」のように北イタリア独立を求める声は、少なくとも周りにはありません。
一等地に住むアリストクラシー以外、現在でもミラノに住んでいる、生粋のミラノ人など、全体の何パーセントなのでしょう。周りを見回してもあまり思いつきません。教えている学生たちも、大体親の世代に南から移住してきた家族が目につきます。南には仕事がないので、北に移住してくるのです。
ミラノでも、少し離れたブリアンツァの小都市に出かければ、恐らく今でも土地の出身者はそれなりの数住んでいるのかもしれません。
カタロニアの事情は分かりませんが、少しは近しい部分もあるのかも知れないと思いながら、移民者の一人としてニュースを読んでいます。
—
10月某日 ミラノ 自宅
今月末で家人の滞在許可証が切れるので、更新に必要の書類作りに奔走。驚いたのは、現在まで10年も滞在許可証を貰っていて、市役所に戸籍登録されていなかったこと。最初は何かの手違いだったのだろうが、今となっては原因は分からない。改めて戸籍登録をして事なきを得る。
最初はミラノの市役所に出かけて、該当する人物は見つからないと言われ、あなたと子供さんだけモンツァから転出されてきている、きっとあなたはモンツァに奥さんの戸籍を忘れてきたのよと笑われ、朝一番の列車でモンツァの市役所まで出かけて尋ねると、「スギヤマ」は何人か登録されているが、該当する「スギヤマ」はいないようだと言われ、狐につままれた思いで帰宅した。
日本で、外国人不法滞在者や不法移民が話題に上ると、決まって自国へ早急に送還すべきと言われるので、正直なところ、内心穏やかではない。日本の滞在許可申請について明るくないが、申請書類を準備するのに思いがけず時間がかかったりして、全く不可抗力的に滞在許可証が切れ、再発行手続きが間に合わないことも考えられる。事実イタリアでは、以前は滞在許可証が切れても何日以内かに申請すれば、更新手続きとして受領して貰えたが、現在どうなっているか分からない。保育園や小中学校の子供の声は近所迷惑で、育児休暇もむつかしく、子連れの外出も憚られ、出生率は当然低下しつつ、外国人は風紀を乱すし、外国人でもクリアしなければいけない専門職の試験は、我々でも分からないむつかしい日本語が並び、近隣諸国は嫌いだとすると、これから日本の国力はどうやって上げてゆけるのだろう。
まあ、怪しげな移民の立場では偉そうなことも言えない。
10月某日 パドヴァ ホテル
ヴェニス行き特急に乗り、ヴェニス一つ手前の停車駅、パドヴァ駅で降りる。この街には、今から20年以上前に、一度だけパドヴァ大学の演奏会にやってきた。当時は伊政府給費が突然止められた時だったから、文字通り無一文で、作曲の先生だったゴルリがそれを見かねて、自分のアンサンブルの演奏会の折に、アシスタントとして雇ってくれた。何をするわけでもないのに、一緒についてゆき、ホテル代も出してもらっていた。リハーサルを聴いて、バランスや音間違いなどをチェックした程度だったに違いない。本当に彼のお陰で生き長らえたと改めて思う。パドヴァ大の演奏会で、確か「主のない槌」がプログラムにあったような気がするが、間違っているかもしれない。場末のホテルにチェックインした時、彼がホテルに出した身分証明書にアレッサンドロ・ゴルリと書いてあって、初めて本名はアレッサンドロで、通名がサンドロと知った。あの時は、とても寒くて、暗い印象ばかりが残っている。実際にその通りだったのかもしれないし、鬱々とした毎日を過ごしていたのかもしれない。
食べるものにも事欠く状態だったはずなのに、食事に関してはあまり惨めな印象が残っていないのは、市役所を罷めて八百屋を始めた友人がいたからだ。
相変わらず曇り空で肌寒いパドヴァ駅で、そんなことを想う。
10月某日 パドヴァ ホテル
いつもリハーサルに出かけるとき、忘れ物がないかととても不安に駆られる。幸い楽譜は揃っていたが、本番用の黒シャツを詰めるのを忘れていた。
パドヴァ駅の案内所で男物の洋品店を尋ねると、駅の向かいにあると云う。そこは中国人が経営する所謂場末のアウトレットだったが、黒シャツもちゃんと一種類置いてある。17ユーロ。一体、どこで誰が、どんな状況でこれらの製品を作っているかと思う。昔モンツァの集合住宅に暮らしていた頃、隣の部屋は階下の中華料理屋の使用人たちが暮らしていた。とても狭い部屋に一体何人暮らしていたのだろう。何度か警察がやって来たのを覚えている。或る日突然、その部屋の玄関が開け放たれ、中はがらんともぬけの殻になっていて、仰天したことがある。警察に捕まったのなら、調度品など残っていそうなものだから、夜逃げしたのだろうと家人と話した。
捕まっていなければいい、理由はないが漠然とそう思った。夕方になるとランニングシャツ一枚の中国人が、へろへろの外に突き出た通路にもたれて煙草を吸っていて、イタリアは好きかと聞くと、寂しそうに笑って、「家に帰りたい」、とたどたどしい伊語で答えた。
今回パドヴァでリハーサルするプログラムに、カン・ヘスンを独奏者に迎えて郭文景(Guo Wenjing)のヴァイオリン協奏曲があるのを思い出し、マオカラーの黒い国民服みたいなシャツはないか尋ねてみる。一瞬怪訝な顔をしたが、果たしててらてらの中国生地のシャツがあって、15ユーロ。どちらが本番服に合うかわからないので、二つとも購入して計32ユーロ。安い製品を購入するのは、搾取される労働力に幾何か還元する唯一の道なのか、さもなければ奴隷扱いに等しい経済構造にただ拍車をかけるだけなのか。
10月某日 パドヴァ ホテル
パドヴァ・ヴェネト州立室内管リハーサル。古くはヴィオラのジュランナ、暫く間までピアノのアシュケナージが音楽監督だったが、現在のアンジュスに替わって以来、近現代作品を演奏する回数が飛躍的に上がった。ジュランナとグッリと録音したモーツァルトの「協奏交響曲」の名演が忘れられなくて、このオーケストラと現代作品を演奏する現実感が伴わない。練習会場は、郊外の宗教施設に併設された古い劇場で、時には映画も上映していた風情も漂う。外のインターホンにはオーケストラの名前が書かれていたし、2階には事務所と楽譜庫があったから、今は専らリハーサル会場として使われているようだ。
愕いたことに、リハーサルが始まる14時から15時半まで、一帯が工事停電する、と今しがた通告されたと言う。どうしましょう、とステージマネージャーは困り果てた顔をする。最初のリハーサルは、筝の後藤さんを迎えた岸野さんの作品だったが、左右舞台脇の出口の扉を開け放して、外からの寂しい光を頼りに練習を始めた。
光が多少は入ったところで、映画館のような漆黒の空間に差し込む二筋の太陽光では、到底オーケストラが練習できる筈もなく、暫く試してすぐに頓挫。冗談みたいなことを、真剣に出来ると思う不思議。イタリアに歴史に残る天才が数多く残る証かも知れない。
夜、散歩中に見つけた「狙撃隊」というヴェネト料理屋に入る。「肉が食べられないのですが、何かありますか」と尋ねると、烏賊の煮込みとカジキマグロのパスタを用意してくれる。一杯くらいワインはどうかと言われたので、疲れていたので、珍しく頂くことにする。白ワインか赤ワインかと尋ねられ、一旦は白をと答えたものの、ウェイトレスの後姿でふと思い返し「でもここは赤ですよね」と声をかけると、嬉しそうに「そうです」とこちらを振り返った。
10月某日 ヴェニス ホテル
ホテルからすぐのサント・ステファノ広場あたりのバールで朝食を摂ろうと、散歩を兼ねて早朝ヴェニスを歩く。一軒開いていたバールは、覇気のない若い夫婦がやっていて、注文しようと幾ら待っていても目もくれない。ところが、後から入ってきた近所の老人が、菓子パン頂戴と声を掛けるとすぐに出したので、こちらも注文してよいかと尋ねると、「別の用事してんだから待ってなさいよ」と酷い剣幕で言うので、「常識知らずのヴェネチア人、恥を知ればよい」とだけ応え店を後にした。若い夫婦の顔色がさっと変わるのが分かった。
ヴェネチア人が観光客を嫌っているのは、本人たちから何度となく聞いて知ってはいるが、彼らにどこか食堂を紹介してくれと頼むと、「この何某亭に行ったら、馴染みのヴェネチア人に紹介されて、後で待遇がどうだったか確かめて、悪ければ文句をつけに来るそうだ」と脅迫染みた文句まで言わなければ相手にされない、と聞き呆気に取られる。そこまでして、ヴェニスで外食したいとも思わない。
尤も、フランチェスコと昼食を摂ったガリバルディ通りの郷土料理屋は親切で、何より美味だった。フランチェスコは8歳までヴェニスで育ち、それから親の仕事の都合で、嫌々フィレンツェに引っ越した。ヴェネチア人は実はとても優しく話も通じるが、フィレンツェ人はどこまでも攻撃的なので身も蓋もない、と確かに身も蓋もない言い草をする。フィレンツェに引っ越した当時、ストレスからか突然字が書けなくなったそうで、「繊細だったんだろう」と笑う。
観光ガイドに、お薦めの郷土料理屋のリストが載っているのか、観光客相手のレストランには閑古鳥が鳴き、地元の小料理屋にばかり観光客が群がって、文字通り「観光客相手の料理屋」になっている。
10月某日 ヴェニス ホテル
大くんの「ホルン協奏曲」。大くんと初めて会ったのは随分昔にベルリンで、KNMが彼の作品を紹介した時だった。それからは京ちゃんと3人でイタリアをツアーしたり、会っては話し込む機会が続いていたのだけれど、ここ暫くご無沙汰していた。
楽譜を広げると、一瞬単純そうに見える明快な譜面だけれど、演奏は難しいだろうと覚悟していた。実際練習時間は他の曲よりずっと多く取らなければならなかった。
昔から大くんはメジャーコードが好きだと言っていたが、和音をピアノで弾いてゆくと、一つ一つの和音に表情があって、翳ってみたり、くぐもった顔をしたり、光が差し込んできたり、後ろを振り返ってみたり、その変化がとても美しいと思う。
その和音が響かせるためには、オーケストラは互いに耳をそばだてて聴きたい音を探してゆかなければならない。オーケストラが耳を開くと、それが巨大な花びらのように広がってゆき、その中心に独奏の福川くんの音が沁みとおってゆく。
オーケストラで使われる楽器はどれも禁欲的だし、禁欲的な姿勢を強いると思うけれど、ホルンはその最たるものではないか。その佇まいに美しさを見出したところが、大くんの、もしかすると、ヨーロッパ的ではない視点が働いていたのかも知れない。福川くんの音は素晴らしかった。
尤も、今回大くんとは音楽の話より、寧ろ彼が凝っている「腸内細菌」についてばかり話し込んでいた気がする。
10月某日 ミラノ行車中
朝4時半に起きチェックアウトをして、冷え込みの厳しい夜明け前の路地を伝い、5時の水上バスに乗る。
昼間の喧騒が嘘のように静まり返っていて、ただ聴こえるのは波の音と、時たま通る汽船の低い警笛、それにエンジン音くらいだろう。ぽつりぽつりと水面に尾を引く橙色の街灯が、波に揺れていて美しい。
早朝の水上バスは、意外に利用客もいるが、大方が、荷物を抱えて駅に向かう労働者のようにも見え、何人か外人も交じっていた。どういう事情か分からないが、ヴェネチア本島に住んで、メストレ方面に働きに出かける労働者がいるかどうか。
昨晩の演奏会の後、食事を摂りながらヘソンと話していて、彼女が韓国を後にした時の話になった。当時は海外に出るのがとても大変で、それも姉妹で留学したので、親はとても苦労したと言う。何時でも整った身なりをしていて、一見澄ました雰囲気も醸し出しつつ、完璧な演奏をしていた。リピッツァー賞の審査員をした時、日本のヴァイオリン奏者のスタイルが以前とずっと変わっていて驚いたと話していた。韓国より、長く暮らしているフランスの方が暮らしやすいと言う。母親とは気軽にインターネットで連絡が取れるようになったし、でもずっと離れていると、会話の内容が一辺倒になってしまっていけない、と笑った。元来フランスは移民の国だが、それでも最近はフランス人への優先度が高くなり、外人への門戸は途端に狭くなり、留学してくる自分の生徒たちが大変だ、と話す。
10月某日 ミラノ 自宅
息子は吐気と眩暈で布団に突っ伏している。中学時代の自分にそっくりで、何故こういうどうしようもない処ばかり遺伝するのか、息子に申し訳ない思い。親の心子知らずと言うが、両親はどう思っていたのだろう。尤も当時のは明らかに自律神経失調症で、息子に関しては、自律神経なのかウィルスなのか、さもなければ神経なのかも良く分からない。実際に巷では酷い吐き気を伴う風邪が流行っているということで、病院からは吐気止めを処方されたが、効果は見られない気がする。
食べられないので体力も落ちるのだろう、自転車に乗りたがらない。道路を走っている途中で、いきなり力が入らなくなる時があって、恐いのだそうだ。
勿論、それを見越してリハビリも兼ねて乗らせているので、心配しないで乗ればいいのだが、夜半中トイレに立って吐き気と戦っているのを見ると、とても強く励ます気は起こらない。
10月某日 ミラノ 自宅
7月に息子が退院してすぐ、思い立ってサンタゴスティーノの自転車屋へ走った。朝、息子が混んだ路面電車で転んだので、その日の午後から、息子を後ろに乗せて走れるような自転車が必須だった。どういう自転車が必要かと言われたので、12歳の息子を乗せて走れる自転車なら何でもよいと伝えた。
「失礼ですが、一体どういう訳で」と我々くらいの年代の店主に尋ねられたので、事情を説明すると、実は自分も昨日病院から出てきたばかりだと言う。
「私は実は癌でしてね。ちょうど昨日、やっと化学療法が終わって、退院してきたのです。ですからほら、髪の毛も身体中の毛も、すっかり抜け落ちてしまいました。息子さんが癌じゃなくて本当によかった。でも大変ですね。一緒に頑張ろうと伝えてください」。
あれから、自転車が丁度サンタゴスティーノあたりでパンクしたので、店主のところへ持ってゆくと、髪もすっかり生え揃って、見違えるように活動的な姿になっていて、思わず「本当にお元気になって嬉しい」と言うと、そんなことを誰もが思い出してくれるわけじゃない、有難うと、手を取って顔をくしゃくしゃにして答えた。目には涙がたまっているように見えた。
7月、丁度この黒い婦人用Delmaの自転車を購入したばかりの頃、家の玄関先で、アルフレッドに会った。正確な年齢は知らないが、60はとうに過ぎた、ミラノでは名のある建築家で、このマンションの最上階のペントハウスに、何時もケリーブルーテリアを散歩させている、小さな可愛らしい奥さんと住んでいる。このマンションの建築も彼がサンドロと一緒に手がけた。
アルフレッドに声をかけられたと言っても、最初挨拶された時、すっかり痩せこけていて一瞬誰だか分からなかった。
「君のところの息子さんの具合はどうだい。実は僕は癌でね。君と同じように、ニグアルダで治療しているんだ。ちょうど化学療法の治療期間が終わったところでね。ナディアから息子さんの事情は聞いたよ。大変だったね。でも癌じゃなくて本当に良かった」。
台所で家人と二人、夕食の準備をしていると、見かけない黒い車が庭先に止まった。胸騒ぎがして窓を開けて外を見ると、木棺が車に積み込まれるところで、傍らには、いつもより小さく見えるアルフレッドの奥さんの姿があった。彼女は棺が車に収まったのを見届けると、糸の切れた凧のように歩きながら、別の車に乗り込んだ。
二日ほど後、道でいつものように犬を連れている彼女に会って、かける言葉もなくただ肩を抱くと、「本当に、とても辛かったわ」と絞り出すように声を出した。化学療法は途中で肺炎を起こして中断し、再度検査すると、癌はもう手の施しようもない状態になっていた。
10月某日 三軒茶屋 自宅
期日前投票に出かける。自分だったら可能な限り投票したいと思うが、何故投票率がこれだけ低いのか。
イタリアで如何なる投票権を持っていないので、投票権に切実な意義を感じるのかも知れない。何時でも投票用紙が送られて来ると、案外なおざりにしたくなるのかも知れない。三軒茶屋の食卓にスコアを広げて仕事をする。どうこれから譜読みをこなすのか途方に暮れながらも、「一度には一つの事しか出来ず」「急がば回れ」と言い聞かせてみるが、言い聞かせる口調も悲壮なので、余計心臓に良くない気がする。
窓際に、何時も仕事に出かけるときに持ち歩いている、息子がずっと小さかった時に書いた「さいごまでよくがんばったね」というイラスト付きの紙ぺらを飾る。片面には、両親の笑顔が赤ペンで描かれていて、「よくさいごまでがんばったね」と吹き出しの中に書いてあり、その裏にはずっと大きな字で、「でぷろま よくピアノをがんばったね」とある。小学校の時に使っていた、日本の通信教育の冊子の影響だろう。
湯浅先生の新曲「軌跡」の楽譜を読みながら、ドナトーニの「prom」のオリジナルの楽譜を渡された時のことを思い出す。
どちらも似たような大病の直後の作品で、表現力、訴求力の方向性が少し似ているような気がする。強靭な精神力と、生命力を感じる。
音の意味を一つ一つ嚙締めながら、読んでゆく。
10月某日 三軒茶屋 自宅
インターネットが出来たとき、行ったことのない土地の人と話し、世界中の図書館にアクセスすることが出来る、夢の世界の誕生だと言われた。
1971年に作曲され、子供の時分から一度は聴いてみたいと思っている曲があって、思い立って9月半ばから探し始めた。出版社に連絡すると、もう取り扱っていないし、素材も一切残っていないと言われる。楽譜は残っていなかったが、作曲者から初演者の名前を教えてもらった。初演した指揮者は鬼籍に入っていて、初演したオーケストラは破産したと言う。この指揮者の死亡記事を書いた音楽ジャーナリストに直接便りを出して、探している楽譜があって、もしかしたら家族のもとにあるかも知れないと書いたが、返事はなかった。日本でも演奏されたことがあって、テレビでも放映されたという。78年のことだから、自分が9歳くらいの時のことだ。
日本で演奏したオーケストラには楽譜は残っていなかったし、番組の制作会社にも楽譜はなかった。当時のヴィデオは見られるか尋ねたが、もしVTRが残っていたとしても、簡単に再生できないので、とてもお金がかかるだろう、といわれる。
初演はアメリカ西海岸の話だったので、サンフランシスコの劇場で働いている幼馴染に連絡したり、邦楽器で活動している知合いにお願いして、ロサンジェルスのオーケストラのライブライアンと連絡を取ったのは、ロサンジェルスのオーケストラで演奏したという記録も見つけたからだ。
ライブラリアンはとても親切で、ここにはその楽譜は残っていないが、その指揮者の残した資料は、遺族がスタンフォード大に寄贈して、コレクションになっているので、連絡したらどうかと助言してくれる。スタンフォードのコレクションのカタログには、確かに初演時の写真の記録と思しきものもあったので、司書に連絡すると、この写真は別の演奏会のものだった。
実は写真ではなく、楽譜を探していると伝えると、楽譜は全く別の場所に保管しているが、取り寄せて調べてくれると言う。数日して連絡が来て、丁寧に残した楽譜を調べてみたが、該当する楽譜は見つからなかった。ただ、全世界の図書館検索にかけると、ニューヨーク公共図書館と、ドイツの図書館にコピーがあると言う。
ニューヨークに住んでいた作曲の友人に頼んで、この楽譜が閲覧、複製できるか、何度となくやりとりを繰返してもらっている。
物凄く長い旅をしている気がするけれど、会ったこともない人たちとも、もちろん忙しい友人たちにも、本当にとても親切にしてもらっていて、楽譜探しの旅は、人間の温もりを実感する旅のようだ。
10月30日 三軒茶屋にて
別腸日記(9)断酒のテキサス(後編)
新井卓メスカルは竜舌蘭を原料として作られる蒸留酒で、地中に穿った穴で材料を蒸し焼きにするためか、その余韻に泥臭いような、スモーキーな香りがある。遠い昔、記憶の少し黄ばんだ部分をくすぐるような、深い味わいは親戚のテキーラと似て非なるものだ。
テキサス州サン・アントニオで、仲間のアーティストも滞在先のアートペイス(美術NPO)のスタッフも誰ひとりとして酒を飲まない中、わたしは毎日仕事が終わると、窓辺を壮大に彩る夕日を眺めながら、一人寂しくメスカルを嘗めていたのだった。
そんなある日、それまであまり話したことがなかった一人のスタッフが、わたしのスタジオにやってきた。アートペイスで子供向けのプログラムを担当しているメキシコ移民の男で、エルネスト、といった。彼は開口一番、つい先週もう五年近く付きあってる彼氏と別れちゃってさ、落ち込んでるんだよね、とこぼしはじめた。いきなりなんだ、と思いながらも、じつは僕も飲む相手がいなくてつまらなくて……と話すうちに、じゃあ今晩にでも飲みに行こうか、という流れに相成った。
その日、仕事が終わってから、わたしたちは街の北側へ自転車を走らせた。最近の好景気で真新しくなった街区に洒落た服屋やレストランが並び、大通りの入り口には大きな虹の旗が翻っていた。このあたりは比較的成功した(establishedな)LGBTの連中がやってる店が多いんだ、とエルネストが教えてくれた。まずは腹ごしらえを、とハンバーガー・ショップに入り、1パイントの地ビールとアボガド入りダブル・チーズ・バーガーを注文した。肉汁たっぷりのパティは、表面が少し焦げるくらいで香ばしく、オリオン・ソースに混ぜ込まれた刻んだハラペーニョがいいアクセントになっていた。
ウェイターはエルネストの古い友人らしく「あたしもう帰るとこだったけど。フラれちゃって辛そうだからもうちょっといてあげてもいいけど」と言った。エルネストが悪いけど細かいのないんだよね、でも彼、本当はシフト終わってるからちょっと多めに頼むよ、と耳打ちするので、わたしはチップを三倍払った。
それにしても、なぜテキサスの人々は酒を飲まないのか──彼らに疑問をぶつけると、エルネストが皮肉な笑みを浮かべ「それはさ、白人たちと一緒に見て回るサン・アントニオは、本当のサン・アントニオじゃないから」と言った。
ではいったい何が本物のサン・アントニオなのか? 折しも季節は晩秋を迎え、街はハロウィン一色に染まっているかに見えた。10月31日、またエルネストがやってきて、今日はパーティだから一緒にどう? と誘ってくれた。もしかしてハロウィン? と聞くと、まさか! とんでもない、「死者の日」の前夜祭で一晩中飲んで踊るのだ、と満面の笑みで答えた。
夜、工場を改築したアート・センター「ブルー・スター・コンテンポラリー」に行くと、もうパーティは始まっていた。わたしたちが群衆に近づくと、皆がふり返って、ようエルネスト! と声をかける。夜な夜な地元のパーティでDJをこなし、休日には移民の子どもたちにボランティアでシルク・スクリーンを教える彼は、このあたりではちょっとした有名人、アニキ的存在なのだ。
地元の高校生バンドやメキシコから遠征してきたブラスバンドが次々に演奏を披露する中、わたしたちはひたすら飲み、夜の冷え込みに震えながら踊った。また近くのバーに漂っていけば、そこでも別のパーティが花開き、一人の白人もおらずヒスパニックだけの男女がべったりと抱き合い、喧噪の中で飲み、テーブルによじ登って笑いながら歌っていた。
どうやらサン・アントニオには、ふたつの異なる地図が重ね合わされているようだった──エルネストたちが、メキシコをメヒコ、と呼び、テキサスをテハス、と確かめるように発音するように、それらの時空は決して交差することはないだろう。バーにメスカルはなかったので、仲間たち(といってもその晩かぎり二度と会うことのない酒の盟友たち)と安いテキーラを何杯もあおって変な踊りを踊りながら、わたしは全身に染みわたる悦びに浸っていた。その素晴らしい開放感は、アルコールと脳の痺れからくるのか、あるいは、彼の地における一人のマイノリティとしての孤独から絞り出されたものだったか、今ではもう、どちらでもよいことに思える。
人、響きあう
若松恵子秋も深まってきた日々、ボブ・ディランをカバーした2枚のアルバムをよく聴いている。
1枚目はブライアン・フェリーの『DYLANESQUE』(ディラネスク/2007年)。ディラン様式という造語だろうか。ロキシー・ミュージックのボーカリストであるブライアン・フェリーは、確か初めてのソロアルバムもカバー集だったと思う。原曲をよく知らないまま、どことなく魅かれてよく聴いていた。全曲ボブ・ディランのカバーであるこのアルバムも、ブライアン・フェリーらしく、ポップで洒落ていて心魅かれる。ディランが使いそうもない楽器をいっぱい使って、歌われるブルース(憂鬱な気分)も透明で明るい。満員の通勤電車に耐えながら、聴いている。「運命のひとひねり」、「親指トムのブルースのように」「見張り塔からずっと」「イフ・ノット・フォー・ユー」ディランの代表曲が並ぶ。ブライアン・フェリーが愛聴したであろうディランの曲の数々、「こう受け取りましたよ」と言う彼の応答であるカバー、その音の広がりに、満員電車の私は救われている。
2枚目はジョン・オズボーンの『SONGS OF BOB DYLAN』(2017年)。ラジオから流れてきたアルバムの中の1曲を聴いて、たちまち好きになってしまった。彼女のカバーを聴いて、ボブ・ディラン自身が「エクセレント!」と言ったというエピソードが紹介されていた。ディランのこのコメントを聞いて、彼女うれしかっただろうな。このアルバムで初めて知った彼女の略歴を見てみると、1962年生まれで同い年。音楽のキャリアを重ねてきて、自分の力量も、いっしょに演奏する仲間もできて、やっと自分らしくボブ・ディランを表現できるようになったのだろう。ウッドストックの紅葉のなか、車にもたれかかるディランを真似して撮ったアルバムジャケットもちょっと得意気でかわいい。
ディラン自身も気づいていない彼の楽曲の良さが、カバーによって見出されている。
そんなことを思って、2枚のアルバムを聴いている。
この春から「かえるの学校」に通っている。フリーライターの渡邉裕之氏の大森の住まいを「人が交流するきっかけになれば」との思いでフリースペースとして解放して学校にしたもので、渡邉氏が文章教室を、大西寿男氏が「校正教室」を開いている。長く出版の世界に関わるなかで身につけてきた、本づくりや雑誌づくりの技術や考え方を伝えるクラスだが、本作りだけでなく、「実人生でも使えるような知恵を伝えることを目指します。」とある。渡邉氏の文章教室は「インタビュー原稿の書き方を中心に教えますが、そこから「他者の声を聴く力」を模索していきす。」という事であり、大西氏の教室も「校正をただ原稿のまちがいを正していく作業ではなく「他者のことばを力づける(エンパワメントする)」仕事と定義し、授業に臨みます。」と説明されている。
友人に誘われて、私は渡邉氏の文章教室「オーラル・ストーリー」のクラスに参加した。このクラスは「声の物語=「オーラル・ストーリー」を聴きとり、ことばにしていく技術を伝える教室」で、「具体的には、受講生にインタビュー原稿を書いてもらいます。」ということだ。
6月の土曜日の午後、5人のクラスメイトと一緒に菊地文代さんをインタビューして、それぞれが聞き取った物語を1冊の小冊子にまとめた。菊地文代さんは、昭和5年に生まれ、ドキュメンタリー映画製作、共同保育、伊豆河田での「いりあい村」と多彩な人生を送った女性だ。同じ時間を過ごしたのに、それぞれが描いた菊地文代さんは、受け取った者の形に否応なく鋳型されていておもしろい。菊地さんに響いた自分と、他の受講生に響いた自分の両方が居る。私が菊地文代さんから受け取ったもの、それを言葉に表したものが、今、よく聴いているカバーアルバムのように、菊地さん自身にとってもうれしい応答になっていれば良いのだけれど。
植物図鑑ってなんだ?
大野晋先月、長い長い出版延期の末に日本で一番信頼性のあった植物図鑑の改訂新版が完結した。通常、新しい図鑑の刊行には長時間かかるのが当たり前で、何年もかけてひとつひとつの植物について吟味しながら原稿を執筆するので、全巻揃うのに何十年もかかるなんていうこともざらにある。しかし、今回は新しい図鑑の刊行ではなく、定評のある図鑑の「改訂新版」である。しかも、刊行の発表から最初の第1巻までの刊行にさほど時間を置かなかったことから、すでに原稿もできていて、さほど時間もかからないだろうとたかをくくっていた。ところが、蓋を開けてみると出版時期が延期に次ぐ延期でいつできあがるのか、わからない状態になっていた。まあ、とりあえずできてひと段落というところである。
ところが、問題はできてからの方が大きく、一応、10数万円もかけて全巻そろえてみたものの、どう扱うべきか? 悩んでいる。
今回の改訂の目玉は、どうも、国立科学博物館の標本庫も採用したという新しい植物の分類と配列ということらしい。ところが、まず、この「科博が採用」という全くの権威主義のような宣伝文句がいただけない。博物館が採用したということなら、大英帝国が威信をかけて全世界へプラントハンターを派遣して収集したという王立キュー植物園の標本庫は確か独自配列である。全世界の多くの種の命名登録のもとになっている基準標本はキューにあるのでこちらに揃えたというのなら面白いが、学会の新しい学説に合わせてみましたというのはあまり聞こえのいいことではない。しかも、これがさらに大きな問題をはらんでいるのならなおさらだ。
植物分類学の学者の世界は「自然分類」至上主義とでもいうような状況にある。要は遺伝子の研究をしていた学者たちが「俺たちがみつけた配列こそが正しい」という権威付けのために、今までの外見をもとに行ってきた植物の分類を否定しようということらしい。この見解によると、いままでの合弁花、離弁花や単子葉、双子葉といった分類はおろか、木本、草本と区別することも悍ましいということになるらしい。この主義を新しい「改訂新版」は徹底しようとしたために、新しい図鑑では、木も草もなんもかんもごちゃまぜに並ぶことになってしまい、全5巻、数千ページの図鑑の中にどこに何があるのかが容易にわからなくなってしまったのだ。
図鑑とは、名前のわからない植物を探すためにあるものだと思うが、残念ながらこの新しい植物図鑑はそうした用途には向いていない。この問題の出どころはどこなのか考えると、出版者が出版物の目的をよく理解せず、目的の達成から、変えることが目的にすり替わってしまっていることが理由だろう。立ち止まって身の回りを見回すと、こうした問題は意外と多いことに気づく。これはなんなんでしょうね?
十月、台風
仲宗根浩10月はたそがれの国、という小説を初めて読んだのは高校生のころだったか。今では本なぞ全然読まなくなる。近視の老眼、その上に左右視力が異なると遠近両用眼鏡にしても本の活字を読む場合は眼鏡をはずしたほうが楽になり、そのまま長時間となると疲れてどうしようもない。そんな加齢はついに肩にきた。右腕を曲げたままの状態で腕をを挙げようとすると肩に痛みが出て、これが四十肩、齢五十過ぎれば五十肩かと。今まで右肘、左ひざに痛みを感じたときは無理な使い方という原因がはっきりしていたが今回は突然にやってきた。痛みを感じつつ生活をしていると、痛むところを庇うためか、他の関節やらに軽い違和感を感じ、元の肩はだんだんと痛みがやわらいでいき、分散され仕事、日常でも何事もなくなる。
たそがれたい十月なのに選挙やヘリコプター炎上、ある芸人さんが言った昭和のプレロスのような分裂新党などなどかまびすくなる日々。九月の台風の長い強風域で少しは涼しくなるかと思ったが甘い考えで暑さは続き十月の台風21号ランちゃんが過ぎたあとやっと涼むことができ冷房要らずとなったと思ったら22号サオラーちゃんが三年ぶりの直撃でバスは運休、久々の台風の目に入った静かな二時間余りを過ごし、これは仕事が三連休になるかと思い、夕方から家飲み満々の心積もりでいたが勢力今ひとつ足りずお仕事通常稼動でいやいや仕事にいく。強い台風だったらもっと潮のにおいがするから。
以前は朝の七時半に聞こえていた基地から聞こえるラッパの音が最近二分くらい遅れて聞こえてくる。
わからなさの方へ
西荻なな謎は謎のままに生きることがあった方がいいのかもしれない。
答えはすぐに求めてはいけないのかもしれない。
自分の中に答えのない未知の出来事や感情に遭遇した時、その居心地の悪さに耐えかねて、つい取り込みやすい形の、わかりやすい答えや結果を切迫に求めてしまう。ということが、我が身を振り返ってみてとても多いことに気づいた。何かに行き詰まった時、往々にして問題は自分の心の中にある。その答えは自分の心の中にある。それなのに、外側に答えがあるはずだと思って掘り続けてしまう。そこに終わりはない。
もちろん問題の要因が社会にあることだってある。
時に尊厳をかけて闘わなければならないことだってある。
でも、目の前に横たわる謎が必ずしもネガティブなものでなくて、今後どう展開していくのかわからない白黒はっきりしない分からなさであるような場合、不確定で、先が読みにくいもやもやとした不定形なものであるような場合、その中にダイブしてみることを恐れていては、真に冒険に身を委ねることなどできないのかもしれない。
例えば親しい友人との関係に何か暗雲が立ち込めてきた時。何があったの? 私が何かした? と問いを相手に差し向けるのではなくて、ゆったりと次の晴れ間が差してくるまでとにかく待ってみる。その会話や問いを一度宙吊りにして、そこから離れた日常の時間に戻ってみる。他の豊かな何かで自分の心を満たしてみる。
そうして初めて不思議と霧が晴れる瞬間が訪れたりもする。相手に問題があると思っていたことが、ああ私のこんなところに引っ掛かりがあったのかと積年の何かに気づかされたりもする。相手の中に、目の前の何かとの関係を解くことに答えがあると考えて、解を求めることに必死になってしまったならば、わからなさとの戯れの中にあるはずの無数の可能性を見逃してしまう。豊かな時間は目の前にあるのに、そのことに気づかないままに通り過ぎてしまうのかもしれない。
わからないことはそのままに日常の中に漂わせておいて、日々の流れに身をしっかりと委ねてみる。わからなさをしっかりと一度抱えて、わからなさの中に堕ちてみる。そうして別のタイムラインで、別の空間で感じたことをもう一度地上に持ち帰ってみる。今までと違う空気をまとって、違う音楽を奏でられるような何かをそっと目の前に差し出してみる。そこで何が起きるのかを静かに待ってみる。
156立詩(4)刈萱
藤井貞和少女を過ぎてゆく 風
歳月は、 過ぐる
抱いてもくれぬおとこを かやが
見送っていた。 下根
おとこを思い乱れて、 の
かやのした根に、 つゆ
寝みだれる少女はさわる。 ばかり
少女のさわるのは、 ほどなき
くろずむ露をしたたせる暗渠か 世を
〈とそこまで訳して、老後の私が、 や
少女の日をなつかしむ。〉 思ひ乱れむ
(定家の百歌より。)
音についていく
高橋悠治カフカは書く手についていくと言った 石田秀実の作曲は音についていくことだときいて その時はわからなかった 設計図はなく はじめの音から次の音へ 無数の可能性がひらけるなかで 一つの道を採ると 見える風景が変る 水平のメロディーとも垂直の和音ともかぎらず 同時に見える音も崩し つながる音にも越えがたい距離がある 音についていく指や手 からだが左右上下前後にゆれうごくなかで 時間と空間の格子がゆがむように感じられ というより 音の外側に格子のある空間が感じられなくなるまでに 輪郭のない音が溶けて うごいていく光の窓 「人は自然の中で移ろい、多様な音空間に出会う。音空間は人を包み、人はその中に埋もれる。」(「水牛」2006年11月 石田秀実『幾何学と音楽2』) 人も変わり 世界も変る すべてが流れて「霞が気に変わり 気は形に 形は生に いままた死に変る」(莊子至楽篇十八)
ピアノの鍵盤の上で 指と手と前腕が前後左右上下にそろって回転するとき 触れたキーから出てくる音の運動は その場にいて聴く耳には 聞いている身体の上に感じられるだろう 録音し録画すると この感じは薄れる 音が外側に感じられるからか
動いている指が偶然に触れた音もその後の音の進路に影響するので 弾く手についていく音を記録して楽譜にしたものををもう一度弾いてみても おなじにはできないだろうし 手が自然につくりだした音のうごきは かえって不自然に曲がりくねった運動になるだろう ムカデがすべての足の動きを意識したらうごけないように 意識したらおなじうごきは二度と再現できないだろう 平安時代の書をなぞって音の線に変えたピアノ曲『散らし書き』では 見た線の印象を音にしてみた 線をコンピュータ・ソフトで変換したら まったくちがう音になっただろう Earle Brown: Summer Suite ’95 は まさにそれを試みている ブラウンが即興的に描いた線画をコンピュータで変換して楽譜にしているらしい 痙攣するようなリズムと思いがけないピッチの変化は ブラウンらしい音楽ではあるが それまでの作品のなかで図形楽譜や 時間間隔を音符の間の距離で表したtime notation を見ながら演奏する場合とちがって 機械が決めた音やリズムを手がなぞるのはむつかしい
それを練習しながら いわゆる「現代音楽」の演奏から遠ざかってしまったことを あらためて考える ケージの易やクセナキスの確率関数の利用は 慣習的なパターンから逃れるためのくふうだった それに応える演奏技術も練習法も作られている それとはちがう音楽をさがしているうちに忘れてしまった技術を思い出すべきなのか それとも他の音楽のありかたをさがしているいまは 昔の身体技法ではない 別な技法を見つけるべきなのか
2017年10月1日(日)
水牛だよりそこここで金木犀が香る東京の日曜日。酔芙蓉の大きな木にはたくさんの花が咲いています。咲いたばかりは真っ白。時間がたつにつれて淡いピンクから濃い紅色にまで色づいてきます。花は一日でおわり。おしまいに近いのは花びらが閉じて濃い紅色をしていて、次の日にもそのまま木についていたりしますが、ほんとうに酔っ払っているような風情です。太陽に当たることによって、しだいに赤くなっていくというのが真相のようですが、歩きながら美しい酔っぱらいに見惚れます。
「水牛のように」を2017年10月1日号に更新しました。
大野さんの原稿の冒頭にあるように、「10月は休む傾向が」ある、つまり原稿の数が少ないのは今年も当たっているようです。これまで考えたことがありませんでしたが、何か理由があるのでしょうか。まあ、10月はたそがれの国ではあるのです。とはいえ、先月はお休みだった人が復活していたりするので、ひどく少ないというわけではありません。じっくりと読んでください。
次の更新のときには衆議院選が終っています。日本の政治はもう一歩凋落への道を進んでいるかもしれませんが、日々は続きます。
それではまた!(八巻美恵)
155立詩(3)最後に語る昔話
藤井貞和あったてんがない、とんと昔があってなあ、
にわ(土間)で一本の穂を拾ったと。
あいつはそいつを、鍋ん下、がいがいがい、
小豆とともに炊いて、大きなぼたもちさ、
作ったと。 まだ地面の流れて固まらず、
じんるいは生まれてなかったが、
かみくらを、かみくらを満たさねばならぬ。
いっぱいにして待たねばならぬ。
ほんの少しのま、ことばをつなぐしごとを、
土間の神の語らす。 それでこっぽり。
もう滅亡のときなのかよ、待って。
(「最初に語る昔話」というのが昔話集にはあります。)