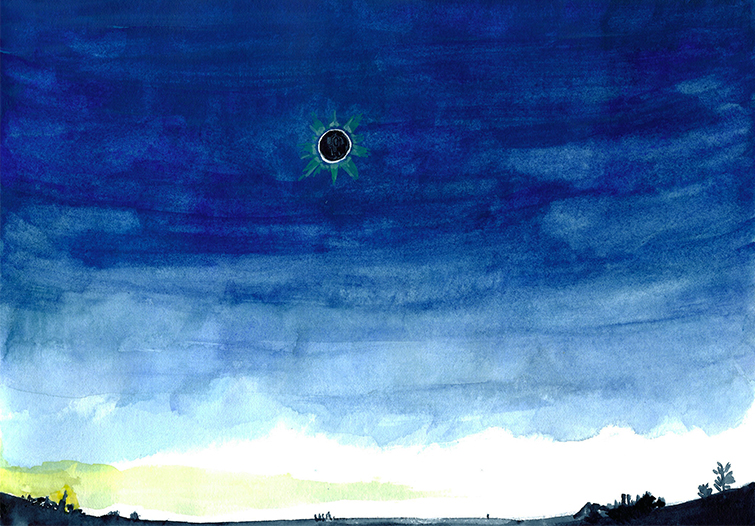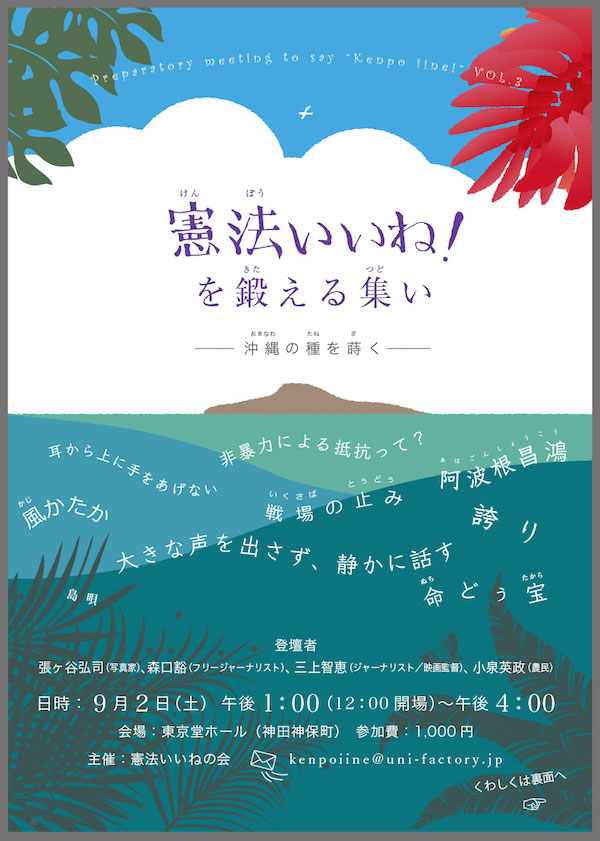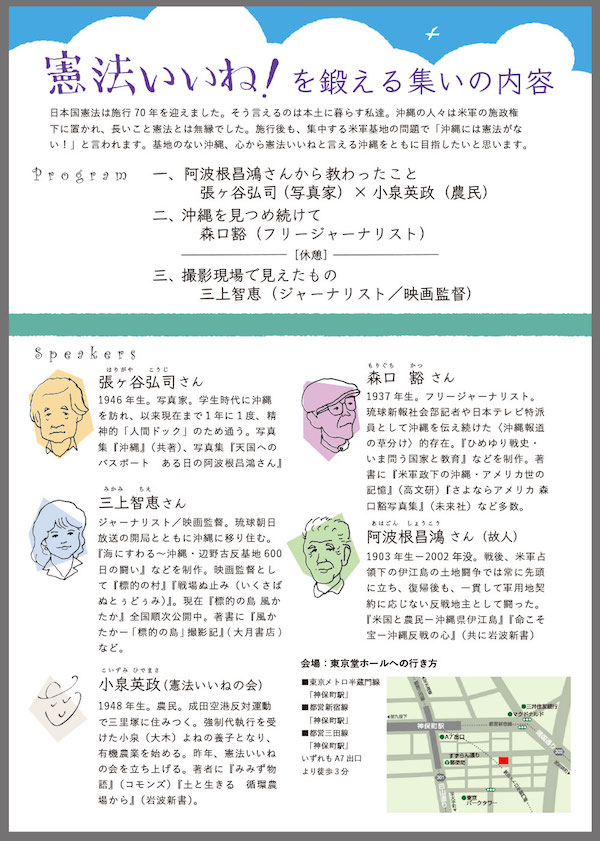練習が終わって家に戻ろうとすると、目の前に雲に墨汁を垂らし一面に広がったような、美しい白黒の空が続いていて、思わず見とれてしまいました。窓際に立て掛けた家族の写真を眺めつつ、日記帳のメモ書きを書き出してみます。政府広報に「ミサイル落下時の行動について」が掲載されたかと思いきや、間もなくJアラートの警報が実際に鳴り響き、それでも目の前の風景はいつもと同じで、自分もごく普通に暮らしている。何も感じないのは、何かが麻痺して感じなくなっているからなのか、そうでないのか。
イタリアに20年以上住んで、政府が「ミサイルが飛翔してきたら」と国民に呼びかけるのを聞いたことはないし、他のヨーロッパ各国を鑑みても、そんな警報が発せられるのは、よほど異常な事態でなければあり得ないのではないでしょうか。
太平洋戦争前夜、国民の大半はこうして何も考えずに普通に暮らしていたのだろうか。井の中の蛙、ではないけれど、気が付いたら周りの風景から、全て色味が抜け落ちていたりするのだろうか。まさか本当に戦争などという馬鹿げた真似はする筈はないと信じていますが、未来永劫、戦争なしにやり過ごせるかと言われれば、それも俄かには信じ難い気がします。
尤も、イタリアに戻れば、ミサイルこそ飛んで来なくとも、どこでもテロと隣り合わせです。本当に不穏な時代になってしまったけれど、その中で自分が音楽をしている意味を考えます。意味はないのかも知れないし、もしかしたら、どこかにはあるのかも知れない。
—
8月某日 ミラノ自宅
大人が座れるようなバランスボールからテニスボールやリハビリ用のスポンジボール、と色、大きさや重さの違うさまざまなボールが家に並ぶ。もともと倉庫を改造した家なので天井も厭に高く、掃除に困っていたのだが、こういう時には都合がよい。フワフワのボールを息子と互いに左手で投げ合う。当初全く力が入らなかったが、不思議なもので、時々息子が「あ、分かった」と叫んで投げると、突然凄い勢いでボールが飛んできたりするので、筋力が落ちているというより、力を入れる神経の回路を思い出しているようにも見えるし、右手、右足と交互に投げたり蹴ったりしつつ、神経に電流を流すコツを見つけているようにも見える。
最近気に入っているリハビリは、綺麗に巻きとってあった包帯を一度解いてから、丹念に丸く巻き直す作業。これは巻くときに力が必要で掌全体も使う動きなので、効果的だという。小学校の算数の最初で一の位、十の位と百の位を学ぶために使う、5ミリ、10ミリ、15ミリの、ほんの小さな色のついたブロックもリハビリ道具だ。目を閉じて左の指の下にこのブロックを置き、大中小のどれかを当てるのだが、案外簡単ではない。
左手や左足に神経を集中すると、すぐに困憊する。仕事をしていると「リハビリして疲れたから抱きしめて」と傍らにやってくる。ピアノを少し弾いてみて、思うように左手が動かないと、右手で左手を持って「もうこんな腕もぎ取ってやりたい」と呟く。
8月某日 ミラノ自宅
「子供の情景」の校正とパート譜を作りを今堀くんに頼んだ。浄書ソフトに暗いものだから迷惑をかけてしまったが、どれだけ助けられたか分からない。息子と日本に発つので3人で朝鮮料理を食べる。肉の食べられない人間が頼めるメニューは、魚のスープと烏賊の辛味炒めと冷麺くらいなので、息子の焼き肉に誰か付き合ってくれると実に有難い。
病気の話になり、今堀くんの近しい知り合いにも左手が使えない人がいると言う。幼少の麻痺が残ってしまったそうで、もちろん息子とは比較にもならない。病院にリハビリに行けば、隣には脚や腕がない人も沢山いて、彼らが明るくリハビリに励む姿に、実はいつも力を貰っている。今堀くんは、今年、ローマのイヴァンの作曲クラスを首席で修了したというから、立派なものだ。2年間彼に学校で指揮を教えて、自分がよい教師だったか分からないけれど、彼は最近特に伸びてきたところなので、是非指揮も続けていってほしい。
8月某日 ミラノ自宅
来月からの息子の学校生活へ向け、慌ただしく準備している。中学の校長に手紙を書き、授業のノートをコンピュータで取ったり、録音したりする許可も貰った。イタリアでは、板書より寧ろ、教師の言葉を書き取って勉強するらしく、長い時間鉛筆を使うのが難しい息子には、少々厄介が伴う。
何時も自転車を頼んでいるマリオには、息子が通学に使う自転車をこしらえて貰っている。リハビリに行こうと混んだ路面電車に乗ったとき、無理に乗り混んできた老人に、重心のまだ定まらない息子は跳ね飛ばされてしまった。その場で老人に凄い剣幕で怒ったので、息子には妙に感心されたが、周りの乗客も一斉に老人を咎めたのに愕いた。哀れな老人は次の停留所で降りていった。
8月某日 三軒茶屋自宅
食事の支度をしながらフランス国際放送のニュースを聴いていて、北朝鮮に名指しされたグアムの特派員の中継になった。グアムでは大きなミサが行われて、信者たちが熱心に神に平和を祈っていると言う。ミサ参列者のインタヴューが流れて、どれだけ自分たちが神に願っているかを切々と話す。日本のマスコミとは目の付け所が違うことに感心する。宗教観の違いなのだろうか。
イタリアにいてもレストランで食事するのは余り好きではない。味は濃すぎることが多いし、どの程度の食材を使っているか分かることもある。家に帰って、自分が好きな素材で、好きな味の料理を作る方が精神衛生上宜しい。
先日、三軒茶屋で夜半何か食べたいと思ったけれど、家には余った大根とシラス、それから実家で作った紫蘇の葉、多少のトマトしか無かった。これらの素材でパスタを作ってみると、思いの外美味だった。
特にイタリアに似た料理はないが、大根はイタリアでよく食される蕪に似ていて、シラスは小魚の湯がきそのものだし、紫蘇も香草なのだから、併せて調理すれば美味しくない筈がない。
自分の好きな量のオリーブ油を使い、好きな塩梅にトマトから果汁を引き出して、シラスから染み出た魚の旨味と合う。紫蘇は使いようによってはバジリコより味が円やかなので多めに入れ、硬めに茹でたパスタを絡めて、ソースで乳化し味が馴染んだところで頂く。これに美味しいオリーブでも入れて煮込めたら文句なかった。
日本のスーパーの食材でイタリア風イタリア料理を作るよりずっと自然で、音楽と同じだと思う。
8月某日 三軒茶屋自宅
秋吉台の講習会が終わり帰宅。
今年はお加減が良くなかった湯浅先生の代わりに、頼暁先生がいらした。頼暁先生は講義の折、音列や構造の抽出の仕方を丁寧に板書されるのだが、それを後から眺めると実に美しい。勿体ないので暫く消さないで欲しいと頼んでも、これは又書直せるからと、何事もなかったかのように消し去ってしまう。
頼暁先生は、講習会の間に、秋吉台の演奏家の名前を使って、弦楽三重奏を作曲された。音列と全体構造までを最初の講義で説明し、後は細切れの時間に作曲されて、新しく書き足された部分が、毎日受付の横に貼りだされていた。基本的な作曲工程が思いの外似ていて、思わず親近感を覚える。ただ、頼暁先生はオクターブ恐怖症で何としてもオクターブを回避するのに比べ、こちらは絶対に同じ繰り返しを強迫的に避ける、繰り返し恐怖症なのが違う。
毎年秋吉台の作曲クラスの後ろに仕事机を置き、皆のディスカッションを聴きながら、楽譜を広げて仕事をする。時々口を挟んだりもするのだが、今年は足立さんがいらして、考えていたことの半分以上は、彼が先に代弁してくれた。そんなに同じことを考えるものかと、内心とても驚いていたのだが、面と向かって足立さんには伝えそびれてしまった。彼の作品で好きな作品もたくさんあるが、基本的に大きな音量が続くと耳が疲れてしまうので、音量の小さい作品はあるのかと尋ねると、そう言われると、確かに音量の大きな作品ばかりだと笑っていらした。
低音デュオの演奏した彼の近作は、面白かったし有難く静かな作品だった。ずるいと思うほど心憎い仕掛けが最後に待っていた。
足立さんが、作曲を学ぶのなら、是非即興演奏も学んで欲しいと言われていたが、尤もだと思う。間違った音楽を排除し、正しい音楽を目指すより、悪い音楽を排し、良い音楽を目指したいと思う。即興はその最たるものでもあるし、もちろんジャズや民族音楽が魅力的なのも、恐らくそこだと思う。
去年自作を指揮していた村上さんが、新しく書いた曲を聴かせてくれる。彼女自身がヴォイスパフォーマンスで参加している室内楽は、物凄く魅力的だった。それに近いことをオーケストラを使って演奏したものは、オーケストラは彼女の魅力を半減させていた。オーケストラは基本的に、西洋伝統音楽を演奏するために発展してきた演奏形態である事実は、如何ともしがたい。それを受入れるか、拒絶するか。さもなくば諧謔に転じるか。
特殊奏法を使えば、音楽の可能性が広がるかと問われれば、それも難しいように思う。西洋楽器は、伝統的な奏法に於いて最も表現の幅が生まれるように発展してきたのだから、特殊奏法を否定するわけではないけれど、可能性を広げているように見えて、案外それは袋小路に過ぎないのではないか。
現在使われている特殊奏法は、プリペアードピアノをはじめ、元来は代替音色の発明だったように思う。現在のようにサンプラーの技術もライブエレクトロニクスの技術も進めば、楽器で特殊奏法をする意味は、もしかしたらまた別の意味合いをもたらす結果になるかも知れない。
作曲学生のディスカッションに登場したコンピュータ浄書は、現代の作曲家にととっては、殆ど必要不可欠になった。譜面とは書くものではなく、最早打つものに変化しつつある。今後、我々はより一層コンピュータに認識されやすいよう、自らを発達させてゆくのかもしれない。そうして思考が画一化してゆくと、個は何を意味するようになってゆくのだろう。そのままゆけば、コンピュータが我々の思考に甲乙を付けるようになるに違いない。
電脳は、ツールではなくなった。
8月某日 三軒茶屋自宅
リハーサルに出かけると、いつも顔を合わせていたメンバーに加えて、古部くんや先週まで秋吉台で一緒だった山澤くん、ずっと会っていなかった菊地くんや斎藤さんの顔を見つけた。振っていると、すごく助けてくれるので嬉しい反面、自分の譜読みがあまりに覚束なく、申し訳ない思いにかられる。
指揮を始めたばかりの頃、「指揮者は、どういう形であっても振り続けていることが一番大切」と古部くんからアドヴァイスを頂いた。とても含蓄のある言葉で、今まで事ある度に反芻してきた。作曲家のNさんが、とても温かい音を出すオーケストラと感激していたけれど、全く同感。譜読みがどんなに辛くても、音が出た瞬間に、一緒に音楽が出来る喜びに払拭される。
練習から帰宅し、千々岩くんのフランクのソナタを聴き、思わず涙がこぼれた。聴き惚れつつ困憊した身体に音が染み通ってゆくのが分かる。一音ごとに音色が変化して、シラブルのイントネーションのように聴こえる。伝える言葉と伝えたい言葉を持っている音楽家は、あれ程淡々と音を紡いでゆくので充分だった。話すように演奏する、という喩えは常套句だけれど、文字通り話すように演奏をしていると実感したのは、初めてだった。名曲過ぎてこのソナタは好きではなかったのだが、考えを改めた。訥々とした深い語り出しに、彼の歩んできた人生の厚みを感じる。
8月某日 三軒茶屋自宅
時間を見つけて母にタブレットを買い、町田に届けにゆく。初期設定をしていて、彼女の誕生日が1935年3月5日なのを見つけた。聞けば彼女は数字の3と5が好きなのだという。この歳になるまで気が付かなかった。
どうして時間は昔に戻せないのだろう。小学校位にまで戻れれば、やり直したいことはたくさんある。やり直せるものなら、今まで自分が犯してきた誤りを全て正した、もう少しだけでも真っ当な人生を送ってみたい。両親はもちろん息子や家人にも、違う自分の姿が見せられたに違いない。ただ、もしそれが出来たとしたら、家人にも、今の息子にも出会えなかった。
(8月31日三軒茶屋にて)