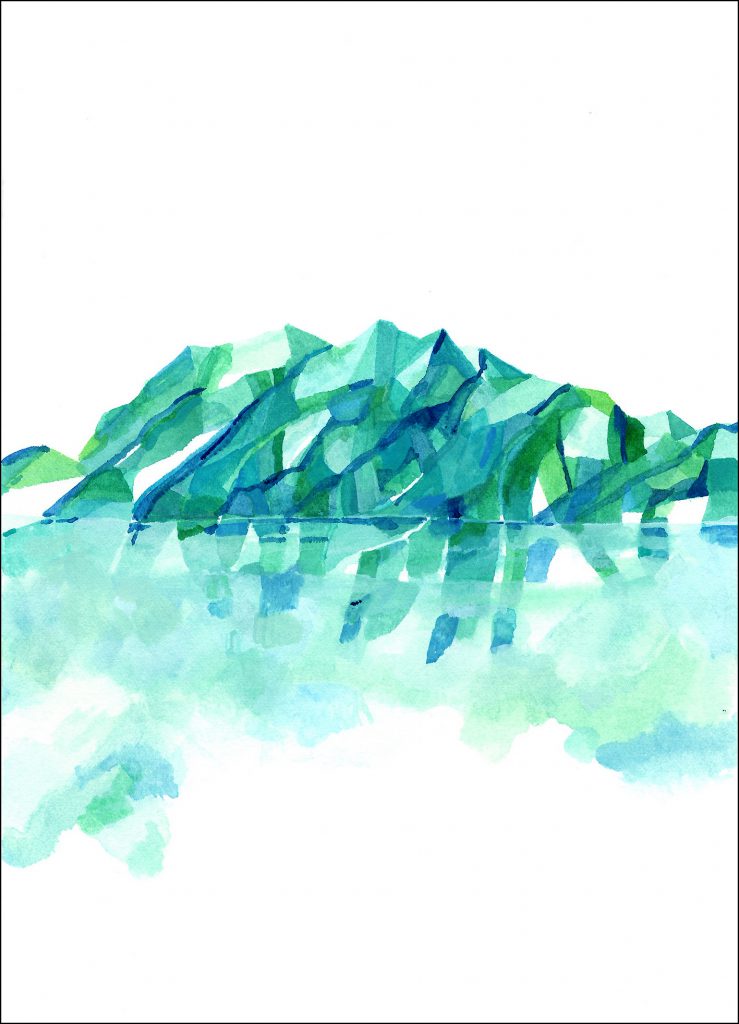前回、ジャワでの伝統「舞踊作品の撮影」について書いたので、今回は私自身が出資してジャワで行った録音の経験について書いてみたい。
私が録音したのは計6回で、うち3回が宮廷舞踊曲であるスリンピやブドヨの録音、2回が自分の舞踊作品のために委嘱した曲の録音、1回が他の人が主催した公演で復曲された曲や創作された曲の録音である。いずれも留学先の芸術大学の録音スタッフに手掛けてもらった。
●雨除け
録音場所は芸大のスタジオで4回、音楽科の教室が1回だが、芸大元学長のスパンガ氏の自宅にあるプンドポで録音したことも1回ある。プンドポとはジャワの伝統的な儀礼用空間で、王宮や貴族の邸宅には必ず設けられている。壁がなく柱で支えられたホールのような空間で、儀礼につきものであるガムラン楽器はこういう場所に置かれている。
スパンガ氏宅での録音については、実は2017年8月号の水牛寄稿記事「ジャワの雨除け、雨乞い」で書いたことがある。この録音は私の宮廷舞踊『スリンピ・ゴンドクスモ』の公演プロジェクトの一環だった。この演奏にはスパンガ氏宅で行われているガムラン練習に参加しているメンバーも多く参加していたからここでの録音となったのだが、それだけでなくプンドポの音響効果が素晴らしいからでもある。スパンガ氏宅は郊外の閑静な住宅地にあり、周囲は水田に囲まれている。とはいえプンドポには壁がないから、夜間に帰宅する車やバイクが家の前の道を通ると、その音が録音に入って困る…というのでその対策で警備係をつけ、家の前を通る道を封鎖して迂回してもらうようにした。実はそれ以上に懸念したのは雨(録音は本格的な雨季に入った11月)で、その対策で霊力のある人に来てもらって雨除けをした…というので、前述のエッセイを書いた次第。インドネシアでは大きな行事の前にこういう霊的な雨除け対策をするというのはわりとよくあることだと思うが、私が録音のために雨除けをしたのはこれ1回だけである。
●スリンピ、ブドヨの録音
スリンピやブドヨの曲は宮廷舞踊曲だから、その権威を示すように多くの人手を必要とする(それだけパートが多い)。私が録音したときの記録を見ると、楽器奏者が約18人、女性の歌い手と男性の歌い手がそれぞれ約4人、クプラ(舞踊家に合図を出す楽器)奏者が1人、計約27人となっている。もっとも、私が芸大のグループと一緒に日本でスリンピ公演した時は楽器奏者と歌い手を合わせて10人。予算の限度があればこんなものである。
この30人近くの人数で40分~1時間近くかかる曲を一発録りをしたのだが、この話をジャカルタの人にしたところ、人件費がものすごくかかると驚かれてしまった。インドネシアでは人件費の地方格差が大きい。2021年の最低賃金で比較してみても、私が留学していたスラカルタ市で月給2,013,810ルピア、一方ジャカルタでは4,276,349ルピアと倍の開きがある。つまり、同じ予算ならジャカルタでは13人くらいしか雇えないことになり、交通費がかかることも考えるとその人数はもっと減る。そのジャカルタの人も宮廷舞踊曲の録音経験があるが、演奏者を5人程度雇い、録音したものに未演奏パートをかぶせて演奏…を何度か繰り返してフル編成に仕立てたという。その人は半分の短縮バージョンで録音しているから、1曲の録音に要するスタジオ経費は私と似たようなものだろう。そのやり方なら人件費は抑えられるうえに、うまくいかなかったパートの録り直しも楽で、演奏技術的にはより間違いの少ない録音ができるのかもしれない。だが、全員で演奏するからこそ生じる音楽の勢いや、息が合った時の醍醐味は薄れるのではないかなあ…という気がしている。宮廷舞踊曲の録音では私もスタジオで踊っているので、特にそう感じるのだ。
私の初めての録音では、実はスリンピ完全版3曲を一気に録音した。今ならこんな鬼のようなリクエストはしない(笑)。これら3曲はスリンピの中でも短くて1曲40分弱だが、音楽はメドレーのように全部つながっている。さらに入退場用の曲がそれぞれ4~5分ずつある。この録音時、3曲目の終わりでこちらの指示以上にテンポが上がってしまった。スリンピでは開始時のテンポ(少し早め)に戻って終わるというのが普通のこととはいえ、いつもより速い。たぶん皆、これで最後、あと少しで終わる!というハイな気分で一致して疾走してしまったのだろう。音楽の勢いみたいなものを強く感じた瞬間だった。と同時に、終盤でテンポが速くなるのは、演出というより演奏者の自然の摂理なのかも…と感じたことだった。
●委嘱作品の録音
上の宮廷舞踊作品とは違って、自分の舞踊作品のために委嘱した2つの楽曲についてはどちらも一発録りではなく、部分的に録音してつなげている。どちらもいくつかの曲から構成された20分余りの作品だ。作曲者も演奏に参加し、演出しながら録音していくというのも伝統曲とは違うところである。
デデッ・ワハユディ氏に委嘱したガムラン曲『陰陽ON-YO』(2002)は、複数の伝統曲と伝統的な手法でデデッ氏が新たに作曲した曲をつないで23分の曲になっている。曲の大部分は5~6人の小編成で演奏するようになっているのだが、最後の6分半は宮廷舞踊曲の演出でフル編成の演奏に斉唱をつけているため、ここは上のジャカルタ方式で録音して、大勢でやっているように見せている。歌も同じ人たちが何度か繰り返し歌って録音したものを重ねている。この方式で良かったと思うのはコロトミー楽器(曲の節目にだけ鳴らすドラなどの楽器)の音入れだ。たまにしか鳴らないが、曲の雰囲気を作るにはそのタイミングだとか音色だとか音量だとかが決定的に重要で、何度か録り直しがあったように記憶している。