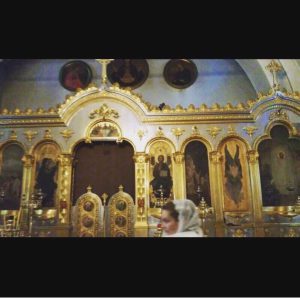12月某日 『現代詩手帖』12月号に「アンケート 今年度の収穫」を寄稿。世界の土地土地から消してはならないことばを「いま」につなぎとめる詩人たちの静かな、しかし揺るぎない意志に敬意を表して以下の本と作品を紹介した。
ウチダゴウ『鬼は逃げる』(三輪舎)
川瀬慈『叡智の鳥』(Tombac)
ミシマショウジ『パンの心臓』(トランジスタ・プレス)
ぱくきょんみ『ひとりで行け』(栗売社)
清水あすか『雨だぶり。』(イニュニック)
和合亮一・吉増剛造「石巻から/浪江から」(『現代詩手帖』連載)
文月悠光の詩「パラレルワールドのようなもの」(『現代詩手帖』9月号)
『現代詩手帖』12月号の「2021年代表詩選」には、ミシマショウジさんの詩集『パンの心臓』より「ヴォイスビートの少年」が掲載されている。
『現代詩手帖』と言えば先月も紹介したが、同誌11月号の「特集=ミャンマー詩は抵抗する」はクーデターによって権力を奪った軍に抵抗する市民たちの声に応答するミャンマーの詩人と日本の詩人たちが、鼎談とエッセイで詩という表現の本質をあらためて問い直す充実の内容でなんども読み返している。月刊誌だから月が変わると多くの書店からフェードアウトしてしまうのがあまりにも惜しい。特集を再編集したブックレット的な本になるといいのに。
12月某日 『神歌とさえずり』(七月堂)の著者で詩人の宮内喜美子さんより、琉球弧の詩人・高良勉さんの主宰する詩と批評の同人誌『KANA』をご恵送いただいた。特集は「沖縄の日本復帰50周年と私」。勉さんのほかに、詩人のおおしろ建さん、今福龍太先生らの寄稿。安冨祖ゆうさ氏の掌編小説も。2021後半の最高の文学のおくりものだ。大切にしたい。
《72年沖縄返還という、沖縄社会の大きな世替りと、日本国家・国境の変更、拡大からの歴史的変化を、同人一人一人がどのように受け止め、考え、生活してきたか。その過程における個人史を大切にしたかった。》
——高良勉「半世紀を」
『KANA』のページをめくっていたら電話があり、それはなつかしい奄美からの呼び声だった。沖縄、奄美、琉球弧へ。サウダージ・ブックスで「群島詩人の十字路」という沖縄の詩をひとつのテーマにした詩集を作ったのが、いまから10年ぐらい前のこと。高良勉、川満信一、中屋幸吉……。琉球弧へ群島詩人の声を訪ねる旅をまたしたい。
12月某日 日本写真家協会・第4回笹本恒子写真賞を渋谷敦志さんが受賞。サウダージ・ブックスから刊行した写真集『今日という日を摘み取れ』の編集を担当したご縁で、東京で開催された授賞式に出席した。フォトジャーナリズムの仕事を続けることの難しさ、そして新型コロナウイルス禍。渋谷さんは受賞のスピーチで「それでも撮れない時間が、自分の写真を深めてくれるとつねに信じている」と語っていた。
同協会会長で写真家の野町和嘉さんからの賞状授与の後、選考委員を代表して雑誌『風の旅人』編集長の佐伯剛さんからの講評があった。渋谷さんの写真には「まなざしのやさしさ」があり、その作品には一人ひとりと関係性をむすび、信頼を醸成する長い時間が込められている、と。すばらしい内容のお話で、編集の仕事をするぼくにとっても感無量だった。
2000年代、ぼくが20代後半のころ、『風の旅人』に掲載された野町さん、セバスチャン・サルガドら世界的な写真家の作品、そして思想家や作家の文章によって、上澄みだけをすくうような皮相な情報からは知りえない世界や時代の深層を見つめるまなざしを鍛えられたのだった。
「生命系と人類」をテーマとする15号は、なかでも忘れられない1冊。毎号隅から隅まで貪るように読み込み、企画・構成・印刷の緊張感あるクオリティに圧倒された。そして編集長の佐伯さんの後記には、つねに妥協や追従や忖度のない読者への厳しい問いかけがあった。写真とことばに向き合う佐伯さんの厳しさには遠く及ばないが、せめてその後ろ姿を見失わないよう本作りの道を歩いていきたい。
12月某日 大阪の南田辺で臨床哲学者の西川勝さんと編集中の「認知症移動支援ボランティア養成講座」に関する本のことなどに関する打ち合わせ。その後、西川さんに誘われて、近鉄を乗り継いで奈良まで行き、奈良女子大学名誉教授で心理学者の麻生武さんが主宰する読書会に参加。麻生さんはご自身の子どもの成長を長期間にわたってつぶさに観察した記録をもとにしたおおきな研究をまとめていて、その成果を近年『〈私〉の誕生』(東京大学出版会)や『兄と弟の3歳仲間の世界へ』(ミネルヴァ書房)として発表している。
読書会のテキストはジル・ドゥルーズ&フェリックス・ガタリの哲学書『アンチ・オイディプス』(宇野邦一訳、河出書房新社)。難しい……。2022年は1年をかけて道元の『正法眼蔵』を読むそうだ。夜の奈良駅前は雪でも降りそうなくらい寒く、つめたい風がびゅうびゅう吹いていた。
12月某日 大阪・北加賀屋の名村造船所跡地で開催されたイベント、KITAKAGAYA FLEA 2021 AUTUMN & ASIA BOOK MARKE(LLCインセクツ主催)にサウダージ・ブックスとして出店。ぼくらのブースではサウダージ・ブックスと先輩の出版社トランジスタ・プレスの出版物を販売。詩、エッセイ、写真の本。また2022年春、サウダージ・ブックスより刊行予定の見本や校正刷、チラシも持っていった。
2日間、リバーサイドのきもちのよい空間でたくさんの人、たくさんの本、たくさんのことばに出会うことができた。祝祭的な市(いち)のにぎわい。コロナのパンデミック発生以降ひさしぶりの「対面」と「接触」、やっぱり人間どうしのリアルなコミュニケーションはいいものだなと実感。
拙随筆集『読むことの風』(サウダージ・ブックス)のほかに、トランジスタ・プレス発行のミシマショウジさんの詩集『パンの心臓』とヤリタミサコ氏のエッセイ集『ギンズバーグが教えてくれたこと』、サウダージ・ブックスの2冊の写真集、『今日という日を摘み取れ』と『霧の子供たち』が売れた。ちなみに『パンの心臓』は初日でスピード完売。
イベントには、ミシマショウジさんとも親交のある自家製天然酵母パン・Pirate Utopia も出店していた。昼過ぎに訪ねると、パンはすでにほぼ売り切れ。残っていた野菜と花の美しくおいしいパンをいただいた。
12月某日 KITAKAGAYA FLEAの2日目。本の販売が落ち着いたところで、ほかのブースを駆け足で見てまわる。『71歳パク・マンネの人生大逆転』(パク・マンネ+キム・ユラ著)を訳した韓国語の翻訳者で編集者の古谷未来さんが出店していた。彼女の紹介する韓国のSSE Projectのアート系Zineがかっこよくて一目惚。ソウルの詩集専門書店wit n cynicalから送られてきた詩の本や6699pressの写真集も購入する。
別のブースでインドネシアの作家ソチャさんの本、台湾旅行記、淡路島をテーマにした本なども。2日間、ほぼひとりで店番をしたのでどっとつかれたが、読みたい本がぎっしり詰まった帰り道の鞄の重みがうれしい。
新大阪駅発、最終の新幹線の車内でキム・ヤンヒ監督「詩人の恋」の上映パンフレットをひもとく。ヤン・ヨンヒ監督「かぞくのくに」で見て以来、すっかりファンになった韓国の渋い俳優、ヤン・イクチェンが主演する映画だ。上映中に映画館に行けなかったので、パンフレットをずっとほしいと思っていたのだが、イベントに出店していたLONELINESS BOOKSのブースで購入することができた。
「詩人の恋」は、韓国・済州島を舞台にした映画。その後Netflixで鑑賞したのだが、なかなかよかった。上映パンフレットに収録された文月悠光さんのエッセイ「悲しみの在り方を問う」の中で、済州の詩人ホ・ヨンソンの詩集『海女たち』(姜信子・趙倫子訳)が紹介されているのを見つける。このパンフレットには文月さんの詩「遠い世界へ」も掲載。
12月某日 KITAKAGAYA FLEAで購入した本やZineで我が家でもっとも評判がよかったのは、寺田くれはさんの『100均商品だけで食品サンプルを作ってみた』(クレハフーズ)だった。大学に通いながら食品サンプル職人養成スクールに通った著者による本。
きつねうどん、サンドイッチ、エビフライ、たこ焼き。これらの食品サンプル作りのプロセスを綴る文章がおもしろく、興味深いルポルタージュとして読んだ。100均の「皮むき手袋」って、たしかにエビフライそのものだ。会場でお会いした寺田さんとはK-POPのことを少し話したのだが、いつかトッポギとか韓国の屋台料理の食品サンプルを作ってほしいと思う。
12月某日 東京・新宿のアイデムフォトギャラリー「シリウス」で、日本写真家協会・第4回笹本恒子写真賞の受賞記念、渋谷敦志写真展「今日という日を摘み取れ」が開催され、最終日に見に行った。在廊していた渋谷さんから2022年の作品や展示のプロジェクトについて聞く。会場では写真集『今日という日を摘み取れ』に収録した作品に加えて、コロナ禍をテーマにしたカラーの新作も展示。年の瀬、熱心に鑑賞するお客さんが途切れることなく訪れていた。
雑誌『世界』12月号に、渋谷さんが寄稿している。タイトルは「「いつ割れるかわからないガラスの上を歩いている」——コロナ病棟の看護師たち」。渋谷さんはパンデミック発生以後、医療者たちのコロナとの闘いをいちはやく最前線で取材したひとりだ。現場から問いかける写真家のことばが胸に重く響く。
《私たちの生活は、もっといえば人生は、彼女(看護師)のようなケースワーカーに支えられている。一方で思う。そんな彼女たちに私たちの社会がちゃんと報いたことがあっただろうか》
12月某日 大阪から神奈川にもどり、横浜・妙蓮寺へ。KITAKAGAYA FLEAで隣のブースで出店していた本屋・生活綴方を訪ね、安達茉莉子さんの絵と文章の展示を鑑賞。タイトルは「穴のあいたひとたち」。いま、自分のこころのどこに穴があいているのだろうか、と内省するしずかなひととき。安達さんのエッセイ『私の生活改善運動』vol.1〜4(本屋・生活綴方)を購入。個に根ざした運動のことばは信頼できる。電車の車内でちいさな本を読みはじめ、心が熱くなった。
12月某日 東から西へ、西から東への旅の道中で、韓国の日本文学翻訳家、チョン・スユンのエッセイ集『言の葉の森』(吉川凪訳、亜紀書房)を読み終えた。万葉集などで詠われた恋の歌、その韓国語訳を灯にして、著者自身の胸の奥にしまわれた思い出にひとつひとつ光をあてるようなすばらしいエッセイだった。
《事物はそれぞれ違うように見えるけれど、私たちは巨大な一つだ。私たちはすべて完全に融合していて、引き離すことができない。自然も人間も国家も人種も政治も、互いに別のかけらのように見えているけれど、私たちは一続きのジグソーパズルの中に生きている。みんなそれを知っているのに、気づかないふりをしているみたいだ。》
本の最後のほうに記された、翻訳者ならではの著者のヴィジョンに深くうなずき、鉛筆でしっかりとアンダラインを引いた。
翻訳という仕事の本質は、単にひとつの言語を別の言語に移し替えることだけではない、とも思う。例えば著者は、あるエッセイの中で「木漏れ日」という古き日本語から連想して、ソウルの夏の夜に「木漏れ月」とつぶやく。存在しない、でもすてきなことばだ。読書の最中、ことばのはざまを生きる経験から開かれるこんな思いがけない創造の風景に遭遇するたび、豊かな気持ちになった。異語でもない原語でもない、人間の声が遠く離れながら呼び交わす未知の「言の葉の森」が目の前に広がる。また読み返したい本。
それからチョン・スユンさんのおかげで、自分は山部赤人の歌がけっこう好きなんだなと気づかされた。「春の野に すみれ摘みにと 来し我そ 野をなつかしみ 一夜寝にける」。赤人って元祖バックパッカーじゃないか、いいね。
12月某日 あいかわらず韓国文学を読んでいる。チョン・セランのSF小説集『声をあげます』(斎藤真理子訳、亜紀書房)を一気に読んでしまった。とりわけ巨大ミミズ譚「リセット」に感銘を受けた。人新世的な視点からの文明批評や環境批評のヴィジョンを物語によって創造するという著者の明確な意志がはっきり伝わってきて、しかもめちゃくちゃおもしろい。
所収の短編「リセット」「声をあげます」「メダリストのゾンビ時代」。いずれもコロナ禍を彷彿させる地球規模の人間社会の苦境が描かれるものの、読後にはそこに参加したいと思わせる希望の場が心の中で開かれる感じ。この勢いを借りて、チョン・セランの長編小説『シソンから、』(斎藤真理子訳、亜紀書房)も読みはじめる。
12月某日 目が割れる、ということばが思い浮かんだ。ぱっかーん、と「見る」という経験が真っ二つに割れて、目の前にまあたらしい道が開かれるような。特別な機会をいただき、在ブラジルの記録映像作家・岡村淳監督の短編『富山妙子 炭坑に祈る』(2020)の映像データを深夜に自宅で視聴し、あまりのすばらしさにモニターの前で打ち震えた。
『富山妙子 炭坑に祈る』は、岡村監督自身がつねに意識しているであろう写真家セバスチャン・サルガドの大著『WORKERS』の対蹠地をなす映像作品と直感した。サルガドの写真群が人間の労働の風景から荘厳なる祈りのマクロコスモスを押し開くとしたら、本作はミクロコスモスへと収斂していくベクトルを持つ。荘厳なるものの対極にある簡素なイメージに、しかしサルガド作品に感じるのと同じ深い祈りが込められているのだ。
炭坑労働をテーマとする画家・富山妙子の素描の細部、スケッチ帳に記された文字を含む線の動きや震えにまで官能的に肉迫する岡村さんの「まなざし」を借りて、特定の時代と場所に生きたはずの坑夫たちの残像が、自分の中で何か普遍的な聖なるもののイメージへ次々に変容していくのを感じて興奮した。
杭のようなものを担ぐある坑夫の素描が「十字架の道行き」に見えたのだ。興味本位の連想ではない。岡村さんは長年ブラジルで社会的弱者のために奉仕するキリスト者を記録しており、岡村さん本人から教えてもらったのだが、当地のカトリック教会堂内に飾られた「十字架の道行き」図も作品の霊感源になっているという。
類例のない作品。これまで岡村さんの数々の作品を「ドキュメンタリー」の範疇で理解してきたが、本作はそれを越える「記録映像詩」という新ジャンルの試みだと言える。最後のクレジットで「構成・撮影・編集 岡村淳」のキャプションが添えられた富山妙子の人物スケッチにも驚愕。音楽は高橋悠治さん演奏のピアノ曲、サティ「ジムノペディ」。すごい作品だ。
12月某日 『声をください』に引き続き、刊行されたばかりのチョン・セランの『シソンから、』(斎藤真理子訳、亜紀書房)を読んでいる。韓国、ハワイ、ドイツ、フランス、そして韓国。戦争と移動の時代である20世紀を生き抜いて4人の子を育てたひとりの女性、美術家で作家のシム・シソンからはじまる女の人たちを中心にした家族三代記。
これも、おもしろい。読書はまだ途中だけど、すばらしい小説でぐいぐい引き込まれている。さまざまな旅の物語を内に抱える女の人たちが一堂に会する小説のおもな舞台が、「ハワイ」というところもしっくりくる。海山のあいだで歴史、文化、人間が混じり合うやわらかなクレオール主義世界。抑圧的で排他的な純血主義社会と対極にあるような。
作中の「シム・シソン」はきっといろいろなモデルを参考にして人物造形がされているのだろう。ちょうど韓国と関わりの深い富山妙子の著作をいろいろ読んでいるところで、彼女が対話した画家・朴仁景のことを思い浮かべた。植民地時代と朝鮮戦争の経験、ヨーロッパへの移住、「シム・シソン」と同じような時代を生きている。
《解放前の朝鮮で、女が画家になるというのはよほど特別のばあいです。……今から六十年以上前に、羅蕙錫は女性解放の思想をもっていたのですから、ほんとうに先駆的な女性だったのです》。朴仁景の発言、富山妙子らとの共著『ソウル-パリ-東京』(記録社)より。これを、シム・シソンの声に重ねてみる。小説の続きを読もう。
12月某日 2009年にサウダージ・ブックスの出版活動をはじめたとき、「先達」と仰ぐ出版社がふたつあった。社会批評的なラディカリズムを内に秘め、文学やアート、知への愛をベースにした個人運動として本作りをおこなう版元。ひとつが佐藤由美子さんの営むトランジスタ・プレス。ビート文学関連書を出している。
もうひとつが小川恭平さんがはじめたキョートット出版。先日、大阪のKITA KAGAYA FLEAで小川さんに会うことができて感激した。キョートット出版のトム・ギル『毎日あほうだんす』は聞き書きの名著、2020年に完全版が刊行された。もんでん奈津代さんの『ツバル語会話入門』もある。
12月某日 高校生の娘が「ほら」とスマホを差し出してきて、同級生が公開のSNSアカウントにアップした今年読んだ本の写真を見せてくれた。その同級生はチョン・セラン『屋上で会いましょう』(すんみ訳、亜紀書房)を読んでいる、と以前娘から聞いていて、もちろんその本も写っていた。
ずらりと並ぶそのほかのタイトルも知れば、ぼくの周囲にいる出版関係者はきっと感涙にむせぶと思うが、詳細を明かすのは控えておきたい。本の森を旅する若い人たちを、そっと見守りたいと思うから。どうか、かれらの先に希望ある道が開かれますように。
小説家、詩人、エッセイスト、翻訳家。世界各地のお姉さんから日本の女子高生たちへ。本作りに取り組む人びとの日々の努力によって、ことばは国境すらこえて次世代にしっかり届いている。それは部数だの何だの数の論理では測ることができない書物の真価だ。
12月某日 ぼくも今年(この文章が発表される時点では去年だが)読んだ本をあげてみよう。2021年に、インデペンデント系のスモールプレスや個人が出版した本から、10タイトル。
安達茉莉子『BECAUSE LOVE IS LOVE IS LOVE!』(mariobooks)
小鳥美茂『Sunny Side』(BEACH BOOK STORE)
丸川愛ほか『聞かせてください、あなたの仕事』(horo books)
植本一子『個人的な三ヶ月』
しいねはるか『未知を放つ』(地下BOOKS)
Sakumag Collective『We Act! #2』
壇上遼、篠原幸宏『声はどこから(文庫版)』
橋本亮二『たどり着いた夏』(十七時退勤社)
大阿久佳乃『パンの耳』5〜10号
安達茉莉子『私の生活改善運動』vol.1〜4(本屋・生活綴方)