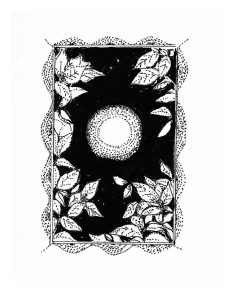空をなつかしむように伸びるポピーを
花環に編むことはしない
曇り空の五月をおだやかに揺らす風が
心を軽く明るく浮かばせて
小鳥はこれからやってくる
果実はこれからふくらむ
犬は首輪を引きちぎり
エンペドクレスの霊を訪ねて火口にゆく
2022年5月号の目次
- 製本かい摘みましては(173) ……… 四釜裕子
- 『アフリカ』を続けて(11) ……… 下窪俊哉
- リンダ・ロンシュタットの物語 ……… 若松恵子
- ベルヴィル日記(7) ……… 福島亮
- しもた屋之噺(243) ……… 杉山洋一
- 「ものを見てかく手の仕事」 ……… 高橋悠治
210 黒雲本
藤井貞和「本日、もう一つ紹介したい本が『逆転の大戦争史』(文春)です。
この本を私は自分の『非戦へ』(編集室水平線)を出版した直後に、
新刊書店で見つけました。ちょうどおなじ時期に出版されました。
この本のカバーの見返しを見て私は驚愕しました。見返しに見る、
キャッチコピーです、「旧政界秩序」では「戦争は合法で政治の、
一手段であった。戦争であれば、領土の略奪も、殺人も、凌辱も、
罪に問われない」と書かれてあります。これは私が書いた趣旨と、
まったく、まったくおなじです。これはイェール大学の法学部の、
先生お二人が渾身の力を込めてお書きになった本だとのことです。
見返しのキャッチコピーに続けて、「「新世界秩序」下に、戦争は、
非合法であり、侵略は認められない」と。「パリ不戦条約という、
忘れられた国際条約から鮮やかに世界史の分水嶺が浮上する」と。
この本にはつまり、私の本とおなじことが書かれているわけです。
私が書いたことをイェール大学の先生たちがフォローしてくれた、
逆かな、この本の海賊版を私が作成した、どちらでもよいですが、
ご紹介しておきます」(佐倉市国際文化大学にて、2020/9/12)。
「〈人類にとり戦争は不可避である〉、だから戦術や戦力を含めて、
戦争を哲学的に考察したり、様々な文学がその中から生まれたり、
という談義が、それらに対して批判的な契機を持たない場合には、
それで終わってしまう。世の中の戦争に関する考え方というのは、
しばしばこのあたりでストップしてしまう。何か戦争にうっとり、
論客が次から次へと戦争論を展開する。まだ戦争学が生まれない、
古代から近代まで、それが第一分類、つまり戦争論でありました。
第二の分類は、ちがうタイプの、たいせつな戦争論であるにせよ、
戦場での兵士、空襲、本土決戦、幼児体験などによる記録や記憶、
文学、映画、アート、戦争忌避、訴え、それらが場合によっては、
非常に強力な反戦の思想などを生み出すことがある、でもそれは、
戦争学の起点になりにくいという現実です。第三に「忘れられた、
パリ不戦条約」とイェール大学の先生たちが、言っておりますが、
忘れられているとしたらば思い出すべき、詩でいえば日本戦後の、
荒地派の詩を忘却から思い出すべき、何か新しい起点が生まれて、
戦争学を始まらせてよいのではないかと思うのです」(同、続き)。
(補足、2022/4/30)
なるほど、専門の方のご本を見ますと、パリ不戦条約というのは、
結局、無駄だったとか、ちょっと戦争を遅らせただけのはなしで、
第二次大戦を起こしたではないかとか、二、三行で片付けられて、
戦争談義にもどりますね。ベルサイユ条約には、米国が参加せず、
敗戦国のドイツに対して多大な賠償金を課して痛めつけたことが、
第二次大戦へとつながってゆく、と。ベルサイユ条約については、
よく論じられる。でも、その8年後の外交の成果でもありました。
それまでは戦争をよしとしていた国際関係から、戦争は悪である、
戦争はやめようと呼びかけて、世のなかが大きく逆転していった、
一九二〇年代の凝縮した時間がここにあるのではないかと思って、
さらに整理して『非戦へ』を作りました。不戦条約という無効性、
そうですね、各国が思惑で参加するという、政治の現実性でなく、
無効に近い百年後、あるいは二百年後へと戦争学は向けられます。
(同、続き)
三要素が〈虐殺、凌辱、掠奪〉(虐、辱、掠)とは舌を噛みそうで、
書けない漢字が並ぶ、ギャグだと思ってくれてよい、と書いたら、
友人が最近になって、「いいえ、けっしてギャグなんかではない、
ギャク、ジョク、リャクはどれが主で、どれが副か、ではないよ、
戦争の三要素だ」と、つよく支持してくれました。難民とは誰か、
虐殺の変形であり、凌辱の変形であり、そして掠奪の変形である、
と言うのです。難民には種類があるにしても、今次の東部欧州の、
虐殺を忌避するから、凌辱を忌避するから、掠奪を忌避するから、
という古典的な戦争であることが、ギャグであってはならないと、
戦争学の必要性を改まりつよく感じた、という友人のメールです。
(黒雲とは、噴煙を見ていると、空気を押しのけるから、
ほんとうは透明なかたちなんだ、と。戦争を見る論客もわれわれも、
惨害を、路上を、崩れ落ちた十五階を、難民を映像で「見る」。
それはそうだけど、戦争学は透明な平和を、非戦を見るんだ。
戦争と戦争とのあいだの端境期でよいから、一九二〇年代から、もう、
百年が経過しつつあるけれど、二百年後に向けてでよいから、
第二次、あるいは第三次ウクライナ戦争のあとでか、阻止できたか、
すべてが透明になり、分かり合え、人類の終わりに立ち会えるように、と、
友人は戦争学を提唱する。佐倉市での「講演」では〈「文学の言葉」と、
「非戦の言葉」〉と題し、『非戦』(坂本龍一、二〇〇二)を引用した。
九・一一のあと、各国の大統領や首相が、これは戦争だ、
テロは戦争だといって復讐戦にはいっていったのに対し、
坂本さんたちは逆に「報復するな、報復しないことが真の勇気なのだ」と、
そんな言い方で始めているというか、終わっている本だ。)
逃げたパン(上)
イリナ・グリゴレある朝、いつものように娘たちと朝ごはんを食べる時、会話に花を咲かせた。私が長女に、蒸しパン食べたいなあ、近いうちに作ろう、と話かけると、次女がおびえて「虫パン嫌だああ」と泣き始めた。昨年まで普通に蟻を捕まえ、ダンゴムシで遊んでいた次女は今年になって虫が怖いと言い始めた。それは幼稚園で他の女の子は怖がるとみて集団生活で虫を見ると=女の子が叫ぶ、逃げるというリアクションを習得したからだ。でも民族によって虫は大事な栄養だし、ママは田舎でたくさんの虫と一緒に暮らしたようなものだと説明すると、彼女も「じゃあ、ピンク色の虫パンだったら…」と納得し始めた。絵が得意な長女はすぐに「虫パン」を書き始めて、そして絵をよく見ると「逃げたパン」というタイトルとなって、描かれた虫パンの上の虫は逃げ始めていると気づく。
この朝の会話で生まれた「虫パン」のイメージがしばらく頭から離れなかった。女の子は虫が怖いということもこんな小さい時から覚えるし、それより虫だらけのパンの絵が印象に残る。ルーマニアで子供の時に初めて暗記したお祈りの言葉の中ではpâinea noastră cea de toate zilele (私たちの毎日のパン)と pâinea spre ființă (存在するパン)という言葉がある。この祈りは誰でも知っている、何があってもずっと心の中でお経のように繰り返していう。ルーマニアの主食はパンなので、この言葉が示している意味は3つある。生活の糧として食べるパン、魂の栄養、聖体儀礼のパンである。こうして考えていくと、ゴッホが初期に描いた「ジャガイモを食べる人々」という有名な絵を思い出す。この絵で農民が食べているのはパンではなくジャガイモなのだ。階層社会のヨーロッパ社会ではパンがどのぐらい「贅沢」な食物であったかが一つのイメージで伝わる。ルーマニアの農民も、パンではなくジャガイモ、インゲン豆、トウモロコシの粉をパンの代わりに主食としていた。
娘の「逃げたパン」という絵を見ると、かわいい虫たちがパンから逃げるというアニメーションみたいなものを想像させられる。今の時代では当たり前のようにパンを食べられるようになったが、いつかこの子供の絵に描かれているように私たちからパンが逃げる時代が来ると寒気を感じる。当たり前であることの当たり前がなくなる気がした。「今」を生きている私たちがいつかの大昔になって、今の食べ物は珍しいものになる。宇宙へ引っ越しして食べる、飲むようになる栄養ドリンク、チューブの中のペーストと、色鮮やかな丸い透明の薬がお皿の上に並ぶ。お皿も必要がなくなるので、陶芸が別の視線から見る「昔の人間の持っているオブジェ」となり、博物館に飾られる。このぐらいのスピードで世界が変わり、追いつかない者からパンが逃げることになるかもしれない。
こうして妄想をしながら、娘が大好きな「ロボットがいるスーパー」へ向かう。昨年からある携帯会社の店の前に置かれているロボットに触れて、娘たちが大喜び。私はどんなリアクションをするのか観察しようと思ってみたのだが、びっくりしたのは、長女は怖がらず、すぐロボットの手を自分の手で触って、ロボットが混乱して認識できないように無駄に手と指を動かした。それでも娘は血が流れてない冷たいロボットの白い指を触って手を繋いだ。人間の子供はこうして無差別にすぐ触りたくなる、手を繋ぎたくなることがよくわかった。娘は「かわいい」とロボットに話しかけた。
人間はこうやって触ろうとするということも、未来ではA Iは人間とはどんな動物だったのかを分析するデータとしてこの文章を見つけるだろう。人間とは触るのが大好き。人間の手は、柔らかくて、温かい。それは恋しいともいう。子供が生まれた時も抱っこしていると最初に感じるのは、「あたたかい、柔らかい感覚」。未来のA Iは人間とは自分の脳に騙されて生きていると思うかもしれない。たとえば、愛という幻はそうかもしれない。でも、私はこのぐらい騙されてもいいと思う。愛だけはパンの変わりにあってもいい。これは人間にとっては栄養だ。毎日のパンのようなものだ。A Iと手を繋いで歩く未来の人間も想像できる。その時には電波で脳が繋がるし、お互いにイメージでお話しができる。もしかしたら、コミュニケーションの面で少し楽な世の中になる。
この前は映像人類学を教える授業で私が尊敬している研究者の映像を見せたら、学生が「匂いまで感じる」、「音楽がすごい」、「触ったような感覚」と言われた。当たり前だが「イメージ」とは五感を通すということを忘れてはいけない。特に若い子はこう感じると気づき、嬉しかった。こうしてみると毎回、新しい命が生まれ、世界がすごいスピードで更新されることは悪いことではない。速度が速いと感じる者もいれば最初からこの速度に合わせて生まれる者もいる。
私の脳に詰まっている祖父母の家のイメージ。匂い、音、家の伝統的な織物の飾りの色、祖母が糸から織った寝巻きの触り心地、風に揺れるカーテンとたくさんの窓からくる眩しい光、庭の葡萄の木の葉っぱの動きと花の匂い、割れるまで成長し、爆発しそうな赤いトマト、キャベツ畑に集まる何百何千ものモンシロチョウ、豚小屋から聞こえる豚のいびきと卵を生む鶏の声、私の足を刺した後に針を無くして死んだ蜂の葬式で忙しい私は、刺されたところが痒い。庭で集めていた死んだ虫のお墓にたくさんの花を飾り、痛痒くて耐えられない足を塩で揉んで、蜂の小さな透明の針を抜いて踊り始める。逃げる虫を追いかけて、足で土を踏んで踊り続けた。
別の授業では、伝統芸能が400年以上前から人から人へ伝えられて、毎回更新されるときのことを喋りながら、将来では人から人へ、ではなく人からA Iへ、そしてA IからA Iへと伝えられることを自然と想像し、必ず続く踊りを想像した。もう一度、娘の絵をみるとパンの上の虫の動きはどうしても踊りにしか見えない。そうか、見方自体でものもスピードも変わる。逃げたパンではなく、踊ったパンというタイトルでどうかなあと娘に聞いてみる。この前もスーパーの駐車場で大きなスピーカーからオルゴールのような音楽が流れて、娘と3人で踊り始めた。駐車場で踊るのも初めてだ。
昨年見た夢。祖父母の村で他の子供と裸足で遊んでいたら、突然大きな音とともに地面が揺れて、目が耐えられないような光と爆発で倒れる。「逃げて」という声に従い祖父母の家に向かって埃と煙を吸いながら、逃げようとしている子供の自分がいた。すると、家の遠く、駅の近くに原発のような建物が見えて、その上にもう一つの太陽が煙の中で光っていた。太陽が二つあるようなイメージだが、家の向こうの太陽は少しずつ核のような丸い光に変わって、周りから「そっちに見ないで、目が見えなくなる」という声が聞こえる。「もう、遅い、見ちゃった」と思いながら夢から覚める。
火星には二つのお月様があると娘に絵本を読んで知ったが、綺麗な景色だと思いつつ、もしかしたら、独裁者は火星のお月様が一個、ほしいのではないか、とつい思っちゃった。
草を食む。
越川道夫今ということを味わっている。
味わっているとは、言葉通り「食べている」ということである。野の草を食べることにしたのだ。今までも、猫の額ほどの小さな庭に生えるユキノシタや明日葉を摘んできて、天麩羅にして食べるほどのことはあったが、今年の春はそれどころではない。虎杖をポキっと折れるところまで折ってきて、皮を剥いだ茎をさっと茹でてポン酢をかけたり炒めたり、思いつく限りのことをして食べる。すると、これが独特の酸味があって爽やかでうまい。虎杖だけではない。蓬を、蒲公英を、野芥子を、ハルジオンを、酸葉を、三つ葉を、蕗を、伸び始めた葛の芽を、蕎麦の葉を、羊蹄を食べる。カキドオシの紫の花が咲き始め、その葉を摘んできて茶にして飲む。いただいた白木蓮の花を、食べられるからと天麩羅にしたのが始まりだったかもしれない。大ぶりな白く開き始めたばかりの花を丸ごと天麩羅にして食べた。すると生姜に似た風味の中に花の甘みが口の中に広がり、その初めて口にする「味」にひどく感心してしまったのだ。野の草の味は、スーパーで買ってきた野菜たちの味とはまるで違っていたし、「旬」ということがあるのならば、これこそが「今の味」であった。春は駆け足で去っていき、野の様相は刻々と移り変わり、少し目を離すと今まで生えていた草が、もうその後から勢いを増して伸び始めた草の下になり見えなくなる。同じ草でも日が経つにつれ、柔らかかったものが固くなり食感だけでなく味すらも変化する。面白いのは、野の草を食べようとすると、そのどれもが微量の毒を含み、その毒が独特の風味にもなっているのだが、また別の草にその毒を打ち消すような効用があって、それもまた微量の毒を含んでいるということだ。
今までは野の草を見ることが楽しみであった。見ることが楽しみなのであって、名前はそれほど重要ではない。名を知っている草もあれば知らない草もあり、何度調べても名を覚えることができない草もあった。だが、それでも構わないのだ。その草ひとつの個性豊かた形を愛でることが楽しいのであって、草はどんな草でもただ生えているだけでよかった。その受用は今も変わらないといえば変わらないのだが、食べ始めるとその草の名前を覚え始めたのは何故だろう。愛着だろうか。確かに、野の見え方が今までとは変わってきたのを感じている。親密さ。その親密さとは、私はそこの草を食べ、草はそこに生えている。私も草も同じものだというような「親密さ」である。私は外から来て、その「草」を鑑賞する者ではない。「私」と「草」は同じ場所に「生えている」というような…。
昨年来、身の回りで何人もの人たちが、この世を去っていった。先月もまた出会って数十年になる旧知の友人が逝き、数日前にも年長の恩人とも呼ぶべき人が亡くなった。仕事場に向かう川縁には大きな桜が連なって生えており、毎年春の時期には人の目を楽しませてきたものだが、昨年の秋から冬にかけて、おそらく行政の指示を受けた業者がやってきてその枝を伐採していった。理由はいろいろとあろうが、それは「無惨」としか呼びようのない切り方であって、今年も桜は咲くには咲いたが痛々しいまでの有様となり、例年に比べ足を止める人の姿も寂しかった。近所に道を覆わんばかりの見事なスダジイの大樹があるのだが、これもまた道に張り出した枝をバッサリと切ってしまい変わり果てた姿を晒している。木に何か憎しみでもあるかのような切り方なのである。胸がつぶれるような思いを抱きながら、野の草を食みながら、私はダラダラと長く生きていようと思った。まもなく桑の実が赤く熟れる。
製本かい摘みましては(173)
四釜裕子田中邦衛出演の映画特集をCSでやっていて、折よく『大日本スリ集団』(1969)を見た。スリ集団の親分・平平平平こと三木のり平と、スリ係の刑事・船越の小林桂樹が主人公だ。船越はひとり娘の将来を心配するあまり、戦友でもある平平に奇想天外なシゴトを頼むのであった……という筋だが、「スリは指の芸術」という平平親分(組合長と言ってたか)による新人教育が可笑しい。最大の道具である人差し指と中指を鍛錬するために熱い湯と水に交互につけたり、両手を上下から背中に回してつなぐのを交互にやったり、自らも、半紙をしわくちゃにしたようなものをちゃぶ台に重ねて、その中からさっと一枚抜き取るような訓練をするのであった。それを眺める若き恋女房、高橋紀子の横顔。ちゃぶ台の端には食べ終えたスイカがふた切れ。手前に黒電話。隣の部屋にはスリ仲間が残した小さな二人の子どもが寝ているようだ。
スリというのは、人差し指と中指でものをつかむことが多いようだ。映画『スリ』(2000)でその手つきを大きく見たことがある。まともに真似ると指がつる。映画では、アル中に苦しむ原田芳雄がスーツを着せたトルソーを前に何度も練習していた。弟子入りしてきた青年には「けなげにやれ!」と喝を入れていた。『フォーカス』(2015)のウィル・スミスはスリというより三代続く詐欺師だったが、弟子入り志願の女性には心理戦を説き、「スリは暗闇のダンス」などと言ってたな。ひたすら「気づかれないように」を信条とする一派とは全く別ものなんだろう。
慶応2年(1866)に生まれ、明治の東京でスリ集団のボスとして名を馳せた仕立屋銀次は、もともと御徒町あたりで仕立屋をしていたのが名の由来だそうだ。指先は器用だったに違いなく、しかし親分になってからは自ら手をくだしたことがないのを”自慢”していたと、本田一郎さんが『仕立屋銀次』に書いている。
〈「わっしゃあ、長えこと掏摸の親分をしていたが、自身で手を下して、他人(ひと)さまの物をかすめたこたあ、ただの一度もごぜえません。これだきゃ、わっしの自慢でごぜえますよ」〉
銀次は紙屑問屋と銭湯を家業としていた家に生まれた。父親が数年後に刑事になり、家にヤクザなども出入りするようになったとかで、十三歳で日本橋の仕立職人のもとへ年季奉公に出されている。年季があけると、早々に結婚して下谷御徒町に店を持つ。腕がよかったんだろう。近所の娘たちが稽古に通うようになり、中の一人と恋に落ちる。その娘の父親がスリの親分で、銀次は実父ゆずりの親分肌だったのか、義父亡きあとはそちらの稼業を継ぐことになる。このとき銀次、三十二歳。
〈銀次は金杉御殿で、愛妾おくにの膝枕をしながら、部下五百の乾分と、全国各地の兄弟分の活動が、手にとる如く判っていた。おくには、銀次の傍にあって、乾分から刻々集まる情報や、稼ぎ高を一々台帳に記入する。台帳は乾分の名前を索引にして、四十二冊ある。〉
こうして羽振りよく稼いだあげくの明治42年、銀次は御用となる。赤坂署に連行されるときの銀次はこうだ。
〈五分刈頭に山高帽を冠り、鼻下に八字髯、本フランネルの単衣物にセルの単羽織をはおり、鼠色縮緬の兵児帯に紺足袋を穿いた。左手薬指には白金の指輪を光らせ、甲斐絹細巻の洋傘を杖いて、ひかれ行く。〉
押収された中に、おくにがいちいち記入したという贓品台帳もあった。
〈贓品台帳は頗る珍品で、西洋紙綴りで厚さ一寸、四六判型に作り、表紙には鴛鴦の絵を描き、二百五十円也というような落書がしてある。〉
三岸好太郎による『仕立屋銀次』の表記絵や当時の銀次のいでたちからすると、この台帳は大福帳スタイルで、おくには筆で書いていたのではないかと想像するが、「西洋紙綴り」で「四六判型に作り」というのはどういうものか。洋紙を切って大福帳みたいに仕立てていたのか。「厚さ一寸」というから少なくとも中綴じではないだろう。そのあたりまで詳しくは書かれていないけれど、本田一郎さんが出所後の銀次に初めて会ったとき、銀次はこう言っている。
〈「ええ、お待たせ申しやした。あっしが銀次でごぜえます。さあ、どうぞ、おあてなすって、洋服じゃ座っちゃ窮屈でげすよ。お楽くになすって下せえ。あっしゃね、こうめえても、でえのハイカラで、若え時分には、洋服がでえ好きでげしたよ」〉
明治の東京で、でえ(大)のハイカラだったスリの親分は、大事な贓品を記すのにどんな帳面を使っていたのだろう。
「市谷の杜 本と活字館」で開催中の「100年くらい前の本づくり」(監修 木戸雄一)の資料を見てみる。日本では1870年代末には本の洋装化が進められたが、需要はあってもその技術や材料が追いつかなかった。それに応えるかたちで〈平綴じの本体にクロスでつないだボール紙の表紙でくるみ、見返しを見開き一枚で接続する〉簡易な方法が広まったのではないかとある。東洋社や慶應義塾出版社が、明治9(1876)年頃から四六判の安価なボール表紙本で啓蒙書を刊行したそうだ。また〈固い表紙を使わず紙一枚でくるみ表紙にする仮綴じ製本〉は官庁刊行物になされていたが、1870年代後半には文部省の「百科全書」などの書籍にも見られるようだ。展示会場ではこれらの実物も見ることができる。
こうした本を銀次も目にはしていただろう。仕立ての腕がある銀次なら、それを見て真似ることもたやすそうだ。はやりの洋紙を重ねて穴三つ、ささっと平綴じして一枚の紙でくるめばできあがりだ。和紙ではなく洋紙、そして背があるだけで、十分ハイカラだったろう。この時分、まだそういう「商品」があったようには思えない。ここで今一度、『仕立屋銀次』で贓品台帳の復習をしておこう。どんなことが書かれていたのか。
〈おくにの手になった当時の台帳を繰って見る。/×月××日 細目の安/午前七時から上野、品川の線を使って午前十時、新橋で金マン一つ。/午後四時、黒門町でナマ三十ぱい。〉
これはやっぱり筆文字がよく似合う。罫線もかえって邪魔だろう。
そこで今度は、webマガジン「文具のとびら」で、たいみちさんの「文房具百年」のバックナンバーを見てみる。たいみちさんが蒐集を続ける文房具の写真も美しく、参照元の資料も明快でとても楽しい連載だ。23回目の「日本の洋式帳簿、その始まりの頃」(2020/03/20)と、41回目の「明治以降の日本の帳簿の話」(2021/11/20)で、明治初期の洋式帳簿についてこう書いてある。
〈明治初期の洋式帳簿はどのようなものであったか。前出の第一国立銀行の社史「第一銀行史」にはシャンドのことと共に当時の帳簿について詳しい説明がある。それを見ると最初からすべて洋式帳簿を使用していたわけではなく、一部は和紙に罫線を印刷したものを綴じて使っている。和風の帳簿に中身は英国の簿記に従った記載方法を、筆記具は毛筆で書いているという、いかにも過渡期を感じさせる状態だ〉。
さらに、明治32年には商法で「商人は帳簿を備へ之に日日の取引其の他財産に影響を及ぼすべき一切の事項を整然且つ明瞭に記載することを要す」と定められたそうだが、これで〈洋式帳簿の利用が進んだということはなく、大福帳などの和式帳簿に一切の事項を整然と書いただけだったという〉。
スリ稼業に「帳簿」は求められなくても、銀次チームの台帳はやっぱり洋紙を束ねた大福帳スタイルだったかもしれない。そしてここに付け加えたい妄想は、それを銀次自らが作ったということ。銀次は〈子分たちには豆帳を持たせ、いつどこで、いかなる方法でスリに成功したか、日誌をつけさせた〉そうでもあるから、小さな帳面などというのも、ささっと見本を作ったかもしれない。なにしろ銀次は、刑務所でよく裁縫をしていたそうだ。本田一郎さんにそう言っている。スリのボスのくせに自ら手をくださないことを自慢していたなんて、それが親分というものなのかもしれないけれど、どうも銀次は、それを自分の指に言い聞かせていたような気がしてならない。
『アフリカ』を続けて(11)
下窪俊哉 前回の続きで、井川拓『モグとユウヒの冒険』を本にする話。自分で立てた予定を押しに押して、4月の終わりが見えてきたところでようやく仕上げ、入稿をすませたところだ。
締め切りがないといつまでも仕上げることが出来ない、とは思うけれど、あまり締め切りに急かされるのも嫌だ。焦って、納得していない状態のまま出してしまうのは止めたい。ただ、どうなったら納得するのか、と言われるとうまく説明出来ないのだった。これでよし! という瞬間は必ず訪れるので、そのタイミングでいったん終わらせる。そういう瞬間がいつまでも来なかったら? なんて考えるのは止そう。いつかは来るのだから。
完璧な仕事はない。完璧を目指していたら永遠に完成しない。少しだけ欠けたところのある方が親しみやすいかもしれないし、つくっている人たちの手が感じられる。ついでに言うと、ミスも面白い方がよいかもしれない。文章であれば読んでいるうちにどんどん自由になってゆき、ついには文字が踊り出して飛んで行ってしまうというのをよく思い浮かべる。とはいえ、今回の本は遺稿であり、著者に何か提案したり、相談することが出来ない。自分の仕事は読めるように、読みやすいように整えて、なるべくそのまま出すことだ、と考えていた。
私は本や雑誌をつくるのに編集会議をしない。編集するのは自分なのだから、やりたいようにやりなさいよ、と声をかけてあげるくらいだ(自分で自分に、ね)。ただし決定するのが自分だというだけで、相談はする。いつも誰かに相談していると言ってもいいくらいだ。『モグとユウヒの冒険』の場合、著者の姉・伊東佳苗さんとは殆ど毎日のようにやりとりをして、お互いの感じていることを言語化してキャッチボールしていた。装丁と挿画を頼んだ髙城青さんは、もう少し引いた視点で制作中の本を眺めて、その見え方を話してくれた。集まって話をすることはない。いつでも個別に、1対1でやる。校正にかんしてはいつものように黒砂水路さんに手伝ってもらった。彼は私の気づけないようなミスをしっかり指摘してくれるし、今回はルビの提案もしてくれた。それから、映像制作集団・空族の富田克也さんとも久しぶりに話せた。著者が生前、どんなふうに創作活動に向かっていたかを一番よく知っているひとりではないか、と思って声をかけたのだった。私の書いた井川拓伝というべき解説も、富田さんが追悼文集に書いた文章「二度目の不在」が手元になければ書き得なかったかもしれない。没後11年たって、いまだから話せることもあるから、と何時間も話し込んだ。
そうやって話をしてゆくと、自分の知らなかったことも出てくるし、ただ読むだけでは感じられなかったことも感じられてくる。本をつくるということは、その作品を新たに読み解いてゆく、ということなのかもしれない。その作業がないとどうなるかというと、いわゆる本という既成の枠組みに作品をはめるだけになってしまう。ある程度は仕方がないとしても(本ができないのも困る)、それだけでは私は納得しない、というか大いに不満なのだ。
そうなると、手元にあるゲラが未完成の原稿なのだ、というニュアンスが自分の中で強まってきた。これは遺稿なのだ。そのまま出せばいいのだと思う一方で、本にするからには完成させなければ、という気持ちが出てきた。そう思ったところで著者はもういないのだからどうしようもない。あのとき死なないでほしかったよまったく。その憤り(?)は、校正でピークに達した。最初の頃は、明らかなミスだけを修正しよう、などと言っていた。しかし、どこまでが明らかで、どこからは明らかでないのか。加筆が必要なミスは、どう加筆するのか。迷いがあったのだが、やってゆくうちに吹っ切れてきて、「著者はおそらくこんなふうに書きたかったのだろう」という想像を元に修正することにした。例えば印象深かったのは、「悴(かじか)む」ということばを、こどもが家では泣き虫なのに学童保育所では泣けない訳として書いている箇所で、佳苗さんから出てきた「心が悴む」にしたらどうか? という提案。あれには痺れた。心が悴むかあ。そこの加筆は「心が」の2文字ですんだ。
「井川くんから完成物というものを受け取った試しがなかった」と富田さんは言っていた。20代の頃、富田さんは映画をつくりたい、井川さんは小説を書きたいと話して、お互いの創作物を見せ合っているような仲だった。「俺には、映画は完成させなきゃって言うわけ。そういうもんかあと思って感心してさ、頑張るんだけど、そう言う彼はいつも出来ないの。最初、すんごい抽象的な構想だけぐわーっと聞かされて、こっちは待っている。そろそろ書き終わるのかなと思っていたら、何だか途中で息切れしてる。いやあ、ダメやわ、とか言って。で、次の作品の構想に行くんだけど、やっぱり完成しない。延々とそれをくり返してるような人で、本人も思い悩んでいた」
でも映画は共同作業なので、映画『エリコへ下る道』のシナリオはいちおう書き上げられて、ある程度まで撮影されたらしい(どんな映画だったのか、いつか機会を設けて書きたいところだ)。でも、「彼が本当に書きたい小説というものにかんして、完成したことは一度もなかったんじゃないか」と言う。
私は亡くなる直前の8ヶ月間の付き合いしかなかったが、そういう人だったと言われて驚きはしない。まあそうだろうと思う。だから、そんな彼が『モグとユウヒの冒険』をかなりのところまで仕上げて、残してあったことの方に驚いたのだ。これはある種の奇跡なのかもしれない。いや、そうやって煽るのは止めよう。それまでの構想は全てボツになったとしても、これは書けた。『モグとユウヒの冒険』の構想は、持続するもの、長く生きるものだったのだろう。よく書きましたね! と声をかけてあげたいのだ。
富田さんはこんなことも言っていた。「子供のために書くんだとか、例えば甥っ子のためにこれをつくるんだとか、そういうふうに限定してやったことで完成させることが出来るというか。本当の意味で広げた大風呂敷というのは収拾不可能で、自分の文学的達成というのはそこにあったんだろうけど、児童文学を目指したのは対象を限定するということだったんじゃないか。自分の内側にあるものを吐露しようとしたら完成させられないんだけど、誰か人のためにということになって初めて、書けたんじゃないかな」
何だかわかる気がする。私はそこに付け加えて、限定することで広がる、普遍的になることもありますね、と話していた。まだまだこれからの作家だったのだ。
水牛的読書日記5月
アサノタカオ4月某日 毎月はじめの更新を楽しみにしているウェブマガジン「水牛のように」の各連載。うんうん、4月号はこんな感じか、どれから読もうか、などと目次を眺めていて、ふと気がついた。あれ、自分の、「水牛的読書日記4月」が、ない……! 瞬間、頭の中が真っ白になった。連載の原稿を書くことも、八巻美恵さんに送ることも、完全に忘却していたのだ。
4月某日 明星大学人文学部日本文化学科の非常勤講師に就任した。「編集工学」という講義を担当。神奈川の自宅から東京・日野にある明星大学に通うには途中、分倍河原駅で乗り換え(JR南武線⇄京王線)をするので、行き帰りに駅前のマルジナリア書店に立ち寄れることがうれしい。7月には、大阪の阪南大学国際コミュニケーション学部の総合教養講座で外部講師として話すことも決まった。その頃にはしばらく西日本に滞在していると思う。
4月某日 毎年この季節には、ホ・ヨンソン詩集『海女たち』(姜信子・趙倫子訳、新泉社)をひもとく。韓国の詩人でジャーナリストでもある著者が済州島の海女たち、女性たちへの聞き書きをもとに詩を書き、一冊にまとめた本。
《生きているときは 一度もあなたと一緒に触れることのできなかった/夜の海 ひとり水に身をあずけましょう/赤い唇のような椿の花に包まれて/青い舌のような波のしとねに横たわりましょう……》
1948年、済州島でおこった四・三虐殺事件をテーマにした詩のことばと向き合う。
4月某日 雨の日に、神奈川・大船にある最寄りの書店、ポルベニールブックストアで買い物。ゆっくり棚を眺め、雑誌『中くらいの友だち 韓くに手帖』10号などの注文しておいた本を買った。
4月某日 イ・ヘミのルポルタージュ『搾取都市、ソウル』(伊東順子訳、筑摩書房)を一気に読了。ここ数年、小説を中心に韓国文学をいろいろ読んでいるが、こういう韓国社会の今に迫るノンフィクションを読みたかったのだ。おもしろかった。
ソウルで「チョッパン」と呼ばれる最底辺住宅に暮らす人びと、その背後に存在する「貧困ビジネス」をめぐる韓国日報記者の調査報道ルポだ。生々しい格差の現実を伝える文章の随所から、「幼い頃から貧困と戦ってきた」という著者の歯ぎしりも聞こえる。本書では「はじめに」で「私」が「貧者の物語を書く」意味があらかじめ示されている。著者の主義主張ははっきりしているが、語りや文体はクールで私情に溺れることはない。ノンフィクションの内容のみならず、こうした叙述のスタイルも興味深いものだった。
4月某日 東京・学芸大学駅近くのSUNNY BOY BOOKSへ、サウダージ・ブックスの本を納品。新しく作ったPOPも届けた。書店で、自分たちが作った本と読者とのよい出会いがつづいているようだ。
4月某日 香川・高松から仕事で東京にやってきた写真家・宮脇慎太郎と目黒のふげん社で待ち合わせ。2015年、移転前のふげん社のギャラリーで開催されたライター・編集者の南陀楼綾繁さんの企画「地方からの風」の中で写真集『曙光』(サウダージ・ブックス)刊行記念の展示をおこない、南陀楼さん、宮脇くんのトークイベントに自分も写真集の編集者として出演したのだった。
今回、リニューアルオープンしたふげん社へようやく訪問。さらにすてきなギャラリー&ブックカフェの空間になっていた。この場所を拠点に『Sha Shin Magazine』の発行や「ふげん社写真賞」の活動もスタートしている。写真評論家の飯沢耕太郎さんとばったり遭遇した。
4月某日 社会学者・見田宗介氏の訃報に接する。見田氏が「真木悠介」として書いた『気流の鳴る音』(ちくま学芸文庫)を読もうと思い立ち、本棚の中を探すが見つからない。本書の初版が刊行されたのは1977年。学生時代から数え切れないほどなんども読み返し、旅先で知り合った人に渡したり、メッセージを残すような気持ちで宿の本棚に置いてきたりして、なんども買い直している本。どこにいってしまったのか。
1983年に刊行された詩人・山尾三省の宮沢賢治論『野の道』(野草社)には、真木悠介さんの「呼応」という序文が掲載されている。2018年に本書の新版を編集した際、三省さんらのヴィジョンに応答できるのはこの人しかいない、と文化人類学者の今福龍太先生に新たな解説の執筆を依頼したのだった。先生は「土遊び、風遊び、星遊び」というすばらしい文章を寄せてくれた。
そして刊行後、当時すでに体調不良のため外出を控えていた真木さんから美しいメッセージが届き、本屋B&Bで開催した今福先生のトークイベントで朗読してもらった。宮沢賢治、山尾三省、真木悠介、今福龍太。『新版 野の道』という本には、詩人思想家たちが呼び交わす声がぎゅっとつまっている。かれらが共有するヴィジョンは、ひと言でいえば「アニミズムという希望」。よい本だと思う。
4月某日 くまざわ書店武蔵小金井北口店では「かまくらブックフェスタ」がスタートし、サウダージ・ブックスも参加することになった。フェア用の書籍やPOPを発送。サウダージ・ブックスの本は少部数の発行で基本的に直接取引店のみで販売している。全国規模の書店チェーンの棚に並ぶめずらしい機会となる。
4月某日 陣野俊史さんの新著『魂の声をあげる 現代史としてのラップ・フランセ』(アプレミディ)が届く。装丁がすばらしい。フランスのラップをテーマにした本だが、注釈など編集的な配慮も行き届いていて、YouTubeで音源を探し、聴きながら読んでみよう。
4月某日 新横浜から新幹線に乗り、広島の福山へ。編集の仕事をしようと「オフィス車両」の指定席をとったのだが、はかどらず。なぜかというと、道中ですごい小説を読み、没頭してしまったからだ。そして一冊、読み切ってしまった。
韓国の作家ファン・ジョンウンの小説『年年歳歳』(斎藤真理子訳、河出書房新社)。母と娘たちの物語、感想を書きたいがことばがなかなか出てこない。噛み切れない思いが自分の外に向かわず内に沈んでいく感じ。そして胸騒ぎが収まらない。いや、胸塞がる気分が、といったほうがいいだろうか。最後のページを閉じた後、岡山を過ぎたあたりの山あいの風景を眺めながら、「家族」として出会いながら「人間」として出会うことなく別れたものたちのことを、ふと思い出した。
4月某日 福山では「風の丘」という眺めのよい場所にある本屋UNLEARNへ。サウダージ・ブックスの新刊、四国・宇和海に面するリアス式海岸の土地とそこに生きる人々を写したで宮脇慎太郎写真集『UWAKAI』の刊行を記念して、店内のギャラリーで収録作品のオリジナルプリントを展示、宮脇くんと編集を担当した自分のトークショーを開催することになったのだ。彼とともに本を作るのも、これで3冊目。
全国的に新型コロナウイルス感染症対策としての「まん延防止等重点措置」が解除されたことで、県境を越える移動を含む行動制限が緩和されたタイミング。各地で店舗営業やイベント開催をめぐる「自粛」ムードがやや薄まってきた感もあるが、コロナ自体が終息したわけではない。このような状況で、しかしありがたいことにトークショーの会場は満席御礼。イベントの前半は『UWAKAI』収録作品のスライドショー、後半は「四国発、ローカルで写真集をつくるには」をテーマに対談をおこなった。
開始前、本屋UNLEARNについてある常連のお客さんが「ここは文化の灯を守る場所」と語るのを聞いて、ぴったりの表現だと思った。そんな書店に流れる独特の気品のある空気にうながされるようにして、本作りにおいて自分たちが大切にし、守りたいと願うことを語り合う密度の濃い内容になったと思う。
写真集『UWAKAI』をあいだにはさんで、参加者のみなさんとのよい出会いがたくさんあった。店主の田中典晶さんからは、写真集について「厳しさ、畏怖を感じる」と評してもらい、うれしかった。店内の棚に真木悠介『気流の鳴る音』の文庫をみつけたので購入、福山駅前の沖縄料理店で食事をした後、宮脇くんの車に同乗して高松まで2時間ほどの夜のドライブ。
4月某日 高松で終日、書店めぐり。午前中は宮脇書店本店、ジュンク堂書店高松店へ。午後は瓦町界隈の完全予約制の古本屋なタ書、本屋ルヌガンガ、古本屋YOMSを周遊。そして高松港近く北浜まで足を伸ばしてBOOK MARÜTEへ。MARÜTEでは、写真家の川島小鳥さんと画家の小橋陽介さんの展示を鑑賞。
本屋ルヌガンガで店主の中村夫妻から売れ筋の本のことをいろいろ教えてもらい、出版企画のアイデアが次々に湧き出す。韓国文学、人類学、ローカル……。資料として気になるテーマの書籍をいろいろ購入。中村涼子さんから、話題の料理家ウー・ウェン氏の著作をすすめられ、こちらも数冊購入。新刊の『ウー・ウェンの炒めもの』(高橋書店)は装丁や造本がすばらしい、と思ったらアートディレクション・デザインを担当しているのは、尊敬する関宙明さんだった。
ゆっくり本を探しながら書店ですごす時間は幸せな時間。書店めぐりをしながら、あらためてそう思った。おもしろそうなZineもあれこれ買った。
4月某日 本屋ルヌガンガで、宮脇慎太郎写真集『UWAKAI』刊行記念トークの第2弾を開催。宮脇くんと自分のほか、本書のデザイナーで高松在住の大池翼さんも出演し、写真集のデザインに関わるこだわりのポイントや苦労話などを聞いた。大池さん、育児に仕事に超多忙の中、イベントに駆けつけてくれて感謝。著者とデザイナーと編集者、この3人で誕生したばかりの本について話せてよかった。
今回の写真集に関しては、印刷製本を愛媛・松山の松栄印刷所にお願いし、香川県で5年ほど暮らしたことのある自分も仲間に入れてもらえるなら、著者および編集制作チームは「オール四国」で構成。ローカルの本の作り手がそれぞれに抱く思いを間近で聞いて、「尊い時間だった」と感想をつたえてくれた参加者もいた。忘れられない高松の夜になった。
トークの会場にはウェブマガジン「HEAPS MAG」で「香川県モスク建立計画を追え!」を連載中のライター・映像作家の岡内大三さんも来てくれて、久しぶりに会うことができた。香川在住のインドネシア人たちによる「モスク建立計画」について、ものすごいおもしろい話を聞いた。
4月某日 旅から戻ると、高知の布作家・早川ユミさんの新著『くらしがしごと』(扶桑社)が届いていた。サブタイトルは「土着のフォークロア」、手に取っただけでたしかな「思想」が伝わる本。詩人のぱくきょんみさんのエッセイ集『いつも鳥が飛んでいる』(五柳書院)も。「済州島へ」と題された旅の話からはじまる詩、ことば、ポジャギ(布)のこと。こちらは17年ぶりの再販。
病を得て入院していた本作りの仲間Nさんから退院の連絡があり、ひとまず手術は無事におわったとのこと。ああ、よかった、と心の底から安堵した。
言葉と本が行ったり来たり(9)『少年椿』
長谷部千彩八巻美恵さま
こんにちは。お元気ですか。いまホテルの一室でこの手紙を書いています。バルコニーに出ると、眼下に広がるのはエメラルドグリーンの海。ここで私が何をしているかというと、普段通り、コツコツと仕事をしています。ワーケーションというやつです。
ワーケーション――誰が言い出したのか、間抜けな造語ではありますが、旅先で仕事をするのが、私は嫌いじゃないのです。コロナウィルスが流行する前から、気が向くとノートPCを鞄に入れて東京を出る。私にはそれが「いつものこと」になっていて、旅先で書いた原稿は既にかなりの数にのぼります。場所を変えることの何が良いかと言うと、音。例えば、今回であればさざ波の音や鳥の声、異国の地であれば、飛び交う外国語を聴きながら考え事をしたり、文章を書いたりしていると、東京では煮詰まっていたものもスルスルとほどけるように進み出し、自室で机に向かっている時とは違う捗り方をするのです。
前置きが長くなりました。
ショートムービーの感想、ありがとうございました。八巻さんの言葉で綴られると、自分たちが制作したのに、とてもいい作品のように思えてきます(厚かましい?)。
ちなみにあのムービーの装花は、表参道ヒルズに店を持つ、フローリスト・越智康貴さんにお願いしました。香りを扱ったあの作品において、花は小道具に留まらない、登場人物と等しく重要な存在です。ですから、監督に「長谷部さんの書く世界を映像化したい」と言われた時、私はすぐさま「ならば、装花は絶対に越智さんで。越智さんじゃないと無理です」と答えたのでした。彼は私の知人でもあるのですが、色彩と造形に対する感覚がずば抜けている。私はそのセンスに絶大な信頼を寄せているのです。
その彼から、BLホラー小説を書いた、と聞いたのは、撮影の打ち合わせを重ねていた頃のこと。BL小説もホラー小説も読んだことのない私の頭には、大きなクエスチョンマークが浮かびましたが、越智さんが書いたものならぜひ読ませて欲しい、と頼むと、何週間かして、一冊の小冊子が郵便で届けられました。『少年椿』と題されたその冊子は、挿画も、写真も入り、薄いけれど製本もされたちゃんとしたものでした。早速ページを繰り、やや大きめの級数で印刷された活字を辿ると、30分もかからずに読み終わる。その短編はちょっと不思議な物語で、BL小説もホラー小説も読んだことがない私の頭の中には、やっぱり大きなクエスチョンマークが浮かびました。狐につままれたようなという表現がぴったりで。でも、いいなあ、と思ったのです。私もこんな風に、構えずに、書いてみた、作ってみた、という楽しさで本を作ることができたら、と。そして、思い出したのです。私自身も、子供の頃、藁半紙に自分でお話を書いて、挿絵を描いて、ホチキスで止めて冊子を作って遊んでいたことを。あの頃は、自分の作るものが他人に見せるに値するかどうかなんて、考えもしなかった。完成すると嬉しくて、ただ無邪気に、母の元に小走りで見せに行ったものです。
さらに面白いと思ったのは、越智さんが、その冊子を、街で声をかけてくれたら差し上げます、とSNSで告知していたことで、そんな方法で自分の作品をひとに届けることもできるのだとはっとさせられました。彼がそこまで深く考えていたかはわかりませんが、本は(リアルであれ、オンラインであれ)書店にならべるものという流通の固定観念に、私自身、毒されていると気づかされた一瞬でした。
越智さんとは年齢もだいぶ離れていますし、一緒にどこかへ出かけたりするわけでもない、たまにお茶する程度の付き合いですが、私にいつも刺激を与えてくれる貴重な知人であることは確かです。
そう言えば、この旅に、前回の手紙で紹介していただいたハン・ガンの『そっと 静かに』を持参しました。私が訪れたことのある韓国はソウルだけ。その全てが仕事の出張だったので、知っているのは空港とホテルとオフィスとレストラン。ですから、エッセイの中には、想像の及ばない情景がいくつも出てきました。でも、想像できない場所があるというのは、いいことだと思っています。これから知ることができる、知る未来があるということですから。
取り上げられている歌の中に、トレイシー・チャップマンの『New Biginning』がありましたね。
もっと良くなるという思いだけが/人生と道を変えるはず
夕暮れの浜辺でしんみりと、引用されたその歌詞を読みました。もっと良くなるという思いだけが、人生と道を変えるはず――。
今週末には東京に戻ります。それでは、また。
2022年4月20日
長谷部千彩
リンダ・ロンシュタットの物語
若松恵子「リンダ・ロンシュタット サウンド・オブ・マイ・ヴォイス」が4月22日よりロードショウ公開された。2021年第63回グラミー賞の最優秀音楽映画賞を受賞した作品だ。ウエストコーストの歌姫、リンダ・ロンシュタットの音楽人生を描いたドキュメンタリーで、リンダの歌う姿に魅了される、あっという間の93分間だった。
「なぜ歌うのと聞かれるけれど、私が歌うのは、鳥が歌うのと同じこと・・・」リンダ自身のナレーションで物語は始まる。ドキュメンタリーを制作するにあたっては、色々な切り口があっただろうけれど、「歌うこと」に焦点をあてて何よりも彼女の歌声と歌う姿のとびきりの映像を選んでつなぐことで1本の映画にまとめた事は正解だったと思う。
実際にステージで歌う彼女の姿を見ると、アルバムジャケットの写真がもたらすイメージより、ずっと幼くて自然で率直で、彼女からまっすぐ出てくる歌声に圧倒される。ロサンゼルスのフォークロックシーンのメッカ的クラブであった「トゥルバドール」に出演するデビューの頃の彼女、ニール・ヤングの前座でたくさんの観衆の熱気のなかで歌う彼女、後にイーグルスとなるバックバンドを従えて歌う彼女、アリーナツアーをタフに続ける頃の彼女、歌う姿はずっと変わらないある種の初々しさを持ち続けている。リンダ・ロンシュタットを理解したいならば、まず彼女の歌を聞くことなのだ。
リンダ自身は作詞作曲をしなかったけれど、曲の魅力を引き出して歌う、そういう点で彼女もアーテイストだったというコメントがあって印象に残った。自分が好きになった曲を歌っていくというのが彼女の音楽人生だったようだ。彼女が取り上げることで無名であったカーラ・ボノフやJ・D・サウザーが有名になり、ロイ・オービソンやバディ・ホリーが若い人たちにリバイバルした。
また、彼女は歌いたい歌を歌うという生き方を貫いて、オペラやメキシコのトラディショナル、ジャズとジャンルも超えて作品を作った。彼女が天から与えられた「声」と「表現力」をフルに使って、どこまでも歌う事の可能性を広げていく生き方をしたということを今回の映画で初めて知った。人が歌うという事の不思議と素晴らしさを感じた。
映画のなかでもうひとつ印象に残ったのは、女性シンガー同士の友情についてだ。ロック業界という男社会の中で、いかに女性ミュージシャンたちが苦労しているのか、一方男性ロッカー自身も、つまらない男の沽券を守ろうとプレッシャーに負けてドラッグに蝕まれてしまうと、浜辺のインタビューでリンダは鋭い見解を述べている。リンダと同じようにずっと歌ってきたエミル―・ハリスが「人生のどん底にいる時、リンダに救われたの」と心からの友情を込めて丁寧に語っている姿が心に残る。1987年にそのエミル―・ハリスと尊敬する先輩ドリー・バートンと一緒につくったアルバム「Trio」のハーモニーはとびきり美しい。リンダが様々なミュージシャンとコラボしていく姿は、「曲」に自分をあけ渡して歌う姿と重なる。ひとりきりでは音楽は奏でられない。歌うという事は、他者に自分の声を届けていくという事なのだ。
2011年に、リンダ・ロンシュタットはパーキンソン病を理由に歌手活動の引退を表明した。映画のラストにナレーションに徹していたリンダが登場する。2019年の、愛らしさの残る年取ったリンダの姿だ。家族と歌う様子が流れる。歌手という仕事はおしまいにしたけれど、歌う事を続けている彼女の姿に胸が熱くなった。歌う事はやはり他者とつながるということなのだと感じられる場面だった。彼女は病を得ても自分に閉じこもらずに歌うことを楽しんでいた。
それぞれの庭
北村周一しき嶋の
やまとごゝろを
説くきみの
肩にむらがる
はなびら隠微
穢されし
サクラはなびら
雨にぬれ
排水口に
屍人のごとし
それぞれの
庭の片隅
ふきだまり
目には見えねば
掃くひともなし
雨あがり
春の気配に
みずたまり
のぞき見ている
くろしろのネコ
校庭の
つちにしみ入る
春の夜の
雨はやさしき
雨音もまた
帽の子ら
赤と白とに
わかれいしが
(もとの隊形に
もどれとだれか)
団欒と
さくら並木と
夕ぐれが
一つになるとき
窓はほころぶ
はじまりより
つねに大地は
震えおり
奢りの春の
花のゆたけさ
うす紫
いろに染まりし
花韮の
土手ゆく猫は
そよかぜのごとし
空間に
双のつばさを
休めんに
線をもとめて
ひらく脚くび
友ありて
その友のありて
百千の
土鳩つぶやく
なかを群れゆく
ごく狭い
範囲のなかで
ごく浅く
つき合うための
スキルを磨く
だぶだぶの
制服に身を
固くして
ゆめみるごとし
一年男子
あれもこれも
詰め込み過ぎて
なにとなく
憂いがちなる
四月の私
卓上に
てのひらのあと
ほんのりと
残しゆくなり
湯あがりのひと
一ドルが
三百六十
円のままに
停まりし時代が
かおを出すとき
布団から
はみ出さぬように
ねむりたい
悪夢はひとの
二のうでが好き
ブースター
接種終えたる
妻の腕に
それは見事な
モデルナ・アーム
脳内で
かんがえすぎると
両の眼が
紅くなるので
早起きが辛い
この歳に
なりてようよう
腑に落ちたり
やまいのすべての
根源は眠り
安宿のような人生
植松眞人 都心の列車に乗って、ドアの脇に立つ。半身になって流れていく赤茶けた鉄路をぼんやりと眺めていると、不意に対向車が大きな音を立ててすれ違う。驚いて鉄路に向けていた視線を上げると対向車の窓の中に見知った顔を見たような気がするのだけれど、たぶん思い違いだろう。しかし、万が一にもそれが見知った顔ならこちらを見られたくはないという判断が瞬時に働き思わず顔を下げる。もともと、こんなに速くすれ違う列車と列車の窓から人の顔を判断することなど出来はしないのに。
そう思いながらもう一度視線を鉄路に下ろすと同時に対向車は行き過ぎ、また同時に雨が降り出した。頼りない破線を窓に描くように水滴が流れ、それが数本確認できたかと思うと、あっという間に土砂降りだ。
あんな言い様をされれば誰だって腹が立つとは思うが、私のように相手が自席に着くのを待ち構え後ろから首筋に自分の腕を巻き付けて頸動脈を締め付けるというチョークスリーパーなる技をかけて落ちる寸前までに攻める理由があったのと言われればそれほどでもない。しかし、子どもの頃からのこらえ性のなさでどうしても、怒りを腹に留めることができず絞めたり、殴ったり、罵倒したりということを繰り返してきた。小学生の頃なら、先生に仲裁され「さっきはごめんね」と言えば、たいがいのことは許してもらえたが、三十を過ぎたいい歳をしたおっさんとなってしまっては、何かするたびに世界が狭くなる一方だ。
そういえば、さっきのすれ違った列車で朦朧とした幻想のように思い当たった見知った顔は、数年前にこちらのミスを指摘され、腹立ち紛れにあることないこと罵倒して辞めさせてしまった女子社員の顔に似ているような気がする。あの女とは一、二度情交もあったがたいした気持ちのやり取りもなく、辞めてやる、と叫んだときもざまあ見ろと思ったくらいだった。しかし、昨年くらいから去った女の身体が惜しく思えることもあり、女々しくツイッターのアカウントをバレないように検索して、日々の行動を監視しながらしたり顔で、大人しくしてればいいんだと独りごちたりしている。
都心から小一時間走った後で列車を降りると、かつて浮浪者があちこちの町角にいたという呪われたような地区のいまだに、「カラーテレビ付き一泊五〇〇円」などと看板をあげた簡易ホテル街の裏手にあるうらぶれたアパートに帰ってくる。おそらく戦後すぐに建てられたであろう木造モルタルのアパートは、一泊五〇〇円の簡易ホテルの外観よりもいかれていて、いまにも崩れそうだ。
一泊五〇〇円だとひと月三十日連泊したとしても一万五〇〇〇円にしかならず、自分が住んでいるアパートと値段が変わらない。しかも、少なからぬ敷金礼金を払わされ、カラーテレビも持っていないとなれば、日々目にするすえた臭いのする浮浪者よりも一段低い暮らしをしているのだと自覚して、酒を飲む気にもならずささくれた畳の上にジャンパーを着たまま寝転がる。
俺は映画を作るのだ、と叫びながら友人達と公開するあてもない映画を作り、出来た映画の不出来に愕然とした日々がなぜあれほど光り輝いていたのだろうという嫌な夢を見ながら嘔吐で畳を汚し、同時に涙を流しながら、この涙の清らかさを誰か見てくれ、誰か見てください、どうぞ見てください、心から願いながら汚物にまみれて眠ってしまうのだった。
ストレス・チェック
篠原恒木年に数回、ストレス・チェックというアンケートに電子メールで答えなければならない。
モンダイは、このアンケートの設問がおれの理解の範疇を超えていることだ。たとえばこういう質問がある。
「一生懸命働かなければならない」
この文のあとに、「そうだ」「まあそうだ」「ややちがう」「ちがう」という四択の答えが用意されていて、どれかひとつにマルをつけなければいけない。
「愚問だ。働くときは誰だって一生懸命だろうが」と、おれは思うので、「そうだ」にマルをつける。
「活気がわいてくる」
という一文も出てくる。
「この年齢になって活気がわいてくるわけがないだろう。覚せい剤を打っているわけでもないのに」と、おれは憤り、「ちがう」にマルをつける。
「元気がいっぱいだ」
というのが次に登場する文だ。ここでおれは「活気がわいてくる」と「元気がいっぱいだ」の違いについて深く考察することになるが、どうにも両者の違いがわからない。かろうじてわかるのは、「活気がわいてくる」に「ちがう」と答えて、「元気がいっぱいだ」に「そうだ」と答えたらそれはかなりの矛盾を生じるのではないかということだけだ。したがっておれは「ちがう」にマルをつける。その次に書いてある一文は、
「生き生きする」
だ。これはもはや愚弄されているのではないかとおれは思い始める。「活気がわく」「元気いっぱい」「生き生き」は文学的にも心理学的にも社会学的にもそれぞれ違う状態なのだろうか。おれは弁証法を駆使して解析を試みるが、哲学的にも解決できないので、これにも「ちがう」にマルをすることになる。次に出てきたのは、
「怒りを感じる」
だった。これまでの設問にかなりの憤りを覚えていたおれは即座に「そうだ」にマルをつける。バカにするのもいいかげんにしろ、とさえ思っているからだ。
「内心腹立たしい」
当然ではないか、と思うおれは、これも「そうだ」にマルだ。
「イライラしている」「ひどく疲れた」「へとへとだ」と続くので、「そうだ」「そうだ」「そうだ」と答えていく。それもこれもみんなこのアンケートのせいだ。
「だるい」
と出てきた。だるいに決まっているではないか。もうすぐ六十二歳ですよ、あーた。ピョンピョン飛び跳ねながら歩いているわけがない。これも「そうだ」にマルである。
「不安だ」「落ち着かない」と連打を受ける。このふたつもかなりニアなニュアンスではないのか。かような新型コロナ、ウクライナ情勢、可処分所得大幅減額のなかで安心して落ち着いていられるわけがない。だからおれも「そうだ」「そうだ」の連打で返す。
お次は「ゆううつだ」「気分が晴れない」とくる。だからぁ、このふたつはどう違うのだとさっきから疑問を呈しているではないか。こうなると完全に嫌がらせの範疇に入ってくるだろう。憂鬱だよ、春は憂鬱に決まってるではないか。桜の花びらがはらはらと散りゆくさまを見てはココロは無常感でいっぱいになるおれなのだ。気分など晴れるわけがない。「そうだ」「そうだ」とマルをつけていく。
「悲しいと感じる」
よくぞ訊いてくれた。こよなく晴れた青空を悲しと思うおれなのだ。そうして長崎の鐘が鳴るのが世の道理なのだ。死ぬまで生きるということはじつに悲しい。これも「そうだ」にマルだ。
「腰が痛い」
これもよくぞ訊いてくれた、ありがとう。つい先日、おれは昏倒した九十八歳の親父を抱きかかえて起こそうとしたときに腰を痛めてしまったのだ。おかげで整形外科でブロック注射を打たれて、大変な目に遭った。老々介護とはよく言ったものだ。よって、これも「そうだ」にマルをつけなければならない。
「仕事に集中できない」
ここに来て何を寝ぼけたことを言っているのだ。こんなにたくさんの設問に答えさせられていたら、仕事に集中できるわけがない。クレームの意味を込めてマルだ。
ここまで数々の愚問に答えてきたおれはフト思った。おれの選択肢は「そうだ」と「ちがう」しかないのか。「まあそうだ」「ややちがう」という項目に、まだ一回もマルをしていないことに気付いてしまったおれはやや反省して、次の一文を読む。
「何をするのも面倒だ」
おれは熟考した。髭を毎日剃るのは面倒だ。脱いだ上着をハンガーにかけるのも面倒だ。しかし、好きなあのコと食事をするのは面倒ではない。ましてや食事後のことも面倒だと思ったことは一度もない。ここで「まあそうだ」か「ややちがう」の出番がついにやってきたとおれは感じた。
ところがまたモンダイが起こった。「髭を剃る」「上着をハンガーにかける」ことが面倒であるという事実に重きを置くのなら、「何をするのも面倒だ」に対するおれの解は「まあそうだ」になるのだが、「好きなあのコ」関係は面倒でないという真実を重視するのなら、おれの解は「ややちがう」となるのではないか。どちらにマルをすればいいのだろう。考えるのが面倒になったことに気付いた俺は、
「そうか、結局おれは何をするのも面倒なんだな」
との結論に達し、「そうだ」にマルをつけた。
ストレス・チェックがかなりのストレスになったおれはようやくすべての質問への回答を終え、メール送信した。
後日、「あなたのストレス度は?」というような診断結果がメールで送られてきた。結果内容をひらこうとしたが、パスワードを入力しないと見ることができない。「これかな」と覚えのあるパスワードを何回か入力したが、どれも「パスワードに誤りがあります」と出て、ついにおれのストレスは最高潮に達した。
ジャワの仮面舞踊
冨岡三智5月7日に仮面舞踊を久々に踊る(10年以上ぶりのような気がする)…というわけで、今回はジャワの仮面舞踊の話。インドネシア語では仮面のことをトペンという。仮面舞踊やワヤン・トペン(仮面舞踊劇)はジャワやバリの各地にある。西ジャワのチレボンだと、ワヤン・トペンもあるけれど、1人の演者が5種類のキャラクターを演じ分けるトペン・ババカンが有名だ。東ジャワなら、マランの『パンジ物語』を題材にしたワヤン・トペンや、『マハバラタ』や『ラマヤナ』を題材にしたマドゥーラのワヤン・トペンが有名である。トペン・マランについては留学中の2001年7月16日にスラカルタの芸大で、トペン・マドゥーラは1991年に国際交流基金アセアン文化センターが招聘した日本公演を見たことを思い出す。トペンの演目は普通は『パンジ物語』なので、それ以外の演目があるというのが新鮮だった。
中部ジャワであれば、スラカルタの王家にもジョグジャカルタの王家にも仮面舞踊がある。仮面舞踊は民間派生のものなので、宮廷儀礼用ではなく貴族層たちの楽しみとして発展した。その両王家のある2都市の間にあって、どちらの宮廷にも多くの芸術家を輩出してきたクラテン村にはワヤン・トペンがある。そして、ダラン(影絵の人形遣いや語りをする人)たちが上演するものは、特にダラン・トペンとも呼ばれている(他の地方でも同様)。ダランたちは昼はワヤン・トペンに出演し、夜はワヤンをしたものだという。
クラテン村のワヤン・トペンは、2001年8月には村の広場に設置されたステージで、2002年8月にはダランの家で見た。ダランの家の正面は少し高くなっていて、約1間半×4間幅くらいの深い庇があり、そこをステージにしている。昔は上演できる場所が限られていたから、いつでも上演できるように家の作りをそうしているという話だった。庇の奥にある3枚の戸口は全部外して、奥の部屋を楽屋にしていた。観客はその家の外側から見るのだが、舞台が進行している奥で楽屋が丸見えなのが可笑しかった。舞台の雰囲気は岩見神楽が上演される神楽殿のような感じだった。(もっとも、岩見神楽では大きくて立派な幕を楽屋と舞台の間に張る…。)
クラテンのトペンで興味深かったのが、足を上げないことだった。現在、芸大や王家などで見られる仮面舞踊では、男性の登場人物たちは仮面をつけていないときと同様に動く。仮面をつけると視野が限られるから、片足を少し上げたり、戦いの場面で素早く場所移動したりするにはバランスを取る技量が必要だ。しかし、クラテンでは、2人戦う場面では肩を組んで互いに前に足を出し合うような振付で、昔の仮面舞踊の素朴さを実感する。歌舞伎の様式的な殺陣という感じだ。
また、台詞を話す際に、仮面を手に持って観客から顔を隠しながら話すというのも面白い。能だと面をかけたまま声を出すが、ジャワでは仮面の裏に取り付けた革をくわえて面を着けるので(つまり紐を使わない)、仮面をつけたまま声を出すことができない。どうやって台詞を話すのかずっと疑問に思っていたので、こうするとまるで仮面が話しているように見えるのか…と納得したことを思い出す。
昨年、このクラテン村のワヤン・トペンのグループの公演を20年ぶりくらいにyoutubeで見た。その中心の人がアカウントを作って発信を始めたことを知ったからなのだが、変わらず素朴な雰囲気があって懐かしい気分に浸り、facebookでもその人に連絡を取ってみた。私が見たときは芸大の協力も入っていたが、廃れつつある芸能で上演費用も大変だったようだ。私も寄付に応じたのだが、変わらず公演が続いているようで嬉しい。
むもーままめ(18)鎌倉で石を買うの巻
工藤あかね10年ほど前になるだろうか。
ある朝、夫が私に尋ねた。
「今日の予定は?」
わたしが「あるといえばあるけど、出かけなければいけない用事はない」と答えると、
鎌倉の先の美術館に行かないか、と言う。
遠足気分で行くのも悪くないし、
何よりその展示には興味があったので
二つ返事でOKし、その日は急遽の遠出になった。
鎌倉駅に着き、鳩サブレのお店などを横目に観ながら、
にぎやかな通りに入って進んだ。
程なくして、夫がぴたっと足を止めた。
ある店の中を食い入るようにじっと眺めている。
石を売っているお店だった。
夫が中に入ると言う。
まあ、眺めるだけなら良いかと思い、
夫のあとに続いて私も店に入った。
店内には、宝石の原石や、隕石やら、
ありとあらゆる石が展示してあった。
夫は隕石を食い入るように見つめ、指で持ち上げた。
「重い!!すごいよ、すごい、重い!!!」
完全に小学生男子のリアクションである。
冷ややかに眺めつつ、
少しくらいは付き合ってやらないと哀れだと思い、
私も石をつまみ上げた。
「重っ!!なにこれ、重い!!」
店員さんがニヤッとしたような気がした。
みんなそうやって騒ぐのだろうね。
しばらくすると、夫はかごを手に取り、なにやら石を選び始めた。
買う気か?これからしばらく歩いて、美術館に行くのに?
帰りも鎌倉から1時間半以上かかるのに?
夫は完全に小学生に戻っていたので、もう誰にも止められない。
いくつかの石をカゴに入れて、
「欲しいのあったら買うよ?」ときた。
半分頭にきていたが、石も一つ一つ見てみると、
実に個性がはっきりしていて、良いものに見えてくる。
お店の人も、「あー、これいいね」
「わー、これもいいね」とか言いながら仕入れているのだろうか。
なんとなく雰囲気に乗せられて、
結局アメジストの原石をカゴに入れた。
会計を済ますと、
結構なお値段と、結構な重さになっていた。
一袋では重すぎるし下手をすれば破けるレベルだったので、
袋は2つに分けてもらった。
ばかだ。完全にばかだ。
これからお昼ご飯を食べて、美術館に行って、
もしかしたら夕食も食べて、
電車に長々と揺られて帰るのに。
電車が混んでいて座れないかもしれないのに。
旅の序盤で大量に石を買うって、
どういう了見なのか。
鎌倉駅で帰りの電車を待つ間、
大量の石を持ってホームに佇んでいる私たちって一体…。
夫は自分の責任で買ったので、重いほうの袋を嬉々と持ったまま
その日の小旅行を終えたのだった。
それから幾星霜。
その時に買った石のいくつかは、
引越しの際に夫に言わずにこっそり処分してしまった。
それでも、いくつかの石はなぜか今も飾っている。
本当は寝室とか玄関先に、謎の石なんて置きたくないんだけど。
ベルヴィル日記(7)
福島亮すっかり日がのびた。いま20時50分なのだが、外はまだ明るい。市場の商品棚に並ぶ顔ぶれも春、というか少しずつ初夏のそれになってきている。地味な色合いの根菜類にかわって、紙箱に詰められた苺、葉付きの人参や色鮮やかな蕪、白アスパラ、そしてまだ多くはないが西瓜などが並んでいる。日本には桜前線という言葉があるが、フランスでは春になると誰もが白アスパラを待っている。バターで焼くもよし、フライパンに湯を沸かして軽く茹でるもよし。マヨネーズソースやバターソースをつけ、指でひょいと摘んで齧ると、みずみずしい甘さのなかにほのかな苦味があり、冬を我慢したご褒美だな、と思う。
ベルヴィルからクーロンヌ、メニルモンタンにかけてはアラブ系の住民、特にカビル人が多い。それは知っていたのだが、4月になった途端に街にアラブ菓子が溢れ始めたので驚いた。よく行くパン屋も軒先に棚を出して山盛りの菓子を売っている。どうしたのかと思って尋ねると、ラマダンだから、とのことである。つまり街に溢れかえっている菓子は夜食なのだ。糖蜜がかかった揚げ菓子や、ピスタチオがまぶされた小さなケーキ、あるいは三日月の形をした白いクッキーのようなお菓子。敬虔さと楽しみの入り混じった非日常の風景がそこにはある。ラマダンが終われば、パン屋はまたもとのパン屋に戻るのだ。
とはいえ、日常と非日常は、そう簡単に分けられるものではない。日々舞い込む情報に触れながら、誰もがそれを身をもって感じているはずだ。
ちょっと前のことになるが、3月27日、ケ・ブランリー美術館のレヴィ=ストロース劇場で宮城聰演出の『ギルガメッシュ叙事詩』を観に行った。日本では今月、5月2日から5日まで「ふじのくに⇄せかい演劇祭」で上演される。物語は大きく分けて二部構成からなっていて、第一部はギルガメッシュとその友エンキドゥがレバノン杉を伐採するために森の守り神であるフンババを征圧する物語である。だが、自然を征服した代償は決して小さくない。ギルガメッシュは友を失うことになる。こうして第二部は、永遠の命を求めるギルガメッシュの旅路が描かれる。
劇場は満員だった。そして、ほぼ全員、マスクをしていなかった。かくいう私も、マスクをしていなかった一人である。マスクをしていないと、確かに呼吸が楽ではある。だが、隣の人が急に咳き込んだりすると、にわかに不安になる。実際、この不安によって観劇中の緊張感は何度か途切れた。マスクなしでの生活が日常に戻ってきたかと思いきや、やはり不安は拭えない。
マスクに関連して、思わぬ葛藤に苦しむこともある。古い雑誌を閲覧するためにアルスナルにある国立図書館に行った。表面が滑らかに摩耗した木製の味わい深い机に座って資料を読んでいると、斜め前の人がマフラーに口を押し当てて咳をしている。咳をする、一粒トローチを口に放り込む。またしばらくすると苦しそうに咳をする、一粒トローチを口に放り込む。要するに、トローチとマフラーで誤魔化しつつ、ノーマスクで咳をしまくっているのである。しまったな、と思った。慣れでマスクを外していたのだ。今からマスクをつけるのは、なんだか申し訳ない。マスクはポケットの中にある。手を突っ込むと、不織布の毛羽だった質感が指先に触れる。さっと取り出して、つければよい。ただそれだけなのだが、なんだか申し訳ない。こんなふうにうじうじしていると、前の席の別の人がおもむろにマスクを手にし、つけた。これ幸いとばかりに、私も便乗してマスクをつけることにした。咳をしていた人は、やはりバツが悪そうだった。私もバツが悪かった。みんながマスクをしていないからしない、あるいは誰かがマスクをしているからする。自分というものがないのか。このように、結局自らを責めることになるのだから、はじめからマスクをしておけば(あるいは割り切ってマスクをしなければ)よかったのである。
ちなみに、フランスの現在の平均感染者数は1日あたり65454人であり、病院で亡くなった人の数は1日平均123人である。決して少なくなったわけではない。それでも、非日常はある瞬間から日常のような顔をしはじめる。慣れ、ではあるが、その慣れは時間の経過によるものもあれば、官製のものもある。フランスの場合、後者の方が目立つように思われる。というのも、地下鉄ではマスク着用が義務付けられているからみんなマスクをしているが、一歩メトロの外に出たら、マスク着用の義務はなく、誰もが晴れ晴れとした顔でマスクを外しているからである。政府が決めた方針に従っているうちに、いつの間にかコロナという非日常は何気ない日常に転ずる……そんな気分を皆味わいたいと思っているのだ。日常とは何なのだろうか。
仙台ネイティブのつぶやき(72)猫の隣で
西大立目祥子猫といっしょに暮らしていると、種の違いより哺乳類同士の近さを感じることの方がはるかに多い。猫は四足で歩行し体は柔らかな毛におおわれ尻尾があって、もちろんヒトはそうではないのだけれど、さわればあたたかく、目は感情を表し、顔の真ん中の小さな2つの孔は吸う吐くという呼吸を繰り返している。背中をなでれば、あたたかな体の中では心臓から送り出された血液が全身のすみずみに運ばれ、毛細血管をめぐって戻ってくることが想像できて、この小さな生きものがヒトと同じ仕組みで生命を保っていることに感じ入ってしまう。近しさと親しみが自然と湧いてくる。
前足だってそう。猫の手足を間近に見るようになって、「猫の手も借りたい」といういい方に合点がいくようになった。猫の前足は5本の指がパァーっとよく広がり、物をつかむときはギュッと縮み、爪をしっかりと立てて抑え込むこともできる。猿のようなわけにはいかないだろうが、犬のそれよりはるかに細やかな動きで、これは手未満、足以上のもの。こんな手を見ていたら、役に立たないとはわかっていても「おい、忙しいんだ。ちょっと、ここ押さえててくれよ」とか、頼みたくもなるというものだ。
長くいっしょに暮らしていると、人間同士のつきあいのように関係性が変わっていくのもおもしろい。私が仕事場にも使ってきた母の住まいには2匹、野良から昇格した15歳のチビと10歳のグーが暮らしている。15歳といえばヒトでいったら中学3年だが、猫年齢では初老くらいか。けっこう長いつきあいなのだが、やはりこの家には年老いた女主人がいると思っているのか、毎日顔を合わせごはんをあげていても、私のことはどうも通いのよそ者としてしか認識していないようだった。それが、母がお泊りサービスに出かけて留守がちになり、私が週に3日泊まるようになって2年、少しずつ飼い主としてというのか、同居人としてというのか認めてもらえるようになってきた感がある。朝に起きるとすぐ近くにいて顔を合わせ、「おはよう」というのが案外大きいのかもしれない。
猫と仲良くなるのは冬、というけれど、たしかにこの冬の間にチビと心を通わせることができるようになった。冬に親しくなれるのは、寒いからだ。温かい飲み物を欲するように猫も体温のある生きものが恋しくなるらしい。なでてくれたり、あれこれことばをかけてくれたり、茶飲み話をするような友だちが。家の端っこの、かつて母がミシンをかけたりするのに使っていた小部屋につれていってなでてやったら、庭全体を見渡せるこの場所がえらく気にいったようで、何かにつけてここに私を誘い込む。外から帰って、玄関に荷物を置くと、すぐにこの小部屋に走り込んで私が行くのを待っている。ガラス戸を開けてもらって、寒くても雨でも雪でも外の空気に当たり、庭をながめて外の気配を匂いで感じ取り、私とあれこれ話をするのを楽しみにしているのだ。
「話をする」と書いたけれど、交歓というのか生きもの同士のやりとりというのか、ことばをかければその声の調子からちゃんと感情が伝わっているのは、犬や猫を飼ったことがある人なら容易にわかることだと思う。私にとっても、どこで鳴らすのかゴロゴロという猫が安心しているときに発する音が聞きながら、いっしょに庭を眺めるのは気持ちのいい心和むひとときだ。
たまたまチビは猫であり、私はヒトである。でもその逆もあり得た。偶然にもいま、別々の器の中に命を注がれていっしょに同じ空気を吸い同じ風景を眺めているだけ。生きものとしての境界を超えてしまうような、そんな思いにかられる。そして、このごろは、「おまえ、キエフの猫じゃなくてよかったね」と、つい口をついて出ることが多くなった。布の袋から頭だけ出して飼い主と避難する猫や、水たまりの水を飲む濡れそぼった猫や、瓦礫の上を足を引きずって歩く猫を報道で見た。苦しくなる。つい2ヶ月前までは暖かな場所で背中をなでてもらっていたろうに。
お腹をなでてやって安心しきると、前足を出したり引っ込めたり、もう少し正確にいうと指を広げたり縮めたりするのを繰り返す。これは、子猫のときに母猫のおっぱいをふみふみして飲むときのしぐさだ。それをエアでやっているわけだけれど、幼いときの行為を老齢になっても記憶として残していることに感じ入る。ヒトの中にも何かそういう乳幼児のときの記憶の残滓というものがあるのだろうか。
と、チビのことを書いてきたけれど、悩みの種はもう一匹の猫、グーのことである。私を飼い主と認めるどころか、どこまでも怖がって近づいただけで逃げる。理由ははっきりとわかっている。子猫だったこの猫が何度も家に入り込もうとしたとき、すでに2匹の先住猫がいたこともあって、私は本気で追い出した。それでも、ここを住処と決めて居着いたのだからあっぱれというしかないのだけれど、以来、私には敵対心をむき出しにする。母にはなついているのに。この先、グーと和解する日がくるだろうか。いや、あれは虐待ともいえるものだったのだろうから、それはないのかもしれない。でもせめて、恐れられない存在にはなれないものだろうか、と思う。
死ぬまで猫といっしょに暮らしたい。できるのだった犬だって飼いたい。部屋の中を四足の動物が歩いているのを見ると、幸せな気持ちでいられるから。最近、ジョージ・オーウェルが相当な動物好きだったことを知ってうれしくなった。ビルマでは山羊や鴨を飼い、帰国した英国の田舎でも山羊と鶏を飼っている。眺める世界に生きものの存在が見えているかいないか。その違いはけっこう大きい気がするなあ。
雨の宵酔い
璃葉“緊急事態宣言”が解除されて、呑み屋やバーが少しずつ活気を取り戻してきた…ような気がしている。気がしているだけなのかもしれない。已む無く閉めた店もあるし、まだまだ人の入りがさびしいところもあるだろうが、行けるところには足を運びたいと思って、バー巡りをちびちび再開している。
この何週間かは突然初夏のような気候になったり、雨の降る寒々しい日が続いたりして、なにだか振り回されっぱなしである。先日、知人ととあるバーに行った日も、土砂降りの雨だった。しかも冬に逆戻りしたような寒さである。風もつよい。突風で安いビニール傘も裏返る。気圧のせいか頭もちょっと痛いし、こんな日は正直おうちでぬくぬくしていたいところだが、1ヶ月以上前から約束していたのだ。楽しみにしていたし、行かないわけにはいかない。
知人は酒の化身なのではないかと思うほどの超絶酒飲みの女性で、しかも、この界隈では有名な雨女らしかった。バーに到着してまもなくその話を本人から聞き、なるほど今日のこの大雨は運命だったのか、と納得するのであった。
連れられて来たバーはとても素敵な空間だった。広くも狭くもなく、照明は明るくも暗くもない。壁棚にはウイスキーのボトルがずらりと並んでいる。あと、緑の壁紙が最高にいい(自分はくっきりした色味の壁色に弱い)。落ち着きがあるのに、そこまでかしこまっていない雰囲気で、気を遣わず、楽にお話しができる。インテリアや品揃え以上に、店主の作り出す何かであったり、見えない色々な何かが混ざり合って出来上がった空間はそこにしかないものであるから、また来たいと思う。こうして好きなお店が増えていくのだ。
ヒューガルデンホワイトから始めて、ウイスキーに雪崩込み、すっかり楽しくなってしまって、話も盛り上がる。何杯飲んだか覚えていないが、久しぶりに酔っ払った。
帰り道、雨はすっかり止んでいた。火照った顔に吹く雨上がりの冷たい風が気持ちいい。冬のような冷たい空気なのに、冬にはぜったいに感じることのない上品な白い花の香りが辺りに充満していた。繁った桜の葉は電灯に照らされて、妙に鮮やかな緑に光っている。やっぱり今は春なのだ。このしっとり澄み切った空気は山の中にいるようだった。するりと流れていく風にのってやってくるいいにおいを肺に入れたくて、思い切り深呼吸をしながら歩いた。貴重な夜道だ。雨女様に感謝である。
しもた屋之噺(243)
杉山洋一今年は庭の芝刈りがすっかり遅れていて、この原稿を送ったら早速とりかかるつもりです。イタリアのマスク規制もこの4月で終わるはずですが、今月は思いがけず親しい友人や息子の学校の先生など、軒並みCovid19で陽性になったりして、これからコロナ禍とどう付き合ってゆくことになるのか、何とも先の見えない心地がしています。ドラギ首相さえも陽性になったため、キーフ訪問がなかなか見通せない状況でした。
4月某日 ミラノ自宅
サンドロ宅で久しぶりにアルテムと再会。家人と一緒にリセンコ作品を何曲か弾いてくれた。昼食時、近くのバングラデシュ料理屋でカレーを食べていると、隣に座っていたスリランカ人がスリランカ暴動の話を始めて止まらない。果ては、敗戦国の日本を分割統治から救ったジャヤワルダナ大統領について、日本ではよく知られているのかと繰返し尋ねられ言葉に窮する。ウィシュマさんの名前まで出たらどうしようか内心はらはらしていたが、幸い話題にのぼらなかった。
4月某日 ミラノ自宅
夜、国立音楽院で、久保君のバスクラリネットとマリンバのための新作を聴く。バスクラリネットは、海をわたる鳥の啼き声のように響く。カモメやウミネコが空を駆けながら発しているような、不思議な広さが目の前に顕れる。協和音は生理的快楽とは一線を画し、素材として自らの意思を持っているように見えた。久保君の身体から抜け出て、自らの領域を築きはじめているのかもしれない。
壮大な脱皮を目の当たりにするかのような清々しささえ覚えたのは、このあと書かれた彼のヴァイオリン協奏曲を既に聴いていたからだろうか。
ダミアーノ作品も美しい。静謐で、二楽器の息遣いを重なりあわせた作品に好感と共感を持って聴く。どちらの演奏も素晴らしかった。とても心地良い晩であった。
4月某日 ミラノ自宅
サンドロ宅で、ズィノヴィと家人の弾くリセンコの悲歌を聴く。リセンコは19世紀のウクライナの作曲家。
ズィノヴィはパヴィアから彼の父の車でやってきた。彼の父親がイタリア語堪能なのには驚いたが、聞けばもう20年イタリアに住んでいると言う。ズィノヴィはウクライナで祖父母に育てられ、最近になってイタリアで暮らしていた父母と住み始めたのだという。彼の父は、民族音楽を奏でるアコーディオン奏者だったそうだ。ズィノヴィも幼少から、民族音楽オーケストラで Tsymbaly というウクライナのダルシマーを弾いていたそうで、民族衣装に身を包みツィンバリを叩くズィノヴィ少年の写真を見せてくれた。
ツィンバリはむつかしいか尋ねると、「簡単です、でも当時は民族音楽は大嫌いでした。クラシックの方がずっと格好良かったですし」と笑った。
意外にもウクライナにはコントラバス奏者が少なく、教師もクラスも限られていたから、イタリアにやってきたと言う。ウクライナにいたころ、ズィノヴィはずっとコントバラスも教えるチェロ教師に習っていて、リセンコの「悲歌」は、元来ウクライナでは広くチェロで愛奏されているから、曲はよく知っていたと言う。
演奏が終わると、彼の父が涙を拭いながら洗面所から出てきて、一同驚く。聴いていたら涙が止まらなくなってしまって、と困ったように笑った。確かに胸に迫る感極まる演奏だった。
4月某日 ミラノ自宅
「Youtube はお客様のコンテンツを削除しました」とのメールが届く。「YouTube チームによる審査の結果、お客様のコンテンツは 嫌がらせ、脅迫、ネットいじめに関するポリシー に違反していると判断されました。そのため YouTube から次のコンテンツを削除いたしました」。
最初は、詐欺・なりすましメールかと思っていたが、どうやら身に覚えのない動画が実際削除されていることがわかり、おどろく。その動画の題名は昔よく使っていたパスワードだったから、ずいぶん悪質だ。
ヴェルディ音楽院に、カニーノさんとルッジェーロの演奏会にでかける。
平均律第一巻誕生300年を記念して、ルッジェーロが、ジョプリンの「エンターテイナー」や、ムゼッタのアリアやジムノペディやハリーポッターのテーマやら様々な旋律の断片でフーガを作り、バッハと一緒に弾いた。
ルッジェーロが自作のフーガを弾くのかと思いきや、カニーノさんがルッジェーロのフーガを弾いた。カニーノさんは思いの外お元気そうで、信じられないほど音が輝いていた。指は勿論だが、耳も頭も声部ごとにしっかりと分離しているのが手に取るようにわかる。
会場でアルフォンソに会うが、何でも学生に「間奏曲 VI」をやらせているという。その学生はアスペルガーで強音癖があり弱音が苦手なので、殆ど音のない「間奏曲 VI」をやらせているそうだ。
4月某日 ミラノ自宅
黒海でロシア軍旗艦 Moskva 撃沈。
アレクセイ・リュビモフがロシア国内のリサイタルでウクライナのシルヴェストロフを演奏して、警察に拘束される。観客はリュビモフに賛同して、演奏後総立ち。久しぶりにロシアの良心を垣間見た気がしたが、リュビモフはその後どうなったのか。プラウダ批判やらジダーノフ批判やらショスタコーヴィチの顔など、古めかしい言葉が頭を過った。
母からのメールで、家にある黄色い清楚な花を咲かせた多肉植物の名前は「薄化粧」だと教えてもらう。
4月某日 ミラノ自宅
40分かかるマンカ新作を聴く。アコーディオン、コントラバスなど特殊な小編成アンサンブルを従えたピアノ独奏曲。マリアグラツィアのピアノが冴える。作曲者は、構造を持たない作品を書いたので、ただ瞬間の連なりとして聴きとってほしいと話していたが、そのせいか40分はあっという間に過ぎて、全く飽きなかった。
強靭で強い意志を持つ音楽。耳で聴くというより、手触り、それも少しざらついた手触りで、音楽に触れながら感じる音楽。無意識ながら彼の音楽に随分影響を受けていたと今更ながら気づく。
会場には昔から知った顔が並ぶ。自分も含めて、みな齢をとったものだ。久しぶりにマンゾーニにも会ったが元気そうで嬉しい。ゴルリは戦争で将来を悲観していた。
4月某日 ミラノ自宅
メルセデス宅で工科大主任のカルロッタと話す。担当クラスにウクライナの学生はいないが、在籍中の何人かのロシア人学生は揃って困窮していると言う。外国送金が禁止され仕送りも届かないので、皆周りの学生に借りるなり、工面してもらうなりして、苦労して暮らしている。ウクライナ侵攻以後、制限がかかっているのか、ロシアの家族と一切電話が通じない学生もいるそうだ。
ウクライナのバレエ団がイタリア公演中で各地で歓待されるとの記事。国歌演奏中の舞台でバレリーナが目頭を抑えている写真が添えられている。ロシア兵の夫にウクライナ人女性への暴行を勧めるロシア人妻の電話が公表。
4月某日 ミラノ自宅
福田さんに「母 Las Madres」を書き送る。
チリの母のうたと、西語圏全土で広く歌われている子守歌「ねんねんころりよころりよ おころりよ Arroro mi nino」を素材に使った。
息子が生まれた時、半年ほどウルグアイ人のメルセデス宅に厄介になり、アルゼンチン、ウルグアイのコミュニティのなかで暮らしていたから、自分にとっては、未だに西語の響きも母的なもの、こどもへの郷愁に繋がる。相変わらずメルセデスは姉のような存在だし、彼女も息子を実の甥のように思っている。
メルセデスに「Arrorro はどう訳せばいいかな」と尋ねると、「ああArrorro mi ninoね」と懐かしそうに旋律を口ずさんだ。
ウクライナ侵攻により、チャイコフスキー国際コンクール、国際連盟より除名。
4月某日 ミラノ自宅
作曲者の心情とは、直截に作品に反映され得るものか。
高校生だった頃、祖父が亡くなった直後にフォーレのレクイエムを聴き、奈落に突き落とされた。曲頭のユニゾンが鳴った瞬間、作曲家は自らの魂で音を書いていると実感し、高邁な精神なぞ縁のない自分には到底作曲できないと感じた。
尤も、作曲中に作者が同じ感情を抱き続けるなど在り得ないから、やはり作品と精神は別の世界に属している気がしたり、ドナトーニの「Duo pour Bruno」を演奏してみて、やはり作曲者の裡と波長が繋がる作品は存在すると思い直したりしながら、この齢になってしまった。
このところ、同じ楽器のために続けて二つの曲を書いて、人間誰しもが持つ、父性母性についても考えている。
元来頼まれて書いたものであっても、作曲して楽譜として記さずにいられない衝動に駆られて、内容も当初のリクエストを大きく逸脱するような影響を受けることがある。
併しながら、それを書かなければ先に進めない、精神の瘤のようになって躰に溜まっているものを摘出しなければ次の作品が書けない、強迫的な感覚は確かに自分の裡にある。
一切の感情を排除して作曲してみようと試みて、ぽろぽろと書いたものをピアノで音を鳴らした途端、隣室で漏れ聴いた家人から悉く酷評され、破棄したこともあるので、作曲の際のモチベーションが案外とても重要なのかもしれない。
戦争について躁的な混沌を「自画像」で書いたから、全く反対に、自らの精神的な世界を「揺籃歌」で書いた。今回の福田さんのための「Las Madres」も、先に諍いについて書いたから、母性を主題にして作曲したくなったのかも知れない。
今まで考えたことすらなかったが、愛憎の感情を露わに戦う父性と、死者を悼み全て赦そうする母性が交互に顕れ、自分を作曲へ駆り立てているようにみえる。
4月某日 ミラノ自宅
息子から、今日は家で一人にしてほしいと頼まれたので、夕刻ふらりとレッコ湖畔を訪れた。
息子が小さい頃、何度となく訪れたレッコ湖から、切りたつ男性的な山肌が大胆に突き出している。空気はとても澄んでいて、静かに波打つ湖面を眺めていると、様々な思い出がとめどなく甦ってくる。
息子が小さい頃は、家族三人で向こう岸辺りにある、ぺスカルロという村に通った。小さな砂浜があって、そこで息子に水遊びをさせていた。
そこへ辿り着くためには、細い石畳の階段で大きな丘を越えてゆかなければならない。春先には村のあちこちで美しい藤の花が咲き乱れていて、眩い風景に目を奪われた。母を連れてぺスカルロまで出かけたこともあったし、息子が病気から快復したころは、抱きかかえて石畳を昇ったりした。
湖畔にある小さな食堂では、湖産の鱸ムニエルが絶品だった。
4月某日 ミラノ自宅
野坂さんとお約束した二十五絃の曲は結局書けなかったが、沢井さんと佐藤さんのための小品のなかに、当時の思いの何かをこめられればうれしい。
野坂さんの葬儀で配られた小さなカードにこう書かれている。
「心の清い人々は、幸いである、その人たちは神を見る。」マタイ5・8
野坂さんのヒルダ・パウラという洗礼名を眺めていて、ヒルデガルド・フォン・ビンデンの名前が頭を過る。自らの幻視体験を綴り描いた、女子修道院長であり作曲家でもあった中世随一の賢女で、深く広く信望を集めたところも、どこか野坂さんと共通している。
野坂さんとは「富貴」を主題にした作品を書く約束をしていたから、それとなにか繋げられるヒルデガルドの作品はないか、彼女の有名な幻視画を眺めながら考えている。
4月某日 ミラノ自宅
千々岩君から連絡を貰ったので、家人と連立ってサロネン指揮パリ管の演奏会へ出掛ける。千々岩君が立派にコンサートマスターを務めていて、友人として今更ながら本当に誇らしい。
亡き王女のためのパヴァーヌ、中国の不思議な役人そして幻想交響曲のプログラムで、サロネンとパリ管は満員のスカラ座で見事な演奏を披露し、聴衆は興奮の坩堝と化した。
イタリアとフランスだけでこれだけオーケストラの音が違うのは、何故だろう。絹糸のような繊細さに於いても、バルトークやベルリオーズの激した表現に於いても、立ち昇る香りと音の明度も全く違うし、激す意味そのものも方向性すら少し違う気もする。国民性が長く培ってきた伝統の違いだろうか。これから、ヨーロッパは何を目指し、どこへゆこうとしているのだろう。
(4月30日 ミラノにて)
母と
笠井瑞丈四月上旬母を連れドライブに出かける
国立インターで高速に乗り藤野で降りる
そして軍刀利神社に行き秋川渓谷を抜け
また高速に乗り自宅に戻る
道中母はいつも
何か喋ってるか寝てるか
そのどちらかだ
もしかしら寝てる方が多い
景色などには興味がない
でも「ドライブに行く」と
誘うといつもいいよと言う
家に着くと楽しかったと
言ってくれるので
決してつまらなかった
ワケではないようだ
なので
また
誘う
ま
た
誘
う
母は僕を産んでリウマチになり
長く病気と共に生活をしている
カラダは何度も色々な所を手術をして
首は曲がり指は変形してしまっている
それでも家事や父の仕事のサポートをし
海外の公演があれば常に同行もしてきた
天使館の全ての公演を
プロデュースしてきた
話は変わりますが
実家は数年前建て直しをした
内装は決してバリアフリーの作りではなく
どちらかと言うとこだわりで作った家です
実用よりもデザイン重視
家雑誌にも載ったこともあり
通りがかりの人が
内装を見せて欲しいと
言ってきた事もあった
母の寝室は二階にあり
朝晩階段を
上り降りる
そんな母が四月中旬に
急に立ち上がることが
出来なくなってしまった
直立すると激しい痛みがきて
寝たきりにになってしまった
頭を支えるチカラが上半身に
なくなってしまったのである
こんな日がいつかは来るとは思っていたが
突然な事で何も準備ができていなかった
寝る場所も一階に移し
二階での生活が終わり
一階での生活が始まる
外を眺め
本を読み
鳥の声を聞き
流れる時間を
またきっと歩ける日が来る
そうしたらまたドライブに行こう
黄色と青の交響曲
さとうまきこの2か月は、ウクライナのニュースでも持ち切り。国会議員はいきなり青いシャツに黄色のネクタイつけているし、女性議員は黄色のスーツに青いシャツ来ているし、町中のパーキングや駅の案内板、ツタヤのカードまで、黄色と青になっていて、目に留まるものが全部黄色と青になっている。「何でもかんでもウクライナ病」に罹ってしまったみたいだ。気が付くと僕も黄色いシャツにブルーのジャージを着て町を歩いているではないか! そもそも黄色のシャツなど持ってないのであるが、私の愛するアルビル・SC(イラクのアルビルのサッカークラブ)のユニフォームが黄色で気が付くとそれを着ていた。
国際社会は、プーチンのウクライナ侵攻を国際法に違反したかつてない蛮行のように批判している。ゼレンスキー大統領は、国連の安保理がロシアの拒否権行使によって機能していないことを批判し改革を強く求めた。バイデンも、「プーチンは虐殺者で権力の座にとどまってはならない」と発言。ただ、国連が機能していないのは、ロシアだけではない。アメリカはイスラエルの入植地拡大に対する非難決議には拒否権を行使。イラク戦争では、安保理の決議を経ずに、アメリカがイラクを攻撃してとんでもない失敗をやらかしてしまった。「それでもサダム・フセイン政権を倒したことで世界は平和になった」とブッシュ大統領は開き直っているではないか。
ロシア兵が略奪やレイプをしているという情報もある。こりゃ本当に最悪だと思うが、アメリカがそのことを声高に批判するのを見ていると思い出すのが、イラクのアンバールで民家に入り、娘たちをレイプし、アブグレイブ刑務所では、男も女もレイプされた。あの時の報道を見たショックが思い出されて、ああまた、戦争がこういうことを引き起こしてしまったんだと落ち込む。
日本政府も今回人道支援に100億円を出すとし、35億円はNGOへと渡るらしい。僕は100億円すべてを国連に出して、その分他の貧しい国も含めてWFPが食糧配給もすればいいと思う。避難民の支援もすでにポーランドの地元のNGOが頑張っている。さらに安全に避難しているウクライナ人を20名日本に連れてくるというのも、これもすでに皆が言っているように仮放免のクルド人などを難民認定するとかビザを出すとかすればいい。収監されて死んじゃったスリランカ人や自殺者まで出している現状はどうなのか?
そういう話をすると、プーチンのやっていることを肯定するのか! けしからん! と厳しく非難されてしまう。それで、今日本の中で論争になっているのは、3つのグループに分かれているらしい。
① 「ロシア、プーチンが絶対悪」(日本政府や日本のメディア)この人たちがエスカレートするとロシア料理のお店にまで嫌がらせをすることも。
② 「どっちもどっち論」(こうなったのは、2014年から内戦状態が続いているウクライナと介入してきたロシア双方の問題)なので、話し合いましょう。
③ 「ロシア以上に欧米が悪い」陰謀論も含む、いわゆる反米左翼
そんな単純に3つに分けられると、自分がどこに入るのかは難しい。今回の侵攻に関しては①プーチンが間違っているが、一刻も早く解決するためには、②のウクライナの少数派の不満をどう解決するかも含めて話し合う。③欧米は全く話し合いのテーブルを作らずに武器ばかり供与しているので戦争を長引かせている。ということだと思う。ただ、僕はイラク惨状をこの目で見てきたから、もともとウクライナの東部の問題があり、②があって③で欧米がロシアともうまく話し合いを進めれば、①は避けられたのではないかと思う。
みんながSNS上で言い合っているのは、○○主義者はこうあるべき見たいな議論で、そんなことよりどう殺人を一日も早く終わらせるかが重要なのに。
モヤモヤしていたら、先輩に頼まれていた合奏集団不協和音のデザインが刷り上がったというので、渋谷で後輩がママをやっているバーで受け取ることになった。謝礼の代わりに2002年もののワインと極上のイタリアの生ハムをいただきながら、お互い知ったかぶって「ウクライナ問題」を無責任に語り合った。今回の演奏曲は、ベートーベンとライヒャ、どちらも1770年生まれでボン大学では仲良しだったらしい。生誕250年記念の2020年秋に、同じ年1808年に書いた交響曲を演奏するという企画で、ボン大学の前で採火した二人が「大友よ!」と喜び合うというイラストの依頼だった。しかしコロナで延期になり、さらに一年後にも延期になり、もうどうなるかわからないけど、とりあえず作ろうということで、Zoomの中でベートーベンとライヒャがリモートで乾杯するというデザインで作ったが、急遽マンボウは明けた。会場の使用許可も出たということで、青空の下の麦畑でおいしそうに乾杯するデザインに変更したのだった
あれ、ここでも無意識に黄色と青のデザインになっている! コンサートは5月8日。第二次世界大戦の終戦記念日の一日前。何とか和平合意して、皆が青空の下で乾杯できればいいなあと祈るばかりである。
帰り際に、先輩は、青いシャツに麦色のジャンバーを羽織った。
「もしかして?」「あ、いや、ユニクロで黄色っぽいの探したらこれ売ってたんで」
そういうと彼は、黄色と青の町に溶け込んで消えていったのだった。
合奏集団「不協和音」第82回演奏会
ライヒャ 交響曲へ長調
ベートベン 交響曲第5番ハ短調
2022年5月8日(日)18:00開演(17:30開場)
入場無料:ルーテル市ヶ谷ホール
「ものを見てかく手の仕事」
高橋悠治このタイトルは平野甲賀の字(『平野甲賀と』p.14)を見て、同じ題の文章もあるが、それは「ものをみて描く手の仕事」(『僕の描き文字』p.80)になっている。
般若佳子に頼まれた無伴奏ヴィオラの曲『スミレ』を書き、山根孝司も加わったクラリネット・ヴィオラ・ピアノの『移動、Iōn』を書いて、金沢市民芸術村で演奏しに行ったのが4月のこと。
先月の「水牛のように」に書いた、デイヴィッド・ホックニーのジョイナーから思いついた作業、1枚の楽譜を見返して、その時眼に留まった音符から思いつく別な音の流れを書き留めながら作曲して、この2曲を作った。元にしたのは、般若佳子に昨年頼まれたが間に合わなかった『イオーン』というヴィオラ曲の下書き。その都度見えたフレーズをちがう楽器にあてがい、他の楽器をそこにあしらう。
今年亡くなった小松英雄(1929-2022)の『平安古筆を読み解く 散らし書きの再発見』(二玄社 、2011)で読んだ「散らし書き」の、分かち書きと続け書き(連綿)を単語の切れ目と一致させない技法、雅楽にもそれと似た方法で句や呼吸を越えて続く流れがある、それと音の長短や順序を変えながら限られた音から途切れがちの流れを作り出して、書き進める。
17世紀フランスで non-mesuré というリュートやクラヴサンの、自由リズムの前奏、style brisé(崩し)と言われた、不規則に和音を分散させるスタイルで、メロディと和音の対立を和らげながら、いくつかの線が、対位法ではなく、対話でもなく、壁の向こうから聞こえるようにして、あいまいに絡まり縺れた状態。音はお互いに避け、離れ、彷徨い、絡まり、揺らぎ、分散と支え合いのバランスが絶えず崩れて変化する。線の偶然の出会いと緩やかな見計らい。小さな変化と、弱い音の焦点を変えながら…