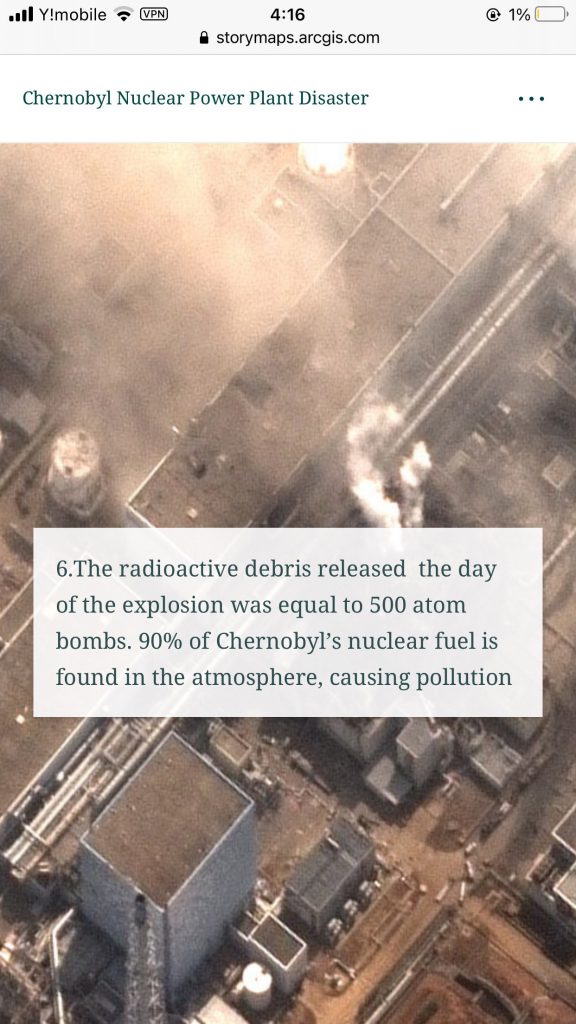2021年10月1日。今日はブソッティ90歳の誕生日です。中学生のころ、澁澤全集と漆黒のサド全集を古本屋で蒐集して、ロートレアモンと一緒に読み耽っていた自分にとって、ブソッティは、澁澤の耽美で倒錯した世界を具現化する稀有な存在でした。
尤も、イタリアで知己になったブソッティの印象は少し違って、三輪明宏と寺山修司、そこに政治信条こそ違えども、僅かばかりの三島由紀夫のエッセンスを雑ぜたような、刺激的で不思議な存在でした。
パゾリーニを想像させる部分もありましたが、底辺には常に音楽とオペラが流れていたように思います。
—
9月某日 三軒茶屋自宅
昼過ぎ、鈴木優人君のオルガンを聴きに初台に出かける。自転車を漕いで渋谷でPCR検査の陰性証明を受取り、そのまま宇田川町を抜け初台へ向かった。躰が困憊しているのを痛感。鈴木君の演奏を聴いていると、溌溂とか颯爽、闊達という形容詞が頭に浮かぶ。
グランドオルガンが、こうも切れ味良く、メリハリのある楽器だと実感していなかったので、認識を刷新した。聴いていて、ふと、シャリーノの2台オルガンのための「アラベスク」の楽譜を、ぜひ彼にプレゼントしたいと思う。
昨年はオーケストラをオルガンに見立て、彼のオルガン演奏、指揮姿を頭に描きながら作曲したが、その想像通りだったので少し驚いた。オルガン奏者も指揮者も、聴衆に背を向け演奏するのは等しい。
アンコールは、この所家人が家で練習しているバッハのフーガであった。
演奏会後、外は酷い雨が叩きつけていて、持参した雨具を着込み自転車に跨る。
9月某日 三軒茶屋自宅
東京よりお便りをいただく。
「作曲家は間に合わないと叫びますが、間に合います。M式のひとつは、全く違う質やジャンルの仕事を同時並行でやることでした。編曲のことですが、おかしな例えだけど、毛糸のセーターの糸を解いては蒸気に当て、糸を柔らかくして編み直す。色も形も同じだけれど、新しい編み手がいるということかな」。
9月某日 ミラノ自宅
一日、川口成彦さんのための作曲。
パラリンピックが終わるや否や、ドイツは日本を感染拡大国に指定した。
イタリアは市民のワクチン接種を義務化するという。それに対し、8割の国民が賛成しているそうだ。徹底的に経済が打撃を受けたので、仕方ないのだろう。これからどうなるのか。
母が結婚前に世話になった、小田原は関本の大角の照ちゃんの行方を捜していたところ、インターネットの電話帳にそれらしい名前が見つかる。
早速母が電話すると、照ちゃんは肺炎で4年前に亡くなっていた。94歳のご主人は矍鑠としていて、半世紀以上経って初めて電話したのに、直ぐに誰だか分かったのよ、と母は驚いていた。
アリタリア航空が10月で会社を閉めるので、引延ばしていた家人と息子のチケット払戻しのため、朝から電話を繋ぎっぱなしにして仕事をする。新聞では誕生から現在までのアリタリア航空の変遷を紹介する記事が盛んに掲載され、「アリタリア航空」の名義を公に売りに出している。
右肩から腕にかけて、誰かが乗移ったような妙な感覚。
9月某日 ミラノ自宅
イタリアに戻って感じるこの解放感は一体何か。さして日本で清廉潔白に過ごしているわけでもあるまい。正しく音楽をやり過ぎているというのか。
ツインタワーのテロから20年が経った。自分の人生に於いて911は大きな転機となった。同世代で同姓同名の杉山陽一さんが犠牲になられて、まさかお前じゃないだろう、お前は元気かと何度となく連絡を貰い、その度にツインタワーの映像が甦った。
彼のお名前は漢字は少し違うけれど、ローマ字では同じ綴りだ。
その所為か、完全に他人事とは思えず、烏滸がましくも自分は生かして頂いている、暮しの節々でそう感じるようになって、現在に至る。
911を機に自分の音楽も次第に社会に近づいていったが、日本に住んでいれば違ったかも知れないし、やはり同じだったかもしれない。
気にかけてくれる友人も恩人もいるし、彼らは亡くなっても、どこかで等しく気にしてくれているように思う。塞翁が馬だと感じつつ、生き長らえる中で、漸次パズルは解けて来た。パズルが完成してあちらの世界に行ったとき、落語の「朝友」のように、別の生き生きしたパラレルワールドが広がっていることを期待している。
昼過ぎ、電話をしていると物凄い音がして、窓ガラスに鳥がぶつかった。
夕方、窓ガラス下の黒い物体に気が付いて、良く見ると黒ツグミが死んでいた。
目から一筋、細い血が流れていて、躰を持ち上げるとベランダには体液の染みが残った。ツグミの巣のある土壁の袂、随分前に息絶えていたツグミを埋めた辺りに、穴を掘って埋めてやる。
9月某日 ミラノ自宅
明け方川口さんに楽譜を送ったので、これから少し寝ようと思う。次の譜読みにどれだけ時間がかかるか、ある程度の目算を立ててから次の作曲にかかりたい。
前回、巨視的に作曲した同じプロセスを、今回は微視的、内視的にやろうとしている。
ここ暫く、一家総出で庭に集う黒ツグミたちの囀り声は姦しいほどだったが、昨日の一件以来一羽も現れず、静まり返っている。悼んでいるのか、慄いているのか。
昨日死んでいた鳥に何があったのか、判然としない。何かの拍子にパニックに陥り窓ガラスに突進したのだろうか。
附近には背の高い梢が並んでいて大小様々な鳥が訪れるが、空を羽ばたく姿を眺めていると、人間より余程能力が長けているように思えてならない。
玉葱を軽く炒めて古いゴルゴンゾーラチーズを絡め、パスタを加えて茹で汁で全体を伸ばしよく馴染ませてゆく。秋の味がする。
9月某日 ミラノ自宅
家人がメタテーシスやピアソラを弾くオンライン配信を聴く。メタテーシスもこなれて来たのか、彼女が弾くとフリージャズのように響く。元来旋法的に書かれていて、それが目まぐるしく変化し、重複してゆくから、ある意味当然かもしれない。悠治さんのお話を伺っていると、音符をデジタルに再生する必要はないようだから、フリージャズやルイ・クープランのように弾いても構わないだろう、などと思いつつ楽譜を貼っていて、ブソッティの訃報が届く。
シルヴァーノがこの夏も無事にやり過ごせて良かった、10月1日、90歳の誕生日を皆が賑々しく祝うだろうと考えていた矢先だった。
9月某日 ミラノ自宅
学生時分、間借りした部屋の幼児の幽霊に水を出すようになって以来、宗教心は皆無のまま家族や恩師、友人らに水を上げ、手を併せている。今朝からそこにブソッティも加わる。宗教とは無縁だから、彼も気にしないだろうし、死は逝く本人より残された周りの人間が作り上げる概念だろうから、当人は最早興味もないだろう。
ブソッティは火曜に荼毘に附された後、土に帰されるだけだという。宗教儀式を一切執り行わないのは、故人の宗教観に基づく。告別式も葬式もなくてはお別れも言えない。マンカはブソッティの訃報が報道機関から不当に軽視されていると憤慨している。彼曰く、エツィオ・ボッシはテレビの追悼番組まで作られたのに、べリオもドナトーニもブソッティが死んでも、皆一様に知らない振りをしている。
9月某日 ミラノ自宅
亡くなった人を想い浮かべるとき、死後そこには彼らの優しさだけが残る。生前彼らが周りに分け与えた愛情だけが残る。恩師や家族、友人も等しく、その温もりだけが、残り香のように漂う。死ぬと人は誰でもそうなるのか。自分がいなくなった時、誰かに向けて同様に温もりを留められるだろうか。
死ねば数ケ月と待たず自身の痕跡も記憶も消失するだろうが、自分の個が明確でなくとも、何某か微かな温もりが、空気か土か、コンクリートかアスファルトの上に、ほんのり色を加えられれば倖せかもしれない。
ブソッティの訃報を受けて、そう思う。
フォルテピアノの川口さんは、既に「いいなづけ」の本まで落掌されたそうだ。深謝。
今から200年前の1827年、マンゾーニはそこから更に200年遡った1629年から2年間に亙るミラノのペスト大流行の姿を資料に基づき忠実に描いた。
「いいなづけ」から100年後にスペイン風邪、200年後にCovid-19がミラノを舐めてゆくなど、露ほども考えないで書いたのだろう。
さもなければ、ペスト禍のミラノをあそこまで緻密に描きあげなかったに違いない。
昔、ミラノにはこんな惨事があった、と透徹に後世に伝えようとしたのだろう。
スペイン風邪は知らないが、Covid-19に関しては、当時ワクチンこそなかったにせよ、陰謀論者が現れるところまで、マンゾーニが書き残した世界は現在と酷似していて、読んでいて居心地が悪くなる。
9月某日 ミラノ自宅
「水牛」に書く原稿と自分の作曲が、最近頓に似てきている。私事と公事を区別せず、日記を並置してゆく。それは概念的でも観念的でもなく、音や文章を無から捻り出す能力や創造力の欠落であり、それ以上でもそれ以下でもない。
1月に東京で演奏した、ブソッティ「和泉式部」断片を、久保木さんが故人を悼んでヴィデオ編集してくださっていて、感謝している。
9月某日 ミラノ自宅
久しぶりにスカラに出かけ、ティートの演奏会を聴く。
桟敷入口でワクチンパスポートを提示し、検温して入場する。知合いに会うのが煩わしく天井桟敷に席をとると、目の前で6人ほどの若者が天井桟敷最前列から身を乗り出し、熱心に聴き入っていた。
作曲を勉強する一団だったようで、フィリディ新作の演奏が終わると興奮冷めやらぬ様子で絶賛しながら、それぞれ口角泡を飛ばして意見をまくしたてている。
彼らの一致した意見によれば、フィリディの最高傑作は「葬式」だそうだ。そんな瑞々しく情熱的な姿を、好感を持って眺める。
後半ドナトーニが始まると、面白そうに聴くものと、スマートフォンを取り出しチャットを始めるものと別れた。チャットの彼の携帯電話は、目の前で画面が点滅して煩わしいが、平土間前列の婦人など、前半からスマートフォンを触り続けているから、この若者を批難する気はおきない。
演奏後、ティートはドナトーニのスコアを高々と聴衆に掲げて賞賛を示した。冒頭の低弦楽器の部分の扱いが流麗で感嘆する。
演奏会最後はストラヴィンスキー「うぐいすの歌」だったが、オーケストラでピアノを弾くヴィットリオが余りに際立っていて、思わず演奏会後に彼にメッセージを送った。
9月某日 ミラノ自宅
ブソッティの告別式も葬式もないと聞き、ちょうどフィレンツェで行われている、ブソッティ90歳記念行事の一つ、Bussotti par lui-même 上映会に出かける。
LGBT、性的少数者の関わる映画祭の一環でもあるので、カヴール通りのLa Compagnia映画館の受付や観客もそれらしい風貌の人たちが集って賑々しい雰囲気だ。
観客の殆どは音楽関係者ではなかったようで、上映会後、観客からは、彼の音楽をもっと聴きたいとの声が口々にあがった。
上映前の簡単な座談会で、ロッコが、スイス国営イタリア語放送局のこのドキュメンタリー番組制作当時の逸話を話す。
当時自分はまだ23歳で未熟だったから、即興で踊りを繋ぐこともできず、途方に暮れながら3小節間立ち尽くしたこともあるという。尤も、観客には、トルソの3小節も充分深い印象を与えたに違いない。
スイス国営イタリア語放送がデジタル化したこの番組は、原版が傷んでいたというために、ロッコが「友人のための音楽」や「水晶」を踊る場面や、エリーズ・ロスが「サドによる受難劇」を歌う場面も割愛されていた。
ロッコ曰く、マスクをしていたから、最初は誰だか分からなかったそうだが、それにしてもお前はなぜフィレンツェにいるのかと驚かれる。
追悼式の予定がないのは、遺言でもなんでもなく、単に今のところ誰からも提案がないからだそうだ。自分で企画したら、誰に任せて誰を招くのか、到底決めかねると言う。
イタリア国営放送ラジオでは、オレステが特別追悼番組を放送して、ブソッティの死を悼んだ。
9月某日 ミラノ自宅
「50年前の演奏です。50年前のふたりです」
雨田光弘先生から、50年前にご夫婦で演奏している録音が送られてきた。日付は1973年8月16日。今はなき福井の松木楽器店の録音、とある。
サンサーンスの「白鳥」と光弘先生の音楽を奏する動物画とともに始まる。
痩せて華奢な信子先生が、ぴんと背をのばし、飄々とした面持ちで演奏される姿が目に浮かぶ。
先生の掌を思い出しながら、ほろほろ、ほろほろと紡ぎ出される音に聴き入る。
無心で耳が音を追うに任せる。音に先生の思いでを投影しながら聴きはじめれば、きっと落着いて耳など傾けていられない。
去年の正月に先生宅を訪れて、おせちを少しご馳走になった。あれからもうすぐ2年になるなど信じ難い。7年間も習っていたが、それは酷い生徒だった。
9月某日 ミラノ自宅
夜半早朝、秋らしさが増してきたとはいえ、未だ緑の葉に覆われている庭の樹の梢で、今朝はリスが盛んに尾を振っている。裏の線路と隔てるレンガ壁に垂れた枝を伝って、茂みに潜り込んでゆく。
久しぶりに入試でマリアに会う。血栓の出来やすい体質でワクチンが打てないと聞いていたから、ワクチン接種証明がなければ学校にすら入れない昨今どうしているか心配していた。相変わらず元気そうで安心したが、48時間ごとに自費でPCR検査をしているという。「もちろんよ。これがなければ、働かせてもらえないんだから」。
9月某日 ミラノ自宅
東京の家人より日本で打ったワクチン接種証明の写しが届く。一昨日それをグリーンパス発行の保険局のサイトに登録したところ、今日、グリーンパスを発行する暗証番号とQRコードが送られてきた。
母からは、笑顔の父の近影が掲載された小冊子の写真が届く。電話口で「どこの好々爺かと思ったわよ」と笑っていた。
先日の入試で、ヴァイオリンのフランコ・メッツェーナの講習会伴奏をしていたナポリ国立音楽院の大学院生、ガブリエレが入学した。大学院は10月半ばに修了予定だそうだ。
南イタリアの学生らしく、とても慇懃で、幾分古めかしい言い回しのメールが届く。
「先生のクラスへ入学許可を頂き誠に有難うございます。大変嬉しく存じます。どうぞ宜しくお願い申し上げます。お礼を申し上げておきながら、早速このようなメールを差上げる失礼をお許し下さい。レッスン開始から2週間は、カラーブリアの実家に戻らなければならず、すぐに先生のレッスンを受けられないのです。大変申し訳ありません。実家のオリーブ収穫を手伝わなければならなくて」。
「全く問題ないですよ。いいね、カラーブリアのオリーブだなんて。羨ましいです」。
「もちろん先生にはお届け致します。これもわたくしどもの習わしです。どうぞ楽しみにしていて下さい」。
(9月30日ミラノにて)