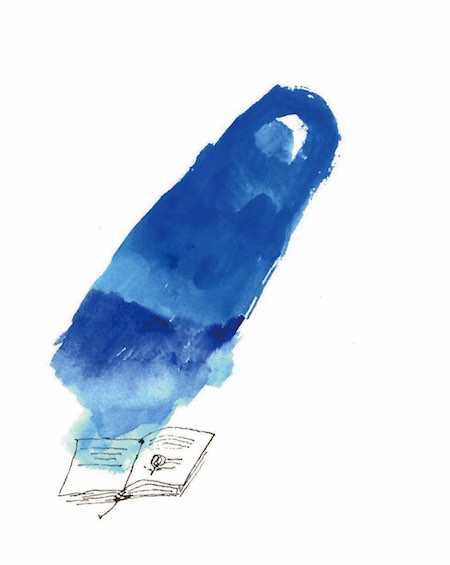目の前で桃色の花がほころび始め、日本から戻ってきたばかりで、まだ刈り込んでいない庭の芝に、黄色いタンポポの花がきままに咲き乱れています。震災直後の4月初め、毎年少しずつでも日本の小学校を体験させたいと三軒茶屋の小学校に息子を通わせて早6年、今月無事に卒業式にも参加させていただきました。震災直後のあの頃も、恐らくこうして目の前にほころびはじめた桃色の花を眺めながら、先に日本に戻っていた家人と、息子の入学式について、喧々諤々電話していたのを思い出します。
—
3月某日 ボルツァーノ アパート
練習に出かけようと玄関を出ると、踊り場で女性に話しかけられる。中庭の茶色のコンテナを指さしながら「あの生ゴミ用コンテナに、ビニール袋で捨てたのは貴方?」。意味も分からぬまま頷いたところ、なんでもボルツァーノでは、生ゴミは支給される紙袋を使わなければ罰金なのだと言う。ミラノとはずいぶん違うと実感して、ボルツァーノの分別収集に関するサイトを見直すと、卵の殻と貝の殻も絶対に生ごみに入れてはいけないとある。今まで生ゴミに入れてしまっていて、反省することしきり。紙袋では油や水で底が抜けそうな気がしたが、防水加工なので問題なかった。この紙袋は街のどのパン屋でも使われていて、生ごみは市が支給するものか、パン屋で使われる紙袋を使うよう指示されている。
屋号にBeckereiとドイツ語で書かれた近所のパン屋に通う。どのジャムが美味しいかと尋ねると、これは特別と差し出さた瓶詰を手に取る。傍らにいた主婦も、そうなのよ、これは本当に美味しくて困ってしまうわ、と笑った。半信半疑で家でパンに塗ってみると、これが本当に旨い。ジャムより寧ろコンポートで、甘すぎず、独特の滑らかさと相まってとにかく口当たりよくて、繰り返し食べたくなる。ミラノに土産に持って帰る度に、一日であらかた食べきってしまうので、パン屋では「例の危険なジャムを頂戴!」と言うようになった。
3月某日 ボルツァーノ アパート
ドレスリハーサルが終わり、荷造りしてミラノに戻る。最終公演の後すぐにミラノに戻り、そのまますぐに東京に発つので、一か月近く暮らした荷物の大半は今回ミラノに持帰る。息子は今日メータのペトルーシュカ最終公演。一度は見たかったのだけれど、日程が合わず、結局一度も見られなかった。バレエだから息子たちは単なる黙役で、市場のシーンなどで風船片手に舞台を歩き回るくらいのものだそうだが、楽しくて仕方がないらしい。ずっとペトルーシュカを口ずさんでいる。初演版の舞台装置はロシアの色味に富んでいて、実に賑々しく美しい。息子曰く「曲としては、春の祭典の方が良い感じ」とのこと。子供の頃に本物の舞台に触れられるのは実に素晴らしいが、お伽の国そのままの風景の中毎日を過ごしていると、公演の後すっかりもぬけの殻になって、学校の勉強に身が入らなかったりするらしい。
3月某日 ボルツァーノ
午後3時、家人と息子を駅で出迎え、一度荷物をアパートに置くとすぐに劇場へ入った。角の金物屋の前で、ミラノからやってきた今堀くんとすれ違う。
もうすぐルカが横浜で演出する舞台があって、そこで英訳の「羽衣」を子役が謡う場面があるらしい。ついては、息子が手本代わりに録音して、それを子役に聞かせて練習させるのだと言う。発音も雅な英国復古調にし、リズムの付け方も、音程の流し方もあれこれ試し、漸く形になった。昨年録音して多少は慣れていたが、息子は相変らず英語が苦手で、緊張するとRをフランス語と間違えてしまうと言う文句が奮っていて、一同大笑い。
録音の後、本番前に少し身体を休ませようとアパートに戻る。家人は、近所で靴を買ってアパートに戻ると言って別れたが、案の定、道に迷って電話してくる。本番終了後パーティーに顔を出し、ずっと学校に出かけていなくて久しぶりに会った今堀くんとアパートで夜半まで話し込む。彼が暮らしていたパリやジュネーブに比べると、ミラノは住みやすく、演奏の機会も増えたと言う。これからも住み続けたいそうで、この世知辛いイタリアが意外ではあったが、頑張っている姿は頼もしく、嬉しい。
3月某日 ボルツァーノ アパート
一日休日。作曲が日ごとに溜まっていくが、今日まで暫く家族で落着いて過ごす時間もなかったので、朝から川伝いに散歩に出かけ、そのまま3人でロープウェイに乗って、過日一人で出かけたサンジェネージオに出かける。朝食を摂ろうと、村の中心で喫茶店を探すが看板は皆無。通りがかった老人に尋ねると、目の前の建物だと言う。外見からは全く分からない。日本に数枚絵端書を書いた。
小さな村なので、郵便局の隣によろず屋が一軒あって、おばさんが一人で切り盛りしている。ハムの切売りもすれば、雑誌や切手も売っている。日本までの切手を贖い、美味しそうなクラッフェンを買う。麓のボルツァーノは、街中イタリア語とドイツ語の併記だが、サンジェネージオはドイツ語話者が97パーセントだとかで、教会脇の掲示板など独語表記のみ。よく手入れの行き届いた墓地には、小さな村らしくドイツ風の同じ姓ばかりが並ぶ。
3月某日 ボルツァーノ アパート
リゲティの「アヴァンチュール」の放送があって、友人が録音を送ってくれる。身振りのある音から身振りをはぎ取り、聴こえなかった音、見えなかった音に焦点が合っている。人体模型をまず思い出し、何故か小学校の頃、買ってきたレコードで初めて「アヴァンチュール」を聴いたときの不思議な感覚がまざまざと甦ってきたのは何故だろう。感情を込めて発声するのではなく、感情が発声する音について、そしてまた、意思を持たせる発音ではなく、意思が発音する強さについて考える。リゲティを大岡さんと歌手の皆さんと作りながら、学んだことは数限りなくある。
3月某日 ボルツァーノ
最終公演の直前、山を越て訪ねてきた旧知の作曲家に会う。彼の奥さんは音楽祭を催すほど財力もあるし、彼も随分うまく立ち回っていると友人たちは陰口を叩いていたが、10年ぶりに会う彼は、見たことがない妙齢を連れていた。整った顔立ちなのだが、笑うと途端に顔が崩れる不思議な妙齢だった。彼が「去年は35回自作の本番があったが、今年は10回ほどしかない」と言うと、傍らの妙齢も悲しそうな顔をし、「しかし来年以降はオーケストラなど新しい大きな仕事が沢山あるから愉しみにしている」と明るい声を出すと、隣の妙齢も朗らかな顔をするので、まるで従順な犬を見ているようだったが、彼は話しながら手元のスマートフォンにずっと目をやっていて、こちらもこれから本番だし、忙しいなら無理に会わなくても良いのに、と意地の悪いことを思う。
公演が終わり、関係者一同自家製のビールを出すビヤホールに繰り出す。実は肉が食べられないと言うと、レスリング選手のような屈強なウェイターに、思い切り笑い飛ばされる。見れば周りは皆厚さが7、8センチはあろうかというステーキを頬張る輩ばかり。彼ら若者は揃ってチロル服を身に着けていて、どうやらチロルの祝日か記念日だったのかも知れない。彼らと別れてから、ボルツァーノを訪ねてくれた浦部くんとアパートで少し話す。マンカの作曲レッスンが思いの外良かったらしく、今秋からミラノに留学を決めたと言う。彼は決断が早い。
3月某日 白河 ホテル
昨日は空港から大荷物を抱えて渋谷のトップに寄る。白河で自分の好きなコーヒーが飲みたくなるのは分かっていたので、いつもの豆を挽いてもらい、小さなドリップを買って荷物に入れる。ボルツァーノでも、馴染みのミラノの焙煎店で挽いてもらった豆を持参して、毎朝好きなコーヒーを淹れた。肉も最早食べられず、無趣味な人間の、ささやかなる愉しみ。
今日初めて地元の中学生6人の歌声を聴く。しっかりとした、そして純粋な声に感動する。歌いたいという意思がよく伝わり、でもオペラに対する不安と戸惑いも伝わってくる。「外国から来た怖そうな指揮者」を目の前にして、どうしても緊張するだろうし、今日で自分が演奏会に出られるか決まる心配もあるだろう。
気持ちと声を揃えて一つの大きな表現をするのが合唱なら、「魔笛」の童子役にはそれぞれ違った人格も個性も求められ、その個性が生む感情によって、初めて声が生まれる。個性や人格は、彼女たちの身体の芯でつぼみのように固くなっているものではなく、彼女たちの身体全体を外側からすっぽりと包みこむ、暖かい空気のようなものにならなければならない。肩の力を抜いて、無理にでも笑顔を作って歌って貰うこと。それから、指揮者の顔を見つめて、指揮者のために歌うのはやめること。
3月某日 白河 ホテル
朝起きて、コーヒーを淹れる。部屋の窓が那須連山に面していて、毎朝山の姿を眺める。数日前までアルプスの麓で暮らしていて、毎朝、山頂は雪が被っているかしらと、確認するのが日課になっていた。那須連山は、雄々しいアルプスよりずっと嫋やかな印象を与える。「山」と一口に言っても、育った環境で目に浮かぶ光景はまるで違うと実感する。尤も、嫋やかに見えるのは、単になだらかに続く平野から遠くに山を望んでいるからで、間近で見れば全く違う迫力をもたらすに違いない。
石を刻み橋を渡して「きざはし」となった。アルプスは、恰も無限に続く天への嶮岨な階のように隔絶な趣だが、目の前の那須連山はなだらかで、かかる拒絶感を覚えない。朝日が眩しいと思っていると、正午前に外に出ると突然雪が降り始め驚く。青空のまま気温も下がらず雪だけが吹き付ける、超現実的な吹雪にも遭遇した。聞けばこれは那須や会津の雪を、風が運んで来るものだと言う。
昼食と夕食に、随分手の込んだお弁当が配られる。努力はしたがどうも肉は身体が喜ばないので、スーパーで寿司など買い込み練習に出かけていると、誰の機転か、数日後から肉抜き弁当を用意して下さって、心遣いに痛く感激した。作曲が遅れていて、誰かと食事に出かけるのもままならなかったが、土地の方の温かさだけは、事あるごとに身に染みた。
「実は放射能については今も疑心暗鬼なんです」と打ち明けられることもあれば、「寧ろ現実をずっと悲観していたので、予想より復興が進んで嬉しい」と言われることもあった。どちらもその通りなのだろう。そんな中、素晴らしい文化交流施設が開館したことの意味と重みを改めて感じている。
中学生の童子役の皆さんから、副指揮の森田君はとても慕われていて、全幅の信頼を得ている。彼に副指揮をお願いして本当に良かった。技術的な問題は文屋さんがとても親切に助けて下さるし、緊張をほぐすため舞台上で新海君や倉本君が飛ばす冗談で、彼女たちの顔もすっかり明るさを取り戻した。誰からも彼女たちは愛されている。彼女たちが懸命に頑張る姿を通して、我々の心も一つに繋がってゆくのを感じる。自分がこの機会に関われること、そしてこうした切欠を与えてくれた彼女たちに感謝している。
3月某日 白河 ホテル
昨日は、飛込み用プールに閉じこめられ溺れかける夢を見たが、今日はローマで足立智美さんがピアノを使ったパフォーマンスを聴きにきた夢を見る。縦型ピアノのフェルトにセンサーがついていて、ピアノ音の替わりに、鍵盤を弾くと足立さんの声が流れる。家人がそのピアノを演奏するのだが、何故足立さん自身でパフォーマンスをしないのか訝しがっていて目が覚める。
立稽古の合間も休憩時間も、少しずつ作曲を続ける。頭の中で、「魔笛」と李白の詩と、古琴の音とトランプ大統領の濁声と、鉄板を叩く音と沢井さんの十七絃の音が、絡みついて離れない。それらは有機的な反応を互いに引き起こしているようで、それが良いのか悪いのか、正直なところよく分からない。南湖について李白が書いた詩を用い、洞庭湖の秋を描いた古琴の音を思い出つつ、ほんのすぐ近くにその南湖があるのを感じながら音を置いてゆく。
3月11日は、東京とは比べ物にならない程、この地にとって重く深い意味を持っているのを痛感する。練習の合間、伊勢さんの合図で淡々と黙祷を捧げただけだが、黙祷後の空間は、何かがまるで変化を来しているのを感じた。そこに居合わせた各人がそれぞれに思い出した時間の重さが、じんわり空間に滲みだしてゆくのが見える。所詮、上辺を繕った言葉で何かが言えるものではなく、淡々と黙祷をするだけで、思いを馳せるのには充分なのだろう。
3月某日 白河 ホテル
東京より「盃」の打合せで有馬さん来白。エレクトロニクスに関してまるで無知なので、念頭にあることを逐一言葉で説明してみると、実際には意味を成さない内容が8割。残りの2割でほぼ頭に描いたものを実現する。
統計的確率的に抽出された予想上の音素材を、たとえ聴衆の耳に同じようにしか聴こえないとしても、敢えて規定された楽譜を通して読みすすめる、有馬さんの思考フィルターを通して発音させたいのは、「アフリカからの最後のインタビュー」の時と同じだ。それは一見徒労のようでもあるが、現代音楽で定着された音符など、乱暴な言い方をすれば、粗方アルゴリズムなどでどうにでも操作は可能ではないか。実際そのように定着された音符も無限に存在しているだろうし、それが悪いとも思わない。自分が敢えてそれを選択しないのであれば、そこに何らかの意味が生じると信じる。或いは、それは単なる「徒労」の意味でしかないかも知れないが。人間とは面白いもので、或る音を意識して聴こうとすれば聴こえたりするし、或る音に意味を感じて発音すると違った音色になったり、音と別の音に関連性を持たせると、無意識に演奏法が変わる位だから、何らかの有機的な変化は生じるに違いない。
3月某日 白河 ホテル
余談。今回有馬さんが滞在中に「緩い」という言葉をよく使っていらして、当初意味が分からなかった。最近の流行り言葉なのだろうか。何度か問い質すうち、否定的な発言をオブラートに包み、アソビを持たせた表現が「緩い」だと理解したが、彼は長く関西の大学の教壇に立っているので、方言かもしれない。結婚当初、関西出身の家人が「この匂いを嗅いで」を「これ臭って」というのが不思議で仕方がなかったが、同じかもしれない。
「緩い」とは違うが、息子が書店で買ってきた若者向け小説を、最近気になって読んだところ、構成や設定は思いの外古典的で驚いた。使われている単語や表現の印象は違うので、自分の知っている日本語とは、別の言語で書かれた文章と思えば、違和感も覚えない。それぞれの登場人物の印象は、悪く言えば掘り下げられていないようでもあり、良く言えば、身の周りの友人たちの最大公約数の部分を使って描写しているようにも見える。絶対に彼や彼女でなければ、という強い表現の意志が薄められて表現されている印象を受けたが、案外言語が単純化してきているだけかもしれない。
古来の和色表現一つとってみても、現在の我々には想像もつかない微細な感覚が散見される。もはや使われなくなった古来の母音や子音表現の日本語の音が醸し出す、我々には知覚できない繊細な彩への感覚は、我々の可能性を遥かに凌ぐ。古代は、光もないままより深い色彩感覚があり、電気などなくとも、より深い音が聴こえていた。もろもろのヨーロッパ言語も、旧くはずっと複雑な言語体系を誇った。インターネットを介し、コンピュータでコミュニケーションするためには、そんな微細な差異は足を引っ張るだけに違いない。
では、音楽はどうなのか。少なくともまだ人間が、大方電気を通さない割と単純な発音体の楽器を使って、阿吽の呼吸で演奏するを良しとしているのであれば、そこまで音楽の内容を単純化しなくてもいいのではないか。もっと言えば、音楽の単純化とは、単純な音価で音符を定着することとは限らない。本当に複雑な音楽とは、単純な仕掛けから生まれる、定着できない揺らぎのようなものだったりするし、演奏するたびに違う音を生み出す音楽より、演奏するたびに同じ音がする音楽の方が、或いは 単純と呼べるかもしれない。
「壁」の作曲が全く遅れているのは、トランプ大統領の大統領令原文がどこに載っているのか調べるのに時間が掛かった、と言うと安江さんに怒られてしまうだろう。白河の歌手陣でも、早坂さんや高橋さんのようにアメリカ生活が長い人たちがいるので、どう調べれば大統領令が分かるのか質問したが誰も知らなかった。実際は「大統領令」Executive Orderと検索すればよかったのだが、慌てると灯台下暗し。
3月某日 三軒茶屋 自宅
白河の新幹線駅に両親を迎えにゆき、タクシーを拾って南湖の畔の「火風鼎」に彼らを連れてゆき、こちらはそのまま会場に入り、本番直前まで控室で作曲。指揮者の大先生は本番前は集中するものと、周りは皆気を使って下さっているのか、お陰でとても作曲に集中できた。本当は、ただ洞庭湖がどうやら、古琴曲の音色やら、まるでモーツァルトとは無関係な想像を逞しくしていたわけだが。
「火風鼎」は、地元の十文字律子さんのお薦めで、歌手の皆が出かけて絶賛していた。ラーメンは食べられないが、替わりに駅前の「大福屋」には、休憩中何度かざるを駆け込みに走った。白河蕎麦も実に美味。まだ正午前で開店30分程度だと言うのに、もう外にまで客が並んでいるので驚く。本番終了後、思いがけず来白していらした池田さん、岩崎さんにお目にかかる。皆さんとても喜んで下さって、特に童子の評判が頗る宜しい。前日平井さんが来白された時にも、全く同じ反応だったので、やはり彼女たちを皆で盛り立てている何かが見えるのか、それに頑張って応えた姿が心を打ったのか。演奏会後、中学生たちから可愛らしい寄せ書きを頂く。
3月某日 三軒茶屋 自宅
昼前上野の入谷口で待ち合わせて、チェロのフランチェスコと翁庵に行く。二人で「ざる」を食べ蕎麦湯を啜って、細川さんの講演を聴きにゆく。彼の奥さんエレナはその後16時から17、18世紀のフィレンツェに於けるオラトリオについて講演。彼女によれば、当時フィレンツェで無数のオラトリオが作曲されたがそれら殆どが消失し、ほんの数曲ウィーンの図書館に作品の一部が残るに過ぎないという。雨が降っていたが、フランチェスコは、滞在しているアパートから借りてきた女児用の派手なプリント柄の、それも数本骨の折れた小さな傘をさしていて、こちらは自転車に乗るときに愛用している汚らしいレインコートを被っていて、二人で入谷口の歩道橋下で顔を見合わせて笑った。
3月某日 三軒茶屋 自宅
朝9時に高円寺に行き、まず貞岡さんに口頭でこんな楽器が欲しいと説明する。メタルシートというか、銅板というか、でも演奏者の身体がすっぽり隠れるくらいの大きさが必要で、サンダーシートのようなべこべこなイメージではなくて。「どんな音が欲しいか歌ってみてもらえませんか」。「真木さんなんかもね、もうこんな感じ!シャチャーン!とか言ってくれてね、そうするとこっちも、パーンと閃くんですよ」。
リハーサル室に入ると、既に3枚の巨大なメタルシートが用意してあり。どのメタルシートも、こちらに挑むような挑戦的な目つきでこちらを見つめている。自分が頭の中で描いていたものに近いものが一枚、もう少しクリスタルな響きなものが一枚、全く想像していたものと違うサンダーシートのお化けみたいのが一枚。大体思っているような音をあれこれ叩いて試していて、想像していた音の一枚にほぼ決めかけていたが、サンダーシートのお化けがどうにも気になって仕方がない。自分の想像以上に、豊かな音がする。他の板より柔らかいが、表現力も演奏効果も高い。何でもアメリカ大統領は高さ9メートルの「壁」を作るそうだから、本当ならあまり表現力のない、もともと想像していた固いメタルシートがよいのだろうが、サンダーシートのお化けの雄弁さに心を打たれて、結局これに決める。そういうと、他の二枚が恨めしそうにこちらを見つめた気がした。
3月某日 三軒茶屋 自宅
息子の小学校卒業式。2列前に座っている父兄が、感激して泣き崩れている。自分の卒業式の予行練習を随分やったのを思い出す。恐らく初めて子供が卒業式に出る親は、誰もが同じことを思うだろう。懐かしいとも思うし、あの頃から同じ伝統が連綿と続いていることに愕くこともあるだろう。当時は、なぜ国旗に向かって敬礼するのか、意味がよく実感出来ていなかった気がする。敬礼していたのかすら怪しいし、国歌斉唱もちゃんとやっていたのだろうか。等とぼんやり思う。イタリアなら国旗に向かって敬礼はしないが、国歌斉唱は大好きで歌う時も胸に手を当てる、などと思いながら眺める。
自分が卒業式をやった頃は、40人学級で1学年6クラスだか7クラスはあった。今は2クラスで、それも25名程度。卒業式に時間的余裕があるからだろう、証書を授与される前、名前を呼ばれると、「はい! わたしは将来医者になって、みんなが苦しむ花粉症を治します!」と大声で自分の将来を宣言する。息子は「はい! ぼくは将来好きなピアノとフルートで、みんなを笑顔にします!」と宣言。へえ歌じゃないのね、と思いつつ、後で息子に尋ねると、先生が色々アドヴァイスを下さると言う。普段、劇場で稽古していて、この間までバレエに出ていたせいか、舞台で歩く姿勢が良いと感嘆。白河でずっと子供たちの舞台の姿勢を注視していたので、余計そう感じたのだろう。こんなところで舞台に出ている恩恵に与かれるとは思わなかった。
後半のクライマックスは「送る言葉」。在校生が卒業生に、卒業生が在校生に「送る言葉」というシュプレヒコール劇。そう言えばこんなことをやったかなあと思いながら、眺める。今まで6年間の出来事を反芻し、核になる言葉のところで、全員が大声で繰り返す。そして、最後は「これから旅立ちます! さようなら、さようなら!」と叫んで幕。周りの親御さんも感極まり号泣している。
「送る言葉」は、過日読んだ息子の小説の文体によく似ていた。恐らく20年以上も日本から離れているうちに、日本語そのものが変化したのかもしれない。毎年これを新しく用意される学校の先生方も、実はとても大変なのではないだろうか。しかし、高揚感など実によく書けているから、案外小説なども上手に書かれるのではないかしら、と余計なことが頭を過る。
「ぼくは将来好きなピアノとフルートで!」も同じだが、ヨーロッパで宣誓に立会う場面は普通に暮らしていれば皆無だ。選手宣誓も普通はないだろう。宣誓と言えば、結婚式で聖書に手を載せて永遠の愛を誓うとか、裁判で虚偽申告、偽証はしないと聖書などに手を載せて誓うくらいではないか。ヨーロッパで右手を挙げ大声上げて宣誓するのは、ムッソリーニ万歳かヒットラー万歳くらいなので、今でも右手をすっと上に向けて挨拶すれば、殆どのヨーロッパ人は露骨に厭な顔をする筈だ。別にヨーロッパ人の真似をする必要は全くないが、もし真似している積りで使っているなら止めた方がよい。
そもそも「シュプレヒコール」という言葉は何を表すどこの言葉だろう、イタリア語では何と言えるのか考えてみたが、相当する言葉はないようだ。合唱はイタリア語では、coroと言い、声を揃えて話す、程度の意味でも用いられる。「皆で声を合わせて言いました」「皆が声を上げました」と言う時もcoroを使う。「シュプレヒコールSprechchor」は独語、英語では「speaking choir」、日本語なら「話す合唱団」。「話す合唱団」を独語で検索すると確かに存在する。シュプレヒゲザングを多用する進歩的合唱団の印象を受けるが、実態はよく分からない。少なくとも卒業式の「送る言葉」で歌が挿入される理由は、「シュプレヒゲザングを多用する進歩的合唱団」だからだと知った。
3月某日 ミラノ 自宅
昨日は息子と二人、ミラノに戻る機中、ずっとトランプ大統領のExecutive Orderのプリント片手に打楽器曲の作曲。長くこの文章を眺めていると、それなりに筋が通って見えてくるから不思議だ。日本を発つ前に、すみれさんと電話で話した。すみれさんと沢井さんのための新作について。何を主題にしようか考えていたが、初演するのはカナダだから、案外「日系人」かしらん、とぼんやり思う。大体日系人とは何を持ってそう呼ぶのか。自分ももうすぐ日系人なのかしら。息子は既に日系人かしら。イタリアに帰化しなければ日本人かしらん。それなら在日の韓国籍の人は、韓系人ではなくて、韓国人なのかしら。
朝から学校に出勤し、夜半、1時40分。家の庭を歩く二人の不審者と話す。布団に入って本を読んでいると、人影が通り過ぎるので、窓を開けて、「何やっているんだ」と声を上げると、「まあまあ落着きなよ。すぐに出ていくから。慌てなさんな Ora vado via subito, stai calmo, stai tranquillo」と思いの外ゆっくりした野太い声が応えた。イタリア人ではないようで、ジプシーなのか、アラブ系なのか、アルバニア系なのか、少し濁ったくぐもった発音だった。
3月某日 ミラノ 自宅
ボルツァーノに入った頃から老子を読み始め、白河でも時間があると老子の本を開く。もう暫く眺めたので、最近ルクレツィオを読み始めた。悠治さんに薦められたスティーブン・グリーンブラッドの本が素晴らしくて、ずっとルクレツィオを読みたくて仕方がなかった。最近、歳とともに涙もろくなってきたのか、「物の本質について」を読み始め、ただ燦々と輝く力強い言葉に圧倒された。老子がじんわり身体に染み通る感動だとすると、ルクレツィオは、空から降り注ぐ太陽のようだ。彼がいなければ、我々のやっている音楽すら全く違った方向に発展したかもしれないと思うと、改めてその偉大さに言葉を失う。この二人は全く反対のようでもあり、しかしその中心はメビウスの輪のように繋がっているようにも見える。
(3月31日ミラノにて)